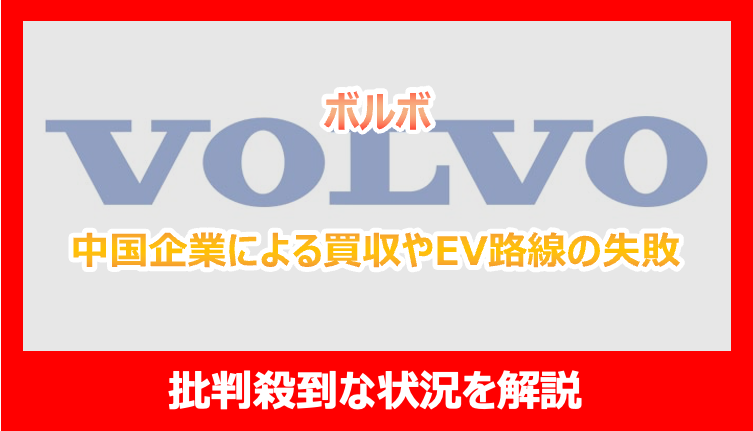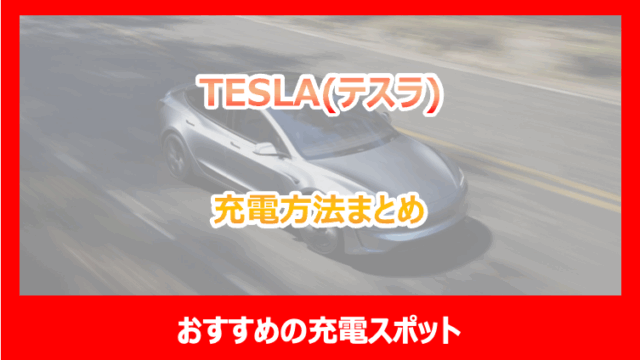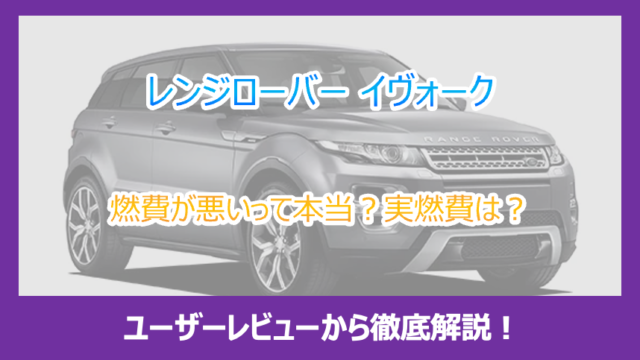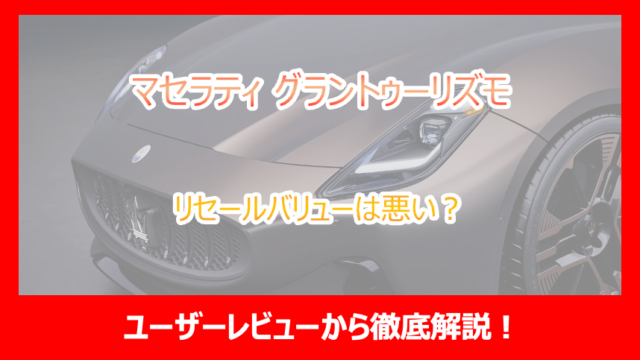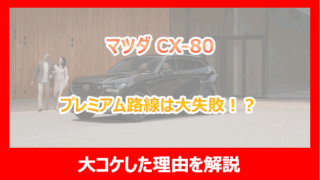スウェーデン発祥の高級車ブランド「ボルボ」。

北欧デザインの洗練された見た目と、安全性能の高さで多くのファンを持つ一方、近年は“EV戦略の失敗”や“中国企業による買収”といったネガティブな話題が相次ぎ、ブランドイメージの悪化が加速しています。
さらに、トランプ前大統領が推進する“関税強化”の影響で、アメリカ市場での販売にも赤信号が点灯。
ボルボは今、本当に終わってしまうのか?本記事では、読者の不安を払拭すべく、ボルボの現状と今後について徹底的にレビューします。
記事のポイント
- ボルボが中国企業に買収された経緯と現在の体制とは?
- EV戦略の失敗と度重なる開発遅延による信頼低下
- トランプ関税の直撃によるアメリカ市場からの撤退危機
- トヨタと比較して浮き彫りになる経営力・対応力の差

新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。
Volvo(ボルボ)の評価急落の背景
中国企業による買収とその影響
買収の背景と経緯
ボルボは2010年、中国の自動車大手「吉利汽車(ジーリー)」に買収されました。

この買収に至った大きな要因は、2008年のリーマンショックによる世界的な金融危機の影響です。特に欧州メーカーの中でも比較的規模が小さいボルボは、自社単独での経営維持が困難になり、資金面での支援を求めていた状況でした。
吉利汽車による支援の実態
吉利汽車は、開発費や研究資源、人員の再配置といった支援を積極的に行いました。これによりボルボは、EXシリーズやXCシリーズといった主力モデルの開発を継続することが可能となり、一時的に技術革新の速度が向上したとされます。しかし、この技術的な恩恵よりも、“中国企業の傘下”という印象がブランド価値の低下を招いたのが現実です。
スウェーデンブランドのイメージ低下
表向きには“スウェーデン企業”という看板を掲げていますが、実態としては中国企業の完全子会社であるため、愛車としてボルボを選ぶことに抵抗感を示すユーザーが増えました。とくにプレミアムブランドとしてのボルボにステータス性を感じていた層からは、「スウェーデン企業のフリをした中国車」と揶揄されることも少なくありません。
中国資本に対する感情的反発
加えて、近年の地政学的な対立構造や経済摩擦などにより、「中国資本=政治リスク」と見る傾向も強まっています。これがボルボのブランド全体に対してネガティブな先入観を生み、周囲から見下されるのではという不安を抱えるユーザーの声も多く寄せられる要因となっています。
ブランドイメージの崩壊
長年のファン層の離反
この買収劇により、多くの旧来のファンは離れ、「V70からXC90まで乗り継いだけど、もう買わない」といった声も少なくありません。

彼らにとってボルボは、北欧らしいクリーンで知的な価値観を象徴するブランドでした。そのイメージが中国企業傘下になったことで崩れ、心理的な拒否感へとつながっているのです。
ステータス性の喪失
とくに欧州車にステータスを求める層からの評価は急落しました。「ボルボ=高級北欧車」という認識はもはや過去のものとなり、「中国車になった時点でボルボは終わった」という厳しい声も見られます。所有することが“自慢”ではなく“説明が必要な選択”になってしまったことも、ブランド価値の毀損につながっています。
市場における影響
実際に中古車市場でも、ボルボ車のリセールバリューが他の欧州プレミアムブランドに比べて劣化傾向にあるとのデータも存在します。これは市場の評価がブランドイメージと密接に結びついている証左であり、買い替えを検討する層にとってもネガティブ要因として機能しています。
今後のブランド再構築の課題
ブランド価値の回復には、単なる車両性能や価格競争力だけでなく、「なぜボルボを選ぶべきか」という存在意義を再定義し、明確に伝えていくブランディング戦略が不可欠です。しかし現状ではそのような取り組みも明確に見えておらず、ブランド再構築には長い時間と多くの試練が伴うと見られています。
EV戦略の大失敗
電動化戦略の背景
近年、世界中で自動車業界の電動化が加速するなか、ボルボも2030年までに全車種をEVに移行するという強気なロードマップを発表しました。その第一弾として投入されたのが、新型EV「EX90」です。このモデルにはボルボが誇る先進的な自動運転支援機能や安全性の向上が期待されていました。
ソフトウェア開発の混乱
しかし、EX90の肝ともいえる自動運転ソフトウェア「Lidar(ライダー)ベースの先進運転支援システム」の開発が大幅に遅れました。理由としては、ソフトウェアとハードウェアの統合性の問題や、設計段階での仕様変更が多発したことが挙げられます。このため最大で6ヶ月の発売遅延が発生しました。
遅延による損失の連鎖
発売が遅れたことで、予定されていた販売計画にズレが生じ、市場投入タイミングを逃したことにより、競合他社に顧客を奪われる結果となりました。さらに、遅延に伴う追加開発費や生産調整費が膨らみ、当初の利益見込みが大幅に狂ったことがボルボの経営に深刻な影響を及ぼしています。
技術先行の落とし穴
EX90には高精度なセンサーやAIによる認識システムなど、最先端の技術がふんだんに盛り込まれていましたが、その分開発・検証にかかる時間とコストが想定を超えてしまいました。技術を前面に出したものの、それを支える体制が整っていなかったことが明るみに出た形です。
消費者からの失望
こうした混乱と遅延を受け、SNSやレビューサイトでは「期待していたのに失望した」「安全性を謳うならスムーズな開発体制を整えるべき」など、ボルボへの不信感を募らせる声が増加しました。ブランドへの信頼を大きく揺るがした失策といえるでしょう。
トランプ関税の影響
25%の追加関税が直撃
2025年、トランプ前大統領が再び導入を掲げた“対中25%関税”がボルボに直撃しました。ボルボは生産コスト削減のため、主力モデルを中国の工場で製造しており、これがアメリカ向け輸出において大きなコスト増を引き起こしました。
中国生産という構造的リスク
生産拠点を中国に集中させていたことで、ボルボは一気に関税の影響を被る構造的リスクを抱えていました。地理的・政治的リスクを軽視した生産体制が、今回のトランプ関税によって一気に表面化した形です。
損失額は純利益の4分の1
この関税による直接的な影響として、2025年第2四半期の決算では、日本円換算で約1750億円の減損損失を計上することとなりました。これは前年の通期純利益4400億円の約4分の1に相当し、経営にとって非常に大きな打撃となりました。
北米市場の販売戦略に大打撃
この関税の影響でボルボは米国市場での販売戦略を大きく見直す必要に迫られました。利益率が確保できない状況では、従来の輸出モデルでは立ち行かず、現地生産へのシフトや価格戦略の再設計など、多方面での対応が求められています。
他社との対応力の差が顕著に
同じく関税の影響を受けたトヨタなどの他メーカーは、北米に強固な生産拠点と柔軟な物流網を有しており、影響を最小限に抑える対策を迅速に講じています。一方ボルボは、中国偏重の生産体制をすぐに切り替えることが難しく、対応力の差が鮮明に浮き彫りになりました。
大量リストラによる構造改革
経営判断としてのリストラ
経営陣は急激な収益悪化に対応するため、従業員の約3000人規模のリストラを断行しました。これは単なるコスト削減策ではなく、企業構造の再設計を伴う抜本的な対策として位置づけられています。
米国内での影響の大きさ
米国内だけでも約800人が対象となり、特にペンシルベニア、バージニア、メリーランドの3つの工場に勤務していた従業員の多くが影響を受けました。これらの工場では主に商用車の製造を担っており、今回の人員整理により稼働率や生産効率の見直しが迫られています。
生産体制の見直しと統合
一部の生産ラインは統廃合され、より効率的な工場運用を目指す動きも加速しています。とくにEX90やXC60といった主力車種の生産を担うサウスカロライナ州チャールストン工場への生産集中が進められ、拠点の再構築によって固定費の圧縮と生産コントロールの最適化が図られています。
リストラの波及的影響
今回のリストラは社内だけでなく、地域経済や下請け企業にも深刻な影響を及ぼしました。地元雇用の喪失により一部地域では経済活動が低下し、ボルボに対する批判も高まっています。
社員の士気とブランド価値への影響
急激なリストラは、残された従業員の士気や企業文化にも負の影響を与えかねません。とくに“北欧流の温かい企業文化”を期待していた層にとって、今回の対応は大きな裏切りと映っており、ブランドイメージのさらなる悪化につながる可能性も否定できません。
米国での生産強化計画
生産拠点の選定と戦略的背景
トランプ関税の影響に対抗するため、ボルボは米国現地での生産体制の強化に踏み切りました。特に注目されているのが、サウスカロライナ州チャールストンに位置する乗用車専用の工場です。この工場は元々、EX90およびXC60といった主力モデルの生産拠点として設計されており、インフラ整備も進んでいる戦略的な拠点です。
年間15万台の生産能力
チャールストン工場は年間最大で15万台の生産能力を誇り、北米市場における販売拡大を支える重要な役割を担います。この規模であれば、現地ニーズに対応したモデルを柔軟に供給することが可能であり、関税による価格上昇を抑える実効性も期待できます。
投資負担を抑えた拡大策
新たに大型工場を建設するのではなく、既存のチャールストン工場を活用することで、巨額の初期投資を回避。これにより短期間での生産切り替えが可能となり、ボルボとしては迅速なコスト対策を図ることができました。限られた経営資源を効率的に活用する戦略と言えるでしょう。
生産拠点の集中とリスク分散の課題
ただし、チャールストン工場一極集中によるリスクも無視できません。自然災害や地政学的影響などに対する脆弱性が指摘されており、中長期的にはさらなる分散型生産体制の構築が求められる可能性があります。
今後の展望と課題
今後、ボルボがアメリカでの生産をどこまで拡大できるかが鍵となります。特にEVの普及が加速する中で、現地での部品調達やバッテリー供給体制の整備も並行して進める必要があります。現時点ではチャールストン工場が唯一の柱となっているため、持続可能な現地生産戦略への進化が求められます。
それでも拭えない“スウェーデン車”としての信頼低下
見た目と中身のギャップがブランドを蝕む
ボルボは今なお「北欧デザイン」を前面に打ち出し、上質なスカンジナビアンスタイルの内外装で一定の評価を維持しています。

しかし、消費者の間では「スウェーデン車に見えるが、中身は完全に中国企業」との声も増えており、表面と実態の乖離がブランドイメージを静かに侵食しています。
国産車との差別化が曖昧に
これまでのボルボは「輸入プレミアムブランド」として日本車や韓国車とは異なる価値を提供してきましたが、信頼性・品質・供給体制において目立った優位性を示せない現状では、競合との差別化が弱まっているのも事実です。これにより、輸入車を選ぶ理由そのものが薄れているという指摘もあります。
情報感度の高いユーザー層からの離反
SNSや自動車レビューサイトなどでは「ボルボ=中国のEVメーカー」という誤解も含めたネガティブなコメントが飛び交っており、とくに情報感度の高いユーザー層からの信頼を失いつつあります。見た目は魅力的でも、実態を知れば選ばないという傾向が強まっています。
信頼回復に必要なステップとは
ブランドの信頼を取り戻すには、透明性のある経営方針の発信や、実際の製品品質・安全性能で他社と明確な差別化を打ち出す必要があります。スウェーデン発祥の価値観に立ち返り、品質と信頼を再構築する姿勢がなければ、かつてのような“北欧プレミアム”としての信頼は回復できない可能性が高いでしょう。
Volvo(ボルボ)の企業戦略の弱さとブランド力の失墜
トヨタも関税の影響を受けている
トランプ関税の影響が避けられなかったトヨタ
トヨタはアメリカ市場において強力なプレゼンスを持っており、ボルボと同様にトランプ前大統領が再導入した対中25%関税の影響を無視することはできません。特に、トヨタは北米での販売台数が全体の約25%を占めるなど、アメリカ市場依存度が高いため、今回の関税政策による影響は深刻です。
想定される損失額の大きさ
2025年だけで1800億円以上の関税関連コスト増を見込んでおり、この額はトヨタにとっても看過できない水準です。営業利益は前年比で約21%減の予想となっており、一時的とはいえ業績に明確な打撃が表れています。
それでも全体戦略には影響を与えず
しかしながら、トヨタはこのような大規模なコスト増にも関わらず、戦略的な方向性を大きく変えることなく、電動化戦略や北米での現地生産強化を継続しています。関税が与える影響を一過性の問題として捉え、中長期的な視点で企業体力を維持・拡大しようとする姿勢がうかがえます。
輸出依存から現地生産強化への転換
これまで日本からの輸出に頼っていた構造を見直し、アメリカ国内での現地生産を一層強化する方向へ舵を切っています。この柔軟な対応力が、同じく関税の影響を受けたボルボとの明確な差を生む一因となっているのです。
それでも営業利益率は約10%を維持
高い収益性の維持が示す底力
注目すべきは、これだけの損失を抱えつつも、トヨタが依然として営業利益率約10%を確保している点です。この数値は、グローバルな自動車業界のなかでもトップレベルであり、平均的なメーカーが5%以下にとどまる中で、群を抜いた健全性と強靭な企業体質を誇示しています。
収益構造の多様化が奏功
この高い営業利益率を実現できている背景には、トヨタが長年かけて築いてきた収益構造の多様化があります。日本国内だけでなく、北米・欧州・東南アジアといった各市場に均等に製品を供給しており、特定地域に依存しないことで外部環境の変動に強いポートフォリオを実現しています。
車種ラインアップの厚み
トヨタは軽自動車から高級SUV、ハイブリッド車、燃料電池車まで幅広い製品群を展開しており、景気変動や消費者ニーズの変化にも柔軟に対応可能です。単一商品に依存せず、全方位的な商品戦略が高い収益率の支えとなっています。
原価管理と規模の経済
さらに、トヨタの原価管理と生産効率の高さは業界随一です。グローバルに展開する巨大な生産ネットワークを活かし、部品共通化や現地調達比率の向上によってスケールメリットを最大化しています。これにより、厳しい市況下でも利益を出せる体制が整っています。
コスト削減と現場改善の徹底
現場主導の改善文化
トヨタの強みのひとつに、「現場で問題を見つけ、現場で解決する」という“現場力”の文化があります。生産ラインで働く社員一人ひとりが改善提案を行い、効率化や無駄の排除を徹底しています。これにより、小さな改善の積み重ねが全社的なコスト削減に直結する構造が確立されています。
ジャストインタイム方式の徹底運用
トヨタ生産方式の代表格でもある「ジャストインタイム」は、必要なものを必要なときに必要なだけ供給するという仕組みで、過剰在庫を防ぎ、在庫コストを最小限に抑えることができます。この仕組みは原材料費が高騰する局面でもトヨタの収益性を支える要因となっています。
グローバル調達と部品共通化
サプライチェーン最適化の一環として、部品のグローバル調達と共通化も推進。例えば、同一のプラットフォームを複数の車種で共有することで開発コストと製造コストを大幅に削減しています。これにより、品質を保ちながらも価格競争力を高めることが可能となっています。
工場の再編とデジタル化
トヨタは地域や需要の変化に合わせて工場の役割を柔軟に再配置しており、特に北米や東南アジアでの生産能力拡大に注力しています。加えて、工場内におけるIoT技術やAIを用いたライン監視、品質管理も強化されており、デジタル化による無駄削減も進行中です。
単なるコストカットではない「攻めの改善」
トヨタの改善は単なるコストカットではなく、競争力強化のための“攻めの改善”です。たとえば、新型車両の設計段階から部品点数の削減や組立工数の簡略化を意識するなど、コスト削減と商品力向上の両立を実現しています。
アメリカ国内への巨額投資
バッテリー生産への本格投資
トヨタは電動化の中核を担うバッテリー生産のために、ノースカロライナ州に大型工場を建設しました。総投資額は約1930億円にのぼり、この工場ではハイブリッド車およびEVに搭載するバッテリーパックの現地生産が行われています。これにより、部品供給の安定化とコスト削減を同時に実現しています。
EV専用工場の新設と量産体制の強化
加えて、ケンタッキー州では新型EVの専用製造ライン構築に向けて約1800億円を投じています。この工場では3列シートSUVなど北米市場のニーズに合わせた車両が生産される予定であり、現地需要を反映した車種展開と生産効率の最大化を目指しています。
地産地消モデルによる関税対策
これらの投資は、トランプ関税に対する直接的な対抗策でもあります。日本からの輸出ではなくアメリカ国内での生産・供給体制を強化することで、関税の影響を回避するとともに、物流コストも大幅に削減できる点がトヨタの戦略的優位性となっています。
雇用創出と地域経済への貢献
また、これらのプロジェクトは現地雇用の創出にも貢献しており、ノースカロライナ州およびケンタッキー州の州政府とも連携して補助金や税制優遇措置を活用しています。現地コミュニティとの関係性強化という点でも、長期的にプラスの効果をもたらす見通しです。
持続可能な成長への投資姿勢
これらの巨額投資は、短期的なコスト負担ではなく、長期的な収益基盤を築くための戦略的布石です。トヨタは環境性能・コスト競争力・現地適合性の3軸で北米市場を攻略するための下地を着実に整えており、その姿勢が競合との明確な差を生み出しています。
リストラを回避する経営方針
経営理念に根付く“人を大切にする文化”
トヨタは「人こそが企業の財産である」という哲学のもと、原則としてリストラを行わない方針を掲げています。この考え方は、創業期から続く「社員は家族」という思想に基づいており、経営判断においても一貫して“人を守る”ことを優先しています。
苦い過去の教訓が方針を形成
1950年、トヨタは経営難に陥り、企業として初めて大規模なリストラを経験しました。この出来事が創業家や経営陣に大きなトラウマとして残り、「二度と社員を守れない経営はしない」との強い決意が今なお息づいています。
組織の一体感と士気向上につながる
このような姿勢があるからこそ、従業員の忠誠心や士気は非常に高く、現場からの改善提案や挑戦的な業務推進が生まれやすい土壌が育まれています。結果として、企業全体のパフォーマンス向上やブランド価値の維持にもつながっています。
危機の中でも雇用を守る姿勢
トランプ関税や半導体不足といった厳しい外部環境にあっても、トヨタは極端な人員整理を行うことなく、業務の再配置や社内教育の強化を通じて雇用を維持しようと努めています。これにより、社会的信用の向上にも寄与しています。
長期的視野での信頼形成
人を大切にする経営は、短期的なコスト削減こそ見込めませんが、長期的に見れば企業の信頼性と持続可能な成長を支える根幹となります。この方針が、トヨタを世界有数の企業へと押し上げた要因のひとつと言えるでしょう。
ブランドへの信頼と継続的な成長戦略
顧客との信頼関係を最優先
トヨタは、短期的な利益を追求するよりも、価格転嫁を避けることでユーザーの信頼を維持することを重視しています。原材料や物流コストの上昇があっても、可能な限り販売価格を据え置く姿勢は、長年築き上げてきたブランドイメージの維持につながっています。
次世代技術への継続的な投資
トヨタは、EV(電気自動車)・水素燃料電池車・ソフトウェア定義車両(SDV)など、次世代モビリティ技術への研究開発を継続的に行っています。将来的な主力市場での競争力を見据えた開発が進行中であり、単なる流行ではなく、持続可能な革新を目指しているのが特徴です。
中長期視点での成長戦略
収益が減少してもリストラや開発投資の削減を選ばず、むしろ中長期的に競争優位を構築するための布石を打っているのがトヨタの強みです。これは株主・取引先・ユーザーの三方にとって安定性をもたらす経営判断といえます。
ブランド強化と多角化の両立
またトヨタは、LEXUSブランドの高級路線を進めつつ、ダイハツやトヨタ車体を通じて低価格帯もカバーしており、あらゆる層のニーズに対応する「多角化経営」が継続的な成長の基盤となっています。このバランスの良さが、トヨタに対する信頼感をさらに高めています。
ボルボとの明確な差異
対照的にボルボは、短期的な損失カバーのためにリストラや生産縮小に追い込まれており、中長期的な投資やブランド強化への余力が乏しいのが現状です。
まとめ
ボルボは現在、経営の根幹を揺るがすほどの重大局面を迎えています。中国資本傘下によるブランドイメージの崩壊、EV戦略のつまずき、そしてトランプ関税による市場喪失といった要素が複合的に重なり、かつての“北欧プレミアムブランド”としての輝きは失われつつあります。対して、トヨタは同様の外部環境の変化にも柔軟かつ大胆に対応し、長期的視野での成長戦略を堅持しており、両社の差はますます広がる一方です。
結論として、今後ボルボの車を購入することを検討するのであれば、ブランドイメージだけでなく、経営の安定性、将来性、サービス体制までも慎重に見極める必要があるでしょう。