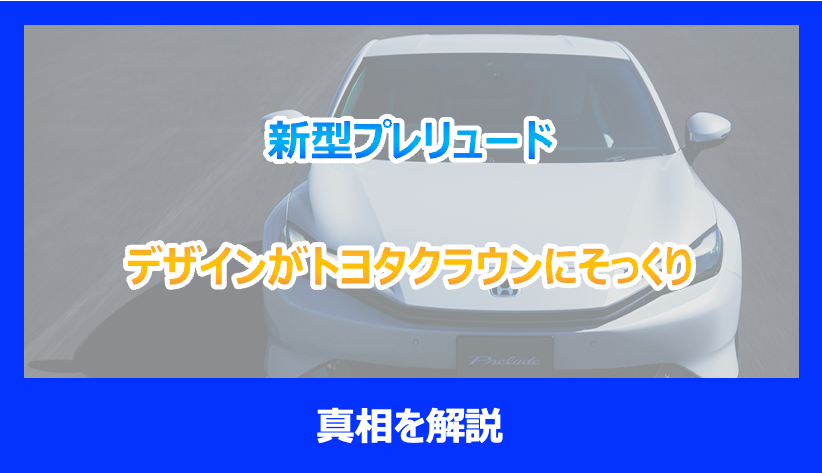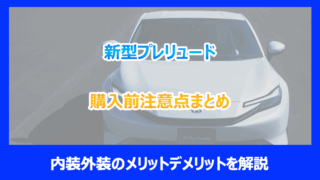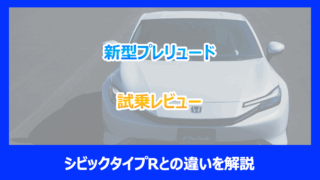モータージャーナリスト兼コラムニストの二階堂仁です。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、満を持して復活したホンダの新型プレリュードのデザインが、トヨタのクラウンやプリウスに「そっくりだ」と感じ、その理由が気になっているのではないでしょうか。

引用 : HONDA HP (https://global.honda/jp/news/2025/4250731.html)
私も往年のプレリュードファンの一人として、そして実際に購入検討のためにディーラーへ足を運んだ者として、最初にその姿を見たときの既視感と複雑な気持ちはよくわかります。
しかし、なぜ現代のスペシャリティクーペは、メーカーの垣根を越えて似たようなデザインに行き着くのでしょうか。
この記事を読み終える頃には、単なる「模倣」ではない、デザインの裏に隠された現代の車作りの必然性と、新型プレリュードが本当に目指したものは何なのか、その疑問が解決しているはずです。
記事のポイント
- 空力性能とデザイントレンドの収斂進化
- ホンダとトヨタのデザイン言語の歴史と共通点
- 歴代プレリュードから受け継がれる先進性のDNA
- デザインの奥にある新型プレリュード独自の魅力
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

新型プレリュードのデザインはなぜトヨタ車に似ているのか?
22年の時を経て、ジャパンモビリティショー2023で鮮烈な復活を遂げた新型プレリュード。 往年のファンが待ち望んだその復活劇は、大きな歓声と共に、ある種の「ざわめき」をもって迎えられました。

引用 : HONDA HP (https://global.honda/jp/news/2025/4250731.html)
そのざわめきの正体こそ、「デザインがトヨタのクラウンやプリウスにそっくりではないか?」という声です。 ここでは、まずその類似性の具体的な指摘と、なぜそうしたデザインに行き着いたのか、考えられる複数の理由を深く掘り下げていきます。
SNSで拡散された「そっくり説」の具体例

引用 : トヨタHP (https://www.subaru.jp/forester)
コンセプトモデルが公開されるや否や、SNSや自動車関連の掲示板では、新型プレリュードとトヨタのクラウンシリーズ(特にクロスオーバーやスポーツ)、そして5代目プリウスを並べた比較画像が数多く投稿されました。
- 「フロントマスクが完全にクラウンのハンマーヘッド」
- 「サイドの流麗なシルエットがプリウスと瓜二つ」
- 「ホンダらしさはどこへ行ったのか?」
- 「エンブレムを隠したらどっちの車か分からない」
このような声が、好意的な意見に混じって数多く見受けられたのが事実です。 特に、フロントのヘッドライトを繋ぐように水平に伸びるデイタイムランニングランプと、ボンネットを低く見せることで生まれるシャープな顔つきは、近年のトヨタ車が積極的に採用する「ハンマーヘッド」デザインを強く想起させます。 また、Aピラーからルーフ、そしてリアエンドへと滑らかに続くクーペシルエットも、空力性能を追求したプリウスのモノフォルムシルエットと共通する部分が多いと指摘されています。
理由1:空力性能を突き詰めた結果の「収斂進化」
まず最大の理由として挙げられるのが、現代の自動車開発、特にハイブリッド車やEVにおいて最重要視される「空力性能」の追求です。 生物の世界で、異なる種が同じような環境に適応するために似たような姿形に進化する現象を「収斂進化(しゅうれんしんか)」と呼びますが、現代の自動車デザインにも同じことが言えます。
燃費(電費)を1kmでも伸ばすためには、空気抵抗を極限まで減らす必要があります。 その結果、
- ボディ全体を滑らかな流線形にする
- 不要な凹凸をなくし、面をシームレスに繋ぐ
- フロントの開口部を最小限にする
- Aピラーの角度を寝かせ、ルーフを低く滑らかに後方へ流す
といったアプローチが最適解となり、どのメーカーが開発しても必然的に似たようなフォルムに行き着くのです。 新型プレリュードは「アンリミテッド・グライダー」というコンセプトを掲げ、その名の通りグライダーのような滑空感を走りのテーマにしています。 このコンセプトを実現するためには、優れた空力性能が不可欠であり、その結果として生まれたフォルムが、同じく空力を突き詰めたクラウンやプリウスと似てしまうのは、ある意味で技術的な必然と言えるでしょう。
理由2:世界的なデザイントレンド「シームレス&クリーン」
空力性能と密接に関連しますが、現在の自動車デザイントレンドとして「シームレス&クリーン」という大きな潮流があります。 これは、過度な装飾や複雑なキャラクターラインを排し、シンプルでクリーン、かつ先進的な印象を与えるデザイン手法です。 テスラに代表されるEVメーカーがこのトレンドを牽引し、今や多くのメーカーが追随しています。
ヘッドライトやグリル、ドアハンドルといった各パーツをボディと一体化させ、あたかも一つの塊から削り出したかのような滑らかな造形は、まさにこのトレンドの現れです。 新型プレリュードの水平基調の薄型ヘッドライトや、凹凸の少ないボディサイドの造形は、このトレンドを色濃く反映しています。 そして、トヨタのクラウンやプリウスもまた、同じトレンドの中でデザインされているため、結果として両者のデザイン言語には共通の文法が生まれるのです。
理由3:法規制(歩行者保護)がもたらすフロントデザインの制約
見落とされがちですが、自動車デザインは法規制とも密接に関わっています。 特に近年厳格化しているのが「歩行者保護性能」に関する規制です。 万が一の衝突時に歩行者へのダメージを軽減するため、ボンネットやフロントバンパーには一定の衝撃吸収スペースと、突起物の少ない構造が求められます。
これにより、かつてのように鋭く尖ったノーズや、切り立ったフロントグリルを持つデザインは採用しにくくなりました。 ボンネットを高く、厚みを持たせる必要があり、その中でいかにスポーティでシャープな印象を与えるか。 各社が知恵を絞った結果、ヘッドライトを薄くシャープにし、バンパーの上部を前方に突き出すようなデザイン(ハンマーヘッドもその一種)が、規制をクリアしつつスポーティさを表現する一つの解として広まっているのです。 これもまた、メーカーの垣根を越えてフロントマスクが似てくる一因となっています。
ホンダとトヨタ、それぞれのデザイン哲学を徹底比較
「トレンドや規制でデザインが似るのは分かった。でも、それでもホンダらしさが感じられない」という声も聞こえてきそうです。 では、本当に新型プレリュードは「ホンダらしさ」を失ってしまったのでしょうか。 それを検証するために、両社のデザイン哲学の変遷と、新型プレリュードに込められたホンダならではのこだわりを探っていきましょう。

引用 : トヨタHP (https://www.subaru.jp/forester)
トヨタのデザイン言語「キーンルック」から「ハンマーヘッド」へ
近年のトヨタのデザインを語る上で欠かせないのが、2012年頃から導入された「キーンルック」です。 これは、鋭い目つきをイメージさせるヘッドライトと、逆台形の大きなロアグリル(アンダープライオリティ)を組み合わせた、情熱的でアグレッシブな表情を特徴としていました。 好き嫌いは分かれましたが、一目でトヨタ車と分かる強烈な個性とブランドイメージの構築に成功しました。
そして現在、そのキーンルックはさらに進化し、「ハンマーヘッド」と呼ばれるデザインへと移行しています。 シュモクザメをモチーフにしたこのデザインは、薄く横一文字に伸びるヘッドランプと、立体的なバンパー造形が特徴で、より先進的でスポーティな印象を与えます。 クラウンシリーズやプリウス、bZシリーズなどに採用され、新世代トヨタの顔として定着しつつあります。
ホンダのデザイン言語「ソリッド・ウイング・フェイス」とその進化
一方、ホンダも「ソリッド・ウイング・フェイス」というデザイン言語を長年採用してきました。 これは、Hマークを中心に翼を広げたようなグリルとヘッドライトが一体となったデザインで、N-BOXからシビック、アコードに至るまで多くの車種で展開され、ホンダのファミリーフェイスを形成してきました。
しかし、近年のホンダは、この象徴的なデザイン言語から少し距離を置き、よりシンプルでクリーンな方向へと舵を切っています。 新型アコードやWR-Vなどに見られるように、水平基調を重視し、過度な装飾を排した落ち着きのあるデザインが主流となりつつあります。 これは、ユーザーの生活に寄り添い、長く愛される普遍的な価値を追求する、ホンダの新たなデザインフィロソフィーの現れと言えるでしょう。
新型プレリュードは本当に「ホンダらしさ」を失ったのか?
こうした流れの中で登場した新型プレリュードのデザインは、特定のデザイン言語に固執するのではなく、「スペシャリティクーペ」という車の本質的な魅力を現代の技術とトレンドで再解釈した結果と見るべきです。 確かにフロントマスクはトヨタのハンマーヘッドと似ていますが、細部を見ればホンダならではのこだわりが随所に見て取れます。
例えば、グリルレスに見えるフロントマスクは、かつてのNSXやS2000といったホンダのピュアスポーツを彷彿とさせます。 また、ボディサイドに走る一本のシャープなキャラクターラインや、リアフェンダーの力強い膨らみは、ロー&ワイドなスタンスを強調し、内に秘めたパワーを感じさせます。 これらは、走りの良さをデザインで表現するという、ホンダが長年培ってきたスポーツカー作りの文法に則ったものです。
開発者が語る新型プレリュードのデザインコンセプト「アンリミテッド・グライダー」
新型プレリュードの開発コンセプトは「アンリミテッド・グライダー」。 これは、どこまでも滑空していくグライダーのような、解放感と意のままの走りを目指したものです。 このコンセプトが、デザインにも色濃く反映されています。
不要なものを削ぎ落とした滑らかなボディは、まさに空気の流れを受け流すグライダーの翼そのものです。 そして、インテリアもまた、水平基調のインパネがもたらす広々とした視界と、ドライバーが運転に集中できるシンプルな操作系によって、この「グライダー」の世界観を表現しています。 表面的な形の類似性だけでなく、この根底にあるコンセプトを理解することで、新型プレリュードのデザインが持つ本来の価値が見えてくるはずです。
歴代プレリュードのDNAは新型に受け継がれているか?
新型プレリュードを語る上で、輝かしい歴史を持つ歴代モデルの存在は欠かせません。 「デートカー」という言葉を生み出し、常に時代の最先端を行く技術とデザインで若者を魅了してきたプレリュード。 そのDNAは、22年の時を経て復活した新型に、どのように受け継がれているのでしょうか。

引用 : HONDA HP (https://global.honda/jp/news/2025/4250731.html)
デートカーの代名詞、初代から5代目までの軌跡
| 世代 | 販売期間 | 特徴的なキャッチコピー・装備 | 時代の背景 |
|---|---|---|---|
| 初代 (SN) | 1978-1982 | 「FFスーパーボルテージ」電動サンルーフ | スペシャリティカー市場の黎明期 |
| 2代目 (AB/BA1) | 1982-1987 | 「FFスーパー・リトラ」リトラクタブルライト | “ハイテク”がもてはやされた時代 |
| 3代目 (BA4/5/7) | 1987-1991 | 「FFスーパー・コーナリングマシン」4WS | バブル景気絶頂期、”デートカー”の地位を確立 |
| 4代目 (BA8/9/BB1/4) | 1991-1996 | 「未体験リッド。」先進的なワイド&ローデザイン | バブル崩壊後、より個性的なデザインへ |
| 5代目 (BB5/6/7/8) | 1996-2001 | 「the Right one.」原点回帰のスクエアなデザイン | スポーツクーペ市場の縮小期 |
このように、歴代プレリュードは常に「時代を先取りする先進性」を武器に、若者文化をリードしてきました。 日本初の電動サンルーフ(初代)、画期的な4輪操舵システム「4WS」(3代目)、VTECエンジンと先進的なインパネデザイン(4代目)など、その時代の最先端技術を惜しみなく投入してきたのです。
新型プレリュードが継承した「時代を先駆ける先進性」
では、新型プレリュードに受け継がれた「先進性」とは何でしょうか。 それは、パワートレインにあります。 ベースとなったシビックTYPE Rがピュアなガソリンターボエンジンとマニュアルトランスミッションを組み合わせるのに対し、新型プレリュードは2.0Lのe:HEV(ハイブリッド)を採用しました。
そして、そこにホンダ初採用となる新技術「Sプラスシフト」を搭載。 これは、モーター駆動でありながら、あたかも8段変速のトランスミッションが存在するかのようなダイレクトなシフトフィールと、エンジン回転数とシンクロしたサウンドを演出する技術です。 電動化が進む現代において、「操る楽しさ」をいかに提供するか。 この問いに対するホンダの一つの答えが、このe:HEVとSプラスシフトの組み合わせなのです。 これは、かつて4WSで世界を驚かせたように、電動時代の新たな「走る喜び」を提案する、紛れもないプレリュードのDNAと言えるでしょう。
時代と共に変化した「デートカー」の定義
かつてプレリュードが「デートカー」と呼ばれた時代、その意味するところは「助手席の彼女をスマートにもてなすための車」でした。 豪華な内装、サンルーフ、良い音質のオーディオなどがその象徴でした。
しかし、現代における「デートカー」の定義は大きく変化しました。 単なる豪華さや快適さだけでなく、環境性能への配慮、先進的な安全運転支援システム、そして何より、二人で過ごす時間を豊かにする「体験価値」が求められます。 新型プレリュードは、静かで滑らかなハイブリッド走行による快適な移動空間と、いざとなればスポーティな走りを楽しめる二面性を両立しています。 これは、現代の価値観にアップデートされた新しい「デートカー」の形であり、これもまたプレリュードの伝統を継承していると言えます。
デザインだけじゃない!新型プレリュードの知られざる魅力と実力
ここまでデザインの類似性とその背景を中心に解説してきましたが、新型プレリュードの魅力はもちろんそれだけではありません。 ジャーナリストとして、そして一人のクルマ好きとして、実際にディーラーで見積もりを取り、調べ上げたからこそ分かった、その実力と購入前に知っておくべき注意点を包み隠さずお伝えします。

引用 : HONDA HP (https://global.honda/jp/news/2025/4250731.html)
基本情報とスペックを再確認
まずは、公表されている基本情報を整理しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| グレード | 1グレードのみ |
| 駆動方式 | FF(前輪駆動) |
| 車両本体価格 | 6,179,800円 |
| パワートレイン | 2.0L 2モーターハイブリッドシステム (e:HEV) |
| トランスミッション | 電気式無段変速機(Sプラスシフト搭載) |
| ベース車両 | シビックTYPE R |
| 主要装備 | アダプティブダンパーシステム、Brembo製フロントブレーキ、19インチアルミホイール |
| ナビゲーション | Google搭載ナビゲーションシステム(標準装備) |
価格は600万円オーバーと、決して安価ではありません。 しかし、その中身を見れば、価格に見合うだけの、あるいはそれ以上の価値が秘められていることがわかります。
ベースはシビックTYPE R!走りの実力は本物か?
新型プレリュードの骨格は、世界最速FFの呼び声も高い「シビックTYPE R」がベースとなっています。 これは、走りのポテンシャルが極めて高いことを意味します。 TYPE Rの高剛性ボディをベースに、プレリュード専用のセッティングが施された足回り。 路面状況に応じて減衰力を四輪独立で制御するアダプティブダンパーシステムと、絶対的な制動力を誇るBrembo製ブレーキキャリパーが標準装備されていることからも、ホンダの本気度が伺えます。 ハイブリッドカーでありながら、その本質は紛れもないピュアスポーツ。 ワインディングを駆け抜ける楽しさは、同価格帯のどんな車にも負けないレベルにあると断言できます。
【辛口評価】購入前に知るべき7つの注意点
しかし、手放しで賞賛するだけではジャーナリスト失格です。 実際に私が購入を検討する上で「これは…」と感じた、見過ごせない注意点が7つあります。
- そもそも簡単には買えない可能性 初期ロットは2,000台、月販目標はわずか300台と、生産台数が極めて少ないです。 販売会社によっては抽選販売となり、長年のホンダオーナーでなければ購入権すら得られない可能性があります。 一見客がディーラーに飛び込んでも「申し訳ありません…」となるケースが予想されます。
- ボディカラーと内装色の組み合わせが限定的 シックなブラックの内装を選びたい場合、ボディカラーは「ムーンリットホワイトパール」一択となります。 他のボディカラーでは、ブルーとホワイト(またはブラック)の組み合わせしか選べません。 この仕様には、正直がっかりしました。
- パワーシート、シートベンチレーションが非搭載 600万円を超える価格帯のスペシャリティクーペでありながら、運転席・助手席ともにパワーシートの設定がありません。 また、夏場の快適装備であるシートベンチレーションも非搭載。 快適性を重視する方にとっては大きなマイナスポイントです。
- サンルーフ(パノラマルーフ)の設定なし 歴代プレリュードの多くに設定され、「デートカー」の象徴でもあったサンルーフが、オプションですら用意されていません。 開放感を求めるユーザーにとっては残念なポイントです。
- マルチビューカメラ(360°カメラ)の設定なし ベースのシビック同様、車両を俯瞰で確認できるマルチビューカメラの設定がありません。 もはや軽自動車のN-BOXにすら搭載されている装備だけに、このクラスの車両にないのは疑問が残ります。
- 後部座席はあくまで緊急用 これはクーペの宿命ですが、後部座席は大人が長時間快適に過ごせる空間ではありません。 基本的には2人乗り+荷物置き場として割り切る必要があります。
- Googleナビの仕様(高速道路のパネル表示) 標準装備のGoogleナビは常に最新の地図情報が手に入り便利ですが、従来の国産ナビに標準的だった高速道路のジャンクションやサービスエリアを案内する「パネル表示」が現時点では実装されていない可能性が高いです。 今後のアップデートに期待したいところです。
これらの注意点を許容できるかどうかが、購入の大きな判断基準になるでしょう。
まとめ
今回は、新型プレリュードのデザインがなぜトヨタ車に似ているのか、その真相を多角的に掘り下げてきました。
結論として、その類似性は単なる模倣ではなく、「空力性能の追求」「世界的なデザイントレンド」「法規制」という、現代の自動車開発における必然が生み出した「収斂進化」の結果であると言えます。
その上で、新型プレリュードには、シビックTYPE R譲りの卓越した走行性能、e:HEVと「Sプラスシフト」がもたらす電動時代の新たな操る楽しさ、そして歴代モデルから受け継がれる「時代の先を行く先進性」という、紛れもないホンダ独自の価値と哲学が宿っています。
確かに、内外装のカラーバリエーションや快適装備には物足りなさを感じる部分もあります。 しかし、それらを補って余りある走りの魅力と、22年ぶりに伝説の名を復活させたホンダの情熱がこの一台には詰まっています。
デザインの第一印象だけで判断するのではなく、その背景にある物語と、秘められた実力を知ることで、新型プレリュードは全く違う輝きを放ち始めます。 もしあなたが、他とは違う、走りの本質を追求した特別な一台を求めているのであれば、この現代に蘇ったグライダーは、最高のパートナーになってくれるはずです。 まずはディーラーに問い合わせて、その存在に触れてみることを強くお勧めします。 ただし、買えるかどうかは、また別の話ですが…。