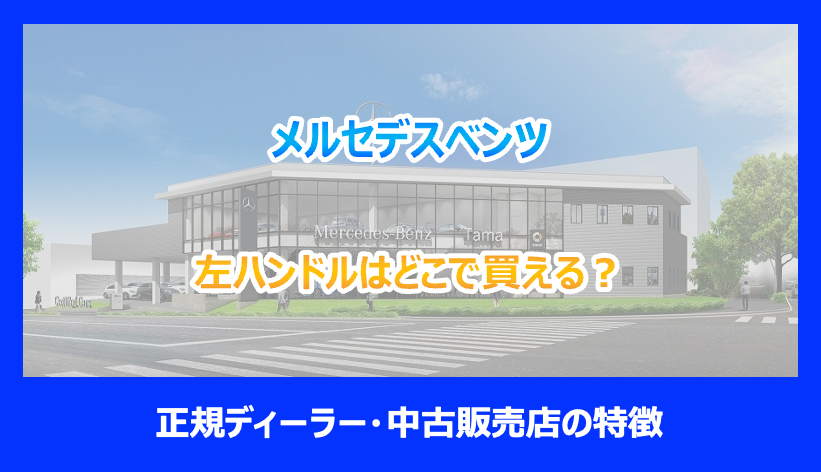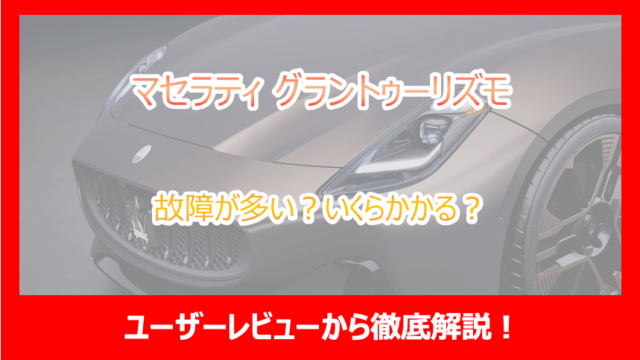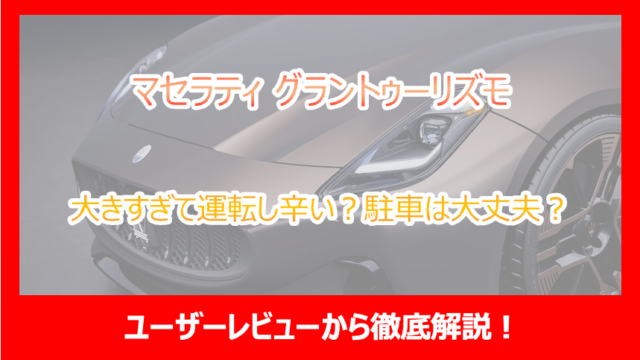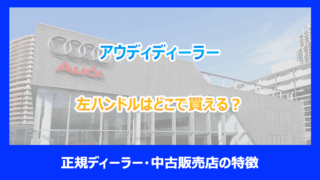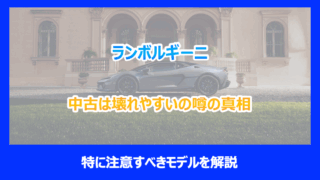モータージャーナリスト兼コラムニストの二階堂仁です。今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、憧れのメルセデス・ベンツ、それも通な左ハンドル車をどこで手に入れられるか、気になっていると思います。私も実際に左ハンドルのメルセデスを複数台所有してきたので、その魅力と探し方のポイントが気になる気持ちはよくわかります。

引用 : メルセデスベンツ日本 (https://media.mercedes-benz.jp/)
かつては輸入車の象徴だった左ハンドルも、今ではすっかり見かけなくなりました。だからこそ「どこで探せばいいのか」「買ってから後悔しないか」といった不安を感じますよね。
この記事を読み終える頃には、あなたに最適な左ハンドルベンツの購入方法という疑問が解決しているはずです。
記事のポイント
- 正規ディーラーでの左ハンドル車の現状
- 中古車市場での探し方の具体的コツ
- 並行輸入というもう一つの選択肢
- 所有者が語る左ハンドルのリアルな実態
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

メルセデス・ベンツの左ハンドル車の日本での現状
「ベンツといえば左ハンドル」というイメージをお持ちの方も多いでしょう。しかし、街中で見かけるメルセデスは、そのほとんどが右ハンドルです。まずは、なぜ左ハンドルが減ってしまったのか、そして今、新車で手に入れることは可能なのか、その現状から詳しく解説していきましょう。

Lexury Motors Journal イメージ
そもそもなぜ左ハンドルが減ったのか?
かつて、輸入車、特にドイツ車は左ハンドルが主流でした。これにはいくつかの理由があります。一つは、生産国であるドイツが右側通行・左ハンドルであるため、そのままの仕様で日本に輸入していたという単純な理由。そしてもう一つは、当時の日本の法規やインフラが、右ハンドル仕様の輸入を難しくしていたという背景があります。
しかし、1990年代後半から状況は大きく変わります。メルセデス・ベンツ日本が、日本の交通事情に合わせた右ハンドル仕様の導入に本格的に力を入れ始めたのです。背景には、「左側通行の日本では右ハンドルの方が安全で運転しやすい」という顧客の声がありました。また、ペダルレイアウトの違和感解消や、ウインカーレバーの位置を日本車と同じ右側に変更するなど、日本人ドライバーのための細やかな配慮がなされたことも、右ハンドル化を加速させました。
結果として、販売台数は飛躍的に伸び、メルセデス・ベンツは輸入車販売台数トップの常連となりました。ユーザーの利便性と安全性を追求した結果、市場のニーズは右ハンドルにシフトし、左ハンドルは徐々に特別な選択肢となっていったのです。私自身、右ハンドルの完成度が年々高まっていることは認めざるを得ません。しかし、それでも左ハンドルにしかない魅力があるのも事実です。
正規ディーラーで左ハンドルは買えるのか?
結論から言うと、現在、メルセデス・ベンツの正規ディーラーで新車の左ハンドルを注文することは、一部の特殊なモデルを除き、原則としてできません。
2024年現在、日本で正規販売されるメルセデス・ベンツのラインナップは、ほぼすべてが右ハンドル仕様となっています。これは、セダン、SUV、コンパクトカーといった主要モデルすべてに共通しています。かつてはSクラスやSLクラスといった上級モデルで左ハンドルの選択が可能でしたが、それらも現行モデルでは右ハンドルのみの設定です。
メルセデス・ベンツ日本の公式見解としても、「日本の交通環境における安全性と操作性を最優先し、右ハンドル仕様を標準としています」とされています。これはメーカーとして、日本の顧客に最適な製品を提供するという責任の表れと言えるでしょう。
AMGモデルなら左ハンドルがあるって本当?
「AMGのような高性能モデルなら左ハンドルが選べるのでは?」という期待を持つ方も多いでしょう。確かに、過去にはAMGモデルの一部、特にエンジン性能を極限まで高めたハイパフォーマンスモデルにおいて、左ハンドルの設定が存在しました。これは、エンジンの補器類などの配置の都合上、右ハンドル化が物理的に困難だった、あるいは左ハンドルの方が最適なレイアウトだった、という技術的な理由によるものです。
しかし、これも過去の話。現在のメルセデスAMGモデルも、GT 4ドアクーペや新型SLなどを含め、そのほとんどが右ハンドル専用設計となっています。技術の進歩により、高性能なエンジンを搭載しつつも、右ハンドルレイアウトを成立させることが可能になったのです。
唯一の例外として、限定車や特別仕様車としてごく稀に左ハンドルモデルが導入される可能性はゼロではありませんが、極めて稀なケースであり、一般の顧客が自由に選べる選択肢ではないのが現状です。
Gクラスに左ハンドルが設定されていた理由
多くのモデルが右ハンドル化される中で、比較的最近まで左ハンドルの設定が残っていたのがGクラスです。特に「G400d」や限定モデルなどで左ハンドルが選択可能でした。これにはGクラスが持つ特殊な背景が関係しています。
Gクラスはもともと軍用車両として開発された経緯を持ち、その基本設計は長年にわたって大きく変更されてきませんでした。堅牢性を最優先した設計思想のため、右ハンドル化への対応が他のモデルに比べて遅れた、あるいは左ハンドルを基本とする設計のほうが合理的だったという側面があります。
また、「ゲレンデヴァーゲン」としての伝統とキャラクターを重視するファンからの強い要望があったことも、左ハンドル設定が維持された理由の一つでしょう。しかし、そのGクラスでさえ、現行モデルでは右ハンドルが標準となり、左ハンドルは特別な存在となっています。
なぜ正規ディーラーは右ハンドルを推奨するのか
正規ディーラーが右ハンドルを標準とする理由は、単に日本の法律が左側通行だから、というだけではありません。そこには、安全性、操作性、そしてリセールバリューという3つの大きな柱があります。
- 安全性: 左側通行の日本では、対向車とのすれ違いや右折時の視界確保において、右ハンドルが圧倒的に有利です。特に、見通しの悪い交差点での右折や、前方の大型車を追い越す際の対向車線の確認は、左ハンドルでは死角が大きくなりがちです。
- 操作性: 駐車場の発券機、ドライブスルー、料金所の支払いなど、日本のインフラは右ハンドルを前提に設計されています。左ハンドルでは、これらの施設を利用するたびに不便を感じることになります。
- リセールバリュー: 中古車市場においては、圧倒的多数のユーザーが右ハンドルを求めます。そのため、左ハンドル車は右ハンドル車に比べて需要が限定され、買取価格や下取り価格が低くなる傾向にあります。ディーラーとしても、将来的な顧客の資産価値を考慮し、リセールバリューの高い右ハンドルを推奨するのは自然な流れです。
新車で左ハンドルを手に入れるための「裏技」?
正規ディーラーで新車の左ハンドルが買えないとなると、諦めるしかないのでしょうか。いいえ、方法はあります。それが**「並行輸入」**という選択肢です。
並行輸入とは、正規代理店(メルセデス・ベンツ日本)を通さずに、海外のディーラーなどから直接車両を買い付け、日本に輸入する方法です。この方法であれば、本国ドイツやアメリカなどで販売されている左ハンドル仕様の新車を日本で手に入れることが可能です。
ただし、並行輸入にはメリットだけでなく、デメリットやリスクも伴います。次の章では、中古車という選択肢と合わせて、この並行輸入についても詳しく掘り下げていきましょう。
左ハンドルベンツの具体的な探し方と購入先の比較
新車での入手が困難である以上、左ハンドルのメルセデス・ベンツを探す主戦場は中古車市場となります。しかし、ひとくちに中古車といっても、その購入先は様々です。ここでは、それぞれの購入先の特徴と、並行輸入という選択肢について、メリット・デメリットを比較しながら詳しく解説します。

引用 : BMW HP (https://motoren-glanz.bmw.jp/ja)
選択肢①:認定中古車で探すメリット・デメリット
メルセデス・ベンツの正規ディーラーが運営する「認定中古車(サーティファイドカー)」は、質の高い中古車を探す上で最も安心感のある選択肢です。
メリット
- 品質への絶大な信頼感: 最大100項目にも及ぶ厳しい点検・整備を経て商品化されるため、車両のコンディションは極めて良好です。修復歴のある車両は原則として扱われません。
- 充実した保証: 年式や走行距離に応じた手厚い保証が付帯します。多くのプランでは、購入後1年間または2年間、走行距離無制限でエンジンやトランスミッションといった主要機関だけでなく、電装品なども保証対象となります。
- 全国ネットワークでのサポート: 万が一のトラブルの際も、全国のメルセデス・ベンツ正規サービス工場で保証修理やメンテナンスを受けられます。旅先での故障など、いざという時の安心感は計り知れません。
- 車両履歴の透明性: 正規ディーラーでメンテナンスされてきた車両が多く、整備記録がしっかりと残っているため、過去の使われ方が明確で安心です。
デメリット
- 左ハンドル車の流通量が極めて少ない: 認定中古車の母体となるのは、正規ディーラーで販売・下取りされた車両です。もともと右ハンドルの販売が大多数であるため、左ハンドル車が認定中古車として市場に出てくることは非常に稀です。
- 価格が高め: 徹底した整備と手厚い保証が提供される分、一般的な中古車販売店に比べて車両価格は高めに設定されています。
- モデルや選択肢が限定される: 流通量が少ないため、希望の車種、年式、ボディカラー、装備の左ハンドル車に巡り会える確率は非常に低くなります。
選択肢②:一般の中古車販売店で探すメリット・デメリット
カーセンサーやグーネットといった中古車情報サイトで検索すると、数多くの中古車販売店がヒットします。ここは、最も現実的に左ハンドルベンツを探せる場所と言えるでしょう。
メリット
- 圧倒的な選択肢の多さ: 全国の中古車販売店の在庫を検索できるため、認定中古車とは比較にならないほど多くの左ハンドルベンツが見つかります。SクラスやGクラスといった人気モデルから、少しマニアックな旧モデルまで、選択肢は豊富です。
- 価格帯の広さ: 高年式の極上車から、手頃な価格の過走行車まで、予算に応じて様々な車両を選べます。価格競争も起きやすいため、掘り出し物が見つかる可能性もあります。
- 希少なモデルに出会える可能性: 正規輸入されなかったグレードや、カスタムされた車両など、個性的な一台に出会えるチャンスがあります。
デメリット
- 品質の見極めが不可欠: 車両の品質はまさに玉石混淆です。販売店によって整備レベルや品質基準は大きく異なります。修復歴やメーター改ざんといったリスクもゼロではないため、購入者自身が車両の状態を厳しくチェックする必要があります。
- 保証内容が店によって様々: 保証が付帯する場合でも、その範囲や期間は販売店ごとに大きく異なります。保証対象がエンジンなどの主要機関のみで、期間も3ヶ月程度と短いケースも少なくありません。保証内容の確認は必須です。
- アフターサービスの不安: 購入後のメンテナンスや修理をどこに依頼するか、考えておく必要があります。特に専門店以外で購入した場合、複雑な故障に対応できないケースもあります。
選択肢③:専門店・並行輸入業者に依頼するメリット・デメリット
メルセデス・ベンツの特定のモデルや、輸入車全般を専門に扱う販売店、あるいは並行輸入を代行してくれる業者に依頼する方法です。よりマニアックで、こだわりの一台を求めるなら、この選択肢が浮上します。
メリット
- 専門知識とノウハウ: 特定の車種に関する深い知識を持っているため、そのモデルの弱点やメンテナンスのポイントを熟知しています。購入後の相談にも的確に対応してくれるでしょう。
- 希少なモデルの入手可能性: 日本未導入のグレードや、本国仕様の最新モデルなど、正規ルートでは手に入らない特別な一台をオーダーできます。新車の左ハンドルを手に入れる最も現実的な方法です。
- 独自のネットワーク: 国内外に独自の仕入れルートを持っているため、市場には出回らない希少な車両を見つけてくれる可能性があります。
デメリット
- 費用が高額になる傾向: 車両価格に加えて、輸入にかかる諸経費(輸送費、関税、ガス検査費用など)や代行手数料が上乗せされるため、総額はかなり高額になります。
- 正規ディーラーの保証は受けられない: 並行輸入車は、メルセデス・ベンツ日本の保証対象外となります。リコールなどが発生した場合も、原則として正規ディーラーでの無償修理は受けられません。
- 納期がかかる: 海外から車両を取り寄せるため、発注から納車まで数ヶ月単位の時間がかかります。
- 業者の信頼性の見極めが重要: 残念ながら、すべての業者が誠実とは限りません。実績や評判を十分に調査し、信頼できるパートナーを選ぶことが成功の鍵となります。
【表で比較】購入先ごとの特徴まとめ
| 項目 | 認定中古車 | 一般の中古車販売店 | 専門店・並行輸入業者 |
|---|---|---|---|
| 品質 | ◎ (非常に高い) | △ (玉石混淆) | 〇 (専門分野は高い) |
| 価格 | 高い | 幅広い | 非常に高い |
| 保証 | ◎ (手厚い) | △ (店舗による) | ✕ (原則なし・独自保証) |
| 選択肢の多さ | ✕ (非常に少ない) | ◎ (非常に多い) | 〇 (希少車に強い) |
| 納期の速さ | 〇 (在庫車のみ) | 〇 (在庫車のみ) | ✕ (時間がかかる) |
| 安心感 | ◎ (最高レベル) | △ (自己責任) | △ (業者次第) |
中古車選びで失敗しないためのチェックポイント
どの購入先を選ぶにせよ、中古車である以上、現車の確認は絶対に欠かせません。特に左ハンドルという趣味性の高い車を選ぶ際は、以下のポイントを重点的にチェックしてください。
- 第三者機関の鑑定書: カーセンサー認定やGoo鑑定など、第三者機関による車両状態評価書があれば、客観的なコンディションを把握できます。
- 整備記録簿(メンテナンスノート): これまでの点検・整備の履歴が記されています。「いつ、どこで、どんな整備をされたか」がわかる、車の戸籍謄本のようなものです。記録がしっかり残っている車は、大切に扱われてきた証拠です。
- 試乗: 必ず試乗させてもらいましょう。エンジンやトランスミッションのフィーリング、異音の有無、エアコンの効き具合など、実際に運転しないとわからないことは数多くあります。特に左ハンドル車は、運転席からの視界やペダルレイアウトに違和感がないか、自分の体で確かめることが重要です。
- 内外装のチェック: 塗装の状態、パネルの隙間、内装の傷や汚れ、スイッチ類の動作などを細かく確認します。不自然な点があれば、修復歴を疑うきっかけにもなります。
所有者が語る!私がこの買い方を選んだ理由
ちなみに私自身は、認定中古車と専門店の両方で購入した経験があります。初めての左ハンドルベンツ(W211のEクラスでした)は、やはり品質と保証への安心感を最優先し、認定中古車で探しました。幸運にも程度の良い一台に巡り会えましたが、見つけるまでには半年近くかかりました。
一方、現在所有しているクラシックなモデル(R107のSL)は、特定の年式と仕様にこだわったため、このモデルを専門に扱うショップに依頼して探してもらいました。時間はかかりましたが、専門店の知識とネットワークのおかげで、納得のいく一台を手に入れることができました。どちらの経験も、何を最優先するかによって最適な購入先は変わるということを教えてくれました。
左ハンドル車の維持費は高い?
「左ハンドルは部品代や修理代が高いのでは?」という心配もあるでしょう。結論から言うと、**「右ハンドルと大きく変わらないが、注意点はいくつかある」**となります。
- 部品代: エンジンや足回りといった主要部品の多くは、左右ハンドルで共通です。ステアリング機構やダッシュボード周りなど、専用部品も存在しますが、極端に高価ということはありません。
- 修理工場: 正規ディーラーでは、並行輸入車や年式の古い車の修理を断られるケースがあります。そのため、輸入車に精通した信頼できる整備工場を見つけておくことが非常に重要です。専門店で購入すれば、そのまま主治医として任せられるのが大きなメリットです。
- 自動車保険: 基本的に、左ハンドルだからといって保険料が割高になることはありません。ただし、並行輸入車の場合、車両保険の加入を断られたり、車両料率クラスが不明確で割高な設定になったりすることがあるため、事前に保険代理店に確認することをおすすめします。
それでも乗りたい!メルセデスベンツの左ハンドルの魅力と現実
ここまで、左ハンドルベンツの探し方や注意点を解説してきましたが、そもそもなぜ、不便さを乗り越えてまで左ハンドルを選ぶのでしょうか。この章では、所有者だからこそ語れる左ハンドルの魅力と、避けては通れない現実について、包み隠さずお話しします。

Lexury Motors Journal イメージ
私が左ハンドルに乗り続ける理由
私が左ハンドルに惹かれる理由は、一言で言えば**「設計思想への共感」**です。車は、その生まれた国の交通環境で最も性能を発揮できるように設計されています。メルセデス・ベンツは、ドイツのアウトバーンを疾走するために生まれました。そのオリジナルな設計思想を、ダイレクトに感じられるのが左ハンドルなのです。
ペダルレイアウトの自然さ、ステアリングフィール、そして運転席から見える景色。すべてが設計者の意図通りであるという感覚は、車との一体感を高めてくれます。もちろん、ステータス性や、少しだけ通に見えるというミーハーな気持ちも否定はしません。しかし根底にあるのは、この車が持つ本来の姿を尊重したいという、作り手へのリスペクトなのです。
左ハンドル車のメリットを徹底解説
実用面でも、左ハンドルには意外なメリットが存在します。
- 左折時の視界の良さ: 左側通行の日本では、交差点での左折時に歩行者や自転車を巻き込むリスクが常にあります。左ハンドルは、運転席が歩道側に近いため、左後方からの自転車や、横断歩道を渡る歩行者の確認が非常にしやすいのです。これは安全運転において大きなアドバンテージです。
- 路肩に寄せやすい: 狭い道でのすれ違いや駐車の際、左側の縁石や壁との距離感が掴みやすく、ギリギリまで寄せることができます。
- ペダルレイアウトが自然: 右ハンドル車の場合、タイヤハウスの出っ張りの影響で、アクセルペダルが左にオフセットしている車種が多くあります。左ハンドル車にはこの問題がなく、自然な体勢でペダル操作ができます。長距離運転での疲労軽減にも繋がります。
- デザインの整合性: ワイパーの停止位置やボンネットのエアインテークなど、エクステリアデザインの細部が左ハンドルを前提に作られているため、見た目のバランスが美しいと感じる人も多いです。
左ハンドル車のデメリットと対策
もちろん、デメリットも数多く存在します。しかし、そのほとんどは慣れと工夫でカバーできます。
- 右折時の視界不良: これが最大の難関です。対向車が見えにくいため、前の車に続いて右折するか、対向車が完全に途切れるまで待つのが基本です。無理な右折は絶対に禁物です。
- 追い越し: 片側一車線の道で前の車を追い越すのは至難の業です。助手席の同乗者に確認してもらうか、よほど見通しの良い直線でない限りは、諦めるのが賢明です。
- 駐車場・料金所・ドライブスルー:
- 対策① ETCの活用: 高速道路の料金所は、ETCがあれば何の問題もありません。
- 対策② 精算機の事前確認: 商業施設などの駐車場では、右側にも精算機がある場所や、クレジットカードが使える精算機を選ぶようにしましょう。
- 対策③ 秘密兵器「マジックハンド」: 駐車券を取る際に非常に役立ちます。常備している左ハンドルオーナーは意外と多いです。
- 対策④ 割り切って降りる: どうしても届かない場合は、素直に車から降りて操作するのが最も確実で安全です。
- 歩道側の乗降: 助手席の人が歩道側から乗り降りするため、ドアを開ける際は後方から来る自転車や歩行者に十分注意する必要があります。
初めての左ハンドル、運転のコツと慣れるまでの期間
初めて左ハンドルを運転する際は、誰しも戸惑うものです。しかし、いくつかのコツを意識すれば、すぐに慣れることができます。
- 車両感覚を掴む: まずは広い場所で、左側の車幅感覚を徹底的に体に覚えさせましょう。左のタイヤがどのあたりを通っているかを意識することが重要です。
- 目線を遠くに: 近くばかり見ていると、無意識に車が左右に寄ってしまいます。常に少し先のセンターラインを見るように意識すると、車は自然とレーンの中央を走るようになります。
- ウインカーとワイパーの間違い: 輸入車の多くは、ウインカーレバーが左、ワイパーレバーが右についています。最初のうちは、曲がるたびにワイパーを動かしてしまう「左ハンドルあるある」を経験するでしょう。こればかりは慣れるしかありません。
- 慣れるまでの期間: 個人差はありますが、毎日乗れば1週間、週末だけの運転でも1ヶ月もすれば、ほとんど違和感なく運転できるようになるはずです。焦らず、安全な場所で少しずつ慣れていきましょう。
今、狙い目の左ハンドルベンツはこれだ!
最後に、ジャーナリストとして、そして一人のオーナーとして、今もし左ハンドルのメルセデスを探すなら、という視点でおすすめのモデルをいくつかご紹介します。
- W221 Sクラス (2005-2013): この世代のSクラスは、現代的な快適装備と、古き良きメルセデスの重厚な乗り味を両立した最後のモデルと言えるかもしれません。中古車価格もこなれてきており、左ハンドルの個体も比較的見つけやすいです。特に後期型のS550は、信頼性も高く狙い目です。
- R129 SLクラス (1989-2001): 80年代の設計ながら、色褪せないモダンなデザインと堅牢な作りが魅力です。ネオクラシックカーとして世界的に人気が高まっており、資産価値も期待できます。左ハンドルの個体が多く、メンテナンス情報も豊富なので、入門用クラシックとしても最適です。
- W463 Gクラス (前期・中期): 現行モデルでは希少となった左ハンドルですが、少し前の年式のGクラスなら、まだまだ多くの個体が見つかります。特にディーゼルモデルのG350dは、経済性と走りを両立した名車です。武骨なスタイルは、左ハンドルで乗ってこそ、その本質が味わえるかもしれません。
これらのモデルは、中古車市場で探すことになりますが、その価値は十分にあります。時間をかけて、信頼できるパートナーと共に、最高の一台を見つけてください。
まとめ
メルセデス・ベンツの左ハンドル車を手に入れる道は、決して平坦ではありません。正規ディーラーでの新車購入はほぼ不可能となり、その探求は中古車市場がメインステージとなります。そこには、認定中古車という安心の道もあれば、無数の選択肢が広がる一般の中古車販売店、そしてマニアックな夢を叶える専門店や並行輸入という道も存在します。
それぞれの道にはメリットとデメリットがあり、あなたの価値観やライフスタイル、そして車に何を求めるかによって、選ぶべき道は変わってきます。
左ハンドルは、確かに駐車場や料金所での不便さが伴います。しかし、それを補って余りある「オリジナルを所有する喜び」や「意のままに操る一体感」、そして「安全運転への貢献」といった魅力があるのもまた事実です。
この記事が、あなたの「左ハンドルベンツに乗りたい」という情熱を、具体的な一歩へと変えるきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。情報を武器に、じっくりと時間をかけて、あなただけの最高の一台を見つけ出してください。その先には、きっと素晴らしいメルセデスライフが待っているはずです。