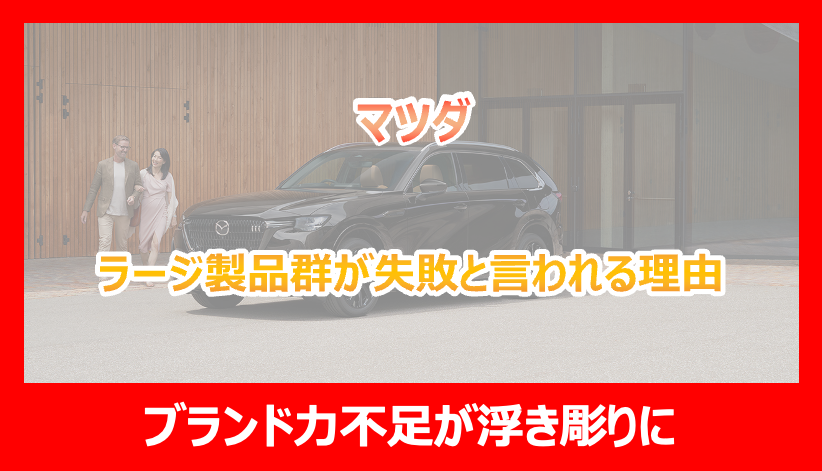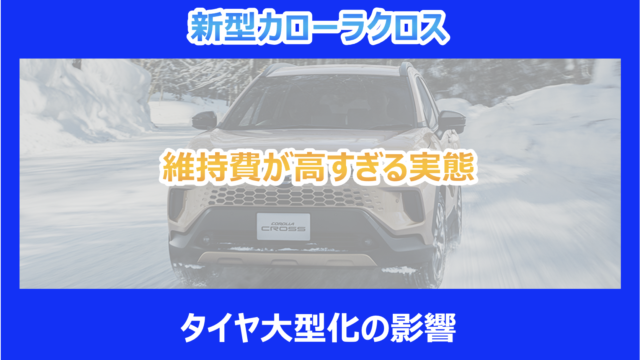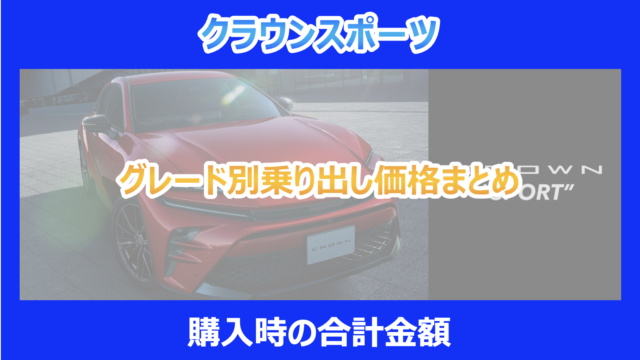モータージャーナリスト兼コラムニストの二階堂仁です。今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、鳴り物入りで登場したマツダのラージ商品群、特にCX-60やCX-80の昨今の評判について、本当のところはどうなのか気になっているのではないでしょうか。

引用 : MAZDA HP (https://www.mazda.co.jp/cars/cx-80/feature/)
私も実際に両方の車両を所有するオーナーとして、その高い志と、市場の厳しい評価とのギャップを肌で感じており、皆様が抱く期待と不安が入り混じる気持ちはよくわかります。
なぜあれほど期待された車が「失敗」とまで言われてしまうのか。この記事を読み終える頃には、マツダのラージ商品群が直面している課題の本質と、その背景にある理由についての疑問が解決しているはずです。
記事のポイント
- 多発した初期不良と信頼性の低下
- ブランドイメージと乖離した強気な価格設定
- 新開発技術の熟成不足が招いた乗り心地の問題
- ユーザーの期待と現実のギャップが生んだ失望
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

マツダのラージ商品群が「失敗」と評価される根本的な理由
満を持して投入されたマツダの新世代ラージ商品群。FR(後輪駆動)プラットフォームに、新開発の直列6気筒エンジンという、クルマ好きの心をくすぐるパッケージングで大きな期待を集めました。
しかし、その船出は決して順風満帆とは言えず、市場からは厳しい声が多く聞かれます。なぜ、このような状況に陥ってしまったのでしょうか。ここでは、その根本的な理由を多角的に深掘りしていきます。

引用 : MAZDA HP (https://www.mazda.co.jp/cars/cx-80/feature/)
CX-60の躓き – 発売初期に多発したリコールと不具合
ラージ商品群の先鋒として登場したCX-60でしたが、そのスタートは非常に厳しいものでした。最大の要因は、発売初期に頻発した不具合と、それに伴う大規模なリコールです。
繰り返されたリコールの詳細
CX-60は発売から1年あまりで、複数回にわたる大規模なリコールを届け出ています。特に深刻だったのは、新開発の8速オートマチックトランスミッション(8AT)や、走行安定性に関わる重要な部分での不具合でした。
- 動力伝達装置の不具合: トランスミッション内部の部品の強度不足により、最悪の場合走行不能に陥る可能性。
- 操舵安定性の問題: アッパーアームの取り付けボルトの緩みにより、走行安定性が損なわれる恐れ。
- ハイブリッドシステムの制御プログラム: エンジンが始動しない、走行中にエンストするなどのトラブル。
これらの不具合は、いずれも車の根幹に関わる部分であり、ユーザーに与えた不安は計り知れません。新開発のコンポーネントを多く採用した意欲作であることは理解できるものの、市場投入前の熟成が不足していたと言わざるを得ない状況でした。このCX-60初期モデルの躓きが、「マツダの新しい車は様子見した方が良い」というネガティブなイメージを植え付け、後続のCX-80の販売にも暗い影を落とすことになったのです。
価格設定の誤算 – プレミアムブランドへの性急な移行
ラージ商品群が市場に受け入れられにくいもう一つの大きな理由は、その強気な価格設定にあります。マツダがプレミアムブランドへの脱却を目指す戦略車であることは理解できますが、多くのユーザーが抱く「マツダブランド」のイメージと価格が乖離してしまったのです。
競合車種との価格比較
特に3列シートSUVであるCX-80の価格は、多くの議論を呼びました。以下に、CX-80と主な競合車種の価格帯を比較してみましょう。
| 車種名 | エンジン種類 | 駆動方式 | 価格帯(税込) |
|---|---|---|---|
| マツダ CX-80 | 直6ディーゼル/PHEV | FR/4WD | 約530万円~約650万円 |
| レクサス NX | 2.5L HV/PHEV | FF/4WD | 約520万円~約750万円 |
| レクサス RX | 2.4Lターボ/2.5L HV/PHEV | FF/4WD | 約660万円~約900万円 |
| トヨタ ハリアー | 2.5L HV/PHEV | FF/4WD | 約410万円~約620万円 |
| トヨタ クラウン クロスオーバー | 2.5L HV/2.4LターボHV | 4WD | 約440万円~約670万円 |
| BMW X3 | 2.0Lガソリン/ディーゼル | 4WD | 約740万円~ |
| メルセデス・ベンツ GLC | 2.0LディーゼルHV | 4WD | 約820万円~ |
※価格はグレードにより変動します。
この表からもわかる通り、CX-80の価格帯は、国産のライバルであるハリアーやクラウンを大きく上回り、プレミアムブランドの代表格であるレクサスNXと直接競合し、RXのエントリーグレードにも手が届く領域にあります。さらに少し予算を足せば、BMWやメルセデス・ベンツといった輸入プレミアムブランドのSUVも視野に入ってきます。
この状況でユーザーが自問するのは、「トヨタやレクサスではなく、あえてマツダに600万円を支払う価値はあるのか?」という点です。マツダがこれまで築き上げてきた「良質な車を、比較的手の届きやすい価格で提供する」というブランドイメージが、この高価格帯への挑戦の足かせとなってしまった格好です。
ブランドイメージとの乖離 – 「コスパの良いマツダ」からの脱却は成功したか
前述の価格設定の問題とも密接に関わりますが、マツダが目指す「プレミアム」と、市場がマツダに求める価値観の間に、大きなズレが生じています。
これまでのマツダは、「魂動デザイン」という一貫した美しいデザインフィロソフィーと、「人馬一体」に代表される運転の楽しさ、そして欧州車のような質の高い内外装を、国産車ならではの信頼性と価格で実現してきたことが高く評価されてきました。つまり、多くのユーザーにとってマツダは「非常にコストパフォーマンスの高いブランド」だったのです。
しかし、ラージ商品群では、その「コストパフォーマンス」という最大の武器を自ら手放し、レクサスや輸入車がひしめくプレミアム市場に真っ向から勝負を挑みました。この戦略自体は企業の成長のために必要な挑戦であったかもしれません。しかし、ブランドイメージというものは一朝一夕に変わるものではありません。長年かけて築き上げた「コスパの良いマツダ」という強力なイメージを、ユーザー自身がアップデートできないまま、価格だけがプレミアム領域に達してしまった。このギャップが、購入を躊躇させる大きな要因となっているのです。

引用 : MAZDA HP (https://www.mazda.co.jp/cars/cx-80/feature/)
新技術の熟成不足 – 8速ATと足回りの課題
価格に見合うだけの圧倒的な商品力があれば、ブランドイメージとの乖離も克服できたかもしれません。しかし、CX-60の初期モデルでは、乗り心地や運転フィールといった、マツダが最も得意としてきたはずの部分で多くの課題が指摘されました。
ギクシャク感が指摘された8速AT
新開発のトルクコンバーターレス8速ATは、ダイレクト感のある走りを実現するために採用された意欲的な技術です。しかし、特に市街地での低速走行時や、ストップ&ゴーを繰り返すような場面で、変速ショックやギクシャクとした挙動が多くのジャーナリストやオーナーから報告されました。MTのようなダイレクト感を狙ったとのことですが、多くのユーザーがSUVに求めるスムーズさや快適性とは相容れない部分があり、評価が大きく分かれる結果となりました。
硬すぎると評された足回り
FRプラットフォームの採用により、高い運動性能が期待されましたが、CX-60の乗り心地は、特に後席で「硬すぎる」「突き上げが酷い」という厳しい評価が目立ちました。路面の凹凸を正直に拾いすぎてしまい、ファミリーカーとしての快適性に疑問符がつくレベルだったのです。これもまた、マツダが標榜する「上質な走り」とはかけ離れたものでした。
幸いにも、これらの問題点は年次改良によって大幅に改善されています。しかし、一度市場に広まってしまったネガティブな評判を覆すのは容易なことではありません。
販売台数が示す厳しい現実 – CX-60とCX-80の販売状況
市場の評価は、正直に販売台数という数字に表れます。CX-60は発売当初こそ好調な受注を記録したものの、前述したような問題が表面化するにつれて徐々に失速。月間の販売目標台数を下回る状況が続いています。
そして、その影響を真正面から受けたのがCX-80です。CX-60で失われた信頼を回復できないまま、さらに高価格帯で市場に投入されたCX-80の販売は、極めて厳しいスタートを切らざるを得ませんでした。本来であれば、人気の3列シートSUV市場で主役の一角を担うはずでしたが、現状ではその存在感を発揮できているとは言い難い状況です。
マーケティング戦略の疑問 – 誰に届けたい車だったのか
ラージ商品群の苦戦を見ていると、そのマーケティング戦略にも疑問符がつきます。この車は、一体誰に向けて作られ、どのようにしてその価値を伝えようとしたのでしょうか。
長年のマツダファンからすれば、価格が高くなりすぎてしまい、乗り心地も期待とは違いました。一方で、レクサスや輸入車からの乗り換えを狙う新規のプレミアム層から見れば、リコールの多さやブランド力不足がネックとなり、決定打に欠けます。結果として、従来のファン層と新規のターゲット層、そのどちらの心も掴みきれない「帯に短し襷に長し」な状態に陥ってしまったのではないでしょうか。
中古車市場への影響 – リセールバリューへの懸念
新車販売の不振は、必然的に中古車市場、つまりリセールバリューにも影響を及ぼします。初期不良のイメージや、新車販売の苦戦は、将来的な買取価格への不安に繋がり、これもまた新車購入を躊躇させる一因となります。特に高価格帯の車を購入する層にとって、リセールバリューは重要な判断基準の一つです。この点においても、ラージ商品群はライバルに対して不利な状況に置かれています。
競合の存在 – 強力なライバルたちとの比較
最後に、ラージ商品群が置かれている市場環境の厳しさにも触れておく必要があります。彼らが戦うDセグメント以上のSUV市場は、国内外のメーカーが最も力を入れる激戦区です。
トヨタには絶対的な王者ハリアーや、革新的なスタイルで話題のクラウンシリーズがあります。レクサスはNX、RXという強力な布陣でプレミアム市場を盤石に固めています。輸入車勢も、BMW X3、メルセデス・ベンツ GLC、アウディ Q5など、ブランド力、走行性能、先進性のすべてにおいてハイレベルなモデルが揃っています。
このような強力なライバルたちの中で、価格的なアドバンテージを失い、品質への信頼も揺らいでしまったマツダのラージ商品群が、明確な「選ぶ理由」をユーザーに提示できているかというと、残念ながら疑問が残るというのが現状の評価でしょう。
それでもマツダのラージ商品群に価値はあるのか?
ここまで厳しい側面を中心にレビューしてきましたが、ではマツダのラージ商品群は全く価値のない車なのでしょうか?答えは明確に「ノー」です。むしろ、これらの車にしかない唯一無二の魅力があるからこそ、市場の厳しい評価がもどかしく感じられるのです。私自身もオーナーとして、その価値を日々実感しています。

引用 : MAZDA HP (https://www.mazda.co.jp/cars/cx-60/feature/)
唯一無二の存在価値 – 直列6気筒エンジンという選択
現代において、国内メーカーが全く新しい直列6気筒エンジン、それもディーゼルとガソリンの両方を開発し、市場に投入したという事実は、奇跡と言っても過言ではありません。特に3.3L直列6気筒ディーゼルターボエンジン「SKYACTIV-D 3.3」は、この車の最大の魅力です。
アクセルを踏み込んだ瞬間から湧き上がる、分厚く滑らかなトルク。どこまでもスムーズに吹け上がる回転フィール。そして、大排気量ならではの余裕が生み出す静粛性。この感覚は、4気筒エンジンでは決して味わうことのできない、まさに「官能的」なものです。長距離を移動すればするほど、その疲れにくさと心地よさが際立ちます。このエンジンを味わうためだけに、この車を選ぶ価値は十分にあると断言できます。
デザインと質感の進化 – マツダが貫く「魂動デザイン」の深化
デザインに関しても、マツダのこだわりは健在です。ラージ商品群では、従来の魂動デザインをさらに深化させ、FRらしいロングノーズで伸びやかなプロポーションと、引き算の美学によるシンプルで力強い面構成を実現しています。その佇まいは、同価格帯の国産SUVとは一線を画す、凛とした気品と色気を感じさせます。
そして、特筆すべきはインテリアの質感です。特に上位グレードに採用されている、メープルウッドやナッパレザー、そして日本の伝統的な織物技術を取り入れたファブリックなど、本物の素材を惜しみなく使った内装は、もはや欧州プレミアムブランドのそれを凌駕するほどのレベルに達しています。ドアを開け、乗り込むたびに所有する喜びを感じさせてくれる、非常に満足度の高い空間です。
改良による進化 – 年次改良で初期の不満は解消されたか
重要な点として、CX-60の初期モデルで指摘された乗り心地やトランスミッションの問題は、その後の年次改良で劇的に改善されています。
大幅に改善された足回り
2023年秋の大幅改良では、サスペンションのセッティングが見直され、特にリアの突き上げ感が大幅に緩和されました。これにより、初期モデルとは別物と言えるほど、しなやかで快適な乗り心地を実現しています。
洗練された制御プログラム
トランスミッションの制御プログラムもアップデートが繰り返され、初期にみられたギクシャク感は大幅に解消されています。スムーズさとダイレクト感を両立した、より洗練された変速フィールへと進化を遂げました。
もしラージ商品群を検討しているのであれば、必ず改良後のモデル、いわゆる「年次改良モデル」に試乗することを強くお勧めします。初期モデルの評判だけで判断してしまうのは、あまりにもったいないことです。
CX-80の真価 – CX-60の反省は活かされているか
CX-80は、CX-60のデビューから約1年半後に登場したモデルです。当然ながら、その開発にはCX-60で得られた知見や反省点が活かされています。乗り心地に関しては、CX-60の改良後のサスペンションをベースに、さらにホイールベースの長さを活かした、より重厚で落ち着きのある乗り味に仕立てられています。3列目シートの実用性も高く、大人でも短距離なら十分に座れる空間が確保されており、ファミリーSUVとしての完成度は非常に高いと言えます。価格の問題は依然として残りますが、車そのものの出来栄えは、CX-60から着実に進化していると評価できます。
PHEVという選択肢 – 環境性能と走りの両立
ラージ商品群には、もう一つの柱としてプラグインハイブリッド(PHEV)モデルが用意されています。2.5Lのガソリンエンジンに大容量バッテリーとモーターを組み合わせたこのシステムは、約70km以上のEV走行を可能にし、日常的な移動のほとんどを電気だけで賄うことができます。それでいて、システム最高出力は323馬力にも達し、アクセルを踏み込めば胸のすくような力強い加速を披露します。環境性能とパワフルな走りを両立したPHEVは、この車のもう一つの魅力的な選択肢です。
どんな人におすすめできるか – ラージ商品群が輝くステージ
では、マツダのラージ商品群は、どのような人に響く車なのでしょうか。
- 運転が好きで、他とは違う一台を求める人: FRプラットフォームと直列6気筒エンジンがもたらす唯一無二の運転フィールに価値を見出せる方。
- 内外装のデザインや質感にこだわる人: 欧州車にも引けを取らない、美しく上質な内外装デザインに所有欲を満たされたい方。
- 長距離移動が多い人: 特にディーゼルモデルの、余裕ある走りと優れた燃費性能は、高速道路を多用する方に最適です。
- 新しい技術や挑戦を応援したい人: 困難な道だとわかっていても、プレミアムブランドへの挑戦を続けるマツダの心意気に共感する方。
リセールバリューや万人受けする快適性よりも、自らの感性に響くかどうかを大切にする。そんなクルマ選びの価値観を持つ人にとって、ラージ商品群はかけがえのない相棒となり得るでしょう。
マツダの挑戦をどう評価するか – プレミアムブランドへの道
今回のラージ商品群の投入は、短期的に見れば多くの課題を露呈し、「失敗」と評されても仕方ない部分があったのは事実です。しかし、自動車業界が100年に一度の大変革期にある中で、マツダが独自の価値で生き残りを図るためには、避けては通れない道だったのかもしれません。この挑戦から得られた経験は、必ずや次の世代の車づくりに活かされるはずです。一人のクルマ好きとして、そしてマツダ車のオーナーとして、その挑戦が実を結ぶ日を心から期待しています。
まとめ
今回のレビューでは、マツダのラージ商品群がなぜ「失敗」と言われてしまうのか、その理由を深掘りしてきました。
失敗と評される主な理由:
- 信頼性の問題: CX-60の初期モデルで多発したリコールが、ブランドイメージに大きな傷をつけた。
- 価格の問題: ユーザーが抱くマツダのイメージと、実際の価格設定に大きな乖離があった。
- 熟成不足の問題: 新開発のトランスミッションや足回りが、マツダに期待される「上質な走り」を提供できなかった(初期モデルにおいて)。
- ブランド戦略の問題: プレミアム市場への移行を急ぐあまり、既存のファン層と新規のターゲット層の双方を満足させることができなかった。
しかし、その一方で、ラージ商品群には他のどの車にもない、確かな魅力が存在することも事実です。
ラージ商品群ならではの価値:
- 唯一無二のパワートレイン: 滑らかで力強い直列6気筒エンジンは、この車最大の美点。
- 卓越したデザインと質感: 内外装のクオリティは、同価格帯のライバルを凌駕する部分も多い。
- 継続的な進化: 年次改良により、初期モデルの欠点は大幅に改善されている。
結論として、マツダのラージ商品群は、多くの人に手放しでおすすめできる優等生な車ではないかもしれません。しかし、その尖った個性と魅力は、間違いなく一部のユーザーの心に深く突き刺さるものです。もしあなたが少しでもこの車に興味を持ったのであれば、必ず「改良後のモデル」に試乗してみてください。ネット上の評判だけではわからない、この車が持つ本当の価値に触れることができるはずです。マツダの野心的な挑戦が、あなたの感性と共鳴するかどうか。ぜひ、ご自身の五感で確かめてみることをお勧めします。