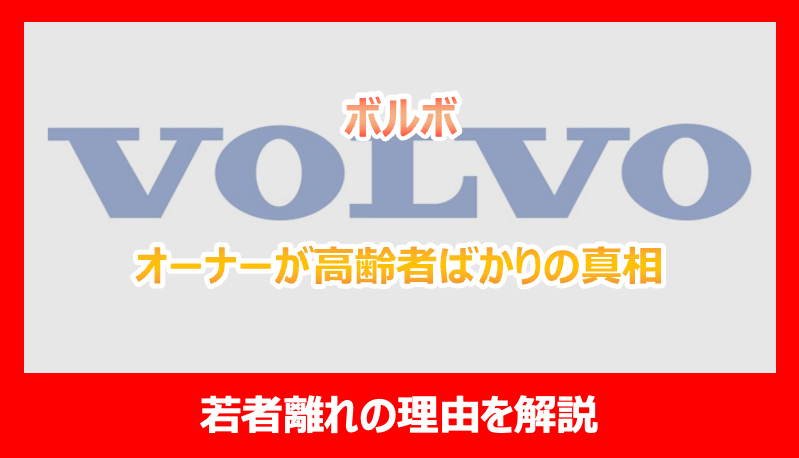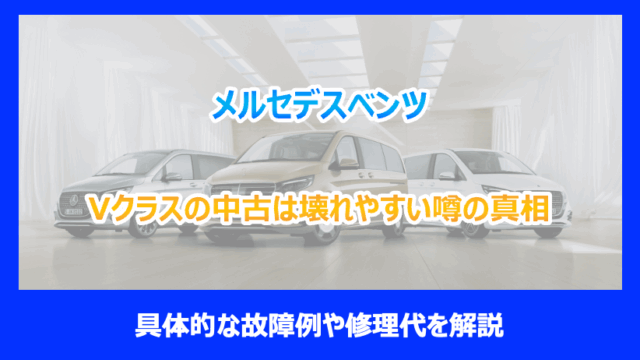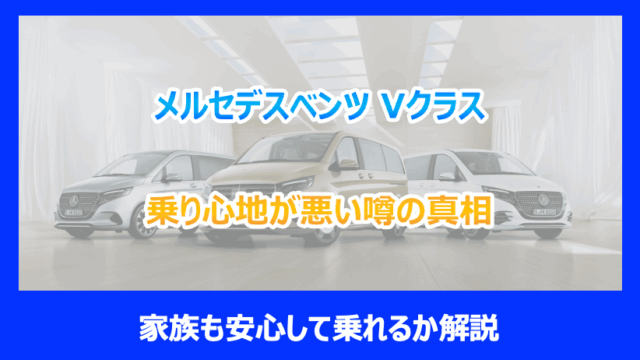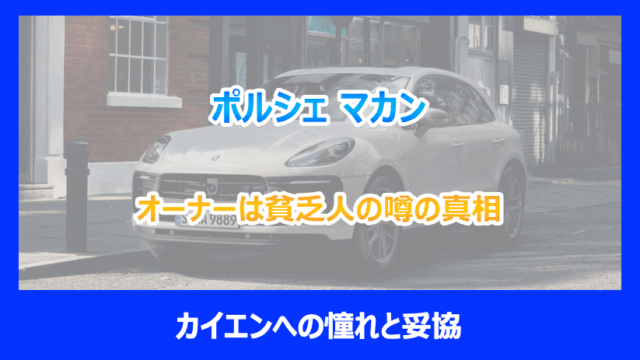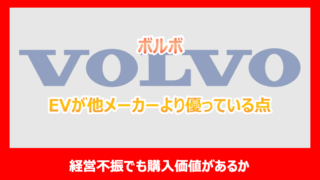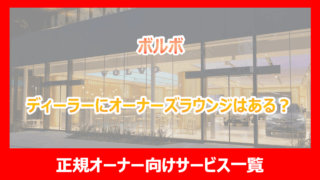モータージャーナリスト兼コラムニストの二階堂仁です。今回も多く寄せられている質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいるあなたは、「街で見かけるボルボ、なんで年配のドライバーばかりなんだろう?」「若者はなぜボルボを選ばないのか?」といった疑問をお持ちなのではないでしょうか。

引用 : ボルボ公式画像 (https://www.volvocars.com/jp/)
私も複数のボルボを所有してきた経験から、そうしたイメージがあることは重々承知していますし、その背景にある理由は実に興味深いものです。
この記事を読み終える頃には、ボルボのオーナー層に関するあなたの疑問が、きっとスッキリ解決しているはずです。
記事のポイント
- ボルボが高齢者層から絶大な信頼を得る理由
- 若者がボルボを候補から外しがちな根本原因
- 安全性におけるボルボの真の優位性と他社比較
- 中国資本やEV戦略に関する誤解と最新の動向
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

ボルボのオーナーが高齢者ばかりと言われる理由
街中でボルボを見かけたとき、ステアリングを握っているのが落ち着いた年代の方であるケースが多いと感じるのは、決して気のせいではありません。
実際に、ボルボのオーナー層は他の輸入車ブランドと比較して年齢層が高い傾向にあります。では、なぜボルボは経験豊富なドライバーたちに選ばれ続けるのでしょうか。私自身の所有経験や多くのオーナーへの取材から見えてきた、その核心に迫ります。

引用 : ボルボ公式画像 (https://www.volvocars.com/jp/)
理由1:揺るぎない「安全神話」と長年積み上げた信頼性
ボルボが高齢者層に選ばれる最大の理由は、なんといっても「安全」というブランドイメージが盤石であることです。これは一朝一夕に築かれたものではありません。
自動車史に残る安全技術への貢献
ボルボは1959年に世界で初めて3点式シートベルトを開発し、その特許を無償で公開しました。これにより、今日までに100万人以上の命が救われたと言われています。この「安全は独占されるべきではない」という哲学は、ブランドの根幹として今も脈々と受け継がれています。
他にも、
- 1972年: 後ろ向きチャイルドシートの開発
- 1991年: 側面衝突吸収構造(SIPS)の導入
- 1998年: むち打ち症対策安全シート(WHIPS)の導入
など、枚挙にいとまがありません。こうした歴史的な功績は、自動車の進化をリアルタイムで見てきた世代にとって、「ボルボ=安全」という絶対的な信頼感につながっています。若い世代にはピンとこないかもしれませんが、これは単なるイメージ戦略ではなく、数十年かけて積み上げられた実績そのものなのです。
現代の先進安全技術「インテリセーフ」
もちろん、ボルボの安全性は過去の遺産だけではありません。現代のボルボ車には、「インテリセーフ(IntelliSafe)」と呼ばれる先進安全・運転支援技術が標準装備されています。
| 機能名 | 概要 |
|---|---|
| City Safety | 衝突被害軽減ブレーキ。車両、歩行者、サイクリスト、大型動物を検知し、衝突の危険があれば自動でブレーキを作動させる。 |
| パイロット・アシスト | 車線維持支援機能。高速道路などで車線中央を維持するようにステアリング操作をアシストする。 |
| BLIS | ブラインドスポット・インフォメーション・システム。死角に他の車両がいる場合に警告を発する。 |
| CTA | クロス・トラフィック・アラート。駐車スペースから後退する際に、接近してくる車両を検知して警告する。 |
| ランオフロード・ミティゲーション | 道路逸脱回避支援機能。意図せず車線を逸脱しそうになると、ステアリングを補正して車線内に戻す。 |
これらの機能は、加齢による身体能力の変化を感じ始めるドライバーにとって、大きな安心材料となります。「万が一の時でもボルボなら守ってくれる」という信頼が、最終的な購入の決め手になるケースは非常に多いのです。
理由2:華美を嫌う層に響く、落ち着いたスカンジナビアンデザイン
メルセデス・ベンツやBMWといったドイツ車が持つ「成功者の証」のような華やかさやスポーティーさとは対照的に、ボルボのデザインは一貫して穏やかで知的です。
シンプルかつ機能的な内外装
「スカンジナビアンデザイン」と称されるそのスタイルは、シンプルさ、機能性、そして天然素材の活用が特徴です。エクステリアは、派手なプレスラインや装飾を極力排し、クリーンで飽きのこない面構成となっています。インテリアも同様で、上質なウッドパネルや手触りの良いレザー、人間工学に基づいたスイッチ配置など、乗る人が心からリラックスできる空間作りが徹底されています。
この「これ見よがしではない本物の上質さ」が、人生経験を積み、華やかさよりも内面的な豊かさを重視するようになった層の価値観と見事に合致するのです。
理由3:若者にはハードルの高い車両本体価格
ボルボはプレミアムブランドであり、その価格設定は決して安価ではありません。主要なモデルの価格帯を見てみましょう。
| モデル | ボディタイプ | 新車価格帯(目安) |
|---|---|---|
| EX30 | コンパクトSUV (EV) | 559万円~ |
| XC40 | コンパクトSUV | 529万円~ |
| V60 | ステーションワゴン | 619万円~ |
| XC60 | ミドルサイズSUV | 739万円~ |
| XC90 | ラージサイズSUV | 1,034万円~ |
ご覧の通り、最もコンパクトなモデルでも500万円を超え、主力となるXC60やV60は600万円以上からのスタートとなります。これは、社会に出て間もない若者層が気軽に購入できる価格帯とは言えません。
一方で、子育てを終え、経済的に余裕が生まれたシニア層にとっては、長年の信頼と安心感、そして上質なデザインを考えれば十分に納得できる価格設定です。結果として、購買力のある高齢者層が主な顧客となるのは自然な流れと言えるでしょう。
理由4:今なお健在な「四角いボルボ」の強烈なイメージ
現在のボルボは、流麗でモダンなデザインへと大きく変貌を遂げました。しかし、特に50代以上の層にとっては、「ボルボといえば四角いエステート(ワゴン)」というイメージが今なお根強く残っています。
1980年代から90年代にかけて人気を博した240シリーズや850シリーズは、その箱型のデザインから「空飛ぶレンガ(Flying Brick)」という愛称で親しまれました。この質実剛健なスタイルは、当時の安全性や実用性の高さを象徴するものであり、多くのファンを生み出しました。
この時代のボルボに憧れを抱いていた世代が、時を経て購入可能な年齢・所得層になった際に、「あの頃のボルボ」のイメージを重ね合わせて現在のモデルを選ぶ、というケースも少なくありません。
ボルボが若者に選ばれ辛い理由と近年の変化
高齢者層に支持される理由の裏返しが、そのまま若者に選ばれ辛い理由につながっている側面があります。しかし、それ以外にも若者世代特有の価値観や、ブランドに関するいくつかの「誤解」も影響しているようです。

引用 : ボルボ公式画像 (https://www.volvocars.com/jp/)
理由1:「おじさん車」「安全だけど退屈」という固定観念
最も大きな障壁は、やはり「親世代が乗る車」「おじさん車」というブランドイメージでしょう。安全で実用的、デザインも落ち着いているという特徴は、裏を返せば「刺激がない」「退屈」「運転が楽しくなさそう」という印象につながりがちです。
スポーティな側面も
しかし、これは大きな誤解です。現在のボルボは、電動化技術を活かした力強い加速性能を持っており、決して退屈な車ではありません。特に、ハイパフォーマンスブランドの「ポールスター」が手掛けたモデルや、「R-Design」といったスポーティなグレードは、ドイツのプレミアムブランドにも引けを取らない走行性能を秘めています。
ただ、こうしたスポーティな側面が、若者層に十分に認知されていないのが現状です。ブランド全体の落ち着いたイメージが先行し、試乗する機会すら持ってもらえないケースが多いのは非常にもったいないと感じます。
理由2:中国資本(吉利汽車)へのアレルギーと品質への誤解
「ボルボって中国の会社になったんでしょ?品質は大丈夫なの?」という声もよく耳にします。これは事実誤認を含んだ、非常に根深い誤解です。
買収後の驚くべき進化
確かにボルボ・カーズは2010年に中国の浙江吉利控股集団(Geely Holding)に買収されました。しかし、これにより品質が低下したという事実は一切ありません。むしろ、その逆です。
フォード傘下時代は、グループ内の他ブランドとの兼ね合いもあり、開発資金が潤沢とは言えない状況でした。しかし、吉利汽車の傘下に入ってからは、ボルボの独立性が尊重され、かつてないほどの巨額な投資が行われました。
その結果、
- 新世代プラットフォーム「SPA」「CMA」の開発
- 新世代エンジン「Drive-E」ファミリーの開発
- 現在のデザイン言語の確立
などが実現し、商品力は飛躍的に向上しました。買収後のXC90(2代目)が世界中で高い評価を受けたのがその証拠です。吉利汽車による買収は、ボルボにとってまさに「恵みの雨」だったのです。「中国資本=品質低下」という短絡的な見方は、現在のボルボの実力を見誤る原因となっています。
理由3:「EV戦略の失敗」という噂の真相
ボルボは2030年までに販売するすべての新車をEV(電気自動車)にすることを宣言しており、自動車業界の中でも特に急進的な電動化戦略を掲げています。この動きに対して、「急ぎすぎではないか」「失敗するのでは」といった懐疑的な見方が一部にあるのも事実です。
業界をリードする電動化への本気度
しかし、ボルボのEV戦略は決して行き当たりばったりではありません。コンパクトSUV「EX30」は、そのデザイン性、性能、そして戦略的な価格設定が評価され、見事「2023-2024 日本カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。これは、ボルボのEVが市場に受け入れられている何よりの証拠です。
もちろん、充電インフラや航続距離といったEV特有の課題は存在します。しかし、これはボルボ一社だけの問題ではなく、業界全体で取り組むべき課題です。ボルボは、サステナビリティ(持続可能性)を重視するブランドとして、困難な道であっても率先して突き進む覚悟を決めているのです。この姿勢は、環境意識の高い若者層の価値観と、本来は非常に親和性が高いはずです。
理由4:レクサスやベンツと比較した際の「安全性の優位性」の形骸化
「ボルボは安全というけれど、今の時代、レクサスやベンツだって安全じゃないか」という意見もごもっともです。事実、各国の衝突安全テスト(ユーロNCAP、米IIHSなど)では、多くのメーカーが最高評価を獲得しており、先進安全装備も各社ほぼ横並びの状態になっています。
ボルボの安全哲学の神髄
では、ボルボの優位性はもはや存在しないのでしょうか。私はそうは思いません。ボルボの安全哲学の神髄は、単に頑丈なボディや高性能なセンサーを持つことだけではないからです。
ボルボは1970年からスウェーデン本社に「交通事故調査隊」を設置し、ボルボ車が関わる重大事故の現場に駆けつけ、50年以上にわたってデータを収集・分析し続けています。この現実世界のデータに基づいた開発こそが、ボルボの安全性を支える根幹なのです。
他社がシミュレーションやテストコースでの評価に留まる中で、ボルボは「現実の路上で、いかに乗員を守るか」を追求し続けています。この目に見えにくい部分での圧倒的な知見と哲学こそが、今なおボルボが「世界で最も安全な車」と称される所以なのです。
理由5:若者の心を掴む戦略的モデルの登場とこれからの展望
これまで述べてきたように、ボルボには若者から敬遠されがちな要素がいくつかありました。しかし、ブランド自身もその課題を認識しており、近年は明らかに変化の兆しが見られます。
その象徴が、前述したコンパクトEV 「EX30」 です。
- モダンで洗練されたデザイン: これまでのボルボのイメージを刷新する、クリーンで未来的な内外装。
- 環境に配慮した素材: ペットボトル再生繊維や亜麻、リサイクルデニムなどを使用したサステナブルなインテリア。
- 軽快な走行性能: コンパクトなボディにパワフルなモーターを搭載し、街中をキビキビと走る楽しさ。
- 戦略的な価格設定: 補助金を活用すれば400万円台から購入可能という、輸入EVとしては破格のプライス。
EX30は、まさに環境意識やコスト意識が高く、新しい価値観を持つ現代の若者に向けて開発されたモデルです。この車が市場に浸透していけば、「ボルボ=高齢者の車」というイメージは、近い将来、過去のものになるかもしれません。
まとめ
今回は、「なぜボルボのオーナーは高齢者ばかりなのか」というテーマを深掘りしてきました。
その理由は、「長年かけて築き上げた安全への絶対的な信頼」「落ち着きと上質さを求める層に響くデザイン」「高価格帯という経済的なハードル」、そして「かつての質実剛健なブランドイメージ」 が、主に経済的に余裕のあるシニア層の価値観と強く結びついているからだと言えます。
一方で、若者にとっては、そのイメージが逆に**「退屈」「古臭い」** といったネガティブな印象につながり、候補から外れやすい傾向がありました。また、中国資本やEV戦略に関する誤解も、正当な評価を妨げる一因となっていたかもしれません。
しかし、自動車ジャーナリストとして断言できるのは、現在のボルボは、かつてのイメージのまま語るべきではないということです。特に、日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞したEX30の登場は、ボルボが新しい時代、新しい世代へと本気で舵を切ったことの証明です。
もしあなたが、単なるイメージだけでボルボを敬遠しているのなら、それは非常にもったいないことです。ぜひ一度、お近くのディーラーで最新のボルボに触れてみてください。その洗練されたデザイン、質の高いインテリア、そして静かで力強い走りは、きっとあなたのボルボに対する見方を180度変えてくれるはずです。