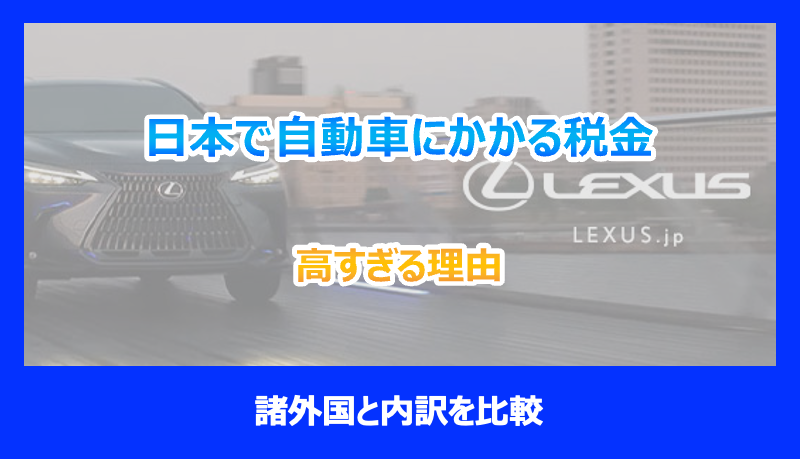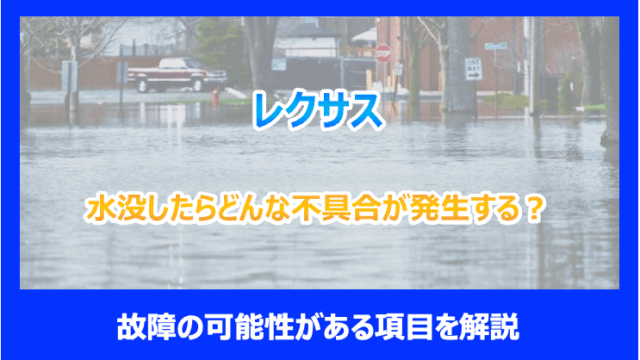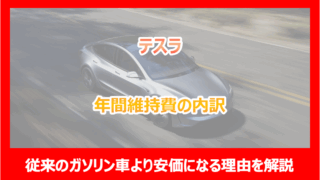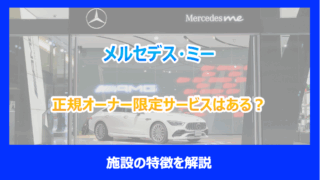モータージャーナリスト兼コンサルタントの二階堂仁です。今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、なぜ日本の自動車税はこんなに高いのか、海外と比べてどうなのかが気になっていると思います。私も実際に複数の車を所有し、毎年の税金の支払額を見るたびに、その負担の大きさを実感しているので、気になる気持ちはよくわかります。

自動車は単なる移動手段ではなく、生活を豊かにしてくれる大切なパートナーです。しかし、そのパートナーと暮らすためには、日本ではあまりにも多くの税金を納めなければならないのが現状です。
この記事を読み終える頃には、日本の自動車税が高い理由と、その複雑な仕組みについての疑問が解決しているはずです。
記事のポイント
- 日本の自動車税が9種類もある複雑な仕組み
- 諸外国と比較して突出して高い日本の税負担
- 税金が高い歴史的背景と二重課税問題
- 今後の税制改正の動向と賢い節税方法

新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。
日本の自動車税はなぜ高い?複雑すぎる9つの税金の内訳を徹底解説
「日本で車を持つと、とにかく税金が高い」。これは、私がコンサルティングの現場で本当によく耳にする言葉です。新車を購入しようと考えている方、あるいはすでに車を所有している方なら、誰もが一度は感じたことのある疑問ではないでしょうか。

引用 : TOYOTA HP (https://lexus.jp/)
結論から言うと、日本の自動車関連税は、国際的に見ても非常に高く、その仕組みは極めて複雑です。なぜ、これほどまでに負担が重いのか。その原因は、幾重にも課される税金の種類と、過去から続く複雑な税制度の歴史にあります。
このセクションでは、まず日本の自動車にかけられている9種類もの税金の内訳を、購入時、保有時、走行時の3つのステージに分けて、一つひとつ丁寧に解説していきます。
購入時にかかる4つの税金
新しい車を手に入れる、あのワクワクする瞬間に、私たちはすでに4種類もの税金を支払っています。それぞれがどのような税金なのか見ていきましょう。
1. 環境性能割
環境性能割は、自動車を取得した際に課される税金で、以前は「自動車取得税」と呼ばれていました。この税金の特徴は、その名の通り「自動車の環境性能」に応じて税率が変わる点です。具体的には、燃費性能が良い車ほど税率が低くなります。
税率は、自家用登録車で0%(非課税)、1%、2%、3%の4段階。軽自動車では0%(非課税)、1%、2%の3段階に設定されています。電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)などは非課税となり、環境負荷の低い車の普及を促進する目的があります。
計算方法は「課税標準基準額 × 税率」です。新車の場合、課税標準基準額はメーカー希望小売価格の約90%が目安となります。
2. 自動車重量税
自動車重量税は、その名の通り、自動車の重量に応じて課される国税です。新車購入時は、車検期間分(通常3年分)をまとめて支払います。
税額は、車両の重さ0.5トンごとに年間4,100円(自家用乗用車の場合)が基本ですが、ここでも環境性能が大きく影響します。エコカー減税対象車の場合、燃費基準の達成度に応じて免税(100%減税)、75%減税、50%減税、25%減税といった措置が適用されます。
一方で、新規登録から13年、18年を経過した車は、環境への負荷が大きいと見なされ、税額が重くなる「重課」という仕組みがあるため注意が必要です。
3. 消費税
自動車は高価な買い物ですが、他の商品やサービスと同様に、車両本体価格やオプション品に対して10%の消費税がかかります。例えば、300万円の車を購入した場合、30万円が消費税として課税されます。
後述しますが、ガソリン価格に含まれるガソリン税にも消費税が課されており、「税金に税金をかける」二重課税として長年問題視されています。
4. リサイクル料金
厳密には税金ではありませんが、自動車を購入する際に支払いが義務付けられている費用です。これは「使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」に基づき、車を将来廃棄する際に必要となるシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類の処理費用を、所有者が予め負担するものです。
料金は車種によって異なりますが、おおよそ1万円から2万円程度が一般的です。
保有時にかかる2つの税金
車を所有しているだけで、毎年継続的にかかってくるのが保有税です。この2つの税金が、家計への負担としてのしかかります。
1. 自動車税(種別割) / 軽自動車税(種別割)
毎年4月1日時点の自動車の所有者に対して課される地方税です。自動車税は都道府県に、軽自動車税は市区町村に納めます。
税額は、エンジンの総排気量によって決まります。排気量が大きくなるほど税額は高くなり、自家用乗用車の場合、最も低い1,000cc以下で25,000円、最も高い6,000cc超で110,000円となります。
一方、軽自動車税は排気量に関わらず一律で10,800円(2015年4月1日以降に新規登録された自家用乗用車)となっており、これが軽自動車の維持費が安いと言われる大きな理由です。
この自動車税にも「グリーン化特例」が適用され、環境性能の良い車は翌年度分の税金が軽減されます。
2. 自動車重量税
購入時だけでなく、車検の際にも継続して支払う必要があります。新車購入時以降は、2年ごとの車検のタイミングで2年分をまとめて納付するのが一般的です。
購入時と同様に、エコカー減税の対象となるかどうか、また新規登録から13年または18年を経過しているかどうかで税額が大きく変動します。
走行時にかかる3つの税金
車を走らせる、つまりガソリンを給油するたびに、私たちは知らず知らずのうちに3つの税金を支払っています。
1. ガソリン税(揮発油税および地方揮発油税)
ガソリン税は、ガソリンの価格に上乗せされている国税です。正確には「揮発油税」と「地方揮発油税」の2つを合わせた総称です。
現在の税額は、1リットルあたり合計53.8円です。このうち25.1円は、本来の税率(本則税率)に上乗せされている「特例税率(旧暫定税率)」分であり、この暫定税率が長年維持されていることが、ガソリン価格を高止まりさせている大きな要因です。
2. 石油石炭税
ガソリンや軽油、灯油など、ほぼすべての化石燃料に対して課される税金です。ガソリンの場合は、1リットルあたり2.8円が課税されています。地球温暖化対策のための財源として導入されました。
3. 軽油引取税
ディーゼル車の燃料である軽油に課される地方税です。1リットルあたり32.1円が課税されます。ガソリン税と同様に、道路整備などの財源として使われます。
なぜこんなに多い?道路特定財源制度の歴史的背景
これほどまでに自動車関連の税金の種類が多い根本的な原因は、かつて存在した「道路特定財源制度」にあります。
戦後の高度経済成長期、日本は急ピッチで道路網を整備する必要がありました。その財源を確保するために、自動車の利用者から集めた税金(ガソリン税や自動車重量税など)を道路の建設や維持管理にのみ使う、という目的税の仕組みが作られました。これが道路特定財源制度です。
この制度によって日本の道路は飛躍的に整備されましたが、一方で、一度作られた税金は目的が達成された後も残り続け、結果として多くの税金が複雑に絡み合ったまま現在に至る、という状況を生み出してしまったのです。2009年にこの制度は廃止され、税収は一般財源化されましたが、税金の種類そのものはほとんど変わっていません。
問題視される「Tax on Tax」|税金に消費税がかかる二重課税の実態
日本の自動車税制で最も不合理だと指摘されているのが、「Tax on Tax」と呼ばれる二重課税の問題です。
最も分かりやすい例がガソリン価格です。ガソリンスタンドで表示されている価格には、ガソリン本体の価格に加えて、ガソリン税(53.8円/L)と石油石炭税(2.8円/L)が含まれています。そして、私たちはこの「税金が含まれた価格」の合計額に対して、さらに10%の消費税を支払っているのです。
ガソリン価格の二重課税構造(例)
| 項目 | 金額(円/L) |
|---|---|
| ガソリン本体価格 | 113.4 |
| ガソリン税 | 53.8 |
| 石油石炭税 | 2.8 |
| 小計(消費税課税対象) | 170.0 |
| 消費税(10%) | 17.0 |
| 合計(店頭価格) | 187.0 |
このように、税金であるはずのガソリン税や石油石炭税にまで消費税が課されているのが現状です。これは論理的にも不自然であり、自動車ユーザーの負担を不当に重くしているとして、長年にわたり多くの団体から是正を求める声が上がっています。
世界の自動車税と比較|日本の負担は本当に重いのか?
日本の自動車税が高い、複雑だと言われる一方で、「海外の税金はどうなっているのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。ここでは、主要国であるアメリカ、ドイツ、イギリス、フランス、そして隣国の韓国の自動車税制と比較し、日本の負担が国際的に見てどのレベルにあるのかを検証していきます。

結論から言うと、購入時から保有時にかかる税金の合計額は、日本が突出して高い水準にあります。
自動車税の国際比較|購入時・保有時の税負担を比べてみる
日本自動車連盟(JAF)の調査によると、自家用乗用車(排気量1.8L、車両価格249万円)を13年間使用した場合の税負担総額は、以下のようになります。
| 国名 | 購入時・保有時にかかる税負担総額(13年間) | 日本との比較 |
|---|---|---|
| 日本 | 約180万円 | – |
| ドイツ | 約125万円 | 日本の約0.7倍 |
| フランス | 約107万円 | 日本の約0.6倍 |
| イギリス | 約58万円 | 日本の約0.3倍 |
| アメリカ | 約27万円 | 日本の約0.15倍 |
※2022年のデータに基づき簡略化
この表からも分かる通り、日本の税負担はアメリカの約6.7倍、イギリスの約3.1倍にも達しており、欧州の主要国と比較しても極めて高いことが一目瞭然です。
では、なぜこれほどの差が生まれるのでしょうか。各国の税制度の特徴を見ていきましょう。
【アメリカ】州によって大きく異なる税制度|連邦税はガソリン税のみ
アメリカの自動車税制の最大の特徴は、連邦レベルでの税金がガソリン税など一部に限られ、自動車の購入や保有に関する税金のほとんどが州税である点です。
- 購入時: 多くの州で「売上税(Sales Tax)」が課されますが、税率は州や郡によって異なり、5%〜10%程度が一般的です。中には売上税が非課税の州も存在します。
- 保有時: 「登録料(Registration Fee)」が毎年かかりますが、その額は年間数千円から2万円程度と、日本の自動車税に比べてはるかに安価です。州によっては、車両価格や年式に応じて課される「固定資産税(Property Tax)」がかかる場合もあります。
このように、アメリカでは州による違いは大きいものの、国全体として見れば、自動車の保有にかかる税負担は日本よりも圧倒的に軽いと言えます。
【ドイツ】CO2排出量に基づく公平な税制度|環境意識の高さ
環境先進国であるドイツでは、自動車税は「環境負荷」に応じて課税されるという考え方が徹底されています。
- 購入時: 「付加価値税(VAT)」が19%かかります。これは日本の消費税に相当しますが、税率は高いです。しかし、日本のような環境性能割や重量税はありません。
- 保有時: 「自動車税」が課されますが、その税額はエンジンの種類(ガソリン/ディーゼル)、排気量、そして最も重要な「CO2排出量」に基づいて算出されます。CO2排出量が少ない車ほど税金が安くなる、非常に合理的で公平な仕組みです。
購入時の付加価値税は高いものの、保有時の税金は環境性能によって決まるため、ユーザーは環境に良い車を選ぶインセンティブが働きます。
【イギリス】環境性能で税額が変動|古い車への負担は重い
イギリスの税制度も、ドイツと同様に環境性能を重視しています。
- 購入時: 「付が価値税(VAT)」が20%かかります。また、新車登録時にはCO2排出量に応じた「初回車両税(First Vehicle Tax)」が課されます。排出量がゼロのEVは非課税ですが、排出量が多い車には高額な税金が課されます。
- 保有時: 2年目以降は「標準車両税(Standard Vehicle Tax)」を支払います。ガソリン車やディーゼル車は一律の税額ですが、EVは免税となります(2025年からの課税が決定)。
イギリスの税制は、特にCO2排出量が多い古い車や高級車に対する負担が重くなるように設計されており、環境政策と税制が強く結びついています。
【フランス】厳しい環境規制と高額な税金|マクロン政権の環境政策
フランスも環境性能を基準とした税制を採用していますが、その内容は非常に厳しいことで知られています。
- 購入時: 「付加価値税(TVA)」が20%かかります。さらに、CO2排出量と車両重量に基づいた「重量税(Malus au poids)」と「環境税(Malus écologique)」という2つのペナルティ税が存在します。特に環境税は、CO2排出量が基準を超えると急激に税額が上がり、上限は数万ユーロ(数百万円)にも達します。
- 保有時: 保有税は基本的に廃止されており、毎年支払う税金はありません。
購入時の負担は極めて重いですが、一度購入してしまえば保有段階での税金はないという、メリハリの効いた税制です。新車販売を環境性能の高い車にシフトさせるという強い意志が感じられます。
【韓国】排気量ベースのシンプルな税制|日本との比較
隣国の韓国の税制は、日本と似ている部分もありますが、よりシンプルです。
- 購入時: 「個別消費税」「教育税」「付加価値税」などがかかります。
- 保有時: 「自動車税」が課され、税額は日本の自動車税と同様に排気量に基づいて決まります。しかし、税額は日本よりも安価に設定されています。例えば、2,000ccクラスの車の場合、日本の自動車税が年間36,000円なのに対し、韓国では約半額程度です。
走行距離課税は導入される?日本の自動車税の今後の動向
現在、日本の政府・与党内で、新たな自動車関連税として「走行距離課税」の導入が検討されています。これは、その名の通り「自動車の走行距離」に応じて課税するという考え方です。
この議論の背景には、EVやPHEVの普及があります。これらの車はガソリンを消費しない、あるいは消費量が少ないため、ガソリン税収が減少することが予想されます。そこで、ガソリン税に代わる新たな財源として、走行距離に応じた課税が検討されているのです。
もし導入されれば、地方在住者や運送業者など、日常的に長距離を走行するユーザーの負担が大幅に増える可能性があります。一方で、都市部在住で週末にしか車に乗らないようなユーザーは、負担が軽くなるかもしれません。
この走行距離課税については、まだ議論の段階ですが、今後の自動車税制の大きな焦点となることは間違いありません。私たちユーザーも、その動向を注意深く見守る必要があります。
高すぎる自動車税と賢く付き合う方法
ここまで見てきたように、日本の自動車税は非常に高く、複雑です。しかし、制度を正しく理解し、賢く選択することで、その負担を少しでも軽減することは可能です。自動車コンサルタントとして、具体的な節税方法をいくつかご紹介します。
エコカー減税・グリーン化特例を最大限活用する
最も効果的な節税方法は、環境性能に優れた車を選ぶことです。 「エコカー減税」対象車であれば、購入時に支払う自動車重量税が減免されます。また、「グリーン化特例」の対象車であれば、購入した翌年度の自動車税または軽自動車税が軽減されます。
特に、EV、PHEV、FCVといった次世代自動車は、多くの税金で優遇措置が受けられます。購入時の車両価格はガソリン車より高い傾向にありますが、こうした税金の優遇や、国や自治体からの補助金、そして日々の燃料代(電気代)の安さを考慮すると、長期的な視点で見れば経済的なメリットは大きいと言えます。
購入時期を工夫する|自動車税の月割り課税
普通車の自動車税には「月割り」という仕組みがあります。これは、年度の途中で車を購入した場合、購入した月の翌月から、その年度の3月までの分だけを納めるというものです。
例えば、4月に購入すれば11ヶ月分、9月に購入すれば6ヶ月分の自動車税を納めることになります。そして、3月に購入した場合は、翌月からが新年度になるため、その年度の自動車税はかかりません。
つまり、月末に購入するよりも、月初に購入した方が、わずかですが支払う税額が少なくなるということです。ただし、軽自動車税には月割りの制度がないため、いつ購入してもその年度の税金はかからず、翌年度から課税されます。
排気量の小さい車や軽自動車を選択する
保有時に毎年かかる自動車税は、排気量によって決まります。当然ながら、排気量の小さい車ほど税金は安くなります。
例えば、排気量2,500ccの車の自動車税は年間43,500円ですが、1,500ccの車なら30,500円と、年間13,000円の差が出ます。10年間乗り続ければ13万円もの差になります。
さらに、軽自動車であれば税額は一律10,800円です。近年の軽自動車は、走行性能も安全性も室内空間の広さも、普通車に引けを取らないモデルが増えています。自身のライフスタイルや車の使い方を考慮し、軽自動車を選択肢に入れることは、非常に有効な維持費節約術です。
中古車という選択肢|環境性能割の仕組みを理解する
中古車を購入する場合、税金面で新車とは異なるメリットがあります。 特に大きいのが「環境性能割」です。中古車の環境性能割の課税標準基準額は、年式が古くなるほど低くなります。具体的には、新車時の価格に残価率をかけて算出されます。
この残価率は、登録から年数が経つほど低くなるため、同じ車種でも年式が古い中古車の方が、環境性能割が安くなる、あるいは非課税になるケースが多いのです。
クレジットカード払いでポイントを貯める
多くの自治体では、自動車税をクレジットカードで支払うことが可能です。 税額そのものが安くなるわけではありませんが、クレジットカードのポイント還元を受けることができます。数万円単位の支払いになるため、還元されるポイントも決して少なくありません。
ただし、クレジットカード払いには決済手数料がかかる場合があるため、手数料と還元ポイントを比較して、どちらがお得かを確認してから利用しましょう。
まとめ
今回は、日本の自動車税がなぜ高いのか、その複雑な仕組みと海外との比較について詳しくレビューしてきました。
9種類にも及ぶ税金、歴史的経緯から残る複雑な制度、そして国際的に見ても突出して高い負担額。日本の自動車ユーザーが重い負担を強いられている現状をご理解いただけたかと思います。
特に、ガソリン税に消費税が課される「Tax on Tax」のような不合理な仕組みは、早急に見直されるべき課題です。また、EVシフトが進む中で検討されている「走行距離課税」の動向も、私たちのカーライフに大きな影響を与える可能性があります。
自動車は、私たちの生活を支え、人生に彩りを与えてくれる素晴らしいパートナーです。そのパートナーと少しでも長く、経済的な不安なく付き合っていくために、私たちユーザー自身が税金の知識を身につけ、賢い選択をしていくことが重要になります。
このレビューが、あなたのこれからのカーライフプランを考える上で、少しでもお役に立てれば幸いです。