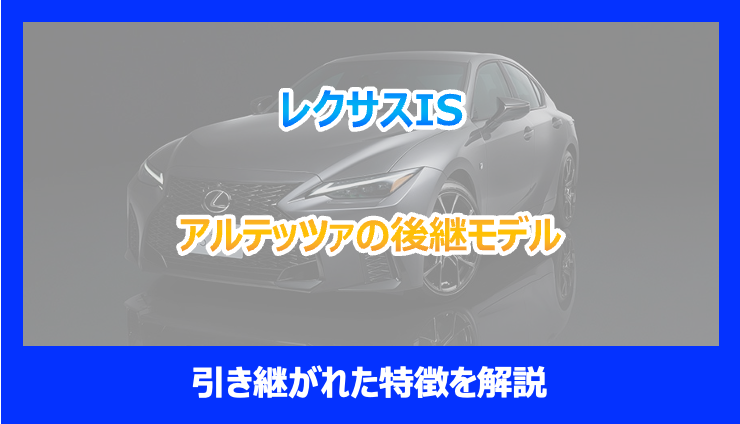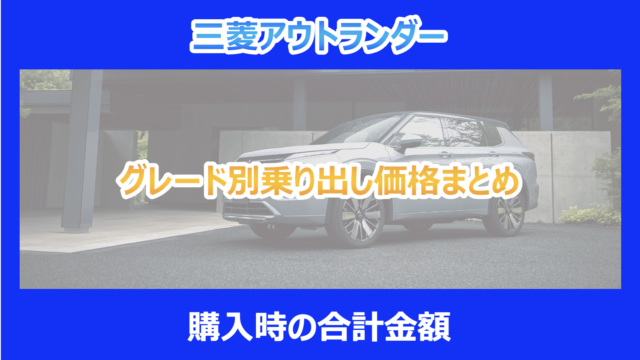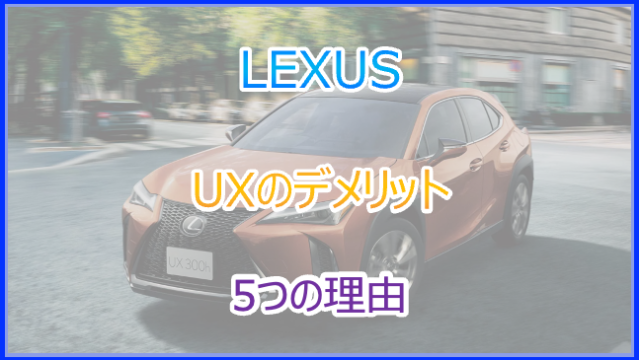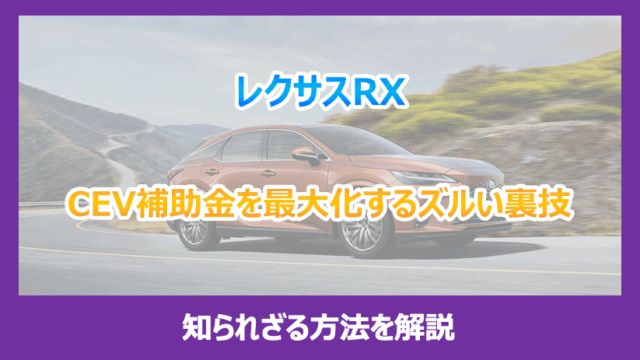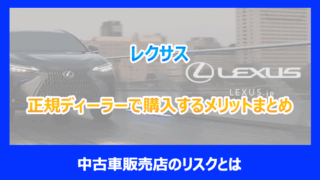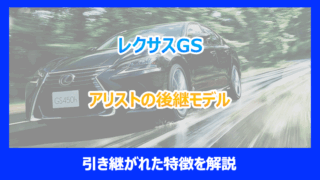この記事を読んでいる方は、かつて一世を風靡したFRスポーツセダン「アルテッツァ」の魂が、現在のどのレクサス車に受け継がれているのか、非常に気になっていることでしょう。

私もアルテッツァのオーナーとして、あの直列エンジンが奏でるサウンドと、意のままに操れるハンドリングの記憶を今でも大切にしています。その熱い想いを知っているからこそ、後継モデルが気になる気持ちは痛いほどわかります。
このレビューでは、単に後継車種を紹介するだけでなく、アルテッツァが目指したものは何だったのか、そしてその精神がレクサスブランドの中でどのように昇華されていったのかを、自身の経験も踏まえながら深く掘り下げていきます。
この記事を読み終える頃には、アルテッツァとレクサスISの繋がり、そしてその進化の軌跡についての疑問が、きっと解決しているはずです。
記事のポイント
- アルテッツァの直接的な後継モデルは「レクサスIS」であること
- 「コンパクトなFRスポーツセダン」という基本コンセプトが継承されていること
- クロノグラフ調メーターなど、象徴的なデザインや思想が進化して受け継がれていること
- 時代の要請と共に、走行性能と内外装のプレミアム性が大きく向上していること
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

アルテッツァとは?色褪せないFRスポーツセダンの魅力を徹底解剖
1998年に登場したアルテッツァは、当時の自動車市場に大きな衝撃を与えました。トヨタが満を持して投入したこのFRスポーツセダンは、多くのクルマ好きの心を掴み、生産終了から長い年月が経った今なお、中古車市場で高い人気を誇っています。まずは、この伝説的なモデルがどのようなクルマだったのか、その魅力を多角的に振り返ってみましょう。

アルテッツァの誕生背景と「駆けぬける歓び」への挑戦
アルテッツァが開発された1990年代後半は、世の中がミニバンやSUVへとシフトし始めていた時代でした。そんな中でトヨタは、あえて「走りの楽しさ」を追求したセダンを開発する決断をします。明確なターゲットとして意識されていたのは、スポーツセダンの世界的なベンチマークである「BMW 3シリーズ」です。
当時のトヨタは、FR(フロントエンジン・リアドライブ)レイアウトのセダンとしてマークⅡ三兄弟(マークⅡ、チェイサー、クレスタ)やクラウンなどをラインナップしていましたが、それらよりも一回りコンパクトで、よりピュアなハンドリング性能を持つモデルを求めていました。
「Fun to Drive」を突き詰めるべく、開発陣は欧州車、特にBMWの徹底的な研究を行いました。ショートオーバーハング&ロングホイールベースによる理想的なプロポーション、ドライバーオリエンテッドなコクピット、そして何よりも「人馬一体」と評されるハンドリング。これらを実現するために、新設計のプラットフォームが採用され、サスペンション形式にもこだわり抜きました。アルテッツァは、トヨタが本気で世界基準のスポーツセダンを創り上げようとした、その情熱の結晶だったのです。
アルテッツァの象徴的なエクステリアデザイン
アルテッツァのデザインは、今見ても古さを感じさせない、非常に完成度の高いものでした。
ショートオーバーハング&ロングホイールベース
アルテッツァのスタイリングを決定づけているのが、このプロポーションです。フロントとリアのタイヤを可能な限りボディの四隅に配置することで、走行安定性と回頭性を向上させると同時に、見た目の躍動感を演出しています。特にフロントは、エンジンを前車軸の後ろ寄りに搭載する「フロントミッドシップ」に近いレイアウトとすることで、理想的な前後重量配分(約53:47)を実現。これが、アルテッツァの素直なハンドリングの源泉となっています。
シャープでクリーンな面構成
ボディサイドには、キャラクターラインを最小限に抑えた、張りのあるクリーンな面が採用されています。これは、光の当たり方によって表情を変え、凝縮感のある塊としての力強さを感じさせます。無駄を削ぎ落としたシンプルな造形だからこそ、飽きが来ず、長く愛されるデザインとなりました。
丸型2灯のテールランプ
アルテッツァのリアビューを最も特徴づけているのが、通称「ユーロテール」や「クリアテール」と呼ばれる、透明なアウターレンズ内にメッキのシリンダー状デザインを施した丸型2灯のテールランプです。この斬新なデザインは当時のカスタムシーンに絶大な影響を与え、多くの車種で模倣されるほどのトレンドとなりました。このテールランプこそ、アルテッツァのアイコンと言えるでしょう。
アルテッツァの心をくすぐるインテリアと装備
アルテッツァの魅力は、エクステリアだけに留まりません。ドアを開けた瞬間に広がるインテリア空間にも、ドライバーの心を高揚させるためのこだわりが凝縮されていました。
クロノグラフ調メーター
最も象徴的なのが、スイスの高級機械式腕時計をモチーフにしたと言われる「クロノグラフ調メーター」です。円形のメーターの中に、速度計、回転計、水温計、燃料計が巧みに配置されたこのデザインは、非常に独創的でスポーティな雰囲気を演出していました。私も初めてこのメーターを見たとき、その精緻なデザインに心を奪われたのを覚えています。この遊び心こそ、アルテッツァが単なる移動手段ではない、「愛車」としての価値を持つことの証明でした。
ドライバーオリエンテッドなコクピット
運転席に座ると、全ての操作系が自然と手に届く範囲に配置されていることがわかります。センタークラスターはわずかにドライバー側に傾けられ、タイトながらも機能的な空間を創出。ショートストロークのシフトレバーや、適度な重さを持つステアリングホイールと相まって、クルマとの一体感を強く感じさせます。
アルテッツァのエンジンラインナップと走行性能
アルテッツァには、性格の異なる2種類のエンジンが用意されていました。これもまた、ユーザーが自身のドライビングスタイルに合わせて選べるという、大きな魅力でした。
スポーツの「3S-GE」型エンジン
スポーツグレードである「RS200」に搭載されたのが、2.0L 直列4気筒の「3S-GE」型エンジンです。ヤマハ発動機が開発に携わったこの名機は、自然吸気ながら可変バルブタイミング機構「VVT-i」を備え、6速MT仕様では最高出力210馬力を7,600rpmという高回転で発生させました。チタン製バルブを採用するなど、レーシングエンジンさながらの技術が投入されており、高回転域まで回した時のシャープな吹け上がりと官能的なサウンドは、多くのドライバーを虜にしました。私も所有するRS200で、ついついシフトダウンしてエンジンを回してしまう、あの感覚は忘れられません。
ジェントルな「1G-FE」型エンジン
上質さを求めるユーザー向けに用意されたのが、「AS200」に搭載された2.0L 直列6気筒の「1G-FE」型エンジンです。最高出力は160馬力と3S-GEには劣るものの、直列6気筒ならではの非常に滑らかで静かな回転フィールが特徴でした。「シルキーシックス」と称されるBMWの直6エンジンにも通じる、ジェントルな乗り味を提供してくれます。街乗りから高速巡航まで、ストレスのない快適なドライビングを楽しめるのが、このエンジンの美点です。
アルテッツァのハンドリングと足回りへのこだわり
アルテッツァの真骨頂は、その卓越したハンドリング性能にあります。これを支えているのが、新開発のプラットフォームと、四輪ダブルウィッシュボーン式のサスペンションです。
ダブルウィッシュボーン式は、構造が複雑でコストもかかりますが、タイヤの接地性を非常に高く保つことができるため、コーナリング時の安定性や乗り心地に優れています。アルテッツァは、この贅沢なサスペンション形式をフロントにもリアにも採用。開発陣がいかに足回りにこだわっていたかが窺えます。
実際にステアリングを握ると、その恩恵は明らかです。ドライバーの操作に対して、遅れることなくクルマが向きを変え、コーナーでは4つのタイヤがしっかりと路面を掴んでいる感覚が伝わってきます。この素直でコントローラブルな特性こそ、アルテッツァが「FRスポーツの入門書」とも言われる所以です。
アルテッツァのグレード展開とそれぞれの特徴
アルテッツァは、大きく分けてスポーツ系の「RS200」と、ラグジュアリー系の「AS200」という2つのグレードで構成されていました。
- RS200: 3S-GEエンジンを搭載するホットモデル。6速MTと5速AT(ステアシフトマチック付)が選択可能でした。専用のエアロパーツや、よりスポーティな足回りが与えられ、走りを重視するユーザーから絶大な支持を受けました。
- AS200: 1G-FEエンジンを搭載する上級グレード。4速AT(後に5速ATに変更)が組み合わされ、滑らかで静かな走りが特徴。内外装の装備も充実しており、快適な移動を求めるユーザーに適していました。
この明確なキャラクター分けにより、幅広い層のユーザーニーズに応えることができたのも、アルテッツァの成功の一因と言えるでしょう。
アルテッツァ・ジータというもう一つの選択肢
アルテッツァには、セダンだけでなく「アルテッツァ・ジータ」というステーションワゴンモデルも存在しました。セダンの優れた走行性能はそのままに、ラゲッジスペースを拡大して実用性を高めたモデルです。
ジータには、セダンにはない3.0L 直列6気筒の「2JZ-GE」型エンジン搭載モデル(AS300)がラインナップされていたのも大きな特徴です。このエンジンは、スープラ(NAモデル)やアリストにも搭載されていた名機で、大排気量ならではのトルクフルで余裕のある走りを提供しました。スタイリッシュで走りも良いワゴンとして、独自のポジションを確立していました。
アルテッツァが中古車市場で今なお愛される理由
生産終了から20年近くが経過した現在でも、アルテッツァは中古車市場で根強い人気を保っています。その理由は、以下のような点が挙げられます。
- 手頃なFRスポーツ: 貴重な国産FRスポーツセダンでありながら、比較的リーズナブルな価格帯で手に入れることができます。
- 豊富なカスタムパーツ: 当時、非常に人気が高かったため、今でも社外のカスタムパーツが豊富に流通しています。自分好みの一台に仕上げる楽しみがあります。
- 高い基本性能: 優れたシャシー性能と魅力的なエンジンは、現代の道路事情でも十分に通用します。
- 色褪せないデザイン: シンプルで完成度の高いデザインは、時代を超えて多くの人を魅了し続けています。
これらの要素が組み合わさることで、アルテッツァは単なる古い中古車ではなく、「自分だけの走りを楽しめる素材」として、多くのクルマ好きから愛され続けているのです。
アルテッツァの後継、レクサスISへの進化と継承
さて、ここからが本題です。多くのファンに愛されたアルテッツァですが、2005年にその歴史に幕を下ろします。そして、その魂を受け継ぐ形で登場したのが、プレミアムブランド「レクサス」の「IS」でした。なぜアルテッツァはレクサスISになったのか、そして何が引き継がれ、何が進化したのかを詳しく見ていきましょう。

引用 : TOYOTA HP (https://lexus.jp/)
なぜアルテッツァはレクサスISになったのか?ブランド戦略の転換
アルテッツァは、海外では初代から「レクサス IS」として販売されていました。つまり、もともとレクサスブランドの世界戦略を担う重要なモデルだったのです。
2005年、トヨタは日本国内でもレクサスブランドの展開を本格的に開始します。これに伴い、これまでトヨタブランドで販売されていた一部の車種(セルシオ→レクサスLS、アリスト→レクサスGS、ソアラ→レクサスSCなど)がレクサスブランドへと移行しました。アルテッツァもその流れの中で、2代目へのフルモデルチェンジを機に、日本国内でも正式に「レクサス IS」として販売されることになったのです。
これは、単なる車名の変更ではありません。トヨタブランドのスポーツセダンから、世界と戦うレクサスのプレミアムスポーツセダンへと、その立ち位置を大きく変えることを意味していました。
初代レクサスIS(日本では2代目)の登場と変化
2005年に登場した初代レクサスIS(GSE2#型)は、アルテッツァのコンセプトを継承しつつ、あらゆる面で大幅な進化を遂げていました。
プラットフォームは、上級モデルであるGSと共通の思想で新開発され、ボディサイズも一回り拡大。これにより、走行安定性と居住性が向上しました。デザインも、レクサスブランドのデザインフィロソフィ「L-finesse(エル・フィネス)」に基づいた、よりダイナミックで洗練されたものへと生まれ変わりました。
アルテッツァが持っていた若々しいスポーティさに、レクサスならではの上質さ、プレミアム感が加わったのが、この初代ISだったと言えるでしょう。
2代目レクサスISのデザインに見るアルテッツァの面影
全く新しくなったように見えるISですが、注意深く観察すると、アルテッツァの面影を見つけることができます。
凝縮感のあるプロポーション
ボディサイズは拡大されましたが、ショートオーバーハング&ロングホイールベースという基本的なプロポーションは健在です。FRらしい躍動感のあるスタイリングは、紛れもなくアルテッツァの血統であることを示しています。
リアフェンダーの張り出し
後輪駆動であることを視覚的にアピールする、豊かに張り出したリアフェンダーの造形も、アルテッツァから受け継がれた特徴の一つです。低く構えた安定感のあるリアビューを演出しています。
インテリアのドライバーオリエンテッドな思想
運転席に座った時のタイト感や、操作系がドライバー中心にレイアウトされている思想も共通しています。ただし、質感は大幅に向上。アルテッツァのプラスチッキーな部分が影を潜め、ソフトパッドや金属調加飾が多用された、プレミアムブランドにふさわしい空間へと進化しました。
エンジンとパワートレインの進化(V型6気筒へ)
初代ISで最も大きな変化があったのが、エンジンラインナップです。アルテッツァの象徴だった直列エンジン(3S-GE、1G-FE)は姿を消し、新開発のV型6気筒エンジンが主力となりました。
- IS250 (GSE20): 2.5L V型6気筒「4GR-FSE」エンジンを搭載。1G-FEの後継にあたるグレードで、滑らかさと静粛性をさらに向上させつつ、215馬力という十分なパワーを発揮しました。
- IS350 (GSE21): 3.5L V型6気筒「2GR-FSE」エンジンを搭載。318馬力という、当時のクラス最強レベルのパワーを誇りました。RS200のスポーツ性を受け継ぎながら、大排気量ならではの圧倒的な加速力と余裕を実現した、まさにプレミアムスポーツセダンと呼ぶにふさわしいモデルでした。
このV6エンジンへの変更は、静粛性や振動面で有利であり、プレミアムセダンとしての質感を高める上で必然の選択でした。アルテッツァの荒々しいまでのスポーティさを懐かしむ声もありましたが、時代の要請に応えた正常進化と言えるでしょう。
走行性能の継承とプレミアムスポーツへの深化
走りの面でも、ISはアルテッツァのDNAを色濃く受け継いでいます。四輪ダブルウィッシュボーン式サスペンションという基本形式は踏襲しつつ、各部の剛性アップやジオメトリーの最適化が図られました。
これにより、アルテッツァの持ち味だった素直なハンドリングはそのままに、高速走行時の安定性や乗り心地が劇的に向上。特にIS350の走りは、もはやアルテッツァとは別次元の速さと安定感を両立していました。
また、電子制御デバイスの進化も著しく、VDIM(Vehicle Dynamics Integrated Management)と呼ばれる統合車両姿勢安定制御システムが採用されました。これにより、滑りやすい路面などでも、ドライバーが意識することなく、クルマが安定した挙動を保ってくれるようになりました。アルテッツァの持っていたピュアな操る楽しさに、レクサスならではの「安全・安心」という価値が加わったのです。
3代目、そして現行レクサスISへと続く進化の系譜
レクサスISの進化は止まりません。
3代目IS(2013年~)
3代目では、レクサスの新たなアイコンである「スピンドルグリル」が採用され、よりアグレッシブで個性的なデザインへと変貌を遂げました。この世代から、2.5Lハイブリッドモデル「IS300h」や、2.0Lターボモデル「IS200t(後にIS300に改称)」が加わり、パワートレインの選択肢がさらに広がりました。走りの面では、レーザースクリューウェルディングや構造用接着剤といった新たな生産技術が導入され、ボディ剛性が飛躍的に向上。アルテッツァから続く「走りの楽しさ」が、さらに高いレベルへと引き上げられました。
現行IS(2020年~)
2020年には、ビッグマイナーチェンジが実施され、現行モデルへと進化しました。これは単なるマイナーチェンジではなく、愛知県豊田市に新設されたテストコース「Toyota Technical Center Shimoyama」で徹底的に走り込みが行われ、シャシー性能が根本から鍛え直されました。エクステリアも、よりワイド&ローを強調したデザインとなり、走行性能の進化を視覚的に表現しています。ステアリングを切った瞬間の応答性や、コーナリングでのライントレース性は、歴代ISの中でも最高レベルにあり、アルテッツァが目指した「人馬一体」の一つの完成形と言えるかもしれません。私もこの現行ISを所有していますが、日常の運転からサーキット走行まで、あらゆるシーンでドライバーを満足させてくれる懐の深さには感心させられます。
アルテッツァからISへ引き継がれた「運転の楽しさ」という魂
車名が変わり、ブランドが変わり、エンジンやデザインが大きく変化しても、アルテッツァからレクサスISへと、一貫して引き継がれているものがあります。それは、「運転が楽しいコンパクトなFRスポーツセダン」という魂です。
時代の変化に合わせて、プレミアム性や快適性、環境性能といった要素が加えられてきましたが、その根底には常に「ドライバーが主役である」という思想が流れています。ステアリングを握り、アクセルを踏み込めば、クルマと対話するような感覚が味わえる。この本質的な価値こそが、アルテッツァからISへと続く最大の継承点なのです。
アルテッツァオーナーがレクサスISに乗り換える際の注意点
もし、あなたが今もアルテッツァを愛するオーナーで、その後継であるレクサスISへの乗り換えを検討しているのであれば、いくつか心に留めておくべき点があります。
- 乗り味の変化: ISはアルテッツァに比べて、はるかに静かで快適です。アルテッツァの、ある意味でダイレクトで荒々しい乗り味を好む方にとっては、少し「優等生」すぎると感じるかもしれません。
- 車両価格と維持費: 当然ながら、レクサスISはプレミアムブランドの車両です。新車・中古車問わず、車両価格はアルテッツァよりも高価になります。また、部品代や整備費用も高くなる傾向にあります。
- 電子制御の進化: ISには多くの電子制御デバイスが搭載されています。これは安全で快適な運転をサポートしてくれますが、アルテッツァのようなクルマを自分の操作一つで操る感覚とは少し異なります。
これらの点を理解した上で試乗すれば、レクサスISがアルテッツァの精神を受け継ぎながら、いかに素晴らしい進化を遂げたかを実感できるはずです。
まとめ
今回は、トヨタ アルテッツァの後継車種がレクサスISであること、そしてその進化の過程で何が受け継がれ、何が変わったのかを詳しくレビューしてきました。
アルテッツァは、1990年代の終わりに「走りの楽しさ」を追求して生まれた、情熱的なFRスポーツセダンでした。その卓越したハンドリング性能、心をくすぐるデザイン、そして魅力的なエンジンは、今なお多くのファンを魅了し続けています。
その直系の後継モデルであるレクサスISは、アルテッツァの魂を受け継ぎながら、レクサスというプレミアムブランドにふさわしい上質さと先進性を手に入れました。世代を重ねるごとに、その走りは磨き上げられ、デザインは洗練されてきました。
もしあなたが、かつてアルテッツァと共に過ごした日々に思いを馳せているのなら、ぜひ一度、最新のレクサスISのステアリングを握ってみてください。そこには、形を変え、時代に合わせて進化しながらも、確かに息づいている「駆けぬける歓び」のDNAを感じ取ることができるはずです。アルテッツァという一本の太い幹から、レクサスISという豊かな枝葉が伸びている。その繋がりと進化の物語は、日本の自動車史における素晴らしい一章と言えるでしょう。