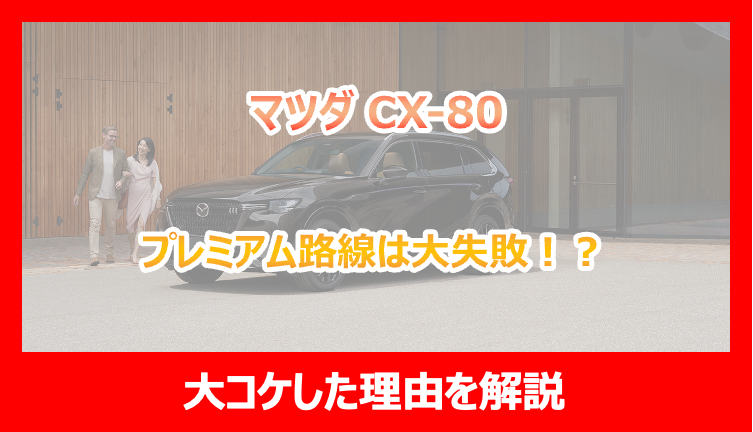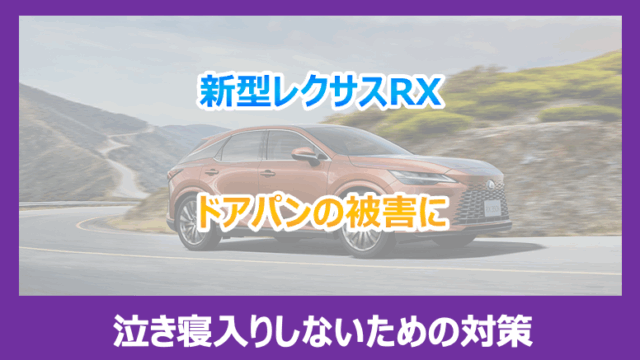2024年に登場したマツダの新型3列シートSUV「CX-80」は、プレミアムブランド戦略の象徴として高価格帯で投入された意欲的なモデルです。

引用 : MAZDA HP (https://www.mazda.co.jp/cars/cx-80/feature/)
しかし、かつての人気モデル「CX-8」とは異なり、販売成績は芳しくありません。
本レビューでは、なぜCX-80が苦戦を強いられているのか、その要因を多角的に分析し、今後の巻き返しの可能性についても深掘りします。
記事のポイント
- CX-80の販売が伸び悩む理由を徹底解説
- プレミアム路線への転換が裏目に出た背景
- CX-60の失敗が与えた影響とは?
- 製品の完成度は高いが、ブランド力に課題
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

マツダCX-80の販売が不調な理由
プレミアム化による価格帯の跳ね上がり
マツダはCX-80を従来の実用SUVとは異なるプレミアム志向の3列SUVとして位置づけました。

引用 : MAZDA HP (https://www.mazda.co.jp/cars/cx-80/feature/)
しかし、500万円を超える価格設定は、CX-8を支持していたコストパフォーマンス重視の層には受け入れがたいものでした。
CX-8との価格差が与えたインパクト
従来のCX-8は約350万〜450万円と手の届きやすい価格帯で、ファミリーユースに最適なモデルとして多くの支持を集めていました。それに対してCX-80は500万円台〜700万円台と、CX-8よりも100万円以上の価格差があり、これが「手が出しづらい」という心理的なハードルを生んでいます。
他ブランドとの価格比較
この価格帯になると、トヨタのランドクルーザープラドやハリアーZレザーパッケージ、さらにはレクサスRXやNXなども視野に入ってきます。ネームバリューの強いトヨタ・レクサス勢と比較すると、マツダには「価格に見合うブランド価値があるのか?」という疑念が生じやすいのが現実です。
装備充実が価格に反映されすぎた?
CX-80には本革シート、BOSEサウンド、先進安全装備などが充実している一方で、それらを標準化した結果、ベースグレードでも高額になってしまっています。エントリーユーザーにとって「選べる安価な仕様」が存在しないことも、販売層の広がりを妨げています。
ローンや維持費を含めた総支出への不安
購入時の支払額だけでなく、自動車保険や重量税、車検費用などを含めた長期的な維持コストを懸念する声もあります。プレミアム価格帯に移行したことで、維持費まで高額になるという印象が強まり、購買判断を鈍らせる要因となっています。
競合ブランドとの差別化に失敗
トヨタのランドクルーザープラドや日産パスファインダーなど、強力なブランドと同価格帯に位置するCX-80ですが、マツダブランドにはそれに見合うネームバリューが不足しています。
ブランドの信頼性と歴史的実績の違い
トヨタや日産といった競合ブランドは、長年にわたる実績や信頼性の積み重ねによって、ユーザーの安心感と期待値を獲得しています。特にランドクルーザーのような歴史のある車種は、悪路走破性・耐久性といった信頼が既に定着しており、プレミアム価格でも納得感が得られやすいのです。
高価格帯に必要な“ラグジュアリー・オーラ”の不足
マツダは内装の質感や装備では高級感を演出していますが、ブランドとしての“格”や“オーラ”がまだ醸成されきっておらず、「高級車を買った」という満足感を得にくい状況にあります。結果として、同じ装備水準でもレクサスやBMWなどの方に消費者が流れやすくなってしまいます。
購入後のリセールバリュー格差
購入後の価値も重要です。マツダ車は全体的にリセールバリューが低めであり、高価格帯モデルになればなるほど中古市場での損失感が際立ちます。ブランド力のある車種であれば資産性も含めた評価が可能ですが、マツダはまだそこまで到達していません。
デザインや走行性能の差別化はあるが伝わらない
実際にはCX-80にはFRベースの走行性能や欧州車ライクなエクステリアデザインなど、独自の強みも存在します。しかし、それらの魅力が競合との差別化要素として十分に市場に伝わっていないのが現状です。差別化を図るには、製品そのものだけでなく、プロモーション戦略全体の見直しも必要でしょう。
CX-60のリコール連発が与えた影響
CX-80と同じラージ商品群であるCX-60はリコールが相次ぎ、ユーザーの信頼を損ないました。その影響がCX-80にも波及し、新モデルにも不安を抱く消費者が増えています。

引用 : MAZDA HP (https://www.mazda.co.jp/cars/cx-60/feature/)
CX-60の信頼失墜の経緯
CX-60は2022年にデビューしたFRベースの新世代SUVとして注目されましたが、走行中のエンストや変速ショック、電子制御系の不具合など、致命的な不具合が複数報告されました。リコールは累計で10件を超え、一部では安全装備に関わるものも含まれており、消費者の安全意識を直撃しました。
メディアとSNSによる悪影響の拡大
不具合の情報はSNSやYouTubeなどで瞬く間に拡散され、”リコール続出のマツダ”というイメージが形成されてしまいました。CX-80を検討していたユーザーの中には、CX-60と構造が近いことから不安を感じ、購入を見送ったケースも少なくありません。
マツダの初動対応の遅れ
CX-60の初期トラブルに対して、マツダはやや後手に回った印象があります。不具合の情報発信や対応策の公表が遅れたことで、誠実さや危機対応能力に対する疑問が生まれ、企業イメージの低下にもつながりました。
CX-80の品質向上努力は伝わらず
実際には、CX-80ではCX-60の教訓を踏まえ、サスペンションの再設計や電子制御系のチューニング見直しなど多くの改善が加えられています。しかし、過去の悪評の影が強く、その努力が十分に伝わっていないことが販売に影を落としています。
信頼回復への道のり
今後マツダが信頼を取り戻すためには、品質管理の徹底はもちろんのこと、購入後のサポート体制や不具合対応の透明性を高めることが不可欠です。また、CX-80の品質改善の具体例を積極的に発信し、イメージ回復に努めるべき局面にあります。
市場とのズレたブランド戦略
マツダは欧州市場を視野に高級路線を進めましたが、日本市場ではその戦略がうまくフィットせず、ユーザーとのミスマッチが生じています。
欧州市場を意識した設計思想
CX-80は全長5m近い大柄なボディ、直列6気筒エンジン、FRベースのプラットフォームなど、欧州のプレミアムSUV市場で戦うことを想定して開発されています。これらは走行性能や内装の質感という点では優位性がありますが、日本の都市部では取り回しや駐車のしにくさがネックになる場面も多く、日常使いには過剰との声もあります。
国内市場のニーズとの乖離
日本市場では、燃費性能や車両サイズ、使い勝手といった実用性が重視される傾向があります。その点で、CX-80は価格・サイズ・仕様いずれも「プレミアム志向に振り切りすぎた」と受け止められてしまった可能性があります。特に家族向けの3列シートSUVとして求められる「手頃で扱いやすい」イメージから乖離したことが、販売の鈍化を招いています。
マーケティングメッセージの不一致
「走りを楽しむ上質なSUV」というCX-80の開発コンセプトは、実際には一定の層に響く魅力ではありますが、それが十分に伝わっていないのが問題です。一般の購買層には「なぜこの価格なのか?」「何が他と違うのか?」という問いへの明確な回答が伝わらず、トヨタ・レクサスとの比較で劣後する印象を残してしまっています。
海外志向の裏返しとしての国内軽視?
海外市場を見据えた開発は決して悪いことではありませんが、日本の消費者にとって「自国ブランドが自分たちを見ていない」と感じさせる要素にもなり得ます。CX-80に限らず、グローバル戦略を展開する際には、地元市場への適応力や説明責任も欠かせません。
マツダのブランド戦略と課題
ブランドイメージの壁
「お手頃で走りが良い」マツダのイメージは根強く、高価格帯のCX-80に対し「そこまでの価値があるのか?」と疑問を持つユーザーも少なくありません。
過去の成功体験が逆に足かせに
マツダはこれまで、手頃な価格でありながら走行性能に優れた車を提供してきたことで高い評価を受けてきました。CX-5やデミオ(現・MAZDA2)といった人気モデルが象徴するように、「賢い選択」「コスパの良さ」がマツダのブランドイメージとして定着していました。そのため、CX-80のような高価格帯のモデルに対して、「マツダがそこまで高いクルマを出す意味があるのか?」という疑念が生まれてしまいやすいのです。
高級車市場での競争力不足
高価格帯での成功には、単なる商品力だけでなく、歴史やブランドストーリー、象徴的な存在感といった“情緒的価値”が不可欠です。トヨタがレクサスを、日産がインフィニティを持つように、長年にわたって高級イメージを培ってきたブランドは、市場における信頼感と安心感が根付いています。一方、マツダは高級セグメントにおいて実績が少なく、消費者が「高額でも買いたい」と思える説得力に欠ける現状があります。
ブランド進化のメッセージが届かない
マツダは「走る歓び」と「上質な所有体験」を重視するプレミアムブランドを目指していますが、それが生活者の日常にどのような価値をもたらすのかが分かりづらいという指摘もあります。単に豪華な装備を増やすだけでは、高級車ユーザーの期待に応えることはできません。ユーザーがブランドに求めているのは「感情への訴求」であり、それが伝わっていないことが、ブランドの壁として立ちはだかっているのです。
伝わらない魅力
CX-80の魅力は実際に乗ってみないと伝わりにくく、購入前に判断しづらいのが弱点。体験型プロモーションの不足も響いています。

引用 : MAZDA HP (https://www.mazda.co.jp/cars/cx-80/feature/)
スペックでは伝わらない“乗り味”の魅力
CX-80のFRレイアウトやサスペンションチューニングによる乗り味の良さは、カタログスペックや写真だけでは把握しづらい部分です。実際にステアリングを握ってみて初めて分かる、自然なフィーリングや静粛性、高速時の安定感は、他のSUVにはない強みですが、それを体験できない限り“価格に見合う理由”が曖昧になってしまいます。
試乗機会の少なさと販売現場の課題
マツダディーラーによってはCX-80の試乗車を常設していないケースもあり、購入を検討している層にとっては体験の機会が限られています。また、販売スタッフがCX-80の差別化ポイントを十分に説明できていないケースもあり、魅力がうまく伝わらないまま購入検討から脱落するユーザーも少なくありません。
感覚に訴えるマーケティング不足
「走る歓び」や「上質な所有感」といった、感覚的な価値を訴求するには、動画コンテンツや試乗イベント、インフルエンサーによるリアルなレビューなど、五感に訴えるプロモーションが不可欠です。現状ではそうした取り組みが他社に比べて弱く、CX-80の持つ“体験価値”が可視化されていないのが現状です。
顧客接点でのストーリーテリングが不可欠
顧客がCX-80を選ぶ理由を明確に感じられるよう、販売現場では「どんなライフスタイルに合うのか」「どんな運転体験が待っているのか」といった情緒的なアプローチが求められます。単なるスペック説明では伝わらない部分こそ、ブランドの存在意義を訴えるチャンスです。
複雑すぎるグレード構成
多彩なパワートレインや装備は魅力ですが、逆に選びづらくなっているという声も。UX改善が必要です。
選択肢の多さが混乱を生む要因に
CX-80では、ガソリン、ディーゼル、PHEVといった複数のパワートレインが用意されており、それぞれに標準・上級グレードが存在します。さらに、駆動方式(2WD/4WD)や内装色、シート構成まで多岐にわたるオプションが組み合わさることで、購入時に“どれを選べばいいのか分からない”という戸惑いを招いています。
カタログやWebサイトの情報設計に課題
マツダ公式のカタログやWebサイトは、仕様ごとの違いが直感的に分かりづらく、細かな差異を比較しにくい構成となっています。結果として、「何が標準装備で、どこからがオプションなのか」が把握しづらく、選択ストレスを感じるユーザーが増えているのが現実です。
グレードによる価格差の幅が大きすぎる
エントリーモデルから上位グレードまでの価格差が100万円以上に及ぶため、コストパフォーマンスを重視するユーザーは迷いがちです。また、同じエンジン構成でも装備差によって価格が変わる構成は、「わかりにくい」「不親切」と受け止められることもあります。
適切な提案ができる販売現場の強化が不可欠
このような複雑な構成をユーザーに正確に伝え、最適なグレードを提案するには、販売スタッフの教育と提案力が重要です。ユーザーの使用目的や家族構成、予算に応じたカスタマイズ提案ができなければ、他ブランドへ流れてしまう可能性も高まります。
リセールバリューの不安
トヨタやレクサスに比べ、マツダ車は中古車市場での評価が低く、購入後の価値低下を心配する声も根強くあります。
中古市場におけるブランド信頼度の差
リセールバリューは単に車両の品質だけでなく、ブランドへの信頼感や知名度によっても左右されます。トヨタやレクサスは国内外でのブランド認知が高く、中古車市場でも一定の需要が常に存在しています。これに対して、マツダは高級ブランドとしての認知がまだ十分とは言えず、特に高価格帯モデルでは中古での買い手が付きにくい傾向にあります。
高額モデルほど目立つ下落率
CX-80のように新車価格が500万〜700万円台に達するモデルは、リセール時の下落幅が目立ちやすい傾向にあります。例えば、3年落ちでの残価が60%を切るような場合、100万円以上の差損が生じることもあり、これが購入時の心理的ハードルとなっています。
グレードやパワートレインによる差も大きい
CX-80はガソリン・ディーゼル・PHEVとパワートレインが多様ですが、PHEVは特に中古市場での価値が読みにくいという側面もあります。充電環境の普及率やバッテリー劣化の懸念が影響し、リセール面ではディーゼルの方が優位とされることも。
マツダの残価設定型ローンとの関係
マツダも他メーカー同様に残価設定型ローン(残クレ)を提供していますが、リセールバリューが相対的に低いため、残価設定額と実際の買取相場にギャップが生じやすく、再契約や下取り時に思わぬ追い金が発生するケースも見られます。
リセール対策には何が必要か?
ブランド力を高める長期戦略とともに、下取り保証制度の拡充やグレード・装備別の将来価値シミュレーションの提供など、ユーザーの不安を緩和する具体的な施策が求められます。購入時に「売るときのことまで考えた提案」があるかどうかが、販売店における信頼にも直結する時代です。
プレミアム戦略の限界
高品質な商品を生み出しても、ブランド価値が伴わなければ販売には繋がりません。マツダの挑戦は今まさに正念場です。
商品力とブランド価値の非対称性
CX-80は、走行性能や装備、内外装の質感など、商品としての完成度は非常に高いものの、マツダというブランドが持つ“高級車”としての印象がまだ浸透しておらず、価格帯に対する納得感を得にくい状態にあります。この非対称性が、販売の足かせとなっています。
プレミアムユーザー層の期待とのギャップ
レクサスやBMWなどのユーザーが求める「所有満足感」「ブランドを通じた自己表現」といった情緒的価値に対して、マツダはまだ応えきれていません。CX-80は確かに性能や装備では肩を並べる部分がありますが、「ステータス」としての選ばれ方には差が残っています。
プレミアム戦略の再定義が必要
今後マツダがプレミアム路線を継続するのであれば、単に価格や装備を引き上げるのではなく、ブランド全体として“選ばれる理由”を創出していく必要があります。店舗体験やアフターサービス、ユーザーコミュニティとの関係性など、商品以外の側面での価値提供も強化しなければ、真のプレミアム化は達成できません。
ラージ商品群の成否が将来を左右する
CX-60やCX-80など、マツダが今後の主力と位置付けているラージ商品群の成功如何は、次世代EVへの投資や北米戦略の持続にも直結します。ここでの失敗は単なるモデル不振にとどまらず、企業の成長シナリオ全体に影を落とすリスクを孕んでいるのです。
北米市場での成功に学べ
マツダが築いた“価値重視”の評価軸
マツダは北米市場において、価格競争ではなく「走行性能」「デザイン性」「作りの丁寧さ」といった“価値”にフォーカスしたブランディングに成功しています。現地のユーザーからは「ドライバーズカーとしての魅力がある」「日本車でありながら欧州車的な質感を持つ」といった評価を得ており、競合との差別化が明確に図られています。
ディーラー改革と販売体験の変化
2016年以降、北米マツダではディーラー改革を推進し、内装のリニューアルや販売スタッフのブランド教育を徹底しました。その結果、単に車を売る場から、“マツダの世界観を体験できる場”へと変貌。これがCXシリーズ全体の販売力強化に大きく貢献しています。
北米戦略から日本市場への応用可能性
この北米成功モデルは、日本市場にも応用可能です。特に、「性能や装備の優位性」ではなく「体験価値の提示」に力を入れること、店舗空間や接客体験を高級ブランド水準に引き上げることが、日本のCX-80の再評価につながる可能性があります。
日本市場での“逆転発想”の重要性
日本では依然として「価格に見合うブランドか?」という問いがつきまといますが、北米での成功は「マツダでも高級車を持つ理由」が明確になった証とも言えます。マツダは今こそ、国内においても“価格より価値”のブランドストーリーを再構築すべき時期に差しかかっています。 マツダは北米で販売記録を更新中。価格ではなく“価値”で勝負するブランディングに成功した好例として、日本市場でも参考になる点が多いです。
マツダCX-80の世間に伝わらない魅力と実力
高い走行性能と静粛性
FRベースのプラットフォームにより、応答性の高いハンドリングと高速安定性を実現。他社のFFベースSUVとは一線を画しています。
応答性の鋭さとドライバーへの一体感
CX-80は前後重量配分に優れたFRレイアウトにより、ステアリング操作に対する応答性が極めて高く、運転者の意図に忠実に動く車両挙動を実現しています。特に山道やワインディングロードでの操縦性は、SUVでありながらスポーツセダンに近いフィーリングを与えてくれます。
高速安定性と直進性能の高さ
長距離走行時におけるCX-80の直進安定性は抜群で、時速100kmを超える高速域でもボディのふらつきが少なく、同乗者も快適な乗り心地を維持できます。これにより、ファミリーユースでのロングドライブにも適したモデルとして評価されています。
遮音構造による静粛性の向上
CX-80ではフロア下、ドア、ルーフに高性能な吸音材や遮音パネルを配置し、路面ノイズや風切り音を大幅にカット。加えて、エンジンルームの遮音対策も徹底されており、アイドリング時や低速走行中の静けさは、輸入高級車にも匹敵するレベルに達しています。
パワートレイン別の走行フィーリング
2.5Lガソリンモデルは軽快さが際立ち、街中での取り回しがしやすく、ディーゼルモデルは厚みのあるトルクによって坂道でも余裕ある加速を実現。一方でPHEVモデルは電動モーターによるレスポンスの良さと静寂性が際立ち、短距離通勤や都市部での使用において真価を発揮します。
ドライバー重視のサスペンションチューニング
マツダの「人馬一体」思想を体現するべく、CX-80のサスペンションは応答性と快適性のバランスを極限まで追求。路面の細かい凹凸を吸収しながらも、ドライバーには必要な情報だけがフィードバックされるように設計されています。これにより、路面追従性と操舵感の両立が高い次元で成立しています。
上質な内装と装備
本革シートやウッド調パネル、12.3インチモニター、BOSEサウンドなど、高級車顔負けの装備を多数搭載しています。
インテリアデザインの美学
CX-80の内装デザインは、直線的かつ水平基調の造形が特徴で、車内に広がりと安定感を演出しています。素材の選定にもこだわり、ソフトパッドや本木目調トリムなどが随所に配置され、高級感と温もりのある空間を両立しています。
上級グレードにみられる特別装備
上級グレードではナッパレザーのシートやオーナメントパネルに本物の木材を使用するなど、ラグジュアリーな質感に徹底的にこだわっています。また、前席にはベンチレーション機能やメモリー付き電動シートが搭載され、快適性も抜群です。
先進的なインフォテインメントシステム
12.3インチの大型センターディスプレイは高解像度で視認性が高く、Apple CarPlayやAndroid Autoに対応。さらに、音声認識機能やドライバーアテンションアラートなども搭載され、操作性と安全性が両立されています。
BOSEサウンドの臨場感
プレミアムオーディオとしてBOSE製スピーカーを搭載し、13スピーカーによる立体的な音響空間を実現。クラシックからロックまで、あらゆるジャンルの音楽が車内で臨場感をもって再生されます。
快適性を高める細やかな装備
フロントとセカンドシートのシートヒーター、リアの独立温度調整可能なエアコン、アンビエントライトなど、細やかな快適装備も充実。夜間走行時には間接照明が室内の質感をさらに高め、長時間の移動でも快適さが持続します。
多彩なシート構成
2列目はベンチシート、キャプテンシート、キャプテンシート+コンソールボックス付きの3種が用意され、家族構成やライフスタイルに合わせて選べます。
乗員数や用途に合わせて選べる柔軟性
ベンチシート仕様では最大7名の乗車が可能となり、大家族や多人数での移動にも対応。一方でキャプテンシート仕様は乗員数を6名に抑える代わりに、2列目の居住性と快適性が格段に向上します。ロングドライブやチャイルドシート利用時にありがたい設計です。
キャプテンシート+コンソールの利便性
キャプテンシート+コンソールボックス付き仕様では、2列目に独立したアームレスト収納やドリンクホルダー、USBポートなどが備わり、まるで航空機のビジネスクラスのような快適さを実現。小さな子どもがいる家庭では、おもちゃやガジェット類の収納にも重宝します。
3列目シートの使い勝手と居住性
3列目シートも十分なスペースが確保されており、大人でも短距離であれば快適に乗車可能。足元の空間も広く、2列目のスライド調整でさらに余裕を持たせることができます。また、乗降時のアシストグリップやワンタッチスライド機構により、後席へのアクセス性も高められています。
ラゲッジスペースとの両立
3列目を使用しない場合には、ラゲッジスペースが大容量に変化。ベビーカーやキャンプ用品も余裕で積載可能です。リアの荷室は電動開閉式テールゲートを採用しており、荷物の出し入れもスムーズに行えます。
優れた安全性能
I-ACTIVSENSEによる先進安全装備を標準搭載し、ACCや車線維持支援、交差点支援などが充実。ファミリー層にも安心です。
標準装備の先進安全機能
CX-80には、マツダの先進安全技術「i-ACTIVSENSE」が全車標準で装備されています。具体的にはアダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)、車線逸脱警報(LDWS)、車線維持支援システム(LAS)、ブラインドスポットモニター(BSM)、スマート・ブレーキ・サポート(SBS)などが含まれており、事故回避性能が飛躍的に向上しています。
交差点支援と夜間歩行者検知
交差点支援機能では、対向車や横断歩行者の動きに対応して自動的にブレーキ制御を行う仕組みが搭載されています。また、夜間でも歩行者や自転車を検知できるカメラ性能があり、暗い時間帯の事故リスクを軽減します。
高齢者にも配慮した設計
加齢により運転能力に不安があるドライバー層に向けて、誤発進抑制制御や360°ビューモニター、駐車時の障害物検知なども整備されており、運転に自信がないユーザーでも安心してハンドルを握れるようになっています。
衝突安全性能の徹底追求
アクティブセーフティに加え、万が一の事故に備えた衝突安全性能も強化されています。軽量高剛性のスカイアクティブ・ボディ構造に加え、複数のエアバッグ、側面衝突対応の骨格設計が施され、乗員の保護性能が大きく高められています。
安全性能の評価とユーザーの声
実際にCX-80を選んだユーザーからは、「安心感が段違い」「高齢の親を乗せるときも信頼できる」といった声が多く聞かれます。安全性能の高さは家族持ちだけでなく、運転支援を求める全ユーザー層にとっての大きな訴求点となっています。
魅力的なPHEVモデル
街乗りではEV走行、長距離ではハイブリッド。理想的な使い分けが可能ですが、家庭の充電環境によっては真価を発揮しにくい点も。
都市部でこそ活きる電動走行性能
PHEVモデルの最大の魅力は、短距離・低速域でのEV走行が可能な点です。通勤や買い物などの日常利用ではガソリンを一切使わずに走行できるため、経済性に優れ、環境負荷も軽減できます。アクセルを踏んだ瞬間のスムーズな加速感も、電動ならではの魅力です。
長距離移動時の安心感あるハイブリッド走行
長距離ドライブではバッテリー容量を使い切った後にエンジンが自動的に作動し、ハイブリッドモードへと移行。燃費性能を維持しつつ、給電スポットを気にせず遠出ができるのは、PHEVならではの大きな安心材料です。
充電環境による利便性の差
PHEVモデルを最大限活用するには、自宅に充電設備があるかどうかが大きなポイントになります。200Vの普通充電器であれば約4〜5時間でフル充電が可能ですが、マンションや賃貸住宅では設置が困難なケースもあり、潜在的な購入障壁となっています。
燃費性能と実燃費のギャップ
カタログ燃費では高い数値が出るPHEVですが、実際の使用状況によってはエンジン稼働が多くなり、燃費メリットが薄れるケースもあります。特に急勾配やエアコン常用、高速走行などが重なると、想定より燃費が伸びないという声もあります。
補助金制度と減税の恩恵
PHEVは政府のエコカー減税や地方自治体の補助金対象となる場合が多く、実質的な購入価格を抑えることができます。特にエネルギー価格が上昇している現在において、経済的インセンティブとしての価値も見逃せません。
将来のEV化を見据えた選択肢として
完全なEVへの移行に踏み切れない層にとって、PHEVは「電動化の橋渡し」として理想的な選択肢となります。充電の習慣やEV走行の体験を積む中で、将来的なEV転換への心理的・実用的なハードルを下げることにもつながります。
ユーザー満足度は高い
実際のオーナーの評価では、走行性能や内装、安全装備などに高評価が集まり、試乗後の即決購入も珍しくありません。
購入者のリアルな声
多くのオーナーからは「運転するたびに感動する」「見た目の美しさと走行性能のバランスが素晴らしい」といった感想が聞かれます。CX-60で感じた硬さや粗さが改善されており、「乗り味が洗練された」「家族が長距離でも快適に過ごせるようになった」といった家族層からの評価も目立ちます。
安全性能と運転支援機能の信頼性
「ACCの精度が高く安心できる」「ブラインドスポットモニターが実用的」など、先進安全装備の使い勝手や信頼性にも満足の声が寄せられています。特に高齢の親を同乗させるユーザーからは「安心感が段違い」とのコメントも。
内装の質感と装備の満足度
「ナッパレザーの肌触りが上質」「BOSEの音響が車内全体に広がる」「大画面モニターが見やすく操作も直感的」など、内装の上質さと装備の先進性についても多くの支持が集まっています。
EV走行の利便性
PHEVモデルを選んだユーザーからは「街乗りではガソリンを使わずに済むのがありがたい」「通勤距離が短いため、ほぼEVで済んでいる」など、電動化のメリットを享受している声も多く見られます。
試乗体験での評価逆転
「乗るまでは価格に抵抗があったが、試乗して即決した」という声もあり、実車体験によってCX-80の魅力に気づくケースが多数存在します。外観・内装・走りの三拍子が揃っており、隠れた実力派という評価も定着しつつあります。
まとめ
マツダCX-80は、車そのものの完成度は非常に高く、走行性能、内装、安全装備、PHEV技術など、全方位で魅力を備えたモデルです。しかし、価格設定やブランドイメージとのギャップ、CX-60のリコール問題、伝わりにくい魅力といった複合的な要因が販売不振を招いています。マツダがこの状況を打破するには、単なる価格調整や宣伝ではなく、「なぜCX-80なのか?」というストーリーを明確に伝え、ブランドの再定義を進めていくことが求められます。