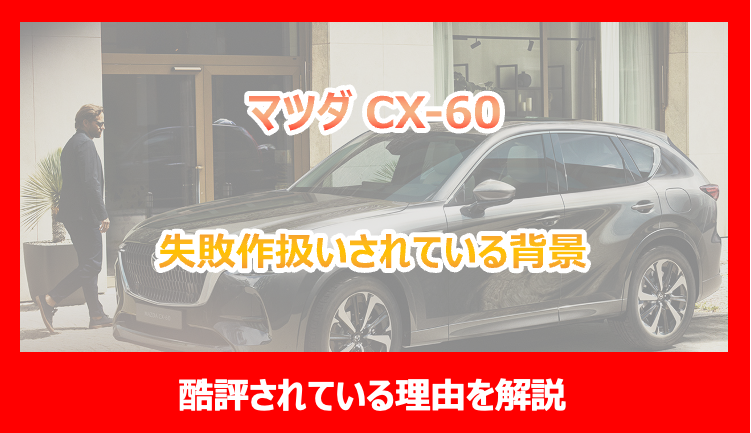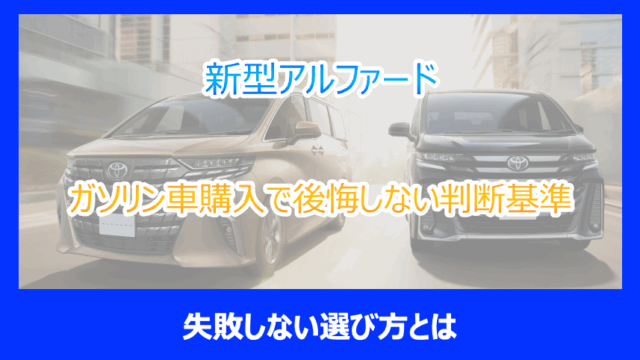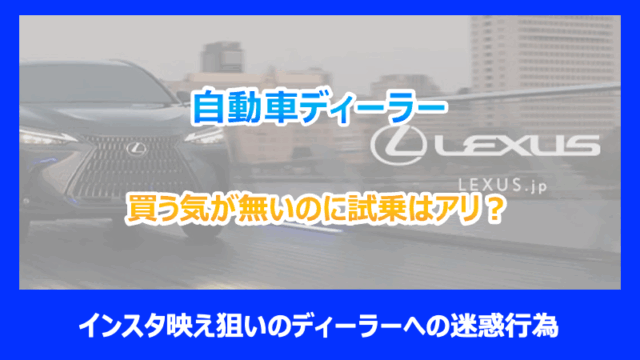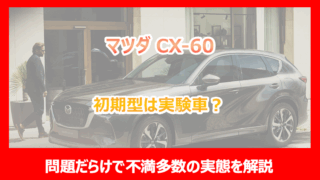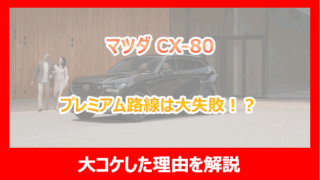マツダが満を持して送り出した新世代SUV「CX-60」。

引用 : MAZDA HP (https://www.mazda.co.jp/cars/cx-60/feature/)
力強いディーゼルエンジンや高剛性ボディなど、多くの魅力を兼ね備えながらも、日本国内では厳しい評価を受け、「失敗作」とまで言われてしまっています。
では、なぜここまで酷評されるのか?その理由をユーザー視点で深堀りしていきます。
記事のポイント
- CX-60が失敗作と呼ばれる要因を7つに分類して徹底解説
- リコールの多さや乗り心地の悪さなど、具体的な不満点を詳細に分析
- 高価格帯におけるライバル車との比較から見るCX-60の位置付け
- 今後の改善ポイントや再評価の可能性についても考察
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

CX-60が酷評される背景とは?
ラージ商品群としての戦略的失敗
CX-60は、マツダが掲げたラージ商品群の第一弾モデルとして、従来よりもサイズ・装備ともに上級志向で設計されました。

引用 : MAZDA HP (https://www.mazda.co.jp/cars/cx-60/feature/)
このラージ商品群はグローバル市場、特に欧州を中心とした海外市場でのプレミアムブランド確立を目的として展開されたものであり、CX-60もそのフラッグシップ的な存在として開発されました。
従来のマツダファンとの価値観の乖離
従来のマツダ車は「走りとコスパのバランスが取れた実用車」という評価を受けており、ユーザーもそれを前提に車選びをしてきました。しかしCX-60は、価格帯も装備も一段階上を狙った設計思想のため、「高額でマツダらしくない」と感じたユーザーも多く存在しました。その結果、初動こそ注目されたものの、継続的な需要を掴むことができませんでした。
プレミアム化戦略の市場不適合
マツダはこのCX-60でBMWやアウディなどの欧州プレミアムブランドに肩を並べようとしましたが、日本市場ではこの戦略がうまく機能しませんでした。特に日本では高価格帯車には「静粛性」「快適性」「ブランド信頼性」が強く求められます。ところがCX-60は、走行性能に振り切った設計により、乗り心地やエンジン音などでネガティブな評価を受けたため、期待とのズレが明確になりました。
ネーミングとコンセプトのわかりにくさ
「ラージ商品群」という呼称そのものが一般消費者には伝わりづらく、「何がラージなのか」「なぜ高いのか」が直感的に伝わりにくいことも、販売面での足かせとなりました。マーケティングの面でも、プレミアム路線をしっかりと伝えるだけの明確な価値訴求ができなかった点は否めません。
ユーザー評価が急落した理由
発売直後は注目度が高く、2023年初頭には月間3000台超の販売実績を記録するなど、華々しいスタートを切ったCX-60。しかし、その勢いは長く続かず、わずか半年ほどで販売台数は急激に減少しました。
急速な販売減少の具体的推移
販売は2023年1月に3023台、2月に4375台、3月に4313台と好調でしたが、4月以降は下降線をたどり、2023年9月にはついに月間販売台数が1000台を下回る事態に。2024年8月にはわずか440台にまで落ち込み、月間販売目標2000台の4分の1以下という深刻な状況に陥りました。
なぜ一気に売れなくなったのか?
この急激な売上低下の背景には複合的な要因が絡んでいます。主に以下の3点が大きな原因と考えられます。
- 初期の期待値が高すぎたことにより、実際の性能や乗り心地とのギャップに失望したユーザーが多かった。
- 発売直後から立て続けにリコールが発生し、信頼性に対する不安が拡大。
- ネット上で悪い口コミが急速に拡散し、購入検討層に強いネガティブイメージを与えた。
ネガティブな口コミの影響力
現代では車の購入前にレビューサイトやSNSで情報収集を行うユーザーが大半を占めています。CX-60は「リコールが多い」「乗り心地が悪い」「エンジン音がうるさい」などの声が多く、それが購買意欲を削ぐ要因となりました。たとえ性能面で優れていても、ネガティブな印象が先行すると販売には結びつきません。
ファーストインプレッションの大切さ
特に高価格帯車においては、最初の数ヶ月の市場評価が中長期的な販売を大きく左右します。CX-60はスタートダッシュに成功したにもかかわらず、その後の品質問題や評価のブレによって“期待外れ”というレッテルを貼られてしまった点が惜しまれます。
頻発するリコールの信頼性低下
CX-60は発売から2年足らずで8回ものリコールを経験しており、その頻度は他の国産車と比べても極めて高い水準です。特に問題視されるのは、その多くが車両の根幹に関わる深刻な不具合だった点です。
初期リコールが与えたインパクト
初期のリコールは、発売からわずか1〜3ヶ月後に発表されました。具体的には、ナットの緩みによる異音発生や、インバーターの不具合でエンジンが始動しないといった問題が報告されており、ユーザーの信頼を大きく損なう結果となりました。新車購入直後にリコールの通知が届くという状況は、購買意欲に冷や水を浴びせることにも繋がります。
3ヶ月に1回の頻度で発生する異常事態
CX-60のリコールは、平均すると3ヶ月に1回以上のペースで発生しており、業界でも極めて異例です。単なる電子系の不具合だけでなく、エンジン出力低下や燃料ポンプの異常など、走行性能や安全性に関わる重要なパーツに不具合が集中しています。
リコールが販売台数に与えた影響
これらのリコールが与えた影響は大きく、発売当初は高評価だったにもかかわらず、販売台数は急激に減少しました。実際にネット上でも「マツダ=リコール多発メーカー」といったネガティブなイメージが定着し、CX-60に限らずブランド全体の信頼性にも陰りを落としました。
改善の兆しと今後の対応
ただし、マツダ側もこうした状況を重く受け止め、リコール対応の迅速化や製造ラインの見直しを進めているとされます。既存オーナーへの丁寧なアフター対応や、原因究明と再発防止策を徹底することが今後の信頼回復の鍵になるでしょう。
リコール内容が致命的
リコールの中には「走行中にエンジンが停止する恐れ」や「減速中に動力が完全に切れてしまい発進不能になる」など、命に関わるような重大不具合も含まれていました。こうしたリスクは、安全性を重視するファミリー層や高齢者にとって、購入を敬遠する十分な理由となります。
エンジン関連の重大トラブル
2023年6月に発表されたリコールでは、エンジン出力が突然低下したり、最悪の場合はエンジンが完全停止する恐れがあると報告されました。特に、高速道路走行中や交差点での発進時にこうしたトラブルが起こると、事故に直結しかねない重大な問題です。
燃料ポンプやトランスミッション系の不具合
2023年9月には、燃料ポンプの不具合により走行中にエンジンが停止する可能性があるとされるリコールが出されました。さらに2024年7月には、トランスミッション制御コンピューターの不具合により、強くブレーキを踏んだ後にエンジン出力が途絶え、アクセルを踏んでも発進できないというリスクも判明しています。
命を預ける製品としての信頼性問題
自動車は生活インフラの一部であると同時に、人命を預かる移動手段でもあります。そのため、これほどの頻度で重大なリコールが発生するという事実は、ブランド全体の信頼性を大きく損なう要因となります。マツダファンであっても「今回は見送る」と判断する声が多かったのも無理はありません。
プレミアム志向と乗り心地のミスマッチ
高級SUVを謳うCX-60ですが、低速域での突き上げや後席の乗り心地の悪さが多くの不満を集めました。これはスポーティな走行性能を追求するあまり、快適性が犠牲になった結果です。
サスペンション設定の問題
CX-60は欧州車のような硬めのサスペンションセッティングが採用されており、特に街乗りでの段差や舗装の荒れた道路での突き上げ感が強く出やすい構造になっています。これは高速道路などでは安定性を生み出す一方、日常の走行シーンでは不快に感じるユーザーも多く、特に同乗者からの評価が厳しい傾向があります。
後席の快適性に対する不満
多くの口コミでは「後席に人を乗せるのが申し訳ない」といった声があり、リアシートのクッション性や路面からの衝撃吸収性が十分でないことが原因とされています。ファミリーユースや送迎目的のユーザーにとって、後席の快適性は重要な選定基準の一つであるため、ここでの不満は致命的です。
プレミアムSUVとしての認識とのギャップ
日本のユーザーが“プレミアムSUV”に求める要素には、しなやかな乗り心地と高い静粛性が強く含まれています。しかしCX-60は「走りの楽しさ」を優先し、そこに振り切った設計であるため、期待とのズレが大きくなりました。価格帯的にもトヨタ ハリアーやレクサスNXと競合する中、快適性で劣っていると評価されてしまうのは非常に不利です。
エンジン音の大きさが高級車にふさわしくない
アイドリング中のディーゼルエンジン音がうるさいとされ、高級車に求められる静粛性が不足しているという指摘が多く見られます。特にハイブリッド車やEVに慣れたユーザーからは、その音の大きさが顕著に感じられ、評価は非常に厳しいものとなりました。
ディーゼル特有の騒音が与える印象
CX-60に搭載されるディーゼルエンジンはパワフルさが魅力ですが、その一方でアイドリング時や加速時のエンジン音が耳に残りやすく、「重厚感」を通り越して「うるさい」という印象を持たれがちです。特に静粛性を重視する高級SUVの購買層にはネガティブに捉えられやすい傾向があります。
他の高級車との静粛性比較
同価格帯にあるレクサスNXやトヨタ ハリアーのハイブリッドモデルは、エンジン音が非常に静かで、車内では会話や音楽が快適に楽しめると高く評価されています。対してCX-60は走行中のエンジンノイズが車内に響く場面もあり、「高級車としての洗練さに欠ける」と言われる要因の一つです。
静粛性を期待していたユーザーの失望
高級車に求められる「静けさ」は、単なる快適性の一部ではなく、購入理由そのものとなることも多い要素です。期待を込めてCX-60を試乗したユーザーの中には、「車自体は良いのに音が残念」「価格を考えるとがっかり」といった感想を持つ人もおり、その失望感がSNSやレビューサイトを通じて拡散され、購入検討者に悪影響を及ぼしています。
コスパの悪さと価格帯の中途半端さ
CX-60は320万円から650万円超まで価格幅がありますが、500万円を超えるグレードが売れ筋であり、手軽とは言い難い価格帯です。その一方で、ライバルには同価格帯で性能・信頼性の高いトヨタハリアーやレクサスNXが存在します。
ライバルとの比較で見えるCX-60の弱点
トヨタ ハリアーとの直接対決
ハリアーは同価格帯でありながら、静粛性・快適性・燃費性能などが高く評価され、国内販売ランキングでも上位をキープ。販売実績においてもCX-60を大きく引き離しています。
ハリアーの販売実績と人気の理由
トヨタ ハリアーは、年間販売台数が4万台を超えることもある人気SUVであり、その人気の背景には「価格に対する満足度の高さ」が挙げられます。ハイブリッドモデルを中心に、低燃費・高静粛性・上質な内装といった要素がバランスよく整っており、幅広い世代に支持されています。
CX-60との価格帯比較
両車の価格帯は重なっていますが、CX-60は500万円超のモデルが売れ筋であるのに対し、ハリアーは400万円前後で高性能なハイブリッドモデルが選べるという価格面での強みがあります。この価格差が「高くて中身が微妙」と感じられがちなCX-60との差別化を生んでいます。
使用目的に対する適合性の違い
ハリアーは街乗り中心のユーザーにとって、柔らかい乗り心地や静粛性が高く評価される一方、CX-60は高速域やワインディングでの走行性能は優れるものの、日常使いにおいては評価が分かれる傾向があります。通勤・買い物・家族移動といった使用用途において、ハリアーの実用性と安心感は非常に大きな武器です。
ブランドイメージと安心感
「トヨタ」というブランドが持つ信頼感は、日本国内で非常に強く作用します。マツダのCX-60は新しい試みが詰まった挑戦的な車である一方、ハリアーは「選んで間違いがない車」という評価が広まっており、初めての高級SUV購入層にも受け入れられやすい存在です。
レクサスNXとのブランド力の差
レクサスは信頼性とブランド力で圧倒的に優位。アメリカの信頼度ランキングでも1位に輝いた実績があり、CX-60が同価格帯で勝負するには無謀とも言える挑戦でした。
レクサスが築いた信頼と実績
レクサスはトヨタの高級車ブランドとして、30年以上にわたり世界中で品質とサービスの高さを評価されてきました。特にアメリカでは『信頼できるブランド』『壊れにくい車』としてのイメージが浸透しており、JDパワーなどの信頼性調査では常に上位を維持しています。
サービス品質とブランド体験の差
レクサスは販売後のアフターサービスにも力を入れており、専用のレクサスディーラーで受けられる丁寧な対応やラグジュアリーなショールーム体験など、ブランド全体として一貫した高級感を演出しています。一方、CX-60は一般のマツダ店舗での対応となるため、購入から保有までの“体験価値”にも明確な差が生じています。
国内市場におけるブランド認知の違い
日本市場では「レクサス=高級」「マツダ=コスパ」というイメージが根強く、同じ価格帯の車でもブランドネームが与える安心感は大きく異なります。特に500万円以上の車両購入においては、長期保有やリセールバリューを重視する傾向も強く、ブランド力のあるレクサスが優先されがちです。
CX-60がレクサスと競合する難しさ
CX-60は走行性能や内装など一部ではレクサスに匹敵する要素を持っていますが、ユーザーが車に求める“総合的な満足感”という観点で見ると、レクサスにはまだ及びません。ブランド力・信頼性・快適性・静粛性・サービス品質といったすべての面で勝負するには、CX-60にとってはハードルが高すぎるというのが現状です。
CX-60のパフォーマンス優位性はあるのか?
エンジン出力や燃費性能では他車を凌駕するスペックを持っています。特に3.3LディーゼルやPHEVモデルのパワーは魅力ですが、それを活かすステージが限られていることも問題です。
走行性能の実力値
CX-60に搭載される3.3L直列6気筒ディーゼルエンジンは、最高出力231PS、最大トルク500Nmという高トルク設計で、一般的なガソリンSUVよりも圧倒的に力強い加速感を実現しています。さらにPHEV(プラグインハイブリッド)モデルでは、システム総合出力327PSと、レクサスNX 350h(243PS)を大きく上回るパフォーマンスを誇ります。
燃費性能の高さも魅力
意外かもしれませんが、CX-60はこの高出力ながらも燃費性能も高水準にあります。ディーゼルモデルでリッター19.6km(2WD)、PHEVモデルでEV走行のみなら最大60km程度の電動航続が可能です。環境性能と経済性を両立した設計は、単なるスポーツ性能だけでないバランスの良さを示しています。
走行ステージの制約
ただし、このパフォーマンスを実感できるステージが限られているのが課題です。街乗り中心の日本の道路環境では、そのエンジン性能を活かす場面が少なく、渋滞や低速走行時には持て余してしまうケースも。逆に高速道路やワインディングでは抜群のパフォーマンスを発揮しますが、それが日常の魅力として伝わりにくいというジレンマがあります。
ユーザーの期待とのギャップ
多くのユーザーは、スペック上のパフォーマンスよりも“快適性”や“取り回しの良さ”を重視する傾向にあり、CX-60のパワーは必ずしも万人向けとは言えません。特に女性ユーザーや年配層には「扱いにくい」「大きすぎる」といった声も上がっており、ハイパフォーマンス=高評価とはなりにくい現実もあります。
海外評価とのギャップ
欧州市場での高評価の理由
CX-60は欧州をはじめとする海外市場では高い評価を受けています。特に注目されているのは、BMWやアウディといった欧州プレミアムブランドと肩を並べるような走行性能とボディ剛性の高さです。3.3L直6ディーゼルエンジンによるトルク感や、FRベースのプラットフォームによる安定した走行フィーリングが、欧州の自動車ジャーナリストやユーザーに好意的に受け止められています。
日本市場との価値観の違い
一方で日本市場においては、SUVに求められる要素が異なります。日本のユーザーは、日常使いにおける静粛性、乗り心地、取り回しのしやすさを特に重視する傾向があります。そのため、硬めのサスペンションやディーゼルエンジンの音など、CX-60が誇る特徴がネガティブに受け止められるケースが多くなっています。
海外評価が販促に繋がらない理由
CX-60のグローバル評価は事実として優れているにもかかわらず、それが日本国内の販売には直結していません。これはマーケティングや販売戦略の問題も大きく、海外での受賞歴や専門誌の高評価が一般ユーザーに十分伝わっていないためです。また、「海外で評価されているから良い車」という論調が、日本の消費者には説得力を持たない傾向も見られます。
ローカライズの重要性
今後CX-60の国内評価を改善するには、海外仕様のまま売るのではなく、日本市場向けに特化した改良やチューニングが不可欠です。たとえば、よりマイルドなサスペンション設定や静粛性を強化した特別仕様など、実際の使用環境に即したローカライズこそが、ギャップを埋める鍵となるでしょう。
欧米では評価が高いCX-60。パワフルな走行性能や高剛性ボディは、海外ユーザーには支持されています。しかし、日本市場での評価はあくまで”日常使い”に求められる快適性や静かさが基準です。
CX-60に評価されているポイントもある
インテリアの質感と素材感
CX-60の内装は「和」の要素を感じさせる織物や本木を使ったデザインが特徴。質感も高く、特に上位グレードのツートン仕様は高級感を演出しています。
和モダンデザインの魅力
ダッシュボードやドアトリムには、日本の伝統美を感じさせる織物や天然木が使用され、視覚的にも触覚的にも上質感を味わえる空間に仕上がっています。特に「墨流し」と呼ばれる模様表現は、日本の工芸美を現代的に取り入れたユニークな取り組みとして高い評価を受けています。
上質な素材使い
上位グレードでは、ナッパレザーや本木目のパネルなど、高級素材がふんだんに使われています。これにより、内装全体が柔らかく包まれるような落ち着いた雰囲気を醸し出しており、乗るたびに「特別な空間」に浸れる設計です。
細部に宿るこだわり
スイッチ類やステアリング周辺などの細部の仕上げも丁寧で、ボタンのクリック感やエアコンダイヤルの質感など、触れる部分にもしっかりとした上質さを感じさせます。このようなディテールのこだわりは、実際に所有する喜びを大きく引き上げてくれる要素です。
静粛性との相乗効果
インテリア素材の質感の高さは、静粛性と組み合わさることでさらなる高級感を演出します。ディーゼルエンジンの音が話題になりやすいCX-60ですが、内装素材の吸音性もあり、車内では落ち着いた印象を受けるとの声もあります。
次世代の装備・機能
顔認証によるポジション調整機能や、先進のドライバーモニタリングシステムなど、最新の運転支援装備が多数搭載されています。特に注目すべきは、PHEVグレードにおけるEV走行モードの存在で、環境性能と快適性の両立が図られています。
顔認証による個人設定
ドライバーが乗車するだけで顔認証により、シートポジションやミラー角度、空調設定まで自動で調整される機能は、利便性と未来感を両立させた次世代装備の象徴といえるでしょう。複数人での共有利用が想定されるファミリー層にも好評です。
電動走行モードの有用性
PHEVモデルでは、EVモードを選択することでエンジンを使わずに静かでスムーズな走行が可能。通勤や買い物など、日常の短距離移動では完全なEVとして活用でき、燃料代の節約と排出ガス削減に貢献します。
全方位運転支援機能
レーンキープアシストや緊急ブレーキ、自動駐車支援機能なども装備されており、運転に不慣れな人でも安心して扱える仕様です。これらの装備は、安全性向上に直結するため、家族を乗せる機会の多いユーザーには心強いポイントです。
インフォテインメントの進化
12.3インチの大型ディスプレイや、Apple CarPlay/Android Auto対応、車内Wi-Fi機能など、コネクティビティも充実。車内を移動空間としてだけでなく、情報端末としても機能させる次世代設計が感じられます。
高速走行時の安定性とスポーティ性能
街乗りでは乗り心地に難がある一方で、高速道路や山道ではその剛性と走行安定性が高く評価されています。特に直進安定性やステアリングの応答性は優れており、運転する楽しさを追求するユーザー層に強く訴求します。
FRレイアウトによる操縦安定性
CX-60はFR(後輪駆動)ベースのプラットフォームを採用しており、重心の配分が理想的であるため、高速域での車体姿勢の安定性が際立ちます。コーナリング時でもリアが安定してついてくる感覚があり、ドライバーの操作に対する車両の反応が自然で一体感があります。
高剛性ボディとダイナミック性能
ボディ剛性の高さは、路面からの入力に対する車体のねじれを抑えるだけでなく、サスペンションの性能をフルに活かす基礎になります。CX-60はフロア構造の強化や溶接点の増加などによって、従来モデルと比べても剛性感が格段に向上しており、安定感のある走行フィーリングを生み出しています。
高速域でも疲れにくい走行感覚
高速道路での直進時の安定性が高く、風や路面の段差による揺さぶりが抑えられているため、長距離移動でも疲れにくいというメリットがあります。運転に安心感があるという点も、家族での旅行や出張用途において大きな利点となります。
スポーティさと快適性のせめぎ合い
スポーティな特性が際立つ一方で、サスペンションの硬さが街乗りでの快適性に影響するという評価もあります。逆に言えば、この設計はあくまで“走り”を楽しみたいユーザーを明確にターゲットにしたものであり、万人受けよりも“走行性能重視派”に最適化された設計思想といえるでしょう。
まとめ
CX-60が失敗作とまで言われる背景には、マツダのブランド戦略と実際のユーザーニーズの乖離が大きく影響しています。高価格帯を狙ったプレミアム戦略は、信頼性の低下や快適性不足、そして価格に見合った価値が見出しづらい仕様構成によって国内市場で受け入れられませんでした。
一方で、走行性能や内装品質、先進装備など評価すべき点も多く、今後の改良によっては再評価される可能性もあります。ユーザーが何を求め、どこに価値を感じるかを的確に捉えたアップデートが鍵となるでしょう。