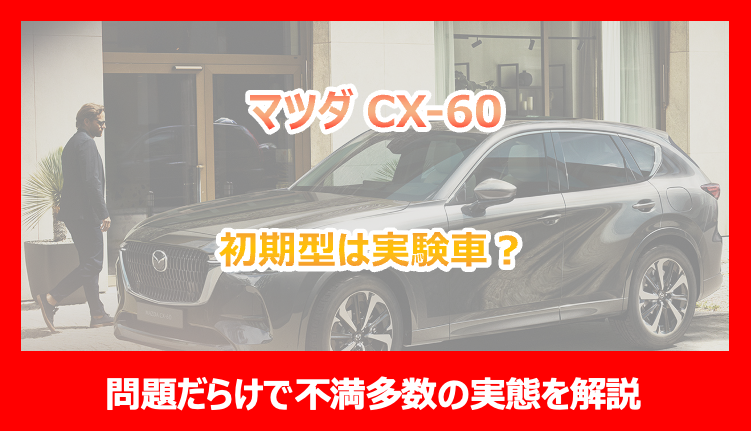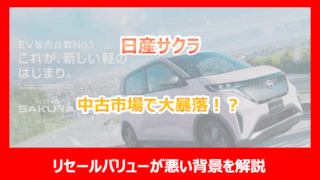見た目の高級感や内装の質感に惹かれてマツダCX-60の購入を検討している方は要注意です。

引用 : MAZDA HP (https://www.mazda.co.jp/cars/cx-60/feature/)
SNSや口コミ、実際のユーザーの声には「想像と違った」「乗り心地が厳しい」など、初期型CX-60に対する不満が多く見られます。
本記事では、購入検討中の方が知っておくべきCX-60の問題点を、実際の体験談を元に徹底解説します。
記事のポイント
- 乗り心地が想像以上に硬いとの声多数
- ハンドルのカクつきがクルーズ中に発生する不具合
- リコール対応後も再発例あり、信頼性に疑問
- 高級感と性能は魅力的だが“未完成感”が拭えない

新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。
マツダCX-60に潜む構造的な問題点
乗り心地が異常に硬い
CX-60最大の不満点として多くのオーナーから指摘されているのが、乗り心地の硬さです。

引用 : MAZDA HP (https://www.mazda.co.jp/cars/cx-60/feature/)
特に一般道を走行中にもドラレコが反応するほどの突き上げがあるとの声が複数寄せられています。SUVでありながらスポーティな味付けがされすぎており、快適性を求めるユーザーには向かないという評価です。
実際の走行体験に基づく違和感
乗り始めた直後から「段差の突き上げが強すぎて身体に響く」との声が続出しています。とくに街乗りや通勤などの日常使用で“常に地面を拾ってしまう感覚”に悩まされるユーザーも多く、普段使いの快適性において重大な欠点とされています。
ライバル車種との比較で感じる劣位性
例えばトヨタ・ハリアーやスバル・フォレスターなどの同価格帯SUVと比較すると、CX-60の足回りは明らかに硬質であり、優雅な移動空間というよりもスポーツカー寄りの緊張感を伴う乗り味に近いという意見が目立ちます。特に高齢者や小さな子どもを乗せる家族層からは「乗員が疲れてしまう」との声も。
メーカーの説明に対する不信感
マツダ側は「距離を重ねることでサスペンションが馴染む」と説明していますが、それが設計上の仕様なのか、あるいは不完全な足回りを“慣れ”で済ませようとしているのかについて、ユーザーの間で疑念が深まっています。「サスペンションの馴染み」といった曖昧な説明は、高級SUVを求める消費者に対しては納得のいかない部分です。
長距離ドライブでの影響
一部ユーザーのレポートでは、100km以上の高速道路走行時でも「突き上げの強さによって同乗者が酔ってしまう」「腰に負担がかかる」などの報告があり、リラックスした長距離移動を期待するドライバーには大きなデメリットとされています。
ハンドリング性能と快適性のアンバランス
CX-60は3.3L直列6気筒ディーゼルエンジンを搭載し、走行性能自体は高く評価されています。
しかし、車高が高いSUVにもかかわらず、あまりにスポーティなサスペンション設定により、街乗りや長距離移動において快適さを損なっています。特に、段差や継ぎ目を超える際の衝撃が強く、同価格帯の他社SUVと比較しても明らかに快適性が劣るとの意見が目立ちます。
エンジン性能と足回りの不整合
パワートレインは文句なしの出来栄えで、トルクの厚さや加速性能には満足しているという声が多く見られます。一方で、その高い動力性能を支えるべき足回りとの整合性に欠けており、結果として「エンジンは素晴らしいが足元がついてこない」という評価に繋がっています。高速走行時の安定感はあるものの、街乗りにおける乗り心地とのギャップが大きく、ユーザーを選ぶセッティングといえます。
スポーティ志向がもたらす誤解
マツダは「人馬一体」の理念を掲げ、ドライバーと車の一体感を重視していますが、CX-60においてはそれが快適性とのトレードオフになってしまっている印象です。あくまで高級SUVとしての側面を期待していたユーザーにとっては、ハンドリングの鋭さや足回りの硬さは“裏切り”ともいえるギャップになり得ます。
市街地での扱いにくさ
低速域でのハンドル操作においても、サスペンションの硬さがダイレクトに伝わるため、細かな凹凸やマンホールを乗り越えるたびにガタつきが生じることがあります。これにより、日常使用でのストレスが蓄積しやすく、特に都市部に住むユーザーからは「扱いにくい」「上品な移動空間とは言えない」といった批判も出ています。
サスペンションが馴染む説の不信感
「ある程度走れば馴染んでくる」とメーカー側は説明しているようですが、ユーザーからは「ただ慣れただけでは?」「本当に構造的に改善されているのか?」といった疑問の声が出ています。実際には、何千km走行しても改善されないというケースもあり、根本的な設計ミスである可能性が否定できません。
馴染むとは何か?定義の曖昧さ
サスペンションが「馴染む」とは具体的にどのような現象なのか、メーカー側から明確な定義が示されていないことが問題視されています。ユーザーの多くは、単に慣れによる体感の変化を「馴染んだ」と錯覚している可能性もあるため、設計者の立場からの技術的な説明が求められます。
サスペンションの寿命との混同
「馴染み」は本当に性能向上なのか、それとも部品の摩耗による劣化の初期段階なのか。多くのユーザーが“乗り心地がマイルドになった”と感じる時点で、実際にはショックアブソーバーが劣化しているというケースもあり、これは「品質向上」とは逆の意味である可能性があります。
他メーカーとの対応差
例えばトヨタやホンダなどの大手メーカーでは、初期段階から快適な乗り心地を提供することを前提に設計されており、「時間が経てば快適になります」といったアプローチはほとんど見られません。この点でCX-60は業界の常識から逸脱しているという指摘もあります。
実際のユーザー報告の信憑性
インターネット上では「2万km走っても硬いまま」といった声もあり、サスペンションが本当に“馴染む”のかについて懐疑的な見方が広がっています。馴染みの兆候すら見られない車両が存在する時点で、「設計段階の問題ではないか」と疑うのは自然な流れといえるでしょう。
個体差があるという不安
一部では「車体によって差がある」といった報告もあり、購入者にとっては“当たり外れ”のリスクが存在することになります。これにより「初期型は実験車では?」との不信感が拡がっています。
品質管理体制への疑問
「同じ車種なのに、当たり外れがある」となると、メーカーとしての品質管理体制に疑問符がつきます。車両ごとに快適性や操作感、さらには不具合の有無が異なるというのは、本来量産車としてあってはならない現象です。
ユーザーの声に見られるばらつき
実際のオーナーからは「自分の車は乗り心地が良好」「全く問題なし」といった声もあれば、「段差の突き上げがひどくて家族が酔う」「異音が出る」など対照的な意見も存在します。この極端なばらつきが、消費者の間に不信感を生んでいます。
初期ロット特有のリスク
初期型に特有の現象として、不具合の発生率が高いという声も多く聞かれます。量産開始後の初期ロットはどうしても試験・調整が甘い傾向にあり、CX-60の場合も「販売を急ぎすぎたのでは?」という見方が根強く存在します。
メーカーの対応姿勢も分かれ目
個体差による不具合や不満に対して、ディーラーやメーカーの対応が誠実かどうかも重要な判断基準です。実際には「仕様です」と一蹴されたケースも報告されており、購入者としては納得のいかない体験につながっています。
他社との比較で見えてくる明確な違い
同価格帯のSUVであるスバル・レヴォーグやトヨタ・ハリアーなどでは、こうした極端な不快感の報告は少なく、CX-60の乗り心地問題はやはり設計そのものに起因している可能性が高いと考えられます。
スバル・レヴォーグとの比較
スバル・レヴォーグはスポーティな走りを持ち味としつつも、サスペンション設定や乗員の快適性を十分に考慮したバランスが特徴です。ハンドリングの応答性も高く、それでいて突き上げが少ないという点で、CX-60よりも日常使いでの快適さが優れていると評価されています。
トヨタ・ハリアーとの違い
トヨタ・ハリアーは静粛性と乗り心地に定評があり、路面の凹凸をいなすサスペンション設定が多くのファミリーユーザーから高評価を得ています。CX-60が硬めの設定でドライバー向けなのに対し、ハリアーは同乗者全体の快適性を優先している印象が強く、「家族向けSUV」としての完成度が高いと言えるでしょう。
ホンダCR-Vや三菱アウトランダーとの評価差
ホンダCR-Vや三菱アウトランダーも同クラスの競合モデルとしてよく比較されますが、どちらも乗り心地と静粛性に重点が置かれています。これらのモデルでは「長距離運転でも疲れない」「上下動がマイルド」といった評価が多く、CX-60のような硬さによるネガティブな意見はほとんど見られません。
総合的な比較評価
結果的に、CX-60は運転者にとっての“走る楽しさ”はあるものの、同乗者の快適性や日常利用のストレス軽減といった視点では、他社の同価格帯SUVに明確に劣る部分が存在します。特に家族構成や用途によっては、CX-60では満足できないケースもあるため、比較検討は必須です。
試乗してもわからない「後から来る違和感」
初期購入層の多くが、試乗せずに予約購入していたことが背景にあります。しかし最近では試乗が可能となっており、購入を検討している方には必ず事前に体感してから判断することが強く勧められます。
試乗では感じにくい長距離ドライブでの疲労感
短時間の試乗では、シートの硬さやサスペンションの突き上げによる疲労感が現れにくいため、「快適だと思っていたが、1時間を超えると腰が痛くなる」といった後悔につながることがあります。特にCX-60のようにスポーティに振った足回りでは、この傾向が顕著です。
操作性や静粛性の評価には時間が必要
ナビゲーションやスイッチ類の操作感、走行中の静粛性なども、試乗では見逃しがちです。特にノイズの種類や音質は、路面の違いによって感じ方が大きく変わるため、短時間の試乗では正確に判断できない場合があります。
経年による変化や初期不具合
試乗車は比較的新しい個体であることが多く、経年劣化や初期不良が発現していないケースも珍しくありません。CX-60では「購入後数千kmで異音が出るようになった」「しばらくしてから電装系に不具合が出た」など、納車後しばらく経ってから気づく不満も多く報告されています。
試乗時に確認しておきたいポイント
購入を検討している方は、試乗時にシートの硬さや足回りの突き上げ、視界の取りやすさ、車内の静粛性、インフォテインメントの応答性などを意識的にチェックすることが重要です。また、助手席や後席にも座って体感することで、家族全体での快適性を見極めることができます。
マツダCX-60のクルーズコントロールによるカクつき問題
ハンドルが勝手にカクつく異常現象
クルーズコントロール使用中、車線維持支援などの機能と連動してハンドルが“ガクガク”と動く不具合が報告されています。SNSで拡散された映像には、ユーザーが不安そうにハンドルを強く握りしめる様子が映っており、快適とはほど遠い様子が伺えます。
ユーザーの実体験に基づく恐怖感
実際にこの不具合に直面したドライバーの声として、「突然ハンドルが小刻みに動き出し、進路が乱れたように感じた」「助手席の同乗者も驚いていた」といった証言が複数確認されています。高速道路での使用を想定した機能であるにもかかわらず、逆に危険を感じるレベルの挙動に、不信感を抱くのも無理はありません。
問題が発生する条件の曖昧さ
特定の条件でのみ発生するのか、常にリスクがあるのかが不明確である点も、ユーザーにとって大きな不安要素です。直線道路・カーブ・雨天時・車線の薄れた場所など、どのような条件で挙動が不安定になるかに関する技術的な説明が不足しており、「いつ発生するかわからない」という精神的ストレスにもつながっています。
本来の目的と逆効果になる可能性
本来、クルーズコントロールと車線維持支援はドライバーの疲労を軽減するための機能ですが、CX-60においてはその逆となり、「かえって神経を使う」「一度体験してからは怖くて使っていない」といった意見が後を絶ちません。
リコール後も再発例がある
この問題はリコール対象となり、一部では「修正された」との報告もありますが、一定期間後に再発したとの声も見受けられます。修理による一時的な回復ではなく、根本的な原因が残っている可能性も否定できません。
修理内容と再発事例の関係
一部ユーザーはリコール対応後しばらくは快適だったものの、「数週間〜数か月後に同じ現象が再発した」と報告しています。これにより、原因の特定が不十分なまま対症療法的に処置されている可能性が指摘されています。
ディーラーの対応姿勢と認識差
再発時にディーラーへ相談したユーザーの中には、「正常範囲内」「再リコール対象ではない」と対応を断られた例もあり、現場レベルでの認識のばらつきが不信感を強めています。メーカーと販売店の連携不足が疑われるケースも存在します。
ソフトウェア・制御系の課題
この不具合がハードウェアの物理的な故障ではなく、制御プログラムやセンサーキャリブレーションの問題である可能性も指摘されています。もしそうであれば、アップデートや再学習での改善も視野に入りますが、ユーザー側での判断が難しいため、情報開示と再検証が求められています。
ユーザーにとっての実害と心理的負担
不具合の再発は、「またなるかもしれない」という常時不安を生み、長距離ドライブや高速道路走行の心理的ハードルを上げる要因となります。これは単なる快適性の問題を超え、安全性と信頼性にかかわる深刻な問題です。
自動運転支援としては致命的
高速道路での快適性を売りにするクルマにとって、クルーズ時のハンドル不具合は致命的です。「半自動運転」を謳うCX-60ですが、こうした挙動はかえって疲労感を与えるものであり、ユーザー体験としてはマイナス要素です。
長距離移動の信頼性に影響
自動運転支援機能は、本来ならドライバーの疲労軽減や安全運転のサポートを担うはずの存在です。しかしCX-60では、「むしろ神経を使う」「不具合が発生しないか常に注意している」といった声が多く、快適性の低下だけでなく、ドライバーの精神的負担増にも直結しています。
他社システムとの明確な違い
他の自動車メーカー、特にトヨタやスバルでは、高速道路におけるアダプティブクルーズコントロールと車線維持支援の連携が非常にスムーズであると高い評価を受けています。CX-60のように、ハンドルが予期せぬ動きをするような事象はほとんど報告されておらず、システムの完成度という点で明確な差が見られます。
信頼を裏切る“売り文句”
マツダは公式に「快適な長距離移動」をCX-60の魅力として打ち出していますが、実際にはその中核を担うべき自動運転支援システムに重大な不安が残ることから、消費者の信頼を裏切る結果となってしまっています。
多くの車に見られない現象
他メーカーの同機能付き車両に乗ってきたユーザーからは、「ここまでの挙動は初めて」と驚きの声もあります。これもまた、CX-60における完成度の低さを示す一例といえるでしょう。
一般的なクルーズ支援の挙動との違い
多くの競合モデルでは、車線維持支援システムが滑らかにハンドル補正を行い、あたかも人間が自然に操作しているかのような感覚が得られます。ところがCX-60では、その補正動作が断続的かつ急激で、「違和感がある」「酔いやすい」といった印象を与えています。
ユーザーが語る他社とのギャップ
「トヨタ車では感じなかった不自然さがCX-60では顕著だった」「スバルのアイサイトではスムーズにカーブを抜けられたのに、CX-60ではカクカクして怖かった」といった体験談もあり、同機能を比較した際にCX-60の技術的な未成熟さが浮き彫りになっています。
システム完成度への不安が信頼を損なう
クルマの自動運転支援機能は日進月歩で進化している分野であり、ユーザーもその恩恵に期待を寄せています。その中で「CX-60はこの価格帯なのに…」という落胆の声が目立つことは、マツダブランド全体の信頼性にも影響を及ぼしかねない懸念材料といえるでしょう。
精密性に欠ける制御システム
制御系のセンサー感度やハンドリング調整に精度の甘さがあるとみられ、安全性の観点からも不安を感じる要素となっています。リコールでの一時対応ではなく、全体設計の見直しが望まれる部分です。
センサーと実走行のギャップ
多くのユーザーが指摘するのは、センサーによる補正動作が実際の路面状況や車線形状に追従しきれていない点です。誤認識や急な補正が頻発し、「むしろ危ない」と評価される場面も見られ、センシング技術のチューニング不足が疑われます。
ハンドリング補正の過敏さ
車線維持支援やステアリング補正が必要以上に敏感であるとの報告もあります。たとえば軽微な車線のゆがみにも過剰反応してハンドルが不安定になることがあり、結果的に運転者が逆に操作を強く意識しなければならない状況に陥ってしまっています。
制御プログラムの熟成不足
これらの挙動は、ハードウェア自体の問題ではなく、制御アルゴリズムの完成度や検証不足に起因している可能性があります。他社ではAIや機械学習を活用したフィードバック制御が進んでいる中、CX-60はその点で一歩遅れているという印象を与えています。
アップデートのアナウンス不足
不具合が報告されているにもかかわらず、制御系のアップデートや調整に関する情報開示が少ないことも、ユーザーの不安を増幅させています。「ソフトウェアの再学習で改善された」という声もある一方で、アップデート方法や内容が曖昧なままで、対応の透明性が求められています。
安全面に対する信頼の低下
「安全装備が逆にストレスになる」という意見も出ており、安全性そのものへの信頼を揺るがしかねない状況です。
安全装備がもたらす逆効果
本来であれば、ブラインドスポットモニターや車線逸脱警報といった安全装備は、運転者を補助しリスクを低減するための機能です。しかしCX-60の場合、これらの装備が過剰に反応したり、誤作動するケースがあるとの報告があり、「かえって注意がそれる」「誤警報で驚かされる」など、逆に事故を誘発しかねないとの不安を抱くユーザーもいます。
複数の不具合が信頼性を損なう
一つの機能にとどまらず、クルーズコントロールやステアリング制御、さらにはブレーキ制御といった複数の分野で不具合が報告されていることで、「車全体の信頼性に問題があるのではないか」という疑念が強まっています。これは単に個別の不具合ではなく、車両制御システム全体への不信感につながります。
ブランド全体の信頼に波及するリスク
これまで「走りのマツダ」として一定の評価を得てきたマツダですが、CX-60のようなフラッグシップSUVにおける信頼性低下は、ブランド全体の価値にも悪影響を及ぼしかねません。ユーザーは単に1車種だけでなく、マツダ車全体に対して疑念を抱き始めるリスクがあるのです。
ユーザーに求められる“慎重な選択”
安全装備を過信せず、必ず自身の目で確認しながら運転する姿勢が求められる現状は、本来の“安心”とは真逆の状況です。購入を検討する際には、装備の作動状況を試乗中にしっかり確認し、自分にとって本当に信頼できるものかどうかを慎重に見極める必要があります。
CX-60は本当に“熟成された車”なのか?
これらの報告を踏まえると、CX-60はまだ市場において“成熟”した車とは言いがたく、むしろ「実験車」「見切り発車の初期型」などの疑念を持たれても仕方ない部分があるといえるでしょう。
新プラットフォーム採用によるリスク
CX-60はマツダが新たに開発したラージ商品群の第一弾モデルであり、シャシーやパワートレインも刷新されています。これにより先進性やプレミアム性は打ち出せた一方で、初採用ゆえの不具合や調整不足が露呈しやすく、“実験的”と捉えられても無理はありません。
アップデートによる進化途上の印象
度重なるリコールや仕様変更、制御プログラムのアップデートが行われている状況を見ると、製品としての完成度が初期段階では十分でなかったことがうかがえます。改良のスピード感が評価される一方、「発売時点で完成されていなかった」という厳しい意見も少なくありません。
ユーザーの声に見る“未熟さ”の認識
オーナーからは「一台目としては完成度が低かった」「ソフトウェアが洗練されていない」といった声が多く寄せられており、“熟成”という言葉からは程遠い状況にあると受け取られています。車両の基本性能以上に、細部の仕上がりや信頼性に対する疑問が根強く残っています。
今後のモデルチェンジに期待が集まる
現時点ではCX-60の本質的な価値が完全には引き出されていないという見方もでき、今後のマイナーチェンジや派生モデル(CX-70やCX-80など)でどのように熟成が進むかが注目されています。初期型に関しては「マツダの実験台だったのでは」との疑念が残るものの、改良が進めばポテンシャルは高いとも言えるでしょう。
まとめ
マツダCX-60は、魅力的な内装や高出力なエンジン、プレミアム感あるエクステリアなど、確かに評価すべきポイントも多い車です。しかしながら、実際に所有したユーザーからは、乗り心地の硬さやハンドルの不具合など、多くの問題点が指摘されており、特に初期型ではその傾向が強く見られます。
「ある程度走れば馴染む」といったメーカーの説明や、リコールによる一時的な対処では不安が解消されず、「個体差による品質のバラツキ」「未完成のまま発売された印象」が付きまとう車でもあります。
CX-60の購入を検討している方は、まず試乗を行い、問題点が改善されているかを確認したうえで判断することが不可欠です。とくに初期型を中古で検討している場合は、なおさら注意が必要です。完成度や品質に疑念が残る現状では、焦って購入するよりも、今後の改良版を待つという選択肢も十分に検討すべきでしょう。