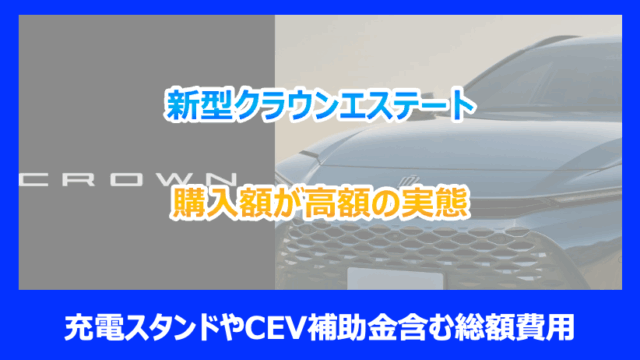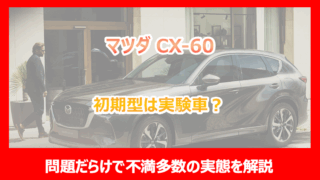日産サクラは、補助金制度を活用することで手の届きやすい価格で購入できる軽EVとして大きな注目を集め、登場当初は爆発的な販売台数を記録しました。

引用 : NISSAN HP (https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/sakura.html)
しかし近年では中古市場にサクラがあふれ、価格も暴落傾向に。なぜこんなにも短期間で手放す人が続出しているのでしょうか?
本レビューでは、サクラの販売不振やリセールバリュー低下の背景を徹底的に解説します。
記事のポイント
- 日産サクラが中古市場で急増した理由を解説
- EV補助金と価格変動がもたらした販売動向
- リセールバリューが悪化した背景と要因
- EVとしての性能と使い方のミスマッチ
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

日産サクラが中古市場であふれる背景
サクラの販売推移と中古車急増の背景
サクラは2022年5月に発売され、初年度は8ヶ月間で21,887台、翌2023年は37,140台と好調な販売を記録。国内EV市場において2年連続で販売台数1位という快挙を達成しました。

引用 : NISSAN HP (https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/sakura.html)
ところが、2024年に入ると月平均販売台数は約1,971台まで落ち込み、前年と比べて約62%もの減少となりました。これは単なる人気の下降というよりも、EV市場全体の頭打ち感や、価格面・利便性に対するユーザーの不満が一気に噴出した結果と見るべきです。
異常な中古在庫数が示す異変 この新車販売の減速と比例して、中古市場においてはサクラの在庫が急増。2024年12月時点でのグーネット掲載台数は約876台に達しており、わずか2年程度でここまで中古車が出回るケースは非常に珍しい状況です。
車検前の放出は異例中の異例 さらに注目すべきは、これら中古在庫の大半が“初回車検前”の車両であること。通常、多くのユーザーは3年後の初回車検時に買い替えや売却を検討するため、それ以前にこれだけの放出があること自体、サクラが「想定外の不満」に直面した証左と考えられます。
中古台数比較から見る異常性 例えば、同じく2022年にモデルチェンジされたトヨタ・シエンタの中古掲載台数は約1,083台とサクラより多く見えますが、販売台数の累計はサクラの約7.8万台に対し、シエンタは約27万台超。この数字を考慮すると、サクラの“中古車率”は圧倒的に高いと言え、事実上「手放されやすい車」という評価が裏付けられてしまっているのです。
補助金制度と保有義務のギャップ
国のEV補助金には4年間の保有義務が課されています。しかし実際には多くのユーザーが2年足らずで手放しており、補助金返還リスクを冒してでも売却を決断しているケースが見られます。

引用 : NISSAN HP (https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/sakura.html)
なぜ補助金を捨ててまで売却?
- バッテリー性能や使い勝手に対する不満
- 補助金ありきの価格感覚で本来の価値と乖離
- 市場全体のEV需要一巡による価値下落
新車価格の値上げと補助金終了の影響
登場当初、補助金を適用すれば178万円から購入可能だったサクラですが、2024年には価格が253万円~382万円にまで上昇。また、地方自治体によっては補助金を終了しているケースもあり、購入メリットが薄れています。

引用 : NISSAN HP (https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/sakura.html)
実際、2022年時点では国から最大55万円、自治体によってはさらに同額程度の補助金が支給され、100万円台中盤でEVが手に入るという“破格”の状況が整っていました。この恩恵が失われた現在、実質的な購入価格は大幅に上昇しています。
補助金制度の地域格差も問題で、東京23区など一部の自治体では比較的手厚い補助が継続されている一方、地方都市では早期に終了してしまっている場合もあります。これにより「場所によっては高く感じるEV」という印象が強まり、購買意欲を削ぐ結果となっています。
補助金制度の変化による心理的影響
- 補助金の打ち切りにより、価格の魅力が薄れる
- 「補助金で安く買える」というイメージが崩壊
- EV価格の不透明さが不信感につながる
加えて、新車価格の2度にわたる値上げ(2022年12月・2024年5月)もユーザーの不満を呼びました。補助金ありきの価格設定だったがゆえに、補助がなくなった途端に「割高感」が一気に顕在化し、価格と性能のバランスに納得できず購入を見送る人も増えているのが実情です。
値上げが招いた購買意欲の低下
- 物価高の中での2度の価格改定
- EV補助金の支給終了地域では実質値上げ
- 軽EVとしてのコスパの悪化
値上げが招いた購買意欲の低下
- 物価高の中での2度の価格改定
- EV補助金の支給終了地域では実質値上げ
- 軽EVとしてのコスパの悪化
EV市場全体の需要減退
2024年のEV販売は前年から約4割減少。中でも軽EVは頭打ち状態にあり、サクラに限らず全体的にユーザー層が飽和してきているのが実情です。
需要一巡による市場の停滞
- EV市場の急成長に伴い、初期需要を支えた層への販売はほぼ完了
- 新たな購買層の開拓が追いつかず、結果として全体の販売ペースが鈍化
特に軽EVは、地方在住で自宅充電環境が整っている高所得層がメインターゲットとなっていました。これらの層には既に一定数行き渡っており、追加需要が生まれにくい構造となっています。
政府目標と実態のギャップ
- 国は2030年までにEV比率20〜30%を目標とするが、2024年時点ではわずか3〜4%
- 普及ペースが目標に追いつかず、政策効果も限定的
加えて、EVの選択肢そのものが限られており、国産EVの新型モデル数は非常に少ないままです。2024年に登場したのは、サクラ以外ではホンダ「N-VAN e:」などごくわずか。このように“欲しいEVがない”という選択肢不足も需要停滞の一因です。
EV販売の伸び悩みがもたらす影響
- メーカーの新型EV投入が遅れる悪循環
- ユーザーのEV全体に対する関心が後退
- 中古市場への過剰流入による価格下落リスクの増加
日産サクラのリセールバリューが悪い理由
EV特有の下取り価格低下リスク
EVはバッテリーの劣化が価値を大きく左右します。特にサクラは20kWhと小型バッテリーを搭載しており、実質の航続距離も180km程度。バッテリー性能の不安が中古価格を押し下げています。
バッテリー劣化と中古価格の関係性
- バッテリーは年数や走行距離に応じて容量が低下し、航続距離も短くなる
- 容量が80%を下回ると著しい価値低下が発生
- 中古車購入者は交換コストを懸念し、価格交渉が厳しくなる
バッテリー寿命に関する情報不足も不安材料
- 現在の多くの中古EVには「バッテリーSOH(State of Health)」の明確な表示がない
- 購入時に劣化状況がわからず、安心して購入できない
- 日産は8年間のバッテリー保証を提供しているが、買い手に十分伝わっていない
バッテリー交換コストと経済的インパクト
- 軽EVクラスでもバッテリー交換には50万円前後かかるケースがある
- 新車価格に対する比率が高く、中古車としての採算性が厳しくなる
- 結果として、売却時に著しく安値で手放さざるを得ない
こうした状況により、EV全般がリセールに不利な構造となっており、とりわけサクラのようにバッテリー容量が小さく、後続距離も短い車種は中古市場での評価が伸び悩んでいるのが現実です。
バッテリーの不安が価格を押し下げる
- 残量可視化の不備(バッテリーSOHが不明瞭)
- バッテリー交換コストが高額
- メーカー保証があっても市場価値には反映されにくい
中古EVに補助金が適用されない
新車購入時に支給されるEV補助金は、中古車には適用されません。そのため、仮に状態の良いサクラでも中古市場では価格競争力を失ってしまいます。
補助金制度の落とし穴
- 新車時にしか使えない補助金制度が、中古車の価値を相対的に下げてしまう
- 購入者にとっては「中古を買うと損」と感じる要因に
- 結果として中古市場全体でEVの需要が伸び悩む構造が生まれている
中古車選びにおける心理的ハードル
- 同じ金額を出すなら「補助金で安くなる新車」を選ぶ傾向が強い
- 状態が良くても補助金がない分だけ“割高感”が生じやすい
- 将来的な下取りや売却も不利になるとの懸念がある
制度改善の余地と今後の可能性
- 海外では中古EVへの補助制度を設ける国も存在し、需要刺激策として機能している
- 日本でも環境配慮型社会の構築を進めるなら、中古EVに対する支援施策の検討が不可欠
- 補助制度の見直しが行われれば、中古EVの市場活性化にもつながる可能性がある
新車と中古車の価格逆転リスク
- 状態が良くても補助金がない分割高に感じる
- 新車価格と比較して購入動機を失うユーザーも
サクラの装備や使い勝手に対する不満
外観や走行性能には満足しているユーザーも多いものの、実用面での不満も根強いです。たとえばスライドドア非採用や、標準で充電ケーブルが付属しない点に対する不満などが挙げられます。
装備面での期待外れ
- スライドドア未搭載で使い勝手に難あり
- 自宅充電用ケーブルがオプション
- プロパイロットなど一部グレードのみ対応
充電インフラの整備遅れと使い勝手のギャップ
日常使いでの利便性をうたっているサクラですが、そもそも日本国内の充電インフラが整備途上であることがネック。集合住宅居住者にとっては家庭充電も難しく、結局運用に困るケースも多く報告されています。
充電設備の設置格差
- 地方の戸建て住宅では自宅充電が比較的容易
- 都市部の集合住宅では200Vコンセント設置が困難
- 分譲・賃貸問わずマンション管理組合の許可が必要で、導入ハードルが高い
公共充電スポットの不足と運用問題
- 近隣に急速充電器があっても、利用者が多く順番待ちが発生
- 商業施設などの充電器は駐車時間制限があり、実用性に欠ける
- 故障やメンテナンス未対応の設備も多く、信頼性に欠ける印象を持たれがち
充電インフラの地域格差と心理的負担
- 地方に比べ都市部ほどEV購入の心理的ハードルが高い
- “充電難民”という言葉が生まれるほど、日常利用に支障をきたすケースも
- この状況がSNS等で共有され、不安が一層拡大
本来は日常使いに適した軽EVのサクラですが、インフラ整備の遅れによって「充電できるかどうか」が最初の障壁となり、EVの魅力そのものが伝わりにくくなっているのが現状です。
日産サクラのEVとしての性能と使い勝手のギャップ
航続距離に対する不満と誤解
サクラの航続距離180kmは、軽EVとしては標準的ですが、ユーザーの期待値が高すぎたため「短い」という印象を持たれがち。特に普通車EVと比較されることによって、相対的に性能不足と誤解されやすいです。
日常使いなら十分な距離
- 一日30km以下の走行が大多数(メーカー調査)
- ご近所中心のセカンドカーとしては問題なし
EVならではの維持費と電気代上昇
ガソリン車と比べてランニングコストは低いものの、近年の電気代上昇やZESP(充電サービス)の割高感が“お得感”を薄れさせています。
ZESP料金体系に対する不満
- 定額プランが高額化
- 月額利用料と電力量課金が併存し割高に
- 自宅充電ができないと恩恵を感じにくい
日本のEVインフラ整備の遅れ
日本の充電器設置数は他国に比べて非常に少なく、国の目標(2030年:30万基)に対して、2024年時点で約3万2千基にとどまっています。都市部では集合住宅が多く、自宅充電が難しい状況も普及を妨げています。
世界とのEV環境格差
- 中国:270万基、欧州:70万基に対し日本は約3万2千基
- 欧州では高速道路60kmごとに設置義務あり
- 都市部でのEV使用に不安がつきまとう
EV市場全体の信頼感の低下
EVに対する期待が過剰だったため、実際に購入後「思ったより使いにくい」「燃費のように電費も計算が難しい」など、ネガティブな感情が蓄積。とくにセカンドカー用途として割り切れなかった人にとっては後悔が残りやすい車種となってしまいました。
期待と現実のギャップがもたらす失望
- カタログスペックと実走行距離の乖離
- 充電時間や頻度への誤解
- 家庭事情により自宅充電ができず不便さを実感
こうした誤算は、EVに関する知識不足や、販売側の説明不足も影響しています。特に従来のガソリン車と同じ感覚でEVに乗り換えたユーザーにとっては、「電気自動車は万能ではない」という現実に直面し、落胆するケースが少なくありません。
口コミやSNSの影響拡大
- ネガティブなレビューが拡散されやすい環境
- 一部の過剰な期待が全体の評価に波及
- ユーザー同士の評価によって信頼感がさらに揺らぐ
結果として、EVに対する信頼感が低下し、「次もEVを選ぶか」と問われたときに消極的な選択肢となってしまう傾向が強まっています。サクラに限らず、EV全体への不安や不信が中古市場の価格下落にも影響を与えているのが現状です。
まとめ
日産サクラが中古市場であふれ、価格が暴落している背景には、補助金制度の盲点やEV特有のバッテリー不安、インフラ整備の遅れ、ユーザーの期待と実際の性能のギャップなど複合的な要因が存在します。
しかし、サクラ自体の完成度が低いというよりも、EV市場や制度設計、日本の環境整備の未成熟さがリセールバリューの低下を招いている構図です。
街乗り中心で日常使いがメインの人にとっては、サクラは今でも十分魅力的な軽EV。むしろ中古価格が落ちてきた今こそ、お買い得な選択肢と考えることもできるでしょう。
大切なのは、車そのものだけでなく、自分の使用目的やライフスタイルに合致しているかどうかを見極めること。そうすれば、日産サクラはコスパに優れた一台として活躍してくれるはずです。