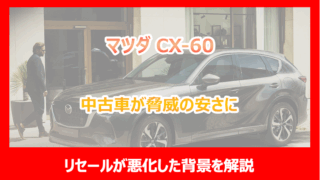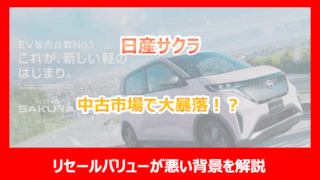この記事では、クラウンスポーツの正直イマイチに感じる点をオーナー目線で徹底解説しています。

今回は、私が愛用していたクラウンスポーツについて、正直な感想と改善してほしい点についてお話ししたいと思います。
クラウンスポーツは、そのスタイリッシュなデザインと走行性能で多くの人々を魅了していますが、実際に使用してみると、いくつかの気になる点も見えてきました。
この記事では、クラウンスポーツの購入を検討されている方、納車待ちの方に向けて、実際のオーナーだからこそ分かる、メリット・デメリットを詳しく解説していきます。
購入前に知っておきたい情報を網羅し、後悔しない車選びをサポートします。
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

クラウンスポーツの走行性能のイマイチな点
クラウンスポーツは、走行性能に関して高い評価を得ていますが、いくつかの気になる点も見受けられました。
キックセンサーの反応
クラウンスポーツに搭載されているキックセンサーは、両手が塞がっている時に便利な機能ですが、反応が悪く、使いにくいと感じることがありました。
- 反応の悪さ: キックセンサーの反応が悪く、何度も足を出し入れしないと反応しないことがあります。
- 反応のコツ: キックセンサーの反応にはコツがあり、足を素早く出し入れするのではなく、センサーが反応する音を聞いてから足を引く必要があります。
- ディーラーでの設定: ディーラーでキックセンサーの感度を調整できますが、それでも反応の悪さを感じる場合があります。
これらの点から、キックセンサーに関しては、反応の改善を求める声が多いのではないでしょうか。
ワイパーの操作
クラウンスポーツのワイパーは、ボンネットの内側から持ち上げる必要があり、掃除や交換時に不便を感じることがありました。
- 操作の煩雑さ: ワイパーを持ち上げるために、エンジンを切り、ボンネットを開ける必要があります。
- 自動ワイパーの要望: 昔のクラウンのように、自動でワイパーが持ち上がる機能があれば、利便性が向上します。
これらの点から、ワイパーに関しては、操作性の改善を求める声が多いのではないでしょうか。
燃費と走行性能
クラウンスポーツの燃費は、カタログ値よりも実燃費が低いと感じることがありました。また、EV走行からエンジン走行に切り替わる際の振動が気になることもありました。
- 実燃費: 実燃費は、街乗りでは12km/L程度であり、カタログ値よりも低いと感じます。
- エンジン始動時の振動: EV走行からエンジン走行に切り替わる際に、振動が気になることがあります。
これらの点から、燃費と走行性能に関しては、改善の余地があると感じる方もいるのではないでしょうか。
ナビゲーションシステムと充電性能
クラウンスポーツのナビゲーションシステムは、高速道路の誤認識や充電性能の低さが気になることがありました。
- ナビゲーションの誤認識: 高速道路を走行していないにも関わらず、高速道路を走行していると誤認識することがあります。
- 純正USBポートの充電性能: 純正USBポートの充電性能が低く、スマートフォンやタブレットの充電に時間がかかることがあります。
- ワイヤレス充電: ワイヤレス充電は便利ですが、充電速度が遅く、スマートフォンが熱くなることがあります。
これらの点から、ナビゲーションシステムと充電性能に関しては、改善を求める声が多いのではないでしょうか。
クラウンスポーツの走行以外のイマイチな点
デジタルインナーミラーと内装の改善を求める声
クラウンスポーツには、先進的な機能が数多く搭載されています。

その中でも特に気になるのがデジタルインナーミラーの画質と、内装の使い勝手です。
デジタルインナーミラーの画質と画角
クラウンスポーツに標準装備されているデジタルインナーミラーは、後方の視界をクリアに映し出す便利な機能ですが、画質と画角には改善の余地があると感じました。
- 画質の粗さ: 純正のデジタルインナーミラーは、社外品と比較すると画質が粗く、特に夜間や悪天候時には後方の視認性が低下します。
- 画角の狭さ: 画角が狭いため、後方の車両が近づいてきた際にナンバープレートが見切れてしまうことがあります。
- 夜間の視認性: 夜間には、後続車のナンバープレートがぼやけてほとんど見えないことがあります。
これらの点から、デジタルインナーミラーに関しては、より高画質で広角な社外品を導入することを検討する価値があるでしょう。
内装の使い勝手と収納スペース
クラウンスポーツの内装は、高級感がありデザイン性も高いですが、日常的な使い勝手や収納スペースには改善の余地があると感じました。
- センターアームレストのシガーソケット: センターアームレスト内のシガーソケットは、アダプターの種類によっては収納時に邪魔になることがあります。
- 収納スペースの不足: サングラスホルダーや小物入れなどの収納スペースが少なく、日常的に使用する小物の置き場所に困ることがあります。
- ドリンクホルダーの位置: ドリンクホルダーの位置が、USBケーブルなどの配線と干渉しやすく、使い勝手が悪いと感じることがあります。
これらの点から、内装に関しては、収納スペースの追加や使い勝手の改善を求める声が多いのではないでしょうか。
照明とアンビエントライト
クラウンスポーツの室内照明は、全体的に暗めに設定されており、夜間には手元が見えにくいことがあります。
アンビエントライトに関しても、もう少し明るく、色味の調整ができれば、さらに快適な室内空間になるでしょう。
- 室内照明の暗さ: 室内照明が暗いため、夜間にはスイッチ類や小物が見えにくいことがあります。
- アンビエントライトの調整: アンビエントライトの色味や明るさを調整できる機能があれば、好みに合わせた室内空間を演出できます。
- トランクの照明: トランクの照明も暗く、夜間には荷物の出し入れに不便を感じることがあります。
これらの点から、照明に関しては、明るさの向上やアンビエントライトの機能拡充を求める声が多いのではないでしょうか。
まとめ
クラウンスポーツは、多くの魅力を持つ一方で、いくつかの改善してほしい点も見受けられました。

これらの情報は、購入を検討されている方にとって、非常に参考になるはずです。
この記事が、皆様の車選びの一助となれば幸いです。もし、クラウンスポーツに関して気になる点や疑問があれば、お気軽にコメント欄で質問してください。
また、クラウンスポーツのオーナーの方で、共感できる点や改善してほしい点があれば、ぜひコメント欄で共有してください。皆様の貴重なご意見は、今後の車選びの参考になります。
この記事が、クラウンスポーツの購入を検討している方々のお役に立てれば幸いです。