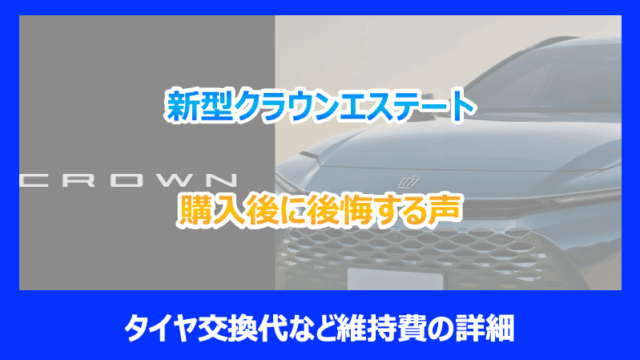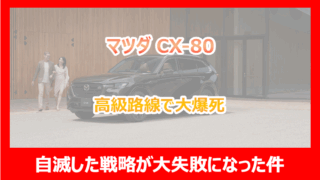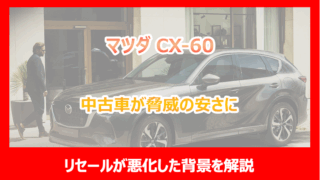新車購入を検討中の方の中には、マツダCX-60が候補に上がっている方も多いでしょう。

引用 : MAZDA HP (https://www.mazda.co.jp/cars/cx-60/feature/)
発売当初はその美しいデザインと質感の高い内装で注目を浴び、好調な売れ行きを見せました。
しかし最近ではリコール問題が相次ぎ、購入を躊躇する声も増えています。
そこで今回は、CX-60に関して購入を見送るべき理由を徹底的に解説します。
記事のポイント
- CX-60はリコール件数が異常に多い
- 重大な不具合が多数報告されている
- 購入者の不満と後悔が広がっている
- 今後登場するCX-80への期待感が高まっている
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

マツダCX-60はリコールの嵐で買うべきではない現状
CX-60リコールの頻発状況
マツダのCX-60は、発売からわずか2年という短期間で、すでに7回ものリコールが発表されています。

引用 : MAZDA HP (https://www.mazda.co.jp/cars/cx-60/feature/)
他車と比較しても異例のリコール頻度
この件数は他社の同クラスSUVと比較しても極めて多く、特にトヨタやスバルと比べても明らかに突出しています。たとえば、同じ中大型SUVセグメントであるトヨタ・ハリアーでは2年以内のリコールは1〜2件程度にとどまっており、CX-60の数字は異常値と言わざるを得ません。
リコールの背景にある品質管理の脆弱性
これだけ頻繁にリコールが発生している背景には、マツダの品質管理体制や開発プロセスの甘さが指摘されています。特に、コロナ禍の影響で開発・試験工程が簡略化された可能性や、急ピッチな新技術の導入による未成熟な製品投入が要因として考えられています。
消費者の信頼を損ねる結果に
リコールの内容も、重大な安全性に関わる部品や制御装置に関するものが多く、ユーザーの信頼は大きく損なわれています。SNSや掲示板でも「次はもうマツダを買わない」「こんなにトラブルが多いなら中古でも避けたい」といった厳しい声が見受けられ、ブランドイメージの低下が懸念されます。
販売現場にも波及する影響
こうした状況は販売現場にも影響を与えており、ディーラーの営業担当者からも「CX-60はお客様への説明が難しく、代替提案が増えている」との声があがっています。結果として、新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客の離反リスクも高まっています。
このように、CX-60のリコール頻発は単なる「新型車あるある」では済まされない深刻な問題となっており、購入希望者は冷静な判断が求められます。
CX-60で発生している主な不具合一覧
CX-60では具体的に次のような不具合が報告されています。
- 足回りが硬すぎる(個体差あり)
- パワーシートが動作しない
- 給油口が開かない
- ハンドルがカクつき、自動運転機能が実質使えない
- 足回りの異音や振動
- 後部座席の不快な突き上げ感
- 緊急ブレーキの頻繁な誤作動
これらの問題は、運転の快適性だけでなく安全性にも直結する重大な欠陥です。
CX-60の初期型は買うべきではない
新車を購入する際、特に初期型には注意が必要です。製造段階でのバグや、実走行による問題点の洗い出しが行われていないことが多く、トラブルが起きやすい傾向があります。CX-60はまさにその典型例であり、初期型を購入した多くのユーザーが実際に不具合に悩まされ、後悔の声を上げています。
初期型ユーザーのリアルな声
SNSやレビューサイトでは、購入直後から複数の不具合が連続して発生したという投稿が相次いでいます。例として、納車後1か月以内にパワーシートの故障、走行中の足回りの異音、緊急ブレーキの誤作動などを経験したという声が複数確認されています。これらの事例は単なる偶然ではなく、製品の信頼性に大きな課題があることを示しています。
リセールバリューの急落
さらに、中古車市場においてCX-60初期型のリセールバリューは大きく下落しています。査定額が同クラスのSUVよりも数十万円単位で低くなるケースもあり、これもまた購入者にとっては深刻な経済的損失です。ディーラー側も積極的に下取りしたがらない傾向があり、売却時の選択肢も狭まります。
改良モデルまで待つのが得策
このような状況を踏まえると、あえて初期型を選ぶメリットは乏しく、今後マツダがリコール対策や設計見直しを施した改良モデルを投入するまで待つのが賢明です。特に安全性や快適性に関する問題は簡単に解決できるものではないため、慎重な判断が求められます。
マツダの品質管理に疑問符
CX-60の相次ぐリコールは、単なる製品トラブルの範疇を超えた、マツダの製造体制と品質管理における本質的な課題を浮き彫りにしています。
品質管理の形骸化が招いたトラブル連鎖
本来、製品開発においては、試作段階から市販直前まで徹底的な品質チェックと実走行試験が実施されるべきです。しかしCX-60に関しては、個体差による足回りのバラつきや電装系のトラブルが頻出していることから、量産化プロセスにおけるチェック体制が十分でなかったことがうかがえます。
コロナ禍による開発体制の影響
多くの業界で見られたように、コロナ禍ではリモートワークの導入により社内連携やダブルチェック体制が弱体化したと言われています。マツダも例外ではなく、開発現場での確認工程が簡素化された結果、潜在的な設計ミスや組み立て時の精度不良が見逃されていた可能性があります。
品質トラブルがブランドイメージに与える影響
かつては「走る歓び」を掲げて信頼を築いてきたマツダですが、CX-60の不具合をきっかけにSNS上では「マツダ離れ」とも呼べる現象が起こりつつあります。特に、高価格帯の車であるにもかかわらずトラブルが相次いだことで、「価格に見合わない品質」との評価が浸透し、ブランド価値の毀損につながっています。
ディーラー現場での苦悩
マツダ車を扱う販売店でも、CX-60に関する説明が難しくなっているとの声が上がっています。説明時に顧客から「またリコール出るのでは?」と問われるケースも多く、営業担当者の負担は増す一方です。こうした現場の声は、マツダ本社の製品開発部門にも強く伝わっていると考えられ、改善への取り組みが急がれます。
改善には全社的な改革が不可欠
単なる技術的な修正だけでは不十分であり、品質保証部門の強化やフィードバック体制の見直し、そして開発フロー全体の再構築が求められます。トヨタやスバルのように「70〜80点で確実に安定した品質を供給する」という戦略にシフトすることも、今後のマツダにとっては選択肢の一つと言えるでしょう。
他車種と比較したCX-60の問題の多さ
トヨタやスバルなどの競合メーカーと比較しても、CX-60のリコール頻度と不具合の多さは際立っています。
トヨタ・ハリアーとの比較
同じく中大型SUVの代表格であるトヨタ・ハリアーは、モデルチェンジのたびに緻密なテストと改良を繰り返しており、初期トラブルの報告は非常に少ないです。仮に問題が発生しても、素早く改修やアップデートが行われるため、ユーザー満足度は非常に高い傾向にあります。これに対し、CX-60はユーザーからの声に対する対応の遅さも指摘されており、信頼性の面で大きな差が開いています。
スバル・レヴォーグとの比較
レヴォーグはマイナーチェンジを経て車体構造や安全装備が熟成され、不具合発生率が極めて低いことで知られています。また、スバル独自のアイサイト技術は半自動運転の精度においても高い評価を受けており、CX-60の自動運転関連のトラブルと比較すると、技術の完成度に明確な違いがあります。
輸入車との比較
ドイツ車や北欧ブランドなどの輸入SUVも比較対象に入れると、初期トラブルこそ多少あるものの、プレミアムブランドはリコールに対する対応スピードや補償制度が手厚く、不具合に対するユーザーの不満は最小限に抑えられています。マツダは国産メーカーとしてこのあたりの顧客対応にも見習うべき部分が多いと言えるでしょう。
CX-60の位置付けが逆効果に?
CX-60はマツダが“高級志向”へ舵を切った象徴的なモデルですが、ブランドとしての実績や信頼が追いついていないまま高価格帯に突入したことが、ユーザーの期待との乖離を生んでいます。トヨタやスバルが長年かけて築いてきた信頼の積み重ねと比べると、CX-60は過渡期の“挑戦的な実験車”という印象が強く残ります。
このように、CX-60の不具合と対応の未熟さは、競合他社と比較することでより明確に浮かび上がっており、マツダにはまだ乗り越えるべき壁が多く残されています。
内装の質感だけではカバーできない不満
CX-60の内装は確かに国産車随一と言えるほどの質感を誇り、デザインや素材選びにおいてはレクサスやクラウンに匹敵する評価を受けています。しかし、それだけで「買ってよかった」と思えるかというと、現実は異なります。
高評価のインテリアに対する実感値
ウッドパネルや本革シート、ナチュラル素材の採用により、プレミアム感を演出しているCX-60のインテリア。展示車両やカタログでの印象は確かに良好で、第一印象で購入を決めたという声も少なくありません。しかし実際のユーザー体験では、「見た目は良くても使い勝手が悪い」「静粛性が低く内装の良さがかき消されている」といった声も挙がっています。
走行性能とのバランスが崩れている
デザインや内装の質感に力を入れた一方で、走行性能や乗り心地に関する基本性能が不安定であるため、トータルでの満足度は大きく低下しています。特に、足回りの硬さや突き上げ感、ステアリングの不自然な動きなどが内装の魅力を帳消しにする要因となっており、「内装だけ良くても意味がない」といった辛口の評価が相次いでいます。
静粛性や振動制御への不満
高級感を演出する内装と相反するように、実走行では風切り音やロードノイズ、足回りからの異音が目立つという声も多く聞かれます。インテリアが豪華であっても、音や振動によって不快感が生まれることで「期待外れ」と感じるユーザーが多く、車全体の完成度のバランスが課題となっています。
高級感だけでは満足できない時代
近年では、デザインや内装だけでなく、走行フィール、安全性、アフターサービスといった総合的な価値が問われる傾向が強まっています。CX-60は「見た目で惹かれて買ったが、乗ってみてガッカリした」という購入者の声が多く、真のプレミアムカーとは言い難い状況です。
このように、インテリアの質感がどれほど高く評価されていても、それだけで数々の機能的・機械的欠陥を補うことはできず、むしろギャップの大きさが不満を助長する結果となっています。
購入者の口コミから見えるCX-60の現実
実際にCX-60を購入したユーザーからは、購入後に発生した不具合に対する不満の声が続出しています。SNS上では「買って後悔している」「もう二度とマツダは買わない」といった厳しい意見が散見され、購入を検討している方には無視できない状況となっています。
SNS上に溢れる“後悔”の声
SNSや掲示板には「納車初日から異音がする」「エラー表示が頻発」「リコールの案内が短期間に何度も届く」といった具体的な報告が目立ちます。特に、CX-60の魅力に惹かれて新車を購入した人々が、期待を大きく裏切られたという感情をあらわにしており、単なるマイナートラブルでは済まない状況です。
ディーラー対応に対する不信感も
一部のユーザーからは、「不具合を相談してもディーラーが対応を渋る」「リコール対象外だと突っぱねられた」といった販売店の対応に関する不満も報告されています。メーカーの信頼を支える現場での対応力が問われる中で、CX-60に関してはその対応も十分とは言えないケースが目立っています。
クチコミサイトでの低評価が拡大
カーオーナー向けレビューサイトや中古車情報サイトでも、CX-60の評価は徐々に低下傾向にあります。5点満点中2点〜3点といった厳しめの評価が並び、「内装は良いが中身が伴っていない」「値段の割にトラブルが多すぎる」といったコメントが繰り返されています。
購入希望者への警鐘として機能
これらの口コミは単なる個人の意見として片づけられないほど広範囲に広がっており、これから購入を検討している層に対する重要な警鐘として機能しています。初めてマツダ車を選ぼうと考えていた人にとっても、CX-60は“第一印象は良いが実態は伴わない”という印象を強く与えてしまっているのが実情です。
ユーザーのリアルな声は、カタログスペックや販売店の営業トークではわからない車の本質を映し出す鏡でもあります。CX-60に対する失望の声がこれほどまでに集まっている現状を重く受け止め、今は慎重な判断が求められます。
CX-60は改善を待つべき車
結論として、現時点でCX-60を購入するのはおすすめできません。マツダが根本的な問題解決を行い、製造工程や品質管理を見直し、改善版が登場するまで待つことが最善策です。
改良版の登場が待たれる理由
現時点では、度重なるリコールと不具合報告により、CX-60の信頼性は著しく損なわれています。マツダ自身もユーザーからのフィードバックを受けて、内部的に構造や電子制御系の見直しを進めているとみられており、次期ロットや改良版の投入が見込まれています。
改善の兆しとマツダの取り組み
2024年後半から一部機能に小規模なマイナーチェンジが入ったモデルも流通し始めており、足回りのセッティング変更や制御ソフトのアップデートが施されたという報告もあります。こうした事例を見る限り、マツダも「CX-60問題」を深刻に捉え、段階的な改善を進めていると考えられます。
待つことで得られるメリット
購入を急がずに数か月待つことで、以下のようなメリットが期待できます:
- 改良版の投入による不具合リスクの低減
- 中古市場での価格下落によりお得に購入できる可能性
- CX-80や他の競合車種との比較検討の時間的余裕
結論:焦らず「熟成」を待つ選択を
マツダは挑戦的な車づくりを得意とするメーカーですが、今回はその「攻め」が裏目に出た印象です。だからこそ、メーカーが確実に課題を認識し、改良したモデルを市場に出してくるまでは、購入を控えるという判断は非常に理にかなっています。焦って購入するよりも、1年後の熟成モデルを選ぶ方が、トータルで満足度の高いカーライフにつながるでしょう。
マツダCX-60の購入候補にCX-80を挙げるべき理由
CX-80に期待が高まる理由
マツダが今後発売するCX-80は、CX-60で発生した問題点を徹底的に洗い出し、構造面・制御面ともに刷新された改良モデルとして投入される見込みです。

引用 : MAZDA HP (https://www.mazda.co.jp/cars/cx-80/feature/)
CX-60の反省を生かし、万全の体制で開発されているため、より信頼できる車となることが期待されています。
CX-60の教訓が活かされる
マツダはCX-60のリコールや不具合に対して市場やメディアから厳しい評価を受けましたが、その声を真摯に受け止めて次期モデルであるCX-80に反映していると見られます。具体的には足回りの調整、電子制御系の安定性強化、品質検査工程の強化などが進められているとの情報があります。
CX-80はグローバル基準での品質を意識
CX-80は欧州をはじめとするグローバル市場への展開も視野に入れており、安全性能や環境性能の面でも国際基準を満たす設計がなされる見通しです。このことから、開発段階での品質テストや市場調査も入念に実施されており、従来のCXシリーズとは一線を画す完成度が期待されます。
CX-80のユーザーターゲット像
CX-80はCX-60よりも大きめのボディを持ち、3列シートの搭載などファミリー層を意識した設計になると予測されています。これにより、実用性と高級感を両立したモデルとして、SUV市場での新たな競争力を持つ存在となるでしょう。
発売延期は品質向上の証
一部では「発売が遅れているのでは?」との声もありますが、これは品質改善のための戦略的な延期と考えられます。マツダはCX-80で“CX-60の汚名返上”を果たすべく、時間をかけて徹底的に問題点をつぶし込んでいる最中であり、この姿勢はむしろ歓迎すべきものです。
CX-80は不具合のない完成形に近づく
CX-60のリコール問題はCX-80の開発において大きな教訓となっており、マツダは「再発防止」という強い意志のもと、CX-80の品質向上に力を注いでいます。そのため、CX-80の発売は当初の予定よりもやや遅れる可能性がありますが、これは製品精度を優先した結果であり、長期的にはユーザーにとって大きな利点となるでしょう。
全領域での見直しが進行中
開発の各段階において、CX-60で指摘された問題—足回りのバラつき、電子制御の不安定性、素材の組み付け精度など—に対して、CX-80では全社横断的な品質レビューが実施されており、設計・製造・検査の各プロセスが再構築されています。
第三者機関との連携による品質保証
CX-80では、社内検証に加え、外部の品質検証機関とも連携し、客観的なチェック体制の強化も図られています。これにより、従来のような初期不具合の見逃しリスクが大幅に低減されると期待されています。
顧客からのフィードバックを活用
マツダはCX-60のユーザーから寄せられたフィードバックを真摯に受け止め、それをCX-80の設計・仕様に反映しています。具体的には、シートのホールド感や乗り心地の最適化、ハンドル操作時の応答性向上など、日常使用で体感できる改善が複数取り入れられています。
「本当のマツダの実力」が問われる一台に
CX-80は、単なる新モデルではなく、CX-60での失敗を糧にした“リベンジモデル”とも言える存在です。マツダがこれまで築いてきた「走りの哲学」と、今回得た苦い教訓を融合させた一台として、ブランドの信頼回復のカギを握る重要なモデルとなることは間違いありません。
CX-80の進化したポイント
CX-80では、CX-60で問題視された足回りの硬さやハンドル操作の不具合、緊急ブレーキの誤作動などを徹底的に見直し、改良を重ねています。また、内装の質感を維持しつつ、機械的・電子的信頼性を格段に高める設計が施されており、ユーザーの満足度向上が強く期待されています。
足回りと乗り心地の最適化
CX-60では足回りの硬さが不満点として多く挙げられましたが、CX-80ではショックアブソーバーの減衰力設定を刷新し、よりしなやかで快適な乗り心地を実現。荒れた路面でも突き上げ感を抑え、同乗者にもやさしい設計となっています。
ステアリングと運転支援の制御改善
CX-60で問題となったハンドルのカクつきやステアリングフィールの不自然さも、CX-80ではEPS(電動パワーステアリング)制御の見直しにより滑らかな応答性が確保されています。これにより、高速走行時やカーブでの安定性も向上し、運転時のストレスが軽減されています。
ブレーキ制御の再調整
緊急ブレーキの誤作動という致命的な問題に対しても、CX-80ではセンサーレイアウトやソフトウェアロジックが全面的に見直され、誤認識の発生頻度を大幅に低減。安心して先進安全機能を使える車に仕上がっている点が注目されます。
内装品質の維持と操作性の向上
CX-60で高評価を得た内装の質感はCX-80でも踏襲されていますが、さらに操作系のレイアウトやナビゲーションシステムのユーザビリティにも手が加えられています。タッチパネルの反応速度やUI設計も改善され、日常的な使いやすさが向上しています。
このように、CX-80ではCX-60で浮き彫りになった多くの課題に対して、設計・制御・快適性の面から丁寧に改善が加えられており、マツダの本気度がうかがえる一台となっています。
まとめ
マツダのCX-60は、見た目の良さや内装の質感の高さから一時は人気を博しましたが、リコール問題の多発により購入は避けるべきです。安全性や快適性の観点からも、今後改良されたモデルを待つか、新たに投入されるCX-80の登場を待つ方が賢明です。マツダの次なる挑戦に期待し、慎重に購入計画を進めていくことをおすすめします。