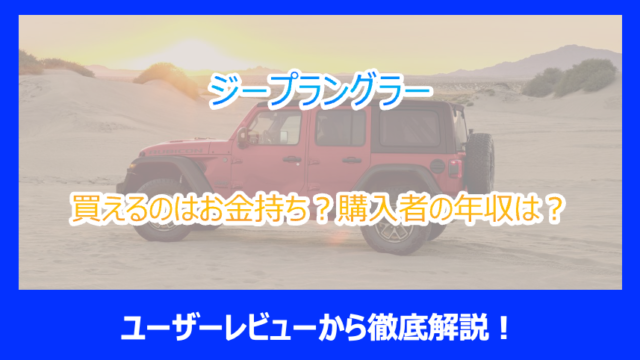モータージャーナリスト兼コラムニストの二階堂仁です。今回も多く寄せられている質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、「BMWを購入して本当に法人税対策になるのか?」「どのモデルを、いつ買えば一番お得なのか?」といった点が気になっていると思います。
私も会社経営者の友人から同様の相談を頻繁に受けますし、自分自身でも節税を目的として車両を購入した経験があるので、その疑問や気になる気持ちはよくわかります。

引用 : BMW HP
巷でよく聞く「4年落ちの中古車が良い」という話には、実は明確なカラクリが存在します。
この記事を読み終える頃には、なぜBMWが法人税対策におすすめなのか、そしてあなたの会社にとって最適な一台を見つけるための具体的な知識と考え方の疑問が解決しているはずです。
記事のポイント
- 高級車購入による節税の仕組みと減価償却
- 4年落ち中古BMWが節税に最適な理由
- 節税効果の高いおすすめBMWモデルの紹介
- 他ブランド比較から見るBMWの強みと立ち位置
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

BMW購入が法人税対策になる仕組みとは?減価償却の基本を解説
「車を買うと節税になる」という話は、特に経営者の間ではよく交わされる会話です。しかし、その具体的な仕組みを正しく理解している方は意外と少ないかもしれません。なぜBMWのような高級車を購入することが、法人税の対策として有効なのでしょうか。その鍵を握るのが「減価償却」という会計上の考え方です。

そもそも減価償却とは?資産価値の減少を経費にする考え方
減価償却とは、車や建物、機械設備といった、時間が経つにつれて価値が減少していく「固定資産」の購入費用を、その資産が使用できる期間(法定耐用年数)にわたって分割して経費として計上していく会計処理のことです。
例えば、600万円の車を現金一括で購入したとします。この600万円をその年の経費として一度に計上するわけではありません。もし一度に経費にできてしまうと、その年だけ利益が極端に少なくなり、翌年以降の利益との比較が難しくなるなど、会社の経営状況を正しく把握できなくなってしまいます。
そこで、会計ルールでは「この資産はこれくらいの期間にわたって事業に貢献するだろう」という目安である「法定耐用年数」を定めています。自動車の場合、新車の普通自動車であれば6年、軽自動車であれば4年です。この期間にわたって、購入費用を分割して経費計上していくのが減価償却の基本的な考え方です。
なぜ高級車が節税につながるのか?利益の繰り延べのカラクリ
減価償却費は、実際にお金が出ていくわけではないのに経費として計上できる「キャッシュアウトを伴わない経費」です。

法人税は、会社の利益(益金)から経費(損金)を差し引いた「課税所得」に対して課せられます。つまり、経費が多ければ多いほど課税所得は減り、結果的に支払う法人税も少なくなるわけです。
ここで、減価償却が節税につながるカラクリが見えてきます。特に大きな利益が出た年に高額な車両を購入すると、その年度から減価償却費という経費が発生します。これにより課税所得が圧縮され、その年の法人税を抑えることができるのです。
これは厳密に言えば「節税」というよりも「課税の繰り延べ」と表現するのが正確です。数年間にわたって支払うはずだった税金を、資産購入によって前倒しで経費計上し、将来に支払う税額を増やしている(あるいは、将来得られるはずだった経費を先に使っている)状態だからです。しかし、手元に残るキャッシュフローを改善したり、突発的な利益が出た年度の税負担を平準化したりする効果は絶大で、多くの経営者がこの手法を活用しています。
購入する車両が高額であるほど、年間の減価償却費も大きくなるため、高級車はより大きな節税効果が期待できるということになります。
自動車の耐用年数と減価償却の計算方法(定額法と定率法)
減価償却の計算方法には、主に「定額法」と「定率法」の2種類があります。
- 定額法: 毎年、同じ額の減価償却費を計上する方法。計算がシンプルで、計画を立てやすいのが特徴です。
- 計算式:
取得価額 × 定額法の償却率
- 計算式:
- 定率法: 初年度に最も多くの減価償却費を計上し、年々その額が減少していく方法。資産の価値は購入当初に最も大きく下がるという考え方に基づいています。
- 計算式:
(取得価額 − 前年度までの減価償却費累計額) × 定率法の償却率
- 計算式:
法人の場合、特に届け出をしなければ「定率法」が適用されます。定率法は購入初期の節税効果が非常に高いため、多くの企業で採用されています。
| 耐用年数 | 定額法償却率 | 定率法償却率 |
|---|---|---|
| 2年 | 0.500 | 1.000 |
| 3年 | 0.334 | 0.667 |
| 4年 | 0.250 | 0.500 |
| 5年 | 0.200 | 0.400 |
| 6年 | 0.167 | 0.333 |
※2012年4月1日以降に取得した資産の場合
中古車が節税に有利な理由|耐用年数の計算式が鍵
新車ではなく、なぜ中古車が節税に有利なのでしょうか。その理由は、中古資産の耐用年数の計算方法にあります。中古車の場合、法定耐用年数から経過した年数を差し引いて、残りの年数を耐用年数として計算します。
具体的な計算式は以下の通りです。
- 法定耐用年数の全部を経過した場合:
法定耐用年数 × 20% - 法定耐用年数の一部を経過した場合:
(法定耐用年数 - 経過年数) + (経過年数 × 20%)
※計算結果の1年未満の端数は切り捨てます。 ※計算結果が2年未満の場合は、耐用年数は2年となります。
この計算式により、中古車は新車に比べて耐用年数が短くなります。耐用年数が短いということは、購入費用をより短期間で経費化できることを意味し、これが大きな節税効果を生むのです。
なぜ「4年落ち」が最強と言われるのか?1年で全額償却のロジック
節税の話でよく耳にする「4年落ち(正確には3年10ヶ月落ち以上)の中古車」が最強と言われる理由は、この耐用年数の計算ロジックにあります。
新車の普通自動車の法定耐用年数は6年です。ここに、例えばピッタリ4年落ちの中古車の情報を当てはめてみましょう。
(6年 - 4年) + (4年 × 20%) = 2年 + 0.8年 = 2.8年
1年未満の端数は切り捨てるため、耐用年数は「2年」となります。
そして、先ほどの償却率の表を見てください。耐用年数が2年の場合、定率法の償却率は「1.000」、つまり100%です。これは、購入費用を1年間で全額経費として計上できることを意味します。
例えば、期首に600万円の4年落ちBMWを購入した場合、その年度の経費として600万円全額を減価償却費として計上できるのです。これにより、その年の課税所得を600万円圧縮できるため、絶大な節税効果が生まれます。これが「4年落ち中古車が節税に最強」と言われるカラクリです。
新車購入は節税にならない?新車と中古車の減価償却シミュレーション比較
では、新車購入では節税効果は全くないのでしょうか?そんなことはありません。ただし、中古車に比べて効果が緩やかになります。
ここで、同じ600万円の車を「新車」で購入した場合と「4年落ち中古車」で購入した場合の減価償却費を比較してみましょう。(法人、定率法、期首購入と仮定)
【ケース1】600万円の新車(耐用年数6年)を購入した場合
| 年度 | 期首帳簿価額 | 減価償却費 (償却率0.333) | 期末帳簿価額 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 6,000,000円 | 1,998,000円 | 4,002,000円 |
| 2年目 | 4,002,000円 | 1,332,666円 | 2,669,334円 |
| 3年目 | 2,669,334円 | 888,923円 | 1,780,411円 |
| 4年目 | 1,780,411円 | 592,897円 | 1,187,514円 |
| 5年目 | 1,187,514円 | 395,442円 | 792,072円 |
| 6年目 | 792,072円 | 792,071円 | 1円 (備忘価額) |
【ケース2】600万円の4年落ち中古車(耐用年数2年)を購入した場合
| 年度 | 期首帳簿価額 | 減価償却費 (償却率1.000) | 期末帳簿価額 |
|---|---|---|---|
| 1年目 | 6,000,000円 | 6,000,000円 | 0円 |
| 2年目 | 0円 | 0円 | 0円 |
※実際には期末に備忘価額1円を残します。
このように、4年落ち中古車の場合は購入したその年に全額を経費にできるのに対し、新車の場合は6年かけて緩やかに経費化していくことになります。どちらが良いかは会社の利益状況や経営戦略によりますが、「特定の年に出た大きな利益を圧縮したい」という短期的な節税ニーズに対しては、4年落ち中古車が圧倒的に有利であることがお分かりいただけるでしょう。
減価償却費として計上する際の注意点
車両を経費で購入する際には、いくつか注意すべき点があります。これを怠ると、税務調査で経費として認められない(否認される)リスクがあります。
事業供用割合(家事按分)
特に経営者一人の会社などの場合、購入した車を事業だけでなくプライベートでも使用することがあるでしょう。その場合、車両の購入費用や維持費の全額を経費にすることはできません。
事業で使っている割合とプライベートで使っている割合を合理的な基準で算出し、事業で使っている分だけを経費として計上する必要があります。これを「家事按分」と呼びます。例えば、走行記録をつけて「週5日は事業で使い、週2日はプライベートで使う」のであれば、7分の5を事業供用割合として経費計上します。この割合の根拠を明確に説明できるようにしておくことが非常に重要です。
事業との関連性
購入する車両が、その会社の事業内容と関連性があるかどうかも問われることがあります。例えば、建設業の会社が現場回り用に高級セダンを購入した場合、「なぜトラックやバンではなく、この車が必要なのですか?」と説明を求められる可能性があります。「顧客への信頼性向上」や「ブランディング」といった目的も認められるケースはありますが、あまりに事業内容とかけ離れた趣味性の高いスポーツカーなどは、経費として認められない可能性が高まるため注意が必要です。
その点、BMWはセダン、SUV、ワゴンなど多彩なラインナップがあり、「取引先への訪問」や「役員移動車」といった事業目的との関連性を説明しやすいブランドと言えるでしょう。
節税だけじゃない!法人が高級車を持つメリット
法人でBMWのような高級車を所有するメリットは、節税効果だけにとどまりません。
- 対外的な信用力・ブランディング: 立派な車に乗っていることは、会社の経営が順調であることの証と見なされることがあります。金融機関や取引先からの信用力向上につながる可能性があります。
- 従業員や経営者自身のモチベーション向上: 魅力的な車を社用車として利用できることは、従業員の満足度やロイヤリティを高める一因になります。また、経営者自身の仕事へのモチベーションアップにもつながるでしょう。
- 安全性の確保: 最新の高級車は、先進的な安全運転支援システムを標準で装備していることがほとんどです。万が一の事故のリスクを低減し、役員や従業員の安全を守ることにもつながります。
これらの副次的なメリットも考慮すると、高級車の購入は単なる経費ではなく、将来への「投資」と捉えることもできるのです。
法人税対策に最適なBMWの選び方とおすすめモデル
減価償却の仕組みを理解したところで、次は実践編です。数ある高級車ブランドの中から、なぜBMWが法人税対策として選ばれるのでしょうか。そして、具体的にどのモデルを選べばその効果を最大化できるのか。長年多くのBMWを所有し、乗り継いできた私の視点から詳しく解説していきます。

引用 : BMW HP
なぜ数ある高級車の中でもBMWが選ばれるのか
私が考える、BMWが法人での購入に適している理由は主に4つあります。
走りの楽しさと実用性の両立
BMWの根幹にあるのは「駆けぬける歓び」というスローガンに代表される、卓越したドライビング性能です。正確なハンドリング、スムーズかつパワフルなエンジンは、日々の移動時間を単なる業務から、心躍る体験へと変えてくれます。しかし、それだけではありません。セダンやツーリング(ワゴン)、SUVモデルは、後部座席の居住性や荷室の積載性といった実用性も非常に高く設計されており、ビジネスユースとプライベートユースを見事に両立させてくれます。
豊富なモデルラインナップ
コンパクトな1シリーズから、ビジネスの王道である5シリーズ、フラッグシップの7シリーズ、そして人気のSUVであるXシリーズまで、BMWは非常に幅広いモデルラインナップを誇ります。これにより、会社の規模や事業内容、使用目的に合わせて最適な一台を選ぶことが可能です。「取引先への訪問用」「役員送迎用」「現場への足」など、あらゆるニーズに対応できる懐の深さがBMWの大きな魅力です。
高いリセールバリュー
節税目的で車を購入する際、出口戦略、つまり「売却時の価格」は非常に重要です。BMWは、輸入車の中でも比較的リセールバリューが高いブランドとして知られています。特に、Mスポーツなどの人気グレードや、人気のボディカラー(アルピン・ホワイト、ブラック・サファイアなど)を選んでおけば、数年後に売却する際も高値が期待できます。減価償却によって帳簿上の価値は1円になっていても、市場では数百万円の価値が残っている、という状況を作りやすいのです。これが、実質的な資産価値を維持しながら節税メリットを享受できる、BMWの大きな強みです。
経営者としてのステータス
前述の通り、車は会社の「顔」でもあります。スポーティーでありながらも知的な印象を与えるBMWのブランドイメージは、多くの経営者に好まれています。過度に華美ではなく、しかし確かな品質と性能を感じさせる佇まいは、ビジネスシーンにおいて信頼感や説得力といった無形の価値をもたらしてくれるでしょう。
節税効果を最大化するBMW選びの3つのポイント
節税という観点からBMWを選ぶ際には、以下の3つのポイントを意識することが重要です。

引用 : BMW HP
ポイント1:4年落ち(正確には3年10ヶ月落ち以上)を狙う
繰り返しになりますが、節税効果を最大化するなら、耐用年数が2年となり、定率法で1年償却が可能になる「3年10ヶ月以上経過した中古車」が最も効率的です。市場では「4年落ち」という言葉で探すのが一般的でしょう。最初の車検(3年目)を終え、価格が一段階落ち着いたタイミングでもあるため、購入価格と節税効果のバランスが最も良いゾーンと言えます。
ポイント2:リセールバリューの高いモデルを選ぶ
いくら節税できても、売却時に二束三文になってしまっては意味がありません。人気のあるモデル、グレード、カラー、そしてオプション装備が充実している車両を選びましょう。
- モデル: SUV人気の高まりからX3、X5は非常に高いリセールを維持しています。伝統的なセダンでは3シリーズ、5シリーズが根強い人気です。
- グレード: スポーティな内外装を持つ「Mスポーツ」は、標準モデルに比べて圧倒的に人気が高く、リセールも期待できます。
- カラー: 定番の白(アルピン・ホワイト)と黒(ブラック・サファイアなど)が最も高値で取引されます。
- オプション: サンルーフ、レザーシート、先進安全装備のパッケージなどはプラス査定の大きな要因になります。
ポイント3:事業用の車として相応しいモデルを選ぶ
税務調査の際に「なぜこの車が必要なのか」を合理的に説明できるモデルを選びましょう。極端な話、2シーターのスポーツモデルであるZ4よりも、4ドアセダンの5シリーズやSUVのX5の方が「役員移動や取引先への訪問」といった目的を説明しやすいのは明らかです。会社の事業内容や規模感と、選んだ車のキャラクターが乖離しすぎないように配慮することが賢明です。
【ジャーナリスト厳選】節税におすすめのBMWモデル5選
上記のポイントを踏まえ、私が今、経営者の友人におすすめするならこの5台、というモデルをピックアップしました。いずれも私自身が所有、あるいは長時間試乗した経験のあるモデルです。
1. BMW 5シリーズ(セダン/ツーリング)
ビジネスセダンの王道であり、最もバランスの取れた一台です。乗り心地、静粛性、運動性能のすべてが高次元でまとまっており、長距離の移動も全く苦になりません。取引先へ訪問する際にも失礼がなく、威圧感も与えすぎない絶妙な立ち位置は、まさにビジネスエリートのための車と言えるでしょう。4年落ちであれば、先代モデル(G30/G31型)が手頃な価格で見つかります。ディーゼルモデルの「523d」は燃費も良く、リセールも安定しているため特におすすめです。
2. BMW X5
圧倒的な存在感と悪路走破性、そして高級感を兼ね備えたSUVのフラッグシップモデル。多用途性に優れ、ゴルフやレジャーといった接待の場面でも活躍します。高い車高からの視界は運転しやすく、安全性も非常に高いレベルにあります。会社のステータスを象徴する一台として、また経営者ファミリーのプライベートユースまでこなせる万能選手として、非常に人気が高いモデルです。価格は高めですが、その分リセールバリューもトップクラスを誇ります。
3. BMW 3シリーズ(セダン/ツーリング)
「スポーツセダンの指標」と評される、BMWの真骨頂ともいえるモデルです。5シリーズよりも一回りコンパクトなボディは日本の道路事情にマッチしており、キビキビとした走りは運転する楽しさを日々実感させてくれます。それでいて後部座席や荷室の使い勝手も犠牲になっておらず、実用性は十分。特に都市部での利用が多い経営者の方には最適な選択肢です。現行モデル(G20/G21型)の4年落ちが市場に出始めており、先進装備も充実しているため満足度は高いでしょう。
4. BMW 7シリーズ
BMWのフラッグシップセダン。後席の快適性はメルセデス・ベンツ Sクラスと比較されるほど高く、ショーファードリブン(運転手付きの車)としての利用にも十分耐えうるクオリティを誇ります。経営者が自らハンドルを握るシーンはもちろん、重要なゲストを送迎する場面など、会社の「顔」としての役割を完璧にこなします。中古車市場では価格の下落率が比較的大きい傾向にありますが、その分、新車価格から考えるとお買い得感は非常に高いです。法人所有のメリットを最大限に享受できる一台と言えるかもしれません。
5. BMW X3
X5ほどのサイズは必要ないけれど、SUVの利便性は欲しい、というニーズに完璧に応えるミドルサイズSUVです。取り回しの良さと室内の広さのバランスが絶妙で、日本市場で最も人気のあるBMWの一つです。日常使いから長距離ドライブ、悪天候時の安定性まで、あらゆるシーンで高いパフォーマンスを発揮します。リセールバリューも非常に安定しており、節税目的の購入対象として極めて優秀なモデルです。
新車での購入を検討する場合の考え方
これまで4年落ち中古車を推奨してきましたが、もちろん新車購入が選択肢にならないわけではありません。
- 長期的な節税計画: 6年間かけて安定的に経費を計上したい場合や、会社の利益が今後も安定して見込める場合には、新車購入も有効です。
- 最新の技術と保証: 最新の安全性能やインフォテインメントシステムを享受できるほか、メーカーの新車保証が付帯するため、故障のリスクや突発的な出費を心配する必要がありません。
- クリーンエネルギー自動車補助金など: プラグインハイブリッド(PHEV)や電気自動車(BEV)のモデルであれば、国からの補助金や税制優遇を受けられる場合があります。これらを活用することで、購入時の負担を軽減できる可能性があります。
会社のキャッシュフローや経営計画に合わせて、中古車による短期的な節税と、新車による長期的かつ安心感のある運用のどちらが適しているかを検討することが重要です。
BMW購入時の資金計画|現金一括、ローン、リースの違い
法人で車両を購入(使用)する方法は、主に「現金一括」「ローン」「リース」の3つです。
| 購入方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 現金一括 | ・支払総額が最も安い ・会社の資産になる | ・手元のキャッシュが大きく減る ・減価償却の会計処理が必要 |
| ローン | ・手元のキャッシュを残せる ・会社の資産になる | ・金利負担が発生する ・減価償却の会計処理が必要 |
| リース | ・頭金が不要な場合が多い ・維持費や税金もコミコミで支払いを平準化できる ・経費処理がシンプル(リース料を計上するだけ) | ・支払総額は割高になる傾向 ・原則、中途解約できない ・カスタマイズができない |
節税という観点では、減価償却をコントロールしやすい現金一括またはローンでの購入が一般的です。特に、利益が多く出た年度に現金で購入し、4年落ち中古車の1年償却を適用するのが最もインパクトの大きい手法となります。
一方、リースは経費処理の手間を省きたい場合や、数年ごとに常に新しい車に乗り換えたい、といったニーズに適しています。
リセールバリューで見るBMW|他高級ブランドとの比較
節税と並行して考えるべきリセールバリュー。BMWは他の高級車ブランドと比較してどのような立ち位置にいるのでしょうか。あくまで一般的な市場の傾向ですが、私の見解を述べさせていただきます。
| ブランド | 代表的な高リセールモデル | 特徴・BMWとの比較 |
|---|---|---|
| ランドローバー | レンジローバー, ディフェンダー | 近年、特にリセールが高いブランド。特にディフェンダーは驚異的な価格を維持。BMWのXシリーズと競合するが、よりオフロード志向で趣味性が強い。安定性ではBMWがやや有利か。 |
| メルセデス・ベンツ | Gクラス, Sクラス | Gクラスは別格のリセールを誇る。セダン系はBMWと同等かモデルによってはやや下回る傾向も。ブランドイメージはよりコンサバティブで、ショーファーニーズも強い。 |
| レクサス | LX, RX | 故障の少なさと信頼性で、国産ブランドの中でもトップクラスのリセール。特に大型SUVのLX、RXは非常に高い価格を維持。BMWに比べるとスポーティーさより快適性重視。 |
| アウディ | Qシリーズ | BMWやメルセデスと比較すると、リセールはやや弱い傾向にある。洗練されたデザインが魅力だが、中古車市場では一歩譲る印象。 |
| マセラティ | ギブリ, レヴァンテ | 官能的なデザインとサウンドが魅力だが、リセールバリューは厳しいと言わざるを得ない。節税目的で購入するには出口戦略を慎重に考える必要がある。 |
【総合的なBMWの立ち位置】 Gクラスやディフェンダーのような突出したモデルはありませんが、どのモデルを選んでも大きく値崩れすることがなく、安定して高いリセールバリューを維持しているのがBMWの強みです。スポーティーなブランドイメージが中古車市場でも高く評価されており、特に「Mスポーツ」の安定感は抜群です。節税目的で購入する上で、この「計算のしやすさ」と「安定感」は非常に大きなメリットと言えるでしょう。
BMW購入後の維持費も経費になる?
車両本体の減価償却費だけでなく、その車を維持するためにかかる費用も、事業で使用している割合に応じて経費として計上できます。
- 自動車税、重量税、自賠責保険料など(租税公課、保険料)
- 任意保険料(保険料)
- ガソリン代、高速道路代(旅費交通費、車両費)
- 駐車場代(地代家賃)
- 車検代、修理代、オイル交換費用など(修繕費、車両費)
これらの維持費も年間で合計するとかなりの金額になります。車両本体の節税効果と合わせて、トータルで会社の経費構造を最適化することが可能です。
まとめ
今回は、BMWの購入がなぜ法人税対策としておすすめなのか、その中心的な仕組みである「減価償却」のカラクリから、具体的なモデル選びのポイントまでを詳しく解説しました。
改めて重要なポイントを整理しましょう。
- 車の購入費用は「減価償却」によって数年にわたり経費化できる
- 中古車は耐用年数が短くなるため、より短期間で経費化でき節税効果が高い
- 特に「4年落ち」の中古普通車は、耐用年数2年・定率法償却率100%となり、1年で全額経費化が可能
- BMWは高いリセールバリューと豊富なラインナップ、ビジネスシーンに適したブランドイメージから、節税目的の車両として非常に優れている
- 節税効果を最大化するには「4年落ち」「高リセールモデル」「事業との関連性」を意識して選ぶことが重要
もちろん、節税はあくまで車を持つ目的の一つです。最も大切なのは、その車があなたのビジネスや日々の生活に喜びや活力を与えてくれるかどうかです。その点において、BMWの「駆けぬける歓び」は、経営者としての日々のプレッシャーを忘れさせ、新たなインスピレーションを与えてくれる、最高のパートナーになり得ると私は確信しています。
このレビューが、あなたの最適な一台選び、そして賢い会社経営の一助となれば幸いです。