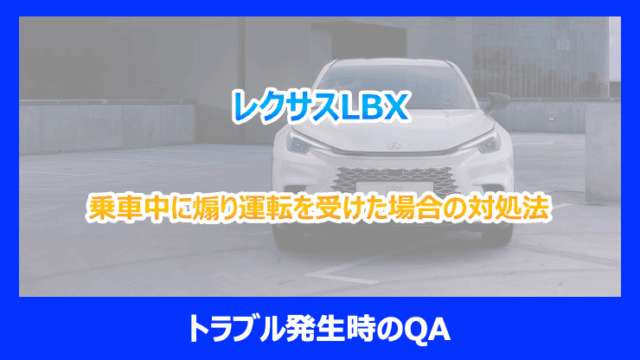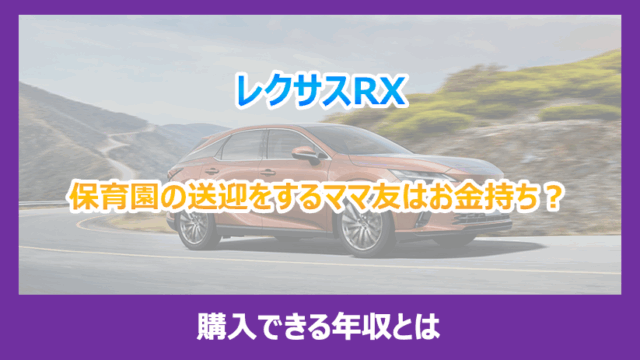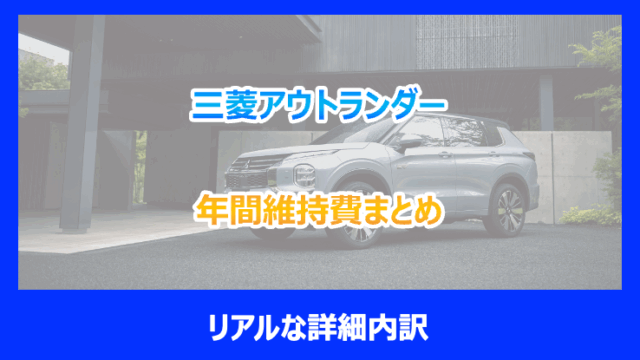モータージャーナリスト兼コンサルタントの二階堂仁です。今回も多く寄せられている質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、雪国で三菱デリカD:5の購入を検討する中で、特に冬用タイヤの費用がどれくらいかかるのか気になっているのではないでしょうか。私も実際にデリカD:5を所有し、冬を迎えるにあたってスタッドレスタイヤ選びで頭を悩ませた経験があるので、その気になる気持ちはよくわかります。

引用 : 三菱自動車HP
ミニバン随一の悪路走破性を誇るデリカD:5ですが、2019年のビッグマイナーチェンジ以降、タイヤサイズが大きくなったことで、冬の準備に思わぬ出費が伴うケースがあるのです。
この記事を読み終える頃には、雪国でデリカD:5を所有する際の冬のコストに関する疑問が解決し、安心して購入計画を進められるようになっているはずです。
記事のポイント
- デリカD:5後期型のタイヤ大型化
- 高額な18インチスタッドレスタイヤの実態
- コストを抑えるインチダウンという選択肢
- 標準装備で十分なデリカD:5の寒冷地性能
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

三菱デリカD:5の冬用タイヤが高額になる理由
「デリカD:5は雪道に強いから安心」と考えている方は多いでしょう。その考えは間違いありません。しかし、その強さを冬道で万全に発揮するためには、スタッドレスタイヤが必須です。そして、そのスタッドレスタイヤの価格が、特に2019年2月のビッグマイナーチェンジ後のモデル(以下、後期型)から、無視できないレベルに上がっているという事実をご存知でしょうか。

引用 : 三菱自動車HP
私も後期型のデリカD:5を所有していますが、最初の冬を迎える際にタイヤの見積もりを見て驚いた一人です。ここでは、なぜデリカD:5の冬用タイヤが高額になるのか、その背景を詳しく解説していきます。
ビッグマイナーチェンジでタイヤが大型化
最も大きな理由は、後期型になって標準装着されるタイヤサイズが大きくなったことです。
前期型(2007年~2019年1月)では、グレードによって16インチと18インチのタイヤが設定されていましたが、後期型では廉価グレードの「M」を除き、ほとんどのグレードで18インチが標準装備となりました。
| モデル | 主な標準タイヤサイズ | ホイールサイズ |
|---|---|---|
| 後期型 (2019年2月~) | 225/55R18 | 18インチ |
| 前期型 (2007年~2019年1月) | 215/70R16 または 225/55R18 | 16インチまたは18インチ |
一般的に、タイヤはインチ数が大きくなるほど価格が上昇します。16インチと18インチでは、同じ銘柄のスタッドレスタイヤでも1本あたり数千円から1万円以上の価格差が生まれることも珍しくありません。4本セットになれば、その差は数万円単位となり、家計へのインパクトも大きくなります。
このタイヤの大型化が、雪国でデリカD:5を検討する際の、以前にはなかった新たな注意点となっているのです。
18インチスタッドレスタイヤの価格相場
では、実際に18インチのスタッドレスタイヤ(225/55R18)はいくらくらいするのでしょうか。国内の主要タイヤメーカーの価格帯を調べてみると、おおよそ以下のようになります。
- タイヤ単体(4本セット)の価格目安:約12万円~22万円
- ホイールセット(4本セット)の価格目安:約16万円~30万円以上
もちろん、選ぶタイヤの銘柄(ブリヂストンのBLIZZAK、ヨコハマのiceGUARDなど)や、組み合わせるホイールのデザイン・ブランドによって価格は大きく変動します。しかし、最低でも15万円前後の出費は覚悟しておく必要があるでしょう。これは、一般的な15インチや16インチのタイヤを装着する乗用車やミニバンと比較すると、かなり高額な部類に入ります。
特に、プレミアムブランドのスタッドレスタイヤを選んだり、デザイン性の高いホイールを組み合わせたりすると、総額はあっという間に25万円、30万円を超えてしまいます。新車購入時の諸費用に加えてこの出費は、予想外だと感じる方も少なくないはずです。
なぜ18インチタイヤは高価なのか?
18インチタイヤが高価なのには、いくつかの理由があります。
- ゴムの使用量と構造の複雑さ 単純にタイヤが大きくなるため、使用されるゴムや内部の補強材(コードなど)の量が増えます。また、偏平率が低く(タイヤの厚みが薄く)なるため、乗り心地や剛性を確保するために、より高度な設計と製造技術が求められ、これがコストに反映されます。
- 需要と供給のバランス 数年前までは18インチ以上の大径タイヤは一部の高級車やスポーツカーが中心でした。しかし近年、SUVやミニバンでも標準装備されるケースが増え、需要は拡大しています。とはいえ、市場全体で見れば15インチや16インチといったサイズが依然として主流であり、製造・流通のコスト効率の面で、大径タイヤはまだ割高になる傾向があります。
- 開発コスト スタッドレスタイヤは、氷上性能、雪上性能、燃費性能、静粛性など、夏タイヤ以上に多くの性能を高いレベルで両立させる必要があります。特に安全に直結する氷上性能は各社がしのぎを削って開発しており、その研究開発費が価格に上乗せされています。大径サイズ専用の設計も必要になるため、コストはさらに増加します。
これらの要因が複合的に絡み合い、18インチのスタッドレスタイヤは高価になっているのです。
純正ホイールを冬用に使う際の注意点
「夏タイヤを外し、純正ホイールにスタッドレスタイヤを組めば、ホイール代が浮くのでは?」と考える方もいるでしょう。確かに一時的な出費は抑えられますが、長い目で見るとデメリットも存在します。
融雪剤による腐食リスク
雪国の道路に撒かれる融雪剤(塩化カルシウムなど)は、塩分を含んでおり、車の金属部分、特にアルミホイールの腐食(サビ)の原因となります。メーカー純正のホイールは品質が高いですが、毎年のように冬の間ずっと融雪剤に晒され続けると、クリア塗装が剥がれたり、白サビが発生したりするリスクが高まります。
せっかくのデザイン性の高い純正ホイールが、数年で見た目を損なってしまうのは避けたいところです。
タイヤの組み替えコストと手間
シーズンごとにタイヤをホイールから脱着する「組み替え」作業には、毎回工賃が発生します。1回あたり数千円から1万円程度の費用がかかり、これを毎年2回(春と冬)繰り返すと、数年間で数万円の出費になります。
また、タイヤやホイールへの負担も無視できません。組み替え作業はタイヤのビード部分(ホイールと接する部分)に負荷をかけるため、繰り返すことでタイヤを傷めてしまう可能性もゼロではありません。
これらの理由から、夏用と冬用でそれぞれタイヤとホイールのセットを用意しておくのが、結果的にコストパフォーマンスも良く、愛車のコンディションを保つ上でも賢明な選択と言えるでしょう。
雪国でのデリカD:5、冬のコストを抑える賢い選択
後期型デリカD:5の冬支度が高額になりがちなことはご理解いただけたかと思います。しかし、諦める必要はありません。少しの工夫で、冬のコストを賢く、そして大幅に抑える方法があります。

引用 : 三菱自動車HP
私自身も実践している、最も効果的な方法が「インチダウン」です。ここでは、インチダウンのメリットや具体的な方法、そして費用感を詳しく解説していきます。
最適な解決策は「インチダウン」
インチダウンとは、その名の通り、標準装着されているホイールのインチサイズを小さくすることです。デリカD:5の場合、標準の18インチから17インチや16インチのホイールに変更し、それに適合するスタッドレスタイヤを装着することを指します。
もちろん、ただ小さくすれば良いというわけではありません。タイヤの外径(直径)を純正サイズとほぼ同じに保つことが重要です。外径が変わってしまうと、スピードメーターに誤差が生じたり、走行安定性に影響が出たりするためです。
デリカD:5のインチダウンでは、前期型でも採用されていた16インチが最もポピュラーで、選択肢も豊富なためおすすめです。
インチダウンのメリット(コスト、乗り心地、性能)
インチダウンには、雪国で車を所有する上で多くのメリットがあります。
圧倒的なコスト削減
最大のメリットは、やはりコストです。前述の通り、18インチと16インチではタイヤの価格が大きく異なります。
- 16インチスタッドレスタイヤ(215/70R16)の価格相場
- タイヤ単体(4本セット):約7万円~13万円
- ホイールセット(4本セット):約9万円~18万円
18インチのセットと比較すると、安価な組み合わせであれば5万円以上、場合によっては10万円近くも初期費用を抑えることが可能です。これは非常に大きなメリットと言えるでしょう。
乗り心地の向上
インチダウンをすると、タイヤの厚み(偏平率)が増します。これにより、タイヤ内部の空気の量(エアボリューム)が増え、路面からの衝撃をよりしなやかに吸収してくれるようになります。結果として、乗り心地がマイルドになる傾向があり、荒れた路面や段差を乗り越える際の突き上げ感が緩和されます。
雪道での走行性能
一般的に、タイヤの幅が少し狭くなることで、タイヤにかかる面圧(単位面積あたりの圧力)が高まります。これにより、雪を掘り進む力や、圧雪路にタイヤを食い込ませる力が強くなり、雪道でのグリップ性能が向上する場合があると言われています。特に新雪や深い雪の中を走行する際には、インチダウンの恩恵を感じられるかもしれません。
インチダウンのデメリットと注意点
もちろん、インチダウンにはいくつかの注意点もあります。
- 見た目の変化 ホイールが小さくなり、タイヤのゴム部分の面積が大きくなるため、良く言えば「ワイルド」「オフロード感が増す」、悪く言えば「スタイリッシュさが薄れる」と感じる方もいるでしょう。これについては個人の好みが大きい部分です。
- ホイール選びの重要性 どんな16インチホイールでも装着できるわけではありません。デリカD:5のブレーキキャリパー(特に後期型)に干渉しないデザインのホイールを選ぶ必要があります。購入時には必ず「デリカD:5(後期型)装着可能」と明記されている製品を選ぶか、専門店で相談するようにしましょう。
- 走行性能の変化 乗り心地がマイルドになる反面、ドライ路面でのコーナリングなどでは、タイヤのたわみが大きくなるため、応答性がやや穏やかになります。とはいえ、スタッドレスタイヤでスポーティーな走行をする場面は少ないため、実用上はほとんど問題にならないレベルです。
おすすめのインチダウンサイズは16インチ
デリカD:5のインチダウンで最も定番かつおすすめなのが、215/70R16というサイズです。
| 項目 | 18インチ(標準) | 16インチ(インチダウン) |
|---|---|---|
| タイヤサイズ | 225/55R18 | 215/70R16 |
| タイヤ外径 | 約705mm | 約708mm |
| 差 | – | +3mm |
このように、タイヤ外径の差はわずか3mmで、スピードメーターへの影響はほぼありません。このサイズは前期型デリカD:5の純正サイズでもあるため、タイヤ・ホイール共に市場に流通している製品数が非常に多く、価格やデザインの選択肢が豊富なのが最大の強みです。
インチダウンした場合の費用シミュレーション
ここで、18インチを維持した場合と16インチにインチダウンした場合の費用を比較してみましょう。(※価格はあくまで一般的な目安です)
| 項目 | 18インチ維持プラン(タイヤ+ホイール) | 16インチインチダウンプラン(タイヤ+ホイール) | 差額 |
|---|---|---|---|
| タイヤ(中級グレード) | 約160,000円 | 約90,000円 | -70,000円 |
| ホイール(廉価デザイン) | 約80,000円 | 約60,000円 | -20,000円 |
| 合計 | 約240,000円 | 約150,000円 | -90,000円 |
ご覧の通り、インチダウンを選択するだけで、約9万円ものコストを削減できる可能性があります。この差額があれば、他のオプションを追加したり、家族で旅行に行ったりすることもできますね。
タイヤの保管はどうする?
夏用・冬用のタイヤセットを持つと、次に問題になるのが「使わない方のタイヤをどこに保管するか」です。
自宅で保管する場合
直射日光や雨風が当たらず、風通しの良い冷暗所が理想です。タイヤはゴム製品なので、紫外線や熱、水分によって劣化が進みます。保管前にはタイヤをきれいに洗い、しっかり乾燥させることが重要です。ホイール付きの場合は、空気圧を半分程度に減らし、平積みで保管するのが一般的です。
タイヤ保管サービスを利用する
自宅に十分な保管スペースがない場合や、重いタイヤの運搬が大変な場合は、カー用品店やタイヤ専門店、ガソリンスタンドなどが提供している「タイヤ保管サービス」を利用するのも良い選択です。年間1万円~2万円程度の費用はかかりますが、最適な環境で保管してくれる上、シーズンごとの交換作業もスムーズに行えます。
タイヤ以外に雪国で気になるデリカD:5のポイント
さて、冬の最大の懸念事項であるタイヤの問題が解決の目処を立てば、次はデリカD:5そのものの雪国での実用性が気になるところでしょう。私自身、雪深い地域でデリカD:5を日常的に使用していますが、結論から言うと「これ以上頼もしいミニバンはない」と断言できます。

引用 : 三菱自動車HP
ここでは、寒冷地仕様の必要性や、実際の走行性能、燃費など、気になるポイントを私の実体験を交えて解説します。
寒冷地仕様は必要?結論:不要な場合が多い
新車購入時、特に雪国にお住まいの方が悩むのが「寒冷地仕様」オプションを付けるべきか、という点です。三菱自動車の場合、デリカD:5には以下のような寒冷地仕様がメーカーオプションで設定されています。(※年式やグレードにより内容は異なります)
- ホットプラスパッケージ
- 運転席&助手席シートヒーター
- ステアリングヒーター
- ワイパーデアイサー(フロントガラスのワイパーが凍り付くのを防ぐ熱線)
- リヤヒーターダクト(後席足元への温風ダクト)
しかし、実はデリカD:5は標準仕様の状態でも、すでに寒冷地に対応できる高い性能を持っています。
例えば、バッテリーは寒さに強い大容量のものが標準ですし、発電機(オルタネーター)も能力の高いものが搭載されています。クーラント(冷却水)も、もちろん寒冷地対応の濃度です。
そのため、北海道や東北の極寒地にお住まいの方でなければ、必ずしも必須のオプションではありません。もちろん、シートヒーターやステアリングヒーターは一度使うと手放せないほど快適な装備ですので、予算に余裕があれば追加する価値は十分にあります。
頼もしいディーゼルエンジンと4WD性能
デリカD:5が雪道で絶大な信頼を得ている最大の理由は、そのパワートレインと4WDシステムにあります。
低回転から力強いディーゼルターボ
後期型のクリーンディーゼルエンジンは、アクセルを少し踏んだだけの低い回転数から、車体をぐいぐいと前に押し出す力強いトルクを発生します。この特性が、滑りやすい雪道での発進時に非常に有利に働きます。タイヤが空転するのを抑えながら、スムーズかつ力強くスタートできるのです。
電子制御4WDの絶大な安心感
デリカD:5の4WDシステムは、「2WD」「4WDオート」「4WDロック」の3つのモードをダイヤル一つで切り替えられます。
- 4WDオート: 普段は基本的にこのモードで走行します。路面状況に応じて、コンピューターが前後のタイヤに最適な駆動力を自動で配分してくれます。圧雪路や凍結路など、ほとんどの冬道はこれで十分対応できます。
- 4WDロック: 深い新雪にはまってしまった時や、急な登り坂など、より強力な駆動力が欲しい場面で使用します。後輪への駆動力配分を増やし、悪路からの脱出を強力にサポートしてくれます。このモードがあるというだけで、精神的な安心感が全く違います。
私自身、この4WDシステムに何度も助けられてきました。吹雪で視界が悪く、どこが道かわからないような状況でも、デリカD:5は不安を感じさせることなく、確実に目的地まで運んでくれる、まさに「走るシェルター」のような存在です。
冬場の実燃費はどれくらい?
ディーゼルエンジンは一般的に燃費が良いとされていますが、冬場はいくつかの要因で燃費が悪化する傾向にあります。
- 暖機運転の時間が増える
- 外気温が低く、エンジンが温まりにくい
- スタッドレスタイヤは夏タイヤより転がり抵抗が大きい
- 4WDでの走行が増える
これらの要因を踏まえ、私のデリカD:5(後期型)の冬場の実燃費は、おおよそ以下の通りです。
- 市街地走行(ストップ&ゴーが多い):8~10km/L
- 郊外・高速走行:11~14km/L
夏場と比較すると1~2km/Lほど悪化しますが、この大きな車体と4WD性能を考えれば、十分に経済的と言えるでしょう。特に長距離移動が多い方にとっては、軽油の価格の安さも相まって、ガソリン車と比較して燃料代を大きく節約できます。
融雪剤対策!アンダーコートの必要性
純正ホイールの項目でも触れましたが、融雪剤はボディ下回り(アンダーフロア)のサビの大きな原因となります。デリカD:5はもともと防錆性能が高い車ですが、より長く良いコンディションを保つためには、「アンダーコート(防錆塗装)」の施工を強くおすすめします。
特に新車購入時に施工するのが最も効果的です。ディーラーオプションで選択することもできますし、専門の施工業者に依頼する方法もあります。費用は数万円かかりますが、数年後の下回りの状態を見れば、その価値を実感できるはずです。愛車をサビから守るための、雪国ならではの重要な投資と言えるでしょう。
冬用ワイパーへの交換
見落としがちですが、冬用ワイパーへの交換も安全運転のために重要です。冬用ワイパーは、ブレード全体がゴムで覆われているなどの工夫がされており、低温下でも硬くなりにくく、凍結を防ぎます。
通常のワイパーでは、関節部分が凍り付いてしまい、ガラスの曲面への追従性が悪くなって拭きムラが発生し、視界不良の原因となります。数千円で安全性が向上するので、ぜひ交換をおすすめします。
あると便利な追加装備
最後に、私が実際に使ってみて「これは雪国でデリカD:5に乗るなら絶対にあった方が良い」と感じる装備をいくつかご紹介します。

引用 : 三菱自動車HP
- リモコンエンジンスターター: 寒い朝、家の中からエンジンをかけて車内を暖めておくことができる装備です。フロントガラスの霜や氷を溶かしておくこともでき、朝の忙しい時間の時短に繋がります。
- ラバー製フロアマット: 雪や泥で汚れた靴で乗り込んでも、手軽に水洗いできるラバー製のマットは非常に便利です。純正品だけでなく、車種専用設計の社外品も多く販売されています。
- スノーブラシ・解氷スプレー: 車に積もった雪を下ろすためのスノーブラシと、ガラスの氷を溶かす解氷スプレーは冬の必需品です。
まとめ
今回は、雪国で三菱デリカD:5の購入を検討されている方が気になる、冬のコストと実用性について、私の経験を基に詳しくレビューしてきました。
最後に、この記事の重要なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 2019年以降の後期型デリカD:5は、18インチタイヤが標準となり、スタッドレスタイヤが高額になる傾向がある。
- 冬のコストを抑える最も効果的な方法は、16インチへの「インチダウン」。数十万円の費用削減も可能。
- デリカD:5は標準仕様でも寒冷地性能が高く、必ずしも「寒冷地仕様」オプションは必須ではない。
- ディーゼルエンジンの力強さと電子制御4WDシステムは、雪道で絶大な安心感をもたらしてくれる。
- 長く良い状態を保つために、融雪剤対策として「アンダーコート」の施工を強く推奨する。
確かに、冬の準備には一手間とコストがかかります。しかし、それを補って余りあるほどの頼もしさと走る楽しさが、デリカD:5にはあります。適切な準備と知識があれば、デリカD:5は雪国における最強のファミリーカーとなり、冬のドライブを特別な体験に変えてくれるでしょう。
このレビューが、あなたのデリカD:5選びの一助となれば幸いです。