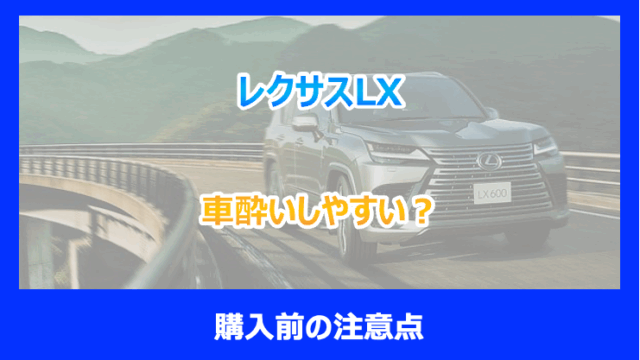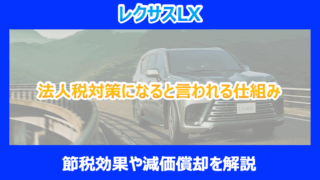モータージャーナリスト兼コラムニストの二階堂仁です。今回も多く寄せられている質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、先行公開されたホンダの新型ヴェゼル e:HEV RSのデザインが、マツダのCX-60にそっくりだと感じ、ネット上の「パクリではないか?」という声に疑問や不安を感じているのではないでしょうか。私も実際に両方の車両を所有し、日々乗り比べているからこそ、そうした声が上がる気持ちはよくわかります。

引用 : HONDA HP
しかし、ご安心ください。この記事を読み終える頃には、ヴェゼルRSとCX-60のデザインパクリ疑惑の真相、そして両社のデザイン戦略に関するあなたの疑問がスッキリ解決しているはずです。
記事のポイント
- ヴェゼルRSとCX-60のデザイン徹底比較
- デザインパクリ疑惑の真相をジャーナリストが考察
- ホンダとマツダのデザイン哲学と今後の戦略
- オーナーだからこそわかる両車の真価と選び方
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

炎上の発端!ホンダ ヴェゼル e:HEV RSのデザイン詳細
まずは、今回の話題の中心となっているホンダ ヴェゼル e:HEV RSが、どのような車なのかを詳しく見ていきましょう。ノーマルグレードとの違いや、RSならではの魅力に迫ります。

引用 : HONDA HP
2025年モデルで待望の復活を遂げた「RS」
「RS」は、ホンダのラインナップにおいてスポーティーな走りを象徴する特別なグレードです。初代ヴェゼルにも2016年から設定され、専用の内外装と引き締められた足回りで人気を博しました。しかし、2021年に登場した現行の2代目ではラインナップから姿を消しており、多くのファンが復活を待ち望んでいました。
そして2025年モデルの一部改良のタイミングで、約4年の時を経てついにヴェゼルにRSが帰ってきたのです。「アーバンスポーツ」をコンセプトに掲げ、デザインと走りの両面で大幅な進化を遂げたことで、発表直後から大きな注目を集めています。
ヴェゼルRSのエクステリアの特徴|ノーマルグレードとの違い
RSの魅力は、何と言っても一目でノーマルグレードとの違いがわかる専用のエクステリアデザインにあります。細部にわたり手が加えられ、より精悍でスポーティーな印象を強調しています。

引用 : HONDA HP
RS専用フロントグリルとバンパー
最も大きな変更点はフロントフェイスです。現行ヴェゼルの特徴であったボディ同色のシームレスなグリルから一変し、RSにはブラックアウトされた大型のメッシュタイプグリルが採用されました。これにより、開口部が大きく見え、非常にアグレッシブで力強い表情を生み出しています。
また、フロントバンパーロアグリルも、ノーマルのZグレードが格子状なのに対し、RSでは水平基調のデザインに変更。ワイド&ローを強調し、安定感のあるスタンスを視覚的に表現しています。
ダーククロームメッキの加飾
RSでは、全体の印象を引き締めるために、各所のメッキパーツがダーククロームメッキに変更されています。フロントバンパーモールディング、ドアロアガーニッシュ、リアバンパーモールディングなど、通常モデルではシルバーに輝く部分が、トーンを落とした深みのある輝きを放ちます。
この「光り物を抑える」という手法は、近年のスポーティーモデルのトレンドでもあり、ヴェゼルRSに上質さと凄みを与えています。派手さではなく、玄人好みの渋いカッコよさを演出しているのです。
15mmローダウンサスペンション
走りのRSを象徴するのが、専用のローダウンサスペンションです。ノーマルグレード比で全高が約15mm低く設定されています。わずか15mmと感じるかもしれませんが、この差が車全体の印象を大きく変えます。重心が下がって見えることで、ドッシリとした安定感が生まれ、スポーツカーのような構えに見えるのです。もちろん、これは見た目だけでなく、実際の走行性能にも大きく貢献します。
専用18インチアルミホイール
足元を飾るのは、RS専用デザインの18インチアルミホイールです。デザイン自体はZグレードと共通ですが、カラーリングが「ベルリナブラック+ダーク切削クリア」という専用色になっています。ダーククロームメッキの加飾と同様に、ホイールもトーンを落とすことで、ボディ全体の一体感を高め、スポーティーなイメージを強調しています。
ヴェゼルRSのインテリアの特徴|スポーティーな室内空間
エクステリアだけでなく、インテリアもRS専用の設えとなり、ドライバーの心を高揚させる空間に仕上がっています。

引用 : HONDA HP
ラックススウェード採用のコンビシート
シートは、プライムスムース(合成皮革)、ファブリック、そして滑りにくい質感が特徴の「ラックススウェード」を組み合わせた専用コンビシートです。特にラックススウェードは、コーナリング時などに体が滑るのを防ぎ、ドライバーと車との一体感を高める効果があります。これは、単なる見た目の違いではなく、走りの質を向上させるための機能的な装備と言えるでしょう。
レッドステッチによるアクセント
ブラックを基調とした内装に、シートやステアリング、シフトノブなどにレッドステッチが施されています。赤はスポーツモデルの定番カラーであり、視覚的に「走るぞ」という気持ちにさせてくれるスイッチのような役割を果たします。派手すぎない絶妙な差し色が、大人のスポーツ空間を演出しています。
走りの進化は?ヴェゼルRS専用チューニングの内容
RSの真骨頂は、やはりその走りです。デザインだけでなく、中身もしっかりと専用チューニングが施されています。
専用サスペンションによる乗り味の変化
先述の15mmローダウンサスペンションは、単に車高を下げただけではありません。スプリングやダンパーの減衰力がRS専用に最適化されています。これにより、コーナリング時のロール(車体の傾き)が抑えられ、より安定した姿勢でコーナーを駆け抜けることができます。
現行ヴェゼルは元々プラットフォームの素性が良く、しなやかな乗り心地が魅力ですが、RSではその上質さを損なうことなく、応答性を高め、キビキビとしたスポーティーなハンドリングを実現していると想像できます。
EPS(電動パワーステアリング)の専用セッティング
見逃せないのが、EPS(電動パワーステアリング)の専用チューニングです。ハンドルを切った瞬間の応答性や、手応えの伝わり方がよりダイレクトになります。ドライバーの操作に対して車がリニアに反応することで、「車を操っている」という感覚が強まり、運転の楽しさが格段に向上します。街中の交差点を曲がるだけでも、その違いを感じられるはずです。
マツダ CX-60のデザイン|魂動デザインの集大成
一方、比較対象として名前が挙がっているマツダ CX-60は、どのような車なのでしょうか。マツダのデザイン哲学とともに、その特徴を解説します。

引用 : マツダ HP
マツダデザインの哲学「魂動(こどう)-SOUL of MOTION」とは
マツダのデザインを語る上で欠かせないのが、「魂動(こどう)-SOUL of MOTION」というデザイン哲学です。これは、単なるスタイリングではなく、「生命感を形にする」という思想に基づいています。まるで生き物が動き出す瞬間のような、力強さや緊張感、そして美しさを車のデザインに落とし込んでいるのです。
2010年から始まったこの哲学は、CX-5の登場以降、全てのマツダ車に貫かれており、CX-60はその集大成かつ、新たな時代の幕開けを告げるモデルとして位置づけられています。
CX-60のエクステリアの特徴|引き算の美学
CX-60のデザインは、日本の美意識に通じる「引き算の美学」が根底にあります。不要な要素をそぎ落とし、光と影の移ろいによって美しさを表現するのが特徴です。
力強いFRプロポーション
CX-60の最大の特徴は、ロングノーズ・ショートデッキという古典的でありながら美しいFR(フロントエンジン・リアドライブ)のプロポーションです。エンジンを縦置きにすることで、ボンネットが長くなり、キャビンが後方に配置されるため、躍動感のある力強いシルエットが生まれます。これは、エンジンを横置きにするFF(フロントエンジン・フロントドライブ)ベースのヴェゼルでは実現できない、CX-60ならではの造形です。
フレームレスグリルとシグネチャーウイング
フロントフェイスは、大型でありながらフレームレスでボディに溶け込むようなグリルが特徴です。グリルの下からヘッドライトへと繋がる「シグネチャーウイング」は、力強い骨格を表現し、マツダ車としてのアイデンティティを明確にしています。
光の移ろいを表現するボディサイド
CX-60のサイドビューには、キャラクターラインと呼ばれるプレスラインがほとんどありません。その代わりに、滑らかな曲面で構成されており、周囲の景色や光がボディに映り込むことで、様々な表情を見せます。静止していても動きを感じさせる、まさに「魂動デザイン」の真骨頂と言える部分です。
CX-60のインテリアの特徴|日本の美意識を体現
CX-60の魅力は、エクステリア以上にインテリアにあると言っても過言ではありません。日本の職人技や美意識が随所に盛り込まれています。
上質な素材(ウッド、ナッパレザー)
ドアトリムやダッシュボードには、メイプルウッドといった本物の木材や、手触りの良いナッパレザーがふんだんに使用されています。また、日本の伝統的な「かけ縫い」という技法を用いたステッチなど、細部にまでこだわり抜いた作り込みは、欧州のプレミアムブランドにも引けを取りません。
ドライバー中心のコックピット
水平基調で広がりを感じさせるダッシュボードは、ドライバーが運転に集中できるよう設計されています。全ての操作系が自然に手を伸ばせる位置に配置されており、人と車の一体感を高めるマツダの思想がここにも表れています。
【徹底比較】ヴェゼルRSとCX-60は本当に似ているのか?デザインパクリ疑惑を検証
さて、いよいよ本題です。両車の特徴を踏まえた上で、デザインが本当に似ているのか、パクリ疑惑は妥当なのかを、ジャーナリストの視点で徹底的に比較・検証していきます。

引用 : HONDA HP
疑惑の核心!フロントフェイスのデザイン比較
多くの人が「似ている」と感じるのが、フロントフェイスでしょう。確かに、両車ともに大型のブラックグリルを採用しており、一見すると印象が近いかもしれません。しかし、細部を見ていくと、その思想は全く異なります。
- グリル形状とパターン: ヴェゼルRSのグリルは、ハニカム(蜂の巣)に近い均一なメッシュパターンで、スポーティーさを前面に押し出しています。一方、CX-60のグリルは縦基調のブロックパターンで、力強さと風格を表現しています。グリルの縁取りも、ヴェゼルRSはボディと一体化していますが、CX-60はシグネチャーウイングによって縁取られ、骨格の強さを感じさせます。
- ヘッドライトの造形: ヴェゼルRSのヘッドライトは薄くシャープで、水平基調のデザインを強調しています。対してCX-60は、グリルと連続性を持たせたL字型のシグネチャーランプが特徴的で、より立体感のある造形です。
- バンパー下部のデザイン: ヴェゼルRSは水平ラインを強調し、ワイド感を演出。CX-60はより立体的な造形で、安定感と重厚感を表現しています。
このように、大型のブラックグリルという共通項はあるものの、ディテールの処理や表現したい方向性は全く異なると言えます。
サイドビューの比較|プロポーションの違い
サイドから見ると、両車の違いはさらに明確になります。これは、車の骨格であるプラットフォームの違いが如実に表れるからです。
- FFベースとFRベースの根本的な違い: ヴェゼルはFFベースのため、ボンネットが比較的短く、キャビン(室内空間)を広く確保する効率的なパッケージングです。一方、CX-60はFRベースのため、前輪からフロントドアまでの距離が長く、伸びやかで力強いプロポーションを持っています。この根本的な骨格の違いが、全体のシルエットを全く別のものにしています。
- キャラクターラインの入れ方: ヴェゼルは、ボディサイドに水平に貫くシャープなキャラクターラインを入れることで、軽快感とスピード感を表現しています。対してCX-60は、前述の通り明確なラインを入れず、面の移ろいで美しさを表現するという、全く逆のアプローチを取っています。
リアビューの比較|それぞれの個性が光る部分
リアビューも、それぞれの個性がはっきりと表れています。
- テールランプのデザイン: ヴェゼルは、左右のテールランプを一直線に繋ぐデザインで、ワイド感と先進性を表現しています。一方、CX-60は、ヘッドライトと呼応するL字型のランプが特徴で、どっしりとした安定感を演出しています。
- バンパーとマフラー周り: ヴェゼルRSはダーククロームの加飾で引き締めているのに対し、CX-60は左右2本出しのマフラーフィニッシャー(グレードによる)が力強さを主張します。
ボディサイズとスペックを比較
デザインの印象だけでなく、実際のサイズも大きく異なります。
| 車種 | 全長 | 全幅 | 全高 | ホイールベース | 駆動方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホンダ ヴェゼル e:HEV RS | 4,330mm | 1,790mm | 1,575mm (推定) | 2,610mm | FF / 4WD |
| マツダ CX-60 | 4,740mm | 1,890mm | 1,685mm | 2,870mm | FR / 4WD |
表を見れば一目瞭然ですが、CX-60はヴェゼルよりも一回り以上大きい、全く異なるクラスのSUVです。全長で41cm、全幅で10cmも大きく、このサイズの違いが、デザインの印象にも大きく影響しています。
ジャーナリストの見解|なぜ「似ている」と感じるのか?
では、なぜこれだけ違いがあるにもかかわらず、「似ている」という声が上がるのでしょうか。私は、いくつかの要因が複合的に絡み合っていると考えています。
- 近年のデザイントレンド: 現在の自動車業界では、フロントグリルを大型化し、存在感を強調するのが世界的なトレンドです。また、ヘッドライトを薄くシャープに見せるデザインも流行しています。両車がこのトレンドを取り入れているため、第一印象として「雰囲気が似ている」と感じてしまうのです。
- SUVというカテゴリの制約: SUVは、広い室内空間や高い走破性を確保する必要があるため、デザインにはある程度の制約が生まれます。その結果、異なるメーカーの車であっても、シルエットや基本的な構成が似通ってくる傾向があります。
- カラーリングによる印象操作: ヴェゼルRSの公式画像で使われているボディカラーと、CX-60のイメージカラーが、共に深みのある色合いであることも、印象を近づける一因かもしれません。
結論として、ヴェゼルRSとCX-60のデザインは、細部を見れば全くの別物です。しかし、現代のデザイントレンドという大きな流れの中で、偶然にも似た要素を持つに至った「収斂進化(しゅうれんしんか)」の結果と見るのが妥当でしょう。「パクリ」という指摘は、表層的な印象論に過ぎず、両社のデザイン哲学を理解すれば、全くの見当違いであることがわかります。
パクリではない!ホンダとマツダのデザイン戦略と今後の展望
今回の騒動は、両社のデザイン戦略が新たなフェーズに入ったことを示唆しています。それぞれの今後の展望を探ってみましょう。
ホンダのデザイン戦略|「Hマーク」エンブレムの変更に込められた意味
今回のヴェゼル改良モデルから、e:HEV(ハイブリッド)モデルのフロントエンブレムが、従来の青みがかったものから、ガソリン車と同じ黒い背景のものに変更されました。
これは、トヨタなども追随している動きで、「ハイブリッドだから特別」という時代が終わり、電動化が当たり前になったことを象徴しています。ホンダは今後、ハイブリッドをことさらに主張するのではなく、走りやデザインそのもので車の魅力を訴求していくという意思表示と読み取れます。ヴェゼルにRSというスポーティーなグレードを復活させたのも、その流れの一環でしょう。これまでの「シンプル&クリーン」路線を維持しつつも、走りや個性を求めるユーザー層に向けて、より力強いデザインを投入していく戦略が見て取れます。
マツダのデザイン戦略|ラージ商品群で目指すさらなる高み
一方のマツダは、CX-60を皮切りに「ラージ商品群」と呼ばれるFRベースのモデル群を展開し、本格的にプレミアムブランドへの道を歩み始めています。魂動デザインをさらに深化させ、内外装の質感を徹底的に高めることで、従来の日本車ユーザーだけでなく、ドイツのプレミアムブランドからの乗り換えも狙っています。
CX-60の成功は、マツダが単なる大衆車メーカーから、独自の価値を持つプレミアムブランドへと脱皮できるかどうかの試金石となります。そのため、デザインには一切の妥協が許されず、圧倒的なオリジナリティと上質感が追求されているのです。
都市型SUV市場の熾烈な競争
では、なぜホンダは、マツダが得意とするような上質でスポーティーな路線に舵を切ったのでしょうか。それは、都市型SUV市場の競争が激化し、ユーザーが求める価値が変化しているからです。
かつてSUVは、悪路走破性や荷物の積載量が重視されていましたが、現在では街乗りがメインのユーザーがほとんどです。彼らがSUVに求めるのは、実用性に加え、所有する満足感を満たすデザインの上質さや、運転が楽しくなるような走行性能です。この領域で先行していたのがマツダであり、トヨタもハリアーなどで成功を収めています。
ホンダは、ヴェゼルRSの投入によって、この「上質・スポーティー」という土俵に本格的に参入し、ライバルに対抗しようとしているのです。
【オーナー視点レビュー】ヴェゼルRSとCX-60、買うならどっち?
デザイン論や戦略論も重要ですが、最終的に気になるのは「で、結局どっちがいいの?」という点でしょう。両車を所有するオーナーとして、それぞれの魅力と、どんな人におすすめなのかを具体的にレビューします。
ヴェゼル e:HEV RSの魅力とおすすめな人
ヴェゼルRSは、一言で言えば「日常をスポーティーに彩る、才色兼備な相棒」です。
- 街乗りでの軽快な走り: コンパクトなボディと専用チューニングされた足回り、そしてモーターアシストによるスムーズな加速は、信号の多い街中で真価を発揮します。キビキビとしたハンドリングは、毎日の通勤路ですら楽しいドライビングコースに変えてくれるでしょう。
- 燃費性能と経済性: e:HEVシステムによる優れた燃費性能は、お財布に優しい大きな魅力です。車両価格もCX-60に比べれば手頃であり、維持費を含めたトータルコストパフォーマンスは非常に高いと言えます。
- コンパクトで扱いやすいサイズ感: 全幅1,790mmというサイズは、日本の狭い道や駐車場でも気兼ねなく運転できます。運転が苦手な方でも安心して扱えるでしょう。
こんな人におすすめ:
- 主に街乗りで車を使う方
- 運転の楽しさと経済性を両立させたい方
- スタイリッシュなデザインが好きだが、大きすぎる車は避けたい方
- キビキビとした軽快な走りが好きな方
マツダ CX-60の魅力とおすすめな人
CX-60は、「人生を豊かにする、本物志向のプレミアムパートナー」です。
- ロングドライブでの圧倒的な安定感とパワー: FRプラットフォームとパワフルなエンジン(特にディーゼルやPHEV)がもたらす高速道路での安定性は、ヴェゼルとは別次元です。どこまでも走り続けたくなるような、疲れ知らずの快適なクルージングが楽しめます。
- FRならではの素直なハンドリング: コーナーを曲がる際の、スッと鼻先が入っていくような素直なハンドリングはFRならでは。車の挙動が自然で分かりやすいため、長距離運転でも疲れにくく、運転が上手くなったような感覚を味わえます。
- 内外装の圧倒的な質感の高さ: ドアを開けた瞬間に感じる、本物の素材が持つ上質な空気感は、日々の満足度を大きく高めてくれます。これは単なる移動手段ではなく、所有する喜びを感じられる工芸品に近い存在です。
こんな人におすすめ:
- 週末や連休に長距離ドライブや旅行に出かけることが多い方
- 走りや内外装の「本物感」にこだわりたい方
- ゆったりとした、質の高い運転フィールを求める方
- 家族や友人を乗せて快適な移動空間を提供したい方
まとめ
今回は、ホンダ ヴェゼル e:HEV RSとマツダ CX-60のデザインパクリ疑惑について、両車の詳細な比較と、それぞれのデザイン戦略から深く考察してきました。
結論として、両車のデザインが似ているという指摘は、現代のデザイントレンドという表層的な部分を捉えたものに過ぎず、「パクリ」という言葉は全く当てはまりません。 むしろ、両車はそれぞれのメーカーが持つ哲学と戦略に基づいて生み出された、全く異なる個性と魅力を持つSUVです。
ヴェゼルRSは、日本の道路環境にジャストフィットするサイズ感と優れた経済性を持ちながら、日常の運転に「楽しさ」というスパイスを加えてくれる、非常にバランスの取れた一台です。
一方のCX-60は、走り、デザイン、質感の全てにおいて、所有者の感性を刺激する「本物」を追求した、マツダの新たな挑戦を象徴するプレミアムSUVです。
今回のヴェゼルRSの登場は、ホンダが今後のSUV市場で、デザイン性と走行性能をさらに重視していくという力強い宣言です。ネット上の一部の声に惑わされることなく、ぜひご自身の目で、それぞれの車の真価を確かめてみてください。きっと、あなたのライフスタイルに寄り添う、最高のパートナーが見つかるはずです。