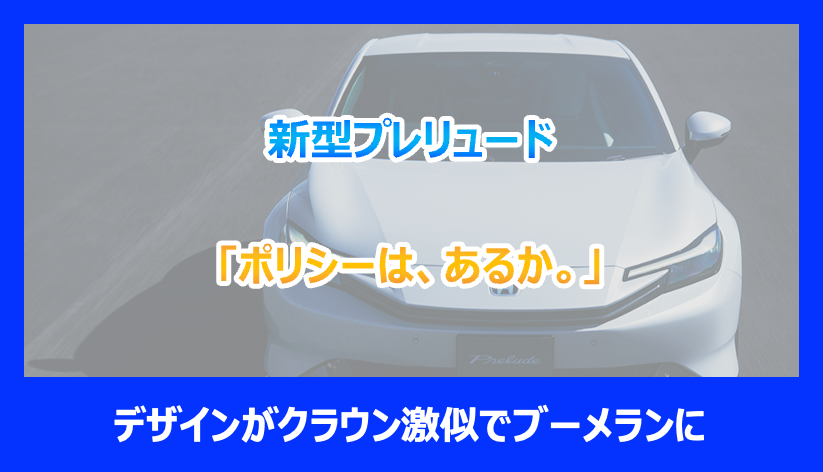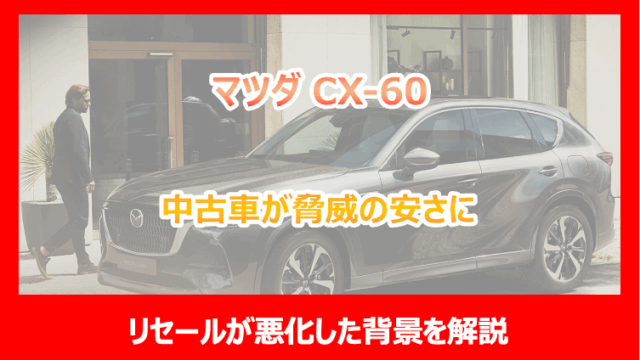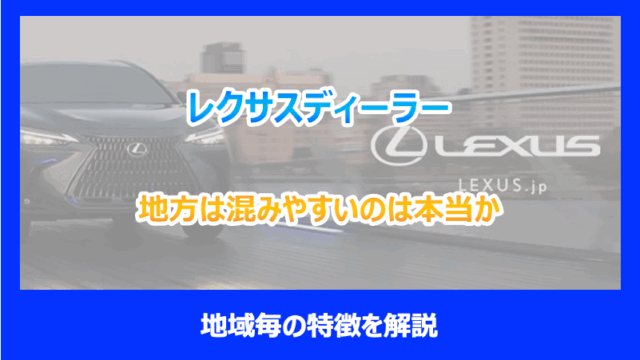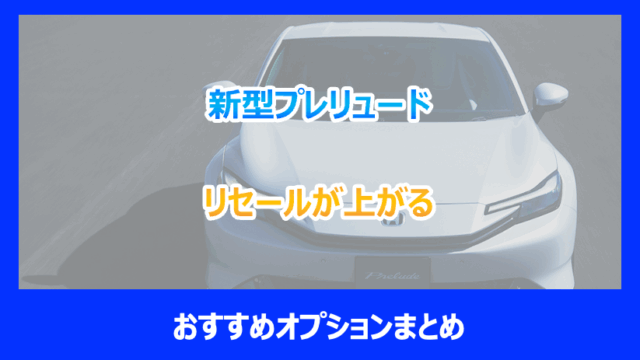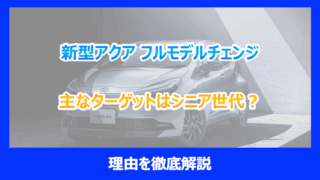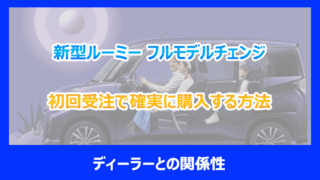モータージャーナリスト兼コラムニストの二階堂仁です。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、ホンダから22年ぶりに復活した新型プレリュードのデザインが、トヨタのクラウンやプリウスに酷似していると感じ、その背景にある過去の因縁が気になっているのではないでしょうか。

引用 : HONDA HP (https://global.honda/jp/news/2025/4250731.html)
私も実際にジャパンモビリティショーで実車を目の当たりにし、そして20年前の「あの広告」を知る者として、皆さんが抱くであろうその複雑な気持ちは痛いほどよくわかります。
この記事を読み終える頃には、なぜ新型プレリュードがこのようなデザインになったのか、そしてホンダの「ポリシー」の行方、さらにはこの車の真の価値についての疑問が解決しているはずです。
記事のポイント
- 新型プレリュードとクラウンのデザイン類似性の徹底検証
- 20年前に勃発したストリームとウィッシュの「ポリシー論争」
- デザインが似てしまう現代の自動車開発が抱える複雑な事情
- 物議を醸すデザインの奥に秘められたプレリュード独自の魅力
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

新型プレリュードのデザインはクラウンの模倣か?徹底比較
2023年10月、多くの自動車ファンの度肝を抜く一台が、ジャパンモビリティショーのホンダブースで静かにアンベールされました。 その名は「プレリュード」。 2001年に5代目の生産が終了して以来、実に22年ぶりにその名が復活したのです。 往年のファンとして、私もこのサプライズには心を躍らせました。 しかし、その斬新なスタイリングに歓喜の声が上がる一方で、多くの人々が既視感を覚えたのもまた事実でした。

引用 : HONDA HP (https://global.honda/jp/news/2025/4250731.html)
往年のファンも驚愕!新型プレリュードのデザインとその衝撃
「プレリュードが帰ってきた!」 そのニュースは、かつてこのクルマと共に青春を過ごした世代にとって、まさに青天の霹靂でした。 プレリュードといえば、いつの時代も最先端のデザインと技術をまとったスペシャリティクーペであり、「デートカー」という文化を日本に定着させた立役者です。 リトラクタブルヘッドライト、世界初の4WS、スタイリッシュなインテリア。 いつの時代も、プレリュードは若者の憧れの的でした。
そんな輝かしい歴史を持つ名前の復活に、誰もが胸を高鳴らせたのです。 しかし、そこに現れた「プレリュード コンセプト」の姿は、良くも悪くも予想を裏切るものでした。 低く流麗なクーペフォルムは確かにプレリュードの血統を感じさせますが、その顔つき、全体のシルエットは、明らかに他のメーカーの特定のモデルを強く想起させたのです。 そう、国内最大のライバルであるトヨタの、それも近年のデザイン言語を象徴するモデルたちです。
新型プレリュードとクラウン、プリウスのデザイン類似点を徹底検証
では、具体的にどの部分が似ていると指摘されているのでしょうか。 細かく見ていくと、偶然では片付けられないほどの共通点が見えてきます。
フロントフェイス:「ハンマーヘッド」はトヨタの専売特許では?
最も多くの人が指摘するのが、フロントマスクのデザインです。 コの字型に発光するポジションランプと、その内側に配置された薄型のヘッドライトユニット。 これはトヨタが「ハンマーヘッド」と呼び、新型プリウスやクラウンシリーズで積極的に採用しているデザインシグネチャーです。 新型プレリュードも、このハンマーヘッドによく似たデザインを採用しています。 もちろん、細部の処理や全体のバランスは異なりますが、第一印象として「クラウン顔」「プリウス顔」と感じてしまうのも無理はありません。
サイドシルエット:空力が導き出した必然の形か
サイドから見たときの、Aピラーからルーフ、そしてテールエンドへと滑らかに続くモノフォルムシルエット。 これもまた、燃費(電費)性能を極限まで追求した新型プリウスと非常に近いラインを描いています。 空力性能を突き詰めると、必然的にこのような形に収斂していくという意見もありますが、それにしてもキャラクターラインの入れ方やウィンドウグラフィックの処理まで、どこか通じるものがあると感じられます。
リアビュー:一文字テールランプの流行
リアコンビネーションランプは、近年世界的なトレンドとなっている左右一文字につなげたデザインを採用しています。 これもクラウンシリーズやプリウスが採用しており、類似性を感じる一因となっています。 テールランプのデザイン自体は各社が工夫を凝らすポイントですが、全体のフォルムが似ている中でテールまで同じトレンドを追うと、どうしても「模倣」という印象が強まってしまいます。
これらの類似点から、SNSや自動車関連の掲示板では、瞬く間に「プレリュード、クラウンのパクリか?」といった声が溢れかえりました。 そして、事情をよく知る古参のファンからは、ある懐かしくも痛烈なフレーズが掘り起こされたのです。
SNSで飛び交う「ポリシーは、あるか。」の声
「ポリシーは、あるか。」

この言葉が、新型プレリュードの話題と共にX(旧Twitter)などで一気に拡散されました。 若い世代の方にはピンとこないかもしれませんが、これは約20年前、ホンダがトヨタを相手に繰り広げた、自動車業界史に残る広告戦争のキャッチコピーなのです。 「かつてトヨタを批判したホンダが、今度は自分たちがトヨタのデザインを真似している。これは壮大なブーメランではないか」 そんな皮肉のこもった意見が、新型プレリュードのデザインに対する評価に付きまとっています。
もちろん、「デザインが似ていても、純粋にかっこいい」「クーペを出してくれただけで嬉しい」といった肯定的な意見も多数存在します。 私自身も、このプレリュードのデザイン単体を見れば、非常にスタイリッシュで魅力的だと感じています。 しかし、過去の経緯を知る者として、この「ポリシー」という言葉の重みと、現在の状況の皮肉さを考えずにはいられないのです。 では、その発端となった20年前の因縁とは、一体何だったのでしょうか。
蘇る20年前の因縁「ポリシーは、あるか。」とは何だったのか
話は2000年代初頭に遡ります。 当時の日本市場は、まさにミニバン戦国時代。 各社がこぞって3列シートのミニバンを投入し、ファミリーカーの主役の座を争っていました。 そんな中、ホンダから市場の勢力図を塗り替える画期的なモデルが登場します。

引用 : HONDA HP (https://global.honda/jp/news/2025/4250731.html)
発端はミニバン市場の覇権争い!ホンダ ストリームの登場
2000年10月に発売された初代ホンダ・ストリーム。 このクルマは、それまでのミニバンが持つ「商用車ベースで背が高く、走りは二の次」というイメージを覆しました。 乗用車であるシビックのプラットフォームをベースに開発された低床設計により、ミニバンでありながら立体駐車場にも入れる1,590mmという低い全高を実現。 さらに、ホンダ得意のVTECエンジンとスポーティな足回りによって、ミニバンとは思えない軽快なハンドリング性能を誇りました。 「7人乗れるスポーティワゴン」という新しいコンセプトは市場に熱狂的に受け入れられ、ストリームは発売からわずか10ヶ月で累計販売台数10万台を突破する大ヒットを記録したのです。
トヨタの追撃!ウィッシュの登場と酷似したコンセプト
このストリームの成功を、王者トヨタが黙って見ているはずがありませんでした。 ストリームの発売から約2年後の2003年1月、トヨタはストリームに真っ向から勝負を挑むモデルを市場に投入します。 それが、トヨタ・ウィッシュです。
このウィッシュ、コンセプトからボディサイズ、価格設定に至るまで、ストリームを徹底的に研究し尽くしているのが誰の目にも明らかでした。 両車のスペックを比較してみると、その類似性は驚くほどです。
| 車種 | 全長 | 全幅 | 全高 | ホイールベース |
|---|---|---|---|---|
| ホンダ ストリーム | 4,550mm | 1,695mm | 1,590mm | 2,720mm |
| トヨタ ウィッシュ | 4,550mm | 1,695mm | 1,590mm | 2,750mm |
全長、全幅、全高に至っては、まさにミリ単位で同じ。 ホイールベースこそ若干異なりますが、5ナンバーサイズいっぱいのボディに3列シートを詰め込み、スポーティな走りを標榜するというコンセプトは完全に一致していました。 トヨタの強大な販売力を背景に、ウィッシュは登場するやいなや大ヒットを記録し、ストリームの牙城を脅かし始めます。
ホンダの痛烈な批判広告「ポリシーは、あるか。」
このトヨタの露骨なまでの後追い戦略に、ホンダは黙っていませんでした。 ウィッシュの発売から約8ヶ月後の2003年9月、マイナーチェンジしたストリームのプロモーションで、ホンダは前代未聞の広告キャンペーンを展開します。 全国紙の新聞に掲載された全面広告。 そこには、ストリームと、ストリームに酷似したシルエットを持つクルマ(明らかにウィッシュを意識したもの)が並べられ、中央には大きくこう書かれていました。
「ポリシーは、あるか。」
さらに、広告の下部には**「Do you have a HONDA?」**という追い打ちをかけるようなコピー。 これは、名指しこそしないものの、トヨタの模倣戦略に対するホンダの痛烈な批判であり、自分たちの独創性(ポリシー)を誇示する強いメッセージでした。 この広告は自動車業界内外で大きな波紋を呼び、「ホンダらしい挑戦的な広告だ」と称賛する声もあれば、「やりすぎではないか」という批判もあり、大いに物議を醸したのです。
20年の時を経てホンダに突き刺さるブーメラン
そして2023年。 奇しくも約20年の時を経て、今度はホンダが発表した新型プレリュードが、トヨタのデザインに酷似していると指摘される事態になりました。 かつてライバルに投げかけた「ポリシーは、あるか。」という言葉が、まるでブーメランのように自分たちに突き刺さっているのです。 この皮肉な状況に、往年のファンは複雑な思いを抱えています。
では、なぜホンダはこのような批判を受けることを予見しながら、あるいは意に介さず、このデザインを採用したのでしょうか。 その背景には、20年前とは全く異なる、現代の自動車開発が抱える根深い事情が存在するのです。
なぜ?ホンダがトヨタのデザインに寄せた背景を徹底考察
「ホンダも落ちたものだ」「オリジナリティを失ったのか」 そう結論付けてしまうのは簡単です。 しかし、一人のジャーナリストとして、そして一人のクルマ好きとして、私はその背景を多角的に考察する必要があると考えています。 メーカーのデザイナーたちが、安易に他社の模倣をすることはありません。 そこには、デザインの類似を誘発する、いくつかの抗いがたい要因が存在するのです。

引用 : HONDA HP (https://global.honda/jp/news/2025/4250731.html)
自動車デザインのトレンド「空力性能と法規制」
現代の自動車開発において、デザイナーが自由に腕を振るえる領域は、実は年々狭まっています。 その最大の要因が「空力性能」と「法規制」です。
空力性能の追求が生む「似た形」
特にプレリュードのようなハイブリッドカーや電気自動車(BEV)にとって、空気抵抗の低減は航続距離を伸ばすための至上命題です。 空気抵抗係数(Cd値)をコンマ1でも下げるために、スーパーコンピュータによるシミュレーションや風洞実験が繰り返されます。 その結果、最も効率的に空気を後方へ流す形状は、物理法則に従ってある程度決まってきてしまいます。 プリウスが採用したモノフォルムシルエットは、まさにその最適解の一つであり、プレリュードもまた同じ結論に至ったとしても不思議ではありません。 かつては個性豊かだったF1マシンが、レギュレーションに縛られてどれも似たような形状になるのと同じ現象が、市販車でも起きているのです。
安全・環境規制の強化
デザインを縛るもう一つの大きな要因が、世界中で年々厳しくなる法規制です。 例えば、衝突時の乗員保護だけでなく、歩行者保護の観点から、ボンネットの高さやフロントバンパーの形状には厳しい制約が課せられます。 ヘッドライトの位置や面積、さらには騒音規制や排ガス規制(これは直接デザインに関係しませんが、エンジンルームの設計に影響を与え、結果的にフロントセクションのデザインを左右します)など、クリアすべきハードルは無数に存在します。 これらの規制をすべて満たした上で、美しいデザインを成立させるのは至難の業であり、結果として各社が似たようなソリューションに行き着くケースが増えているのです。
「売れるデザイン」の呪縛と開発コストの現実
企業である以上、利益を追求するのは当然です。 自動車開発には、一台あたり数百億円から数千億円という莫大なコストがかかります。 特にプレリュードのような、販売台数が多くは見込めないスペシャリティクーペの場合、デザインで大きな冒険をして市場に受け入れられなかった場合のリスクは計り知れません。
近年のトヨタのデザイン、特にハンマーヘッドを採用したモデルは、市場で大きな成功を収めています。 これは、今の時代において「売れるデザイン」「多くの人に受け入れられるデザイン」の一つの答えであると言えます。 ホンダの経営陣や開発チームが、この成功事例を意識しなかったとは考えにくいでしょう。 独創性を追求して失敗するリスクを負うよりも、市場のトレンドを取り入れて商業的な成功確率を高めるという判断は、企業戦略としては合理的と言えるのかもしれません。
グローバル市場での戦いとデザインの標準化
ホンダもトヨタも、日本国内だけでなく世界中でビジネスを展開するグローバル企業です。 北米、欧州、中国、東南アジアなど、文化も好みも全く異なる多様な市場で、同じモデルを販売しなければなりません。 そうなると、特定の地域でしか受け入れられないような尖ったデザインよりも、どの市場でも「悪くない」と思ってもらえる、最大公約数的なデザインが求められる傾向が強まります。 結果として、メーカーごとの「味」や「国籍」が薄まり、デザインの均質化、標準化が進んでしまうという側面も否定できません。
これらの要因が複雑に絡み合った結果、新型プレリュードは「クラウンに似ている」と言われるデザインに行き着いたのではないでしょうか。 それは決して、デザイナーの怠慢や安易な模倣ではなく、現代の自動車開発が抱える構造的な問題の表れなのかもしれません。
新型プレリュードの真価はデザインだけじゃない!その魅力を深掘り
ここまでデザインの類似性について深掘りしてきましたが、クルマの魅力は見た目だけではありません。 むしろ、この新型プレリュードは、その中身にこそホンダの「ポリシー」が色濃く反映されていると私は考えています。 デザインの第一印象だけでこのクルマを判断してしまうのは、あまりにもったいない。 ここからは、その走りや装備、そしてコンセプトに秘められた真の魅力に迫っていきましょう。

引用 : HONDA HP (https://global.honda/jp/news/2025/4250731.html)
プレリュードのスペックと価格設定
まず、このクルマの基本情報を整理します。
- グレード: ワングレードのみ
- 駆動方式: FF
- 車両本体価格: 6,179,800円
- パワートレイン: 2.0L e:HEV(2モーターハイブリッドシステム)
- ベース車両: シビック TYPE R
価格だけ見ると「高い!」と感じるかもしれませんが、その中身を知れば納得できる部分も多くあります。 ベースとなっているのは、世界中のサーキットでFF最速を更新し続ける、あのシビック TYPE Rです。 ピュアスポーツの極致ともいえるTYPE Rのプラットフォームや高剛性ボディをベースに、プレリュード専用のセッティングが施されています。 路面状況に応じて減衰力を四輪独立で制御する「アダプティブ・ダンパー・システム」や、強力な制動力を誇る「ブレンボ製フロントブレーキ」、そして専用開発の19インチホイールなど、走りのハードウェアは一級品が奢られています。 TYPE Rが6速MTの純ガソリンターボエンジンであるのに対し、プレリュードは2モーター式のハイブリッドシステム「e:HEV」を搭載しているのが最大の違いであり、このクルマのキャラクターを決定づけています。
ホンダの新技術「S+シフト」とは?仮想8段変速の正体
プレリュードの心臓部で最も注目すべきは、ホンダ初採用となる新技術「S+シフト」です。 通常、ホンダのe:HEVはモーター駆動が主体で、エンジンは主に発電に徹し、高速巡航時などに直接タイヤを駆動する仕組みです。 そのため、変速機という概念がなく、シームレスで滑らかな加速が特徴です。
しかし、プレリュードでは、このモーター駆動に「仮想的な8段変速」のフィーリングを加えました。 これは、加速時や減速時にエンジン回転数を緻密にコントロールし、あたかも有段ギアのトランスミッションでシフトアップ・ダウンしているかのようなダイレクトな応答性とシフトフィールを実現する技術です。 さらに、スピーカーからエンジンサウンドと同期した迫力ある音を流す「アクティブサウンドコントロール」も搭載。 ハイブリッドカーでありながら、ドライバーの五感を刺激し、クルマとの一体感を高める演出がなされています。 静かで滑らかな電動駆動のメリットと、エンジンを操るスポーツカーのような高揚感を両立させようという、ホンダらしい野心的な試みと言えるでしょう。
実際の購入を考えた時の注意点【見積もり公開】
さて、どんなに魅力的なクルマでも、実際に購入するとなると現実的な問題が出てきます。 私も早速ディーラーで詳細な話を聞き、見積もりを作成してもらいました。 その内容と、購入前に知っておくべき注意点を共有します。
見積もり価格は乗り出し約683万円!
私が作成した見積もりの総額は6,833,000円となりました。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 車両本体価格 | 6,179,800円 |
| メーカーオプション(ボディカラー) | 82,500円 |
| ディーラーオプション合計 | 430,650円 |
| 税金・諸費用など | 140,050円 |
| 合計 | 6,833,000円 |
ディーラーオプションにはフロアマットやドライブレコーダーのほか、約19万円のボディコーティングが含まれているため、これを外せばもう少し安くはなります。 ハイブリッドカーなので、環境性能割と重量税が免税になるのは嬉しいポイントです。 それでも、乗り出しで700万円に迫る価格は、まさに高級スペシャリティカーと言えるでしょう。
購入前の注意点7つ
見積もりを取る過程や、カタログを読み込む中で見えてきた、購入前に必ず押さえておくべき7つの注意点があります。
- そもそも入手が極めて困難 初期生産台数は2,000台、月間販売目標はわずか300台と、非常に生産台数が絞られています。 すでに購入希望者が殺到しており、多くの販売店で抽選や、長年の付き合いがある顧客を優先するなどの厳しい購入条件が設けられています。 「欲しい」と思っても、すぐに買えるクルマではないことを覚悟する必要があります。
- ボディカラーと内装色の組み合わせに制約あり 内装色は「ブルー&ホワイト」と「ブルー&ブラック」の2種類ですが、精悍な印象のブラック内装は、ボディカラーで「ムーンリットホワイト・パール」を選択した時しか選べません。 内外装の組み合わせにこだわりたい方は注意が必要です。
- パワーシートやシートベンチレーションは非搭載 この価格帯のクルマとしては意外かもしれませんが、パワーシートやシートベンチレーションといった快適装備の設定がありません。 走りに特化したキャラクターとはいえ、日常の快適性を重視する方にはマイナスポイントかもしれません。
- サンルーフの設定はなし かつてのプレリュードはサンルーフが大きな魅力の一つでした。 開放的なドライブを楽しみたい方にとって、オプションでもサンルーフが選べないのは残念な点です。
- 360°カメラ(マルチビューカメラシステム)の設定なし ベースがシビックであるためか、360°カメラの設定がありません。 今や軽自動車のN-BOXにも搭載されている装備だけに、車庫入れなどに不安がある方には物足りなく感じるでしょう。
- 後部座席はあくまで緊急用 2ドアクーペの宿命ですが、後部座席は大人が長時間快適に過ごせる空間ではありません。 基本的には2人乗りのパーソナルクーペとして考え、後席は手荷物置き場と割り切るのが賢明です。
- Googleナビの特性 ナビゲーションシステムにはGoogleのOSが搭載されています。 常に最新の地図情報が使えるメリットは大きいですが、従来の日本のナビにあったような、高速道路でのインターチェンジやサービスエリアの詳細なパネル表示が出ない可能性があります。
プレリュードが目指す「スペシャリティクーペ」の新たな形
これらの注意点を踏まえると、新型プレリュードは万人受けするクルマではないことがわかります。 快適装備を充実させた豪華なクーペでもなければ、サーキットでのラップタイムを競うようなピュアスポーツカーでもありません。
このクルマが目指しているのは、電動化が進む時代における、新しい「スペシャリティクーペ」の姿ではないでしょうか。 それは、e:HEVならではの静かで力強いモータードライブによる上質な移動体験と、「S+シフト」がもたらすクルマを操る高揚感。 そして、コンセプトである「アンリミテッド・グライダー」が示すように、まるでグライダーのように滑空する、心地よくてどこまでも走り続けたくなるような走行感覚。 そうした、スペックやタイムでは測れない「感性的な価値」を追求したクルマなのです。 デザインの類似性という物議を乗り越えた先に、ホンダが提案する未来の「走る喜び」が、このプレリュードには詰まっているのかもしれません。
まとめ
今回は、22年ぶりに復活した新型プレリュードについて、デザインの類似性から過去の因縁、そしてその真の魅力までを深く掘り下げてきました。
新型プレリュードのデザインがトヨタのクラウンやプリウスに似ているのは事実であり、かつての「ポリシー論争」を知る者にとっては、何とも皮肉な状況に映ります。 しかし、その背景には、空力性能や法規制、開発コストといった、現代の自動車開発が避けては通れない複雑な事情が存在することも理解する必要があります。
重要なのは、デザインという第一印象だけでこのクルマの本質を見誤らないことです。 シビック TYPE R譲りの卓越したシャシー性能と、ホンダが初採用した新世代のハイブリッド技術「S+シフト」がもたらす走りは、これまでのどんなクルマとも違う、唯一無二の体験をもたらしてくれる可能性を秘めています。
かつてホンダは「ポリシーは、あるか。」と問いました。 その答えは、もはやエクステリアデザインの独創性だけにあるのではないのかもしれません。 電動化という大きな変革期の中で、いかにして「走る喜び」や「クルマを操る楽しさ」というホンダのDNAを守り、進化させていくか。 その挑戦こそが、現代におけるホンダの「ポリシー」なのではないでしょうか。
私も購入権を得られるかは分かりませんが、ひとまずエントリーは済ませました。 一人のジャーナリストとして、そしてホンダファンとして、この意欲作のステアリングを握り、その真価を確かめられる日が来ることを心から楽しみにしています。