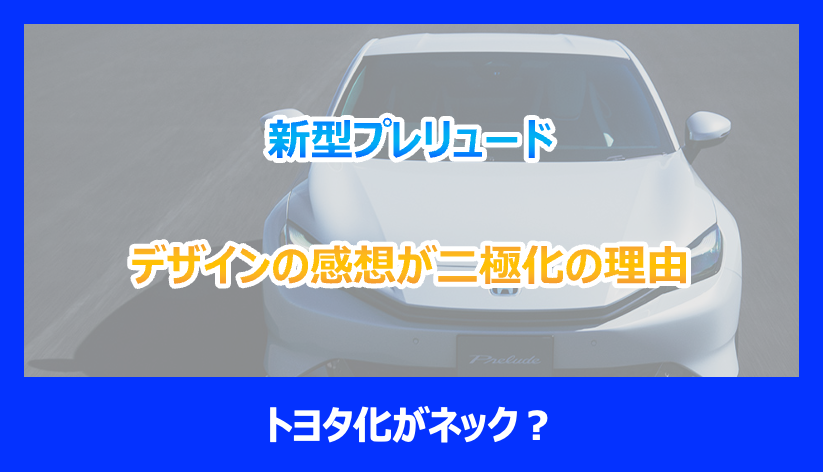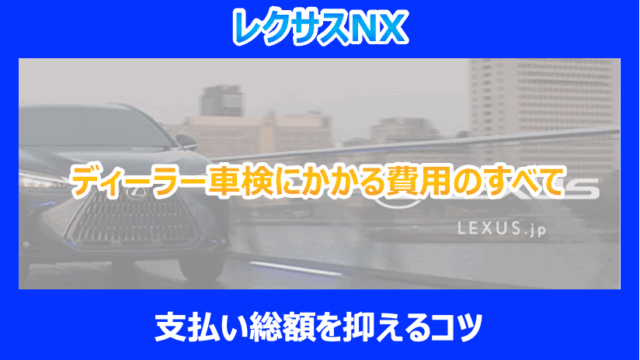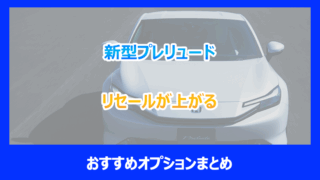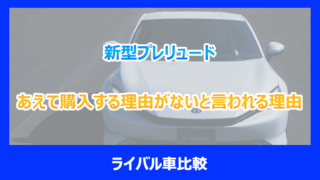モータージャーナリスト兼コラムニストの二階堂仁です。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、ホンダから待望の復活を遂げた新型プレリュードのデザインが、どうも既視感があり「これじゃない感」がある、と感じているのではないでしょうか。 私も実際にコンセプトモデルを見たとき、往年のファンとして嬉しい気持ちと同時に、フロントマスクに少しばかりの違和感を覚えたので、その気持ちはよくわかります。

引用 : HONDA HP (https://global.honda/jp/news/2025/4250731.html)
SNSでは「かっこいい!」という絶賛の声もあれば、「トヨタのパクリだ」「プレリュードらしくない」といった厳しい意見も多く、まさに賛否両論。 なぜ、これほどまでに評価が二極化してしまったのでしょうか。
この記事を読み終える頃には、新型プレリュードのデザインに対する様々な意見の理由、そしてその評価が真っ二つに割れてしまった背景にあるものへの疑問が解決しているはずです。
記事のポイント
- 新型プレリュードのデザインが二番煎じと言われる具体的な理由
- デザインが肯定的に評価されている視点と新しい価値観
- 歴代モデルから見る「プレリュードらしさ」の変遷
- 評価が二極化した時代的背景とジャーナリストによる深い考察
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

新型プレリュードのデザインが「パクリ」「二番煎じ」と言われる理由
待望の復活を遂げた新型プレリュード。 その姿が公開されるや否や、多くの車好きの間で大きな話題となりました。 しかし、その話題の中心は、称賛の声だけではありませんでした。 特に往年のファンやデザインに一家言ある人々から、「何かに似ている」「オリジナリティがない」といった、いわゆる「パクリ」「二番煎じ」ではないかという厳しい指摘が相次いだのです。

引用 : HONDA HP (https://global.honda/jp/news/2025/4250731.html)
私自身、様々なメーカーの車を所有し、日々デザインのトレンドを追いかけている立場として、これらの意見が出てくる背景にはいくつかの明確な理由があると考えています。 ここでは、なぜ新型プレリュードのデザインがそのように見られてしまうのか、具体的な要因を一つずつ掘り下げて解説していきます。
トヨタの「ハンマーヘッド」デザインとの著しい類似性
新型プレリュードのデザイン、特にフロントマスクを見て多くの人が真っ先に思い浮かべたのが、近年のトヨタ車が積極的に採用している「ハンマーヘッド」デザインでしょう。
ハンマーヘッドとは、その名の通りシュモクザメ(Hammerhead shark)をモチーフにしたデザインで、コの字型に発光するシャープなヘッドライトが特徴です。 このデザインは、トヨタのクラウンシリーズやプリウス、bZ4Xなどに採用され、新世代トヨタの象徴的なデザイン言語として広く認知されています。

引用 : トヨタHP (https://www.subaru.jp/forester)
新型プレリュードのフロントデザインを見てみましょう。 薄く横一文字に伸びるポジションランプと、その両端に配置されたヘッドライトユニット。 この構成が、ハンマーヘッドデザインの基本的な骨格と非常によく似ています。 特に、ライトを消灯している状態では、フロントマスク全体の印象がトヨタのそれと酷似していると感じる人が多いのも無理はありません。
自動車のデザインにおいて、フロントマスクはその車の「顔」であり、ブランドのアイデンティティを最も強く表現する部分です。 ホンダほどの企業が、他社の、しかも最大のライバルであるトヨタのデザイン言語とここまで似通った表現を選んだことに対し、多くのファンが戸惑い、そして「パクリではないか」という疑念を抱くのは、ある意味で自然な反応と言えるでしょう。
具体的な比較対象としてのプリウスやクラウンスポーツ
「何かに似ている」という漠然とした感覚は、具体的な比較対象を挙げることでより鮮明になります。 SNS上で新型プレリュードと並べて比較されているのが、主に5代目プリウスとクラウンスポーツです。
5代目プリウスとの比較
5代目プリウスは、その革新的なデザインで世界中に衝撃を与えました。 低いボンネットから滑らかに続くモノフォルムシルエットと、フロントのハンマーヘッドデザインは、これまでのプリウスのイメージを完全に覆すスポーティさを実現しています。 新型プレリュードもまた、流麗なクーペスタイルを持つことから、全体のシルエットとフロントマスクの印象が重なって見えてしまうのです。 特に、ボディサイドのキャラクターラインを極力排したクリーンな面構成は、両者に共通するデザイントレンドであり、類似性をより強調する要因となっています。
クラウンスポーツとの比較
クラウンスポーツは、SUVでありながらスポーティなクーペのようなシルエットを持つモデルです。 こちらもハンマーヘッドデザインを採用しており、プレリュードが目指す「スペシャリティスポーツ」というキャラクターと近いことから、比較対象として名前が挙がりやすくなっています。 プレリュードの持つ塊感のあるボディと、クラウンスポーツの筋肉質なフェンダー周りの造形は、方向性こそ違えど、現代的なスポーツモデルとしての表現方法に共通点が見られます。
これらの具体的な車種と比較されることで、「プレリュードはトヨタのデザインを後追いしている」「二番煎じだ」という印象が、より強固なものになってしまっているのが現状です。
これまでのホンダデザインとの決別という衝撃
往年のホンダファン、特にプレリュードに特別な思い入れを持つ人々にとって、今回のデザインは「これまでのホンダらしさ」からの決別と映りました。 歴代プレリュードは、いつの時代もホンダならではの先進的でチャレンジングなデザインを採用してきました。
例えば、2代目・3代目のリトラクタブルヘッドライトや低いボンネットフードは、当時のホンダの技術力とデザインへのこだわりを象徴するものでした。 4代目の未来的なワイド&ローなフォルム、5代目の縦型ヘッドライトなど、常に他社の模倣ではない、独自の道を切り拓いてきた歴史があります。
しかし、今回の新型プレリュードのデザインは、良くも悪くも「現代のデザイントレンド」に非常に忠実です。 薄型ヘッドライト、シームレスなグリル、クリーンな面構成。 これらは電動化が進む現代において、空力性能や先進性を表現するための合理的な手法であり、多くのメーカーが採用しているものです。
しかし、その合理性ゆえに、かつてのホンダ車が持っていたような「アクの強さ」や「唯一無二の個性」が薄れてしまったと感じるファンが多いのです。 「ホンダなら、もっと違うやり方があったのではないか」「なぜ、今あえてこのデザインなのか」という、期待が大きかったからこその失望感が、「パクリ」という強い言葉になって表出している側面もあるでしょう。 これは単なるデザインの好き嫌いではなく、ブランドへの信頼と歴史に対する思いが絡んだ、非常に根深い問題なのです。
往年のプレリュードファンが抱く「違和感」の正体
では、往年のファンが抱く「違和感」の正体とは、具体的に何なのでしょうか。 それは、プレリュードという車名に込められた「前奏曲」という意味、つまり「時代の先駆け」であってほしいという強い期待感の裏返しに他なりません。
歴代プレリュードは、FFスペシャルティクーペというジャンルを切り拓き、4輪アンチロックブレーキ(当時としては画期的)や世界初の4WS(4輪操舵システム)など、常に新しい技術とスタイルを提案してきました。 特にデザインにおいては、前述の通り、他とは一線を画す先進性で若者たちの心を掴み、「デートカー」という文化の象徴にまでなりました。
ファンが「プレリュード」という名前に期待するのは、単なる懐かしさの再現ではありません。 「現代において、ホンダが『時代の先駆け』として提示する、誰も見たことのない新しいスペシャリティクーペの姿」なのです。
その期待に対して、提示されたデザインが現代のトレンドの最大公約数的なものであり、ライバル社のデザインを想起させるものだった。 このギャップこそが、違和感の最大の原因です。 彼らにとって、プレリュードはフォロワーであってはならず、常にリーダーであってほしい存在なのです。 この熱い思いがある限り、デザインへの厳しい視線が向けられるのは、ある意味でプレリュードの宿命と言えるのかもしれません。 私自身、ガレージに眠る歴代モデルのキーを握りしめながら、新型のデザインに複雑な思いを馳せています。
新型プレリュードのデザインが肯定的に評価される理由
一方で、新型プレリュードのデザインを「かっこいい」「未来的だ」と肯定的に評価する声が多数存在することも事実です。 特に、過去のモデルに強い思い入れがない若い世代や、純粋に新しいデザインとして捉えている人々からは、好意的な意見が多く見られます。 「パクリ」や「二番煎じ」といった批判は、ある特定の視点から見た一面的な評価に過ぎません。

引用 : HONDA HP (https://global.honda/jp/news/2025/4250731.html)
ここでは、新型プレリュードのデザインがなぜ魅力的に映るのか、その理由を多角的に分析し、肯定的な評価の背景にある価値観を探っていきます。 ジャーナリストとして、そして一人のクルマ好きとして冷静にこのデザインを分析すると、そこにはホンダが次世代に向けて発信する明確なメッセージが見えてきます。
未来を感じさせるクリーンで先進的なスタイリング
新型プレリュードのデザインを肯定的に見る人々がまず挙げるのが、そのクリーンで先進的なスタイリングです。 現代の自動車デザイン、特に電動化を視野に入れたモデルでは、複雑なキャラクターラインや過度な装飾を排し、滑らかでクリーンな面で構成する「シームレス」なデザインが主流となっています。
新型プレリュードは、まさにこのトレンドを体現しています。 ボンネットからルーフ、そしてリアエンドへと流れるラインは非常にスムーズで、ボディサイドにも無駄な線は見当たりません。 ドアノブも格納式のフラットタイプが採用される可能性が高く、ボディ全体の「塊感」と「流麗さ」を際立たせています。
このクリーンな造形は、単に美しいだけでなく、「未来感」や「インテリジェンス」を視覚的に表現する効果があります。 ごちゃごちゃとした装飾がない分、見る人の視線はクルマ全体のフォルムの美しさに集中します。 これは、まるでSF映画に登場する未来の乗り物のような、洗練された印象を与えます。 過去のプレリュードが持っていた、ある種の「やんちゃさ」や「ギラギラ感」とは対極にある、知的でクールな佇まい。 これこそが、新しい時代のスペシャリティクーペにふさわしいと評価されているのです。
空力性能を強く意識した機能美の追求
このクリーンなスタイリングは、見た目の美しさだけでなく、優れた空力性能を追求した結果でもあります。 新型プレリュードはハイブリッドカーであり、今後登場するであろうBEV(バッテリー式電気自動車)も視野に入れたプラットフォームから生まれています。 これらの電動車両にとって、空気抵抗の低減は航続距離(燃費)を伸ばすための最重要課題の一つです。
グリルレスデザインの意味
フロントマスクを見ると、エンジンを冷却するための開口部(グリル)が非常に小さいことがわかります。 これは、前面から受ける空気の抵抗を極力減らすためのデザインです。 エンジン搭載車であっても、必要な冷却性能を確保しつつ、いかにグリルを小さく、そしてスマートに見せるかがデザイナーの腕の見せ所となります。 プレリュードのフロントは、この課題に対して非常に巧みな答えを出しています。
全体のフォルムと空力
ボディ全体の滑らかな形状も、空気をスムーズに後方へ流すためのものです。 ルーフからリアへのなだらかな傾斜は「ティアドロップ形状」に近く、これは空気抵抗が最も少ない形状の一つとされています。 デザインと機能が高度に両立された「機能美」。 ここに、ホンダらしい技術的な裏付けとこだわりを感じ取り、高く評価する声が多いのです。 単なる見た目の模倣ではなく、物理法則に基づいた合理的なデザインであるという点が、説得力を持っていると言えるでしょう。
新世代のホンダデザイン言語としての提示
「トヨタのハンマーヘッドに似ている」という批判がある一方で、このデザインを「新しいホンダのデザイン言語の始まり」と捉える見方もあります。 近年、ホンダのデザインはモデルごとに方向性が異なり、ブランド全体で統一された「顔」が存在しないという指摘がありました。 シビック、ヴェゼル、ステップワゴン、N-BOX、それぞれが個性的である反面、一目でホンダ車とわかるような強い共通項は希薄でした。
しかし、北米で発表された新型アコードや、新しいEVシリーズである「Honda 0シリーズ」のコンセプトカーを見ると、薄くシャープなヘッドライトとクリーンな面構成という、新型プレリュードと共通するデザイン要素が見て取れます。
これは、ホンダが電動化時代に向けて、ブランドの新しいアイデンティティを確立しようとしている過渡期にあることを示唆しています。 プレリュードは、その先陣を切る重要なモデルとして、新しい時代のホンダの「顔」を提示しているのかもしれません。 そう考えれば、このデザインは他社の模倣ではなく、ホンダが自らの未来を描くために生み出した、必然的な形であると解釈できます。 今はまだ見慣れないかもしれませんが、数年後にはこの顔が「新しいホンダの象徴」として定着している可能性も十分にあります。
若い世代に響くシンプルモダンなデザイン
最後に、世代間の価値観の違いも、評価が分かれる大きな要因です。 往年のファンがプレリュードに求めるのは、80年代、90年代の華やかさや、ある種の「伊達男」的な色気かもしれません。 しかし、現代の若い世代が車に求める価値観は大きく変化しています。
彼らが日常的に触れるスマートフォンやデジタルガジェットのように、シンプルでミニマル、そして機能的なデザインを好む傾向があります。 過度な装飾や自己主張の強いデザインは、時に「古臭い」「野暮ったい」と受け取られかねません。
新型プレリュードのシンプルモダンなデザインは、まさにこの現代的な感性にマッチしています。 無駄を削ぎ落としたフォルムは、どんなライフスタイルにも自然に溶け込み、所有者のセンスの良さをさりげなく主張します。 特定の時代性に縛られない普遍的な美しさを持っているため、長く乗っても飽きがこないでしょう。
SNSで「かっこいい」とコメントしている若者たちは、過去のプレリュードの歴史や文脈を知らないかもしれません。 しかし、だからこそ彼らは、先入観なく、純粋に一つの工業製品としてこのデザインの美しさを評価することができるのです。 この新しい世代からの支持こそが、プレリュードが未来へと走り続けるための、何よりのエネルギーになるのではないでしょうか。
歴代プレリュードのデザインとその輝かしい変遷
新型プレリュードのデザインを語る上で、その偉大な先代たちの歴史を振り返ることは欠かせません。 「プレリュードらしさ」とは一体何なのか。 その答えは、時代と共に変化し、進化を遂げてきた歴代モデルのデザインの中に隠されています。 各世代がどのようなコンセプトを持ち、いかにして若者たちの心を掴んできたのか。 ここでは、初代から5代目までの輝かしいデザインの変遷を辿り、プレリュードという車が持つ不変の魅力を探っていきます。 私自身、いくつかのモデルを所有してきた経験から、それぞれのデザインに込められた時代の空気感とホンダの情熱を解説します。
初代(SN型 / 1978-1982):国産スペシャルティカーの先駆け
1978年に登場した初代プレリュードは、まさに日本のスペシャルティカー市場の「前奏曲」を奏でた一台でした。 ベースとなったのはシビックですが、その面影はほとんどありません。 低くワイドなフォルムに、当時としては珍しいロングノーズ・ショートデッキのスタイリング。 そして、日本車で初めて電動サンルーフを標準装備したことも、大きな話題となりました。
デザインは、奇をてらうことなく、欧州のクーペを思わせるクリーンで上品なものでした。 角型2灯式のヘッドライトと横長のテールランプは、落ち着いた大人の雰囲気を醸し出しています。 内装も個性的で、「集中ターゲットメーター」と呼ばれる、スピードメーターとタコメーターの針が同心円状に動くユニークなメーターが採用されていました。 初代プレリュ-ドは、大衆車ベースでありながら、パーソナルで贅沢な時間を提供するという、新しい価値観を提示したのです。 この「ちょっと背伸びしたお洒落さ」こそが、プレリュードの原点と言えるでしょう。
2代目(AB/BA1型 / 1982-1987):リトラクタブルライトが象徴した「デートカー」の王道
プレリュードの名を不動のものにしたのが、1982年に登場した2代目です。 このモデルのデザインは、80年代の日本の自動車史における金字塔と言っても過言ではありません。 最大の特徴は、何と言ってもシャープなリトラクタブルヘッドライトの採用です。 これにより、国産車の中でも群を抜いて低いボンネットフードを実現し、未来から来た宇宙船のような圧倒的な先進性を放っていました。
「FFスーパーボルテージ」というキャッチコピーの通り、低く構えたワイド&ローのフォルムは、見るからにスポーティ。 水平基調でクリーンなボディライン、ガラスエリアが広く開放的なキャビン、そして助手席側からでも操作できるサンルーフのスイッチなど、すべてが「二人で過ごす特別な時間」を演出するためにデザインされていました。 この2代目プレリュードの大ヒットにより、「デートカー」という言葉が生まれ、若者たちのライフスタイルにまで大きな影響を与えたのです。 まさに、デザインの力で時代を創った一台でした。
3代目(BA4/5/7型 / 1987-1991):洗練を極めた究極のロー&ワイドフォルム
バブル景気の絶頂期、1987年に登場した3代目は、2代目のコンセプトをさらに昇華させたモデルです。 デザインはキープコンセプトながら、細部はより洗練され、成熟したクーペの佇まいを見せました。 リトラクタブルヘッドライトは継承しつつ、ボンネットフードはさらに低く、ボディのワイド感も強調されています。 その低さは、当時のライバル車と比較しても突出しており、「ボンネットの低い車は美しい」という美学を貫き通しました。
また、3代目のハイライトは、世界で初めて実用化された機械式4WS(4輪操舵システム)の搭載です。 これにより、コーナリング性能が劇的に向上し、「走り」の面でもライバルを圧倒。 デザインの美しさと、ホンダらしい先進技術が見事に融合した3代目は、まさに無敵のデートカーとして市場に君臨しました。 この時代を知る者にとって、「プレリュード」と聞いて真っ先に思い浮かぶのが、この3代目の流麗な姿ではないでしょうか。 私もこのモデルの完成度には、今なお感嘆させられます。
4代目(BA8/9/BB1/4型 / 1991-1996):未来的でワイドなフォルムへの大胆な挑戦
バブル崩壊後の1991年、4代目プレリュードは大きなデザイン変革を遂げます。 3代目までの直線基調のデザインから一転、全体的に丸みを帯びた、未来的でグラマラスなフォルムへと生まれ変わりました。 リトラクタブルヘッドライトは廃止され、薄く横長の固定式ヘッドライトを採用。 全長は短くなったものの、全幅は1,765mmと3ナンバーサイズに拡大され、非常にワイドで安定感のあるスタンスを手に入れました。
内装も革新的で、インストルメントパネルが運転席と助手席を緩やかに包み込むような「バイザレスデザイン」を採用。 アナログメーターとデジタル表示を組み合わせたメーターパネルは、まるで飛行機のコックピットのようでした。 しかし、このあまりにも先進的で個性的なデザインは、市場の評価が分かれる結果となりました。 保守的なユーザーからは敬遠された一方で、その独創性を高く評価する熱狂的なファンも生み出しました。 時代の変化に果敢に挑んだ、ホンダのチャレンジ精神が最も色濃く表れたモデルと言えるでしょう。
5代目(BB5/6/7/8型 / 1996-2001):原点回帰と熟成、縦型ヘッドライトの衝撃
シリーズ最後のモデルとなった5代目は、1996年に登場しました。 デザインは4代目の丸みを帯びたスタイルから再び直線基調へと回帰。 しかし、単なる先祖返りではなく、よりシャープで精悍な印象に進化しています。 最大の特徴は、縦に長い形状のヘッドライトです。 当時のデザイントレンドとは一線を画すこの大胆な試みは、見る者に強烈なインパクトを与えました。 このヘッドライトによって、5代目は歴代モデルの中でも随一の「目ヂカラ」を持つ、非常に個性的なフロントマスクを手に入れたのです。
ボディサイズは再び5ナンバー枠に戻り、取り回しの良さを確保。 走りも熟成が進み、特に高性能エンジンVTECを搭載した「タイプS」は、FFスポーツクーペの完成形とまで言われました。 しかし、時代はすでにミニバンやSUVが主流となり、クーペ市場そのものが縮小。 プレリュードもその流れには抗えず、2001年に惜しまれながらその歴史に幕を閉じることになります。 最後の最後まで独自の個性を貫き通した5代目の姿は、今も多くのファンの心に焼き付いています。
なぜデザイン評価は二極化したのか?ジャーナリストとしての考察
新型プレリュードのデザインに対する評価が、なぜこれほどまでに「絶賛」と「酷評」に二極化してしまったのでしょうか。 単に「トヨタに似ているから」とか「昔の面影がないから」といった表面的な理由だけでは、この現象の本質を捉えることはできません。

引用 : HONDA HP (https://global.honda/jp/news/2025/4250731.html)
そこには、自動車を取り巻く環境の劇的な変化、ブランドが抱える宿命的なジレンマ、そして私たちの情報との向き合い方そのものの変容が、複雑に絡み合っています。 ここでは、一人の自動車ジャーナリストとして、そして長年ホンダというメーカーを見続けてきた者として、この「二極化」の背景にある根深い要因を深く、そして多角的に考察していきます。
時代背景の劇的な変化:求められるデザインの変容
まず考えなければならないのは、プレリュードが最も輝いていた80年代、90年代と、現代とでは、車に求められる価値観が根本的に異なるという事実です。
「デートカー」文化の終焉
かつてプレリュードは「デートカー」の象徴でした。 スタイリッシュなクーペで好きな人を迎えに行くことは、若者にとって一つのステータスであり、憧れでした。 車は自己表現の道具であり、異性へのアピールという側面も色濃く持っていました。 当時のデザインは、そうした時代の空気を反映し、華やかで、どこかセクシーさも感じさせるものが主流でした。
しかし現代では、ライフスタイルが多様化し、車はより実用的な「移動の道具」として捉えられることが多くなりました。 若者の車離れも指摘される中、「デートのために車を買う」という価値観は、もはや一般的ではありません。 現代に求められるのは、華やかさよりも、環境性能や安全性、そして日常に溶け込むクリーンで普遍的なデザインなのです。 新型プレリュードのデザインは、まさにこの現代的な価値観に応えようとした結果であり、過去の文脈で評価しようとすると、どうしてもズレが生じてしまうのです。
ブランドイメージの継承と革新のジレンマ
プレリュードのように、過去に偉大な成功体験を持つモデルを復活させる際には、メーカーは常に「継承」と「革新」というジレンマに直面します。
継承への期待とリスク
往年のファンは、当然ながら過去のモデルが持っていたデザインのエッセンス、つまり「プレリュードらしさ」の継承を期待します。 リトラクタブルライトとは言わないまでも、低いボンネットやシャープなシルエットといった記号を盛り込めば、彼らを喜ばせることはできるかもしれません。 しかし、それは同時に、過去の焼き直しという批判や、現代の安全基準や空力性能との両立が難しいというリスクを伴います。 安易な懐古趣味は、新しい顧客を獲得する妨げにもなりかねません。
革新への挑戦と反発
一方で、完全に新しいデザインで「革新」に挑めば、今度は「これはプレリュードではない」という、古くからのファンからの強烈な反発を招きます。 今回の新型プレリュードは、まさにこのケースと言えるでしょう。 メーカーとしては、未来を見据えて新しい時代のプレリュード像を提示したかったはずです。 しかし、その思いが強すぎたために、過去との断絶を感じさせてしまった。 このジレンマの着地点を見つけることの難しさが、評価の二極化に直結しているのです。
電動化時代におけるデザインのグローバルなトレンド
「トヨタのハンマーヘッドに似ている」という批判は、実はもっと大きな視点で見ると、「電動化時代のデザイントレンドの収斂」という現象の一端に過ぎません。
BEV(電気自動車)やハイブリッドカーは、ガソリンエンジン車ほど大きな冷却口(グリル)を必要としません。 また、航続距離を稼ぐために、空気抵抗を極限まで減らす必要があります。 その結果、世界中のメーカーが生み出すデザインは、必然的に似通ってくる傾向にあります。
- 薄型ヘッドライト: LED技術の進化により、ライトユニットを非常に小さくできるようになりました。これにより、ボンネットを低くし、前面投影面積を減らすことができます。
- シームレスなフロントマスク: グリルを小さく、あるいは無くすことで、空気抵抗を減らし、クリーンで未来的な印象を与えます。
- クリーンな面構成: ボディ表面の凹凸を減らすことで、空気の流れをスムーズにします。
新型プレリュードのデザインも、トヨタのデザインも、そして他の多くのメーカーのデザインも、このグローバルなトレンドという大きな流れの中にあります。 つまり、ホンダがトヨタを模倣したというよりは、「電動化時代の最適解」を追求した結果、両者が似たようなデザインに行き着いた、と見るのがより本質的かもしれません。 この大きな潮流を理解せず、二社間の問題としてのみ捉えてしまうと、本質を見誤ることになります。
SNS時代の到来と「意見の可視化」
最後に、忘れてはならないのが、SNSの存在です。 かつて、自動車デザインへの評価は、自動車雑誌の評論家や専門家の意見が中心でした。 一般のユーザーが自分の意見を広く発信する場は、限られていました。
しかし、今や誰もがTwitter(X)やInstagram、YouTubeなどで、瞬時に自分の感想を発信し、共有することができます。 「かっこいい」と思えばすぐに投稿され、「パクリだ」と感じれば、比較画像と共に拡散されます。 これにより、これまで水面下にあったであろう個々人の感想が「可視化」され、あたかも世論が真っ二つに割れているかのような「二極化」現象が強調されるのです。
肯定的な意見と否定的な意見が、それぞれのコミュニティで増幅され、互いに交わることなく先鋭化していく。 これは自動車デザインに限らず、現代社会のあらゆる場面で見られる現象です。 新型プレリュードのデザイン論争は、まさにこのSNS時代を象徴する出来事の一つと言えるでしょう。 もしかしたら、昔からデザインの評価というものは多様であったのが、現代になってようやくその多様性が誰の目にも明らかになった、ということなのかもしれません。
デザインだけじゃない!新型プレリュードの魅力と購入前の注意点
ここまで新型プレリュードのデザインについて深く掘り下げてきましたが、車の魅力は当然ながらデザインだけではありません。 むしろ、その走りや搭載される技術にこそ、ホンダの真骨頂が表れています。

引用 : HONDA HP (https://global.honda/jp/news/2025/4250731.html)
私が入手した情報や、ディーラーから得た見積もりを基に、デザイン以外の側面に目を向け、新型プレリュードがどのような車なのか、その実像に迫ります。 また、その人気ゆえに、購入を検討する際にはいくつかの注意点が存在します。 ここでは、スペックから見える立ち位置、期待の新技術、そして具体的な購入シミュレーションまで、ジャーナリストの視点で徹底的にレビューします。
シビックタイプR譲りの走りとハイブリッドの融合
新型プレリュードの価格が600万円を超えることに驚いた方も多いでしょう。 その価格設定の背景には、ベースとなっている車両が関係しています。 公式リリースによれば、新型プレリュードはピュアスポーツの性能を追求した「シビックタイプR」の車種をベースに、専用セッティングを施していると明記されています。
これは、走りのポテンシャルが非常に高いことを意味します。 具体的には、以下のようなタイプR譲りの装備が採用される見込みです。
- アダプティブ・ダンパー・システム: 路面状況や運転操作に応じて、四輪のダンパー減衰力を緻密に制御し、高い操縦安定性と快適な乗り心地を両立します。
- ブレンボ製大容量フロントブレーキ: 世界的に評価の高いブレンボ社のブレーキシステムを採用。ハードな走行でも安定した制動力を発揮します。
- 高剛性19インチ大口径ホイール: ノイズリデューシングタイプを採用し、静粛性にも配慮しつつ、シャープなハンドリングに貢献します。
シビックタイプRが持つ卓越したシャシー性能を土台としながら、プレリュードは根本的に異なるパワートレインを搭載します。 それが、2.0Lの2モーターハイブリッドシステム「e:HEV」です。 タイプRがマニュアルトランスミッションのピュアな内燃機関スポーツであるのに対し、プレリュードはモーター駆動を主体とした、滑らかで力強い加速が持ち味のスペシャリティスポーツとなります。 この「タイプRの骨格」と「電動化の心臓」の組み合わせが、どのような走りを見せてくれるのか、今から期待が高まります。
期待の新技術「S+シフト(エスプラスシフト)」とは?
新型プレリュードで最も注目すべき新技術が、ホンダ初採用となる「S+シフト」です。 これは、モーター駆動でありながら、あたかも多段変速機が存在するかのようなダイレクトな操作感と、エンジンサウンドとの一体感を実現するためのシステムです。
その仕組みは、仮想的に8段の変速ステップを設け、加速・減速時にそのステップに合わせてエンジン回転数を緻密にコントロールするというもの。 これにより、従来のハイブリッド車にありがちだった、アクセル操作とエンジン回転、そして実際の加速感がリンクしない「ラバーバンドフィール」を解消し、ドライバーの意のままに操る歓びを追求しています。
さらに、「アクティブサウンドコントロール」というシステムが、エンジン回転数と同期した迫力あるサウンドをスピーカーから流すことで、聴覚的にも高揚感を演出します。 メーター表示も俊敏に反応し、視覚、聴覚、そして体感のすべてで、車との一体感を感じられるように設計されているのです。 コンセプトである「UNLIMITED GLIDER(アンリミテッド・グライダー)」が示すように、グライダーのような静かで滑らかな巡航と、意のままに操るスポーツ走行を両立させるこの新技術。 実際に体験してみないとその真価はわかりませんが、ホンダの「走りへのこだわり」が詰まった、非常に興味深いシステムです。
スペックと価格から見る、新型プレリュードの立ち位置
ここで、判明している情報から新型プレリュードのスペックと価格を整理し、市場における立ち位置を考えてみましょう。
| 項目 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| グレード | モノグレード | 迷う必要のない1グレード展開 |
| 駆動方式 | FF(前輪駆動) | |
| パワートレイン | 2.0L 2モーターハイブリッドシステム(e:HEV) | シビックやアコード搭載のシステムがベースか |
| トランスミッション | 電気式無段変速機(S+シフト搭載) | 仮想8段変速 |
| 車両本体価格 | 6,179,800円(税込) | |
| ボディカラー | 全4色 | ホワイト、グレーは有償色 |
価格は600万円オーバーと高価ですが、これはシビックタイプR(約550万円)をベースに、専用のハイブリッドシステムと新技術を搭載していることを考えれば、ある程度納得できる範囲かもしれません。 ライバルとしては、トヨタのGR86やスバルBRZの上級グレード、日産フェアレディZあたりが価格帯的に近くなりますが、プレリュードはハイブリッドのスペシャリティクーペという独自のポジションを築くことになります。 燃費性能とスポーツ性を両立させたい、そして先進的な技術に魅力を感じるユーザーにとっては、他に代えがたい選択肢となるでしょう。
【重要】購入前に知っておくべき7つの注意点
最後に、私がディーラーを回り、情報を収集する中で判明した、新型プレリュードを購入する前に必ず知っておくべき注意点を7つにまとめました。 デザインや走りに心を奪われても、これらの点を確認せずに契約を進めるのは禁物です。
- そもそも簡単には買えない可能性が高い 初期ロットの生産台数は非常に少なく、月販目標も300台程度とされています。 多くの販売会社で抽選や厳しい購入条件(長年のホンダオーナーであることなど)が設けられており、一見客がディーラーに行って「ください」と言って買える可能性は極めて低いです。
- ボディカラーと内装色の組み合わせが限定的 内装色は基本的にブルー系のツートンですが、唯一のブラック内装を選ぶためには、ボディカラーで有償色の「ムーンリットホワイトパール」を選択する必要があります。 黒内装が好みの方は、必然的にボディも白を選ぶことになるので注意が必要です。
- パワーシートやシートベンチレーションは非搭載 600万円クラスの車としては意外ですが、パワーシートや、夏場に快適なシートベンチレーションの設定がありません。 快適装備を重視する方にとっては、大きなマイナスポイントになる可能性があります。
- サンルーフ(パノラマルーフ)の設定がない かつての「デートカー」の必須装備であったサンルーフですが、新型ではオプション設定すらありません。 開放感を求める方にとっては残念なポイントです。
- 360°カメラ(マルチビューカメラ)の設定がない シビックベースのためか、車両を上から見下ろしたように表示できる360°カメラの設定がありません。 N-BOXにすら搭載されている装備だけに、このクラスの車にないのは少し物足りないかもしれません。
- 後部座席はあくまで緊急用と割り切る 2ドアクーペの宿命ですが、後部座席は非常に狭く、大人が長時間乗るのには適していません。 基本的には2人乗り+荷物置き場、と考えるのが現実的です。
- Googleナビ搭載による表示の違い ナビはGoogleのOSを搭載したものが標準装備されます。 常に地図が最新であるなどメリットは大きいですが、従来の国産ナビに表示されていた高速道路のジャンクション案内などの詳細な「パネル表示」が出ない可能性があります。 この点は今後のアップデートに期待したいところです。
これらの注意点を許容できるかどうかが、購入の大きな判断基準となるでしょう。 まずは、お近くのホンダディーラーに購入可能かどうかを問い合わせてみることから始めるのが賢明です。
まとめ
今回は、待望の復活を遂げた新型プレリュードのデザインが、なぜこれほどまでに賛否両論を巻き起こし、評価が二極化しているのか、その理由を多角的に考察してきました。
結論として、この現象は単なるデザインの好き嫌いを超えた、いくつかの複合的な要因によって引き起こされています。
- 過去の偉大なイメージとのギャップ: 往年のファンが抱く「時代の先駆けであってほしい」という強い期待感と、現代のグローバルなデザイントレンドに則ったスタイリングとの間に生じたギャップ。
- 時代の価値観の変化: 「デートカー」がもてはやされた時代と、現代のミニマルで合理的な価値観との相違。
- 継承と革新のジレンマ: メーカーが抱える、過去のブランドイメージを守ることと、未来のために新しいデザインに挑戦することの難しい舵取り。
- SNSによる意見の可視化: これまで個々人の胸の内にあった感想が、SNSによって瞬時に共有・拡散され、「二極化」という現象をより際立たせている。
「トヨタのパクリ」「二番煎じ」という厳しい批判も、それだけ多くの人々が「プレリュード」という名前に特別な思い入れを持ち、大きな期待を寄せていたことの裏返しに他なりません。 一方で、そのクリーンで先進的なデザインは、間違いなく新しい時代の価値観を捉えており、過去を知らない若い世代からは素直な称賛の声が上がっています。
最終的に、デザインの評価は個人の主観に委ねられます。 しかし、今回のレビューを通じて、様々な意見の背景にある文脈や理由をご理解いただけたのではないでしょうか。 新型プレリュードは、デザインだけでなく、シビックタイプR譲りのシャシー性能と「S+シフト」という新技術を融合させた、走りの面でも非常に魅力的なスペシャリティクーペです。
もしあなたがこの車に興味を持ったなら、ぜひ先入観を捨てて実車と向き合ってみてください。 写真や画面越しでは伝わらない、その佇まいやオーラに、新たな発見があるかもしれません。 プレリュードの「前奏曲」は、まだ始まったばかりなのです。