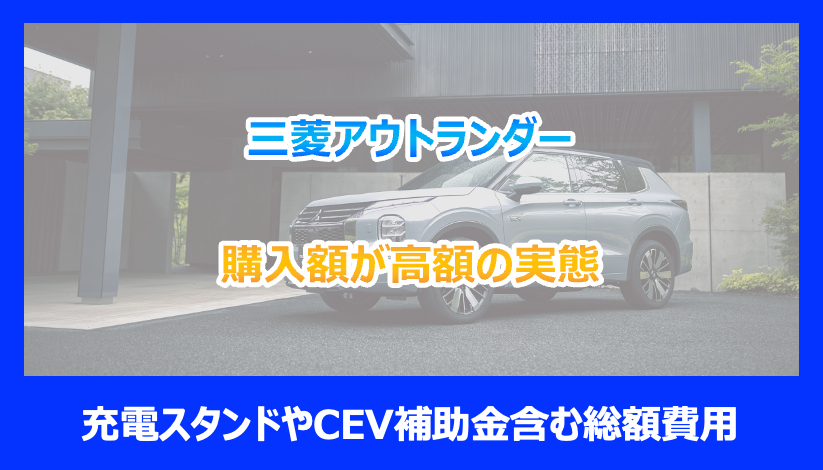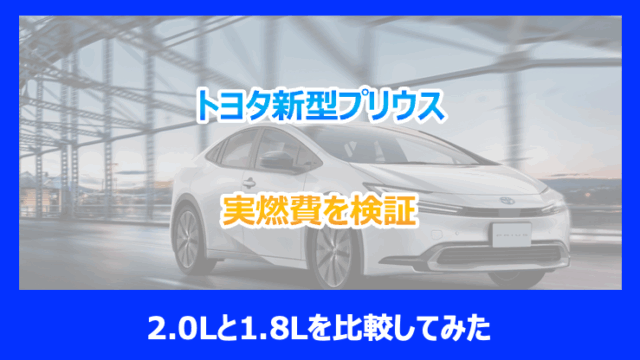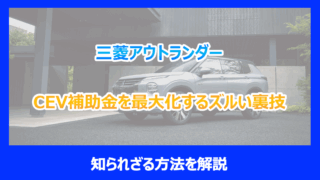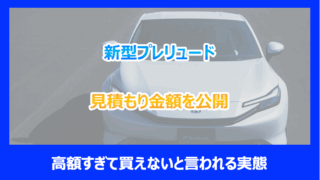モータージャーナリスト兼コラムニストの二階堂仁です。 今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、新型アウトランダーPHEVの購入を検討していて、補助金などを含めた最終的な総額費用が一体いくらになるのか、気になっていることでしょう。 私も実際にアウトランダーPHEVを所有し、補助金の申請や充電スタンドの設置も経験したので、その複雑さや分かりにくさに対する気になる気持ちはよくわかります。

引用 : 三菱HP (https://www.mitsubishi-motors.com/jp/newsroom/newsrelease/2021/20211216_1.html)
この記事を読み終える頃には、新型アウトランダーPHEVの購入に関する費用の疑問がすべて解決しているはずです。
記事のポイント
- アウトランダーPHEVのグレード別価格と諸費用の詳細
- 自宅充電器の設置費用とV2Hという選択肢
- 国と自治体のCEV補助金の詳細と申請方法
- 補助金適用後のリアルな乗り出し総額シミュレーション
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

新型アウトランダーPHEVの購入にかかる総額費用の内訳
「新型アウトランダーPHEVは価格が高い」という話を耳にすることがあるかもしれません。 しかし、その価格は車両本体価格だけを見て判断している可能性があります。 実際には、PHEVならではの補助金制度などを活用することで、見た目の価格よりもずっとお得に購入できるケースがほとんどです。

引用 : 三菱HP (https://www.mitsubishi-motors.com/jp/newsroom/newsrelease/2021/20211216_1.html)
まずは、購入にかかる費用の全体像を正確に把握することから始めましょう。 ここでは、車両本体価格から、意外と見落としがちな諸費用、そして人気のオプションまで、費用の内訳を細かく分解していきます。
グレード別車両本体価格一覧
新型アウトランダーPHEVは、大きく分けて「M」「G」「P」の3つのグレードが基本となります。 それぞれ5人乗りと7人乗りが選択でき、装備の違いによって価格が異なります。 最上位グレードの「P」には、さらに豪華な「BLACK Edition」という特別仕様車も用意されています。
以下に、主なグレードの車両本体価格(税込)をまとめました。 ご自身の使い方や欲しい機能と照らし合わせながら、最適なグレード選びの参考にしてください。
| グレード | 駆動方式 | 乗車定員 | 車両本体価格(税込) |
|---|---|---|---|
| M | 4WD | 5人 | 4,995,100円 |
| G | 4WD | 5人 | 5,454,900円 |
| G | 4WD | 7人 | 5,548,400円 |
| P | 4WD | 7人 | 6,158,900円 |
| BLACK Edition | 4WD | 7人 | 6,329,400円 |
※上記は2025年9月現在のメーカー希望小売価格です。 有料色などを選択した場合は価格が変動します。
私自身は7人乗りの「G」グレードを所有していますが、家族での利用や多人数での移動が多い方には7人乗りが非常に便利です。 3列目シートは床下に完全に収納できるため、普段は広々とした荷室として使えるのも魅力です。
見落としがちな諸費用(初期費用)の詳細
新車を購入する際には、車両本体価格以外にも様々な「諸費用」が必要になります。 これはアウトランダーPHEVに限った話ではありませんが、意外と総額に響いてくる部分なので、事前にしっかりと把握しておくことが重要です。
主な諸費用は以下の通りです。
- 税金・保険料
- 自動車税種別割: 排気量に応じて課税されます。 アウトランダーPHEV(2.4L)の場合、初年度はグリーン化特例により減税されます。
- 自動車重量税: 車両重量に応じて課税されます。 エコカー減税の対象となるため、購入時は免税となります。
- 環境性能割: 燃費性能に応じて課税されますが、PHEVは非課税です。
- 自賠責保険料: 法律で加入が義務付けられている保険です。 通常37ヶ月分を新車購入時に支払います。
- 販売諸費用
- 検査登録手続代行費用: 車両を国に登録するための手続きを販売店に代行してもらう費用です。
- 車庫証明手続代行費用: 車庫証明の取得を代行してもらう費用です。
- 納車費用: 自宅など指定の場所まで車を運んでもらう費用です。 販売店まで自分で引き取りに行く場合は不要なこともあります。
- リサイクル料金: 自動車を将来廃車にする際のリサイクル費用をあらかじめ支払うものです。
これらの諸費用は、合計でおよそ20万円~30万円程度を見ておくと良いでしょう。 販売店によって若干金額が異なる場合があるので、最終的な見積もりで必ず確認してください。
人気のメーカーオプションとその価格
標準装備が充実しているアウトランダーPHEVですが、さらに快適性や質感を高めるためのメーカーオプションも多数用意されています。 後付けできないものがほとんどなので、最初のグレード選びと同時に慎重に検討したいポイントです。
特に人気が高いオプションをいくつかご紹介します。
- 電動パノラマサンルーフ(110,000円)
- 開放感あふれる室内空間を演出します。 特に後席に乗る家族からの満足度が非常に高いオプションです。 リセールバリューにも良い影響を与えると言われています。
- BOSEプレミアムサウンドシステム(115,500円 ※グレードによる)
- 9個のスピーカーで構成され、臨場感あふれるクリアなサウンドを楽しめます。 音楽好きにはたまらない装備でしょう。 静粛性の高いPHEVだからこそ、その真価が発揮されます。
- 有料色(33,000円~88,000円)
- ホワイトダイヤモンドやレッドダイヤモンドといった、深みと輝きのある特別塗装色は有料となります。 エクステリアの印象を大きく左右する部分なので、こだわりたいポイントです。
これらのオプションを追加すると、当然ながら総額も上がります。 予算と満足度のバランスを考えながら、自分だけの一台をカスタマイズする楽しみもあります。
車両購入費用の概算シミュレーション
それでは、ここまでの情報を元に、中間グレードである「G(7人乗り)」に人気のオプション「電動パノラマサンルーフ」を付けた場合の車両購入費用をシミュレーションしてみましょう。
| 項目 | 金額(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 車両本体価格(G・7人乗り) | 5,548,400円 | |
| メーカーオプション | 110,000円 | 電動パノラマサンルーフ |
| 諸費用合計 | 250,000円 | 税金、保険、代行費用など |
| 車両関連費用 合計 | 5,908,400円 | 補助金適用前の金額 |
このように、オプションや諸費用を含めると、車両関連だけで約600万円近くなることが分かります。 「やはり高額だ」と感じるかもしれませんが、ここからがPHEVの真骨頂です。 次の章で解説する充電設備や補助金が、この金額を大きく変えていきます。
PHEVならではの追加費用!自宅充電設備の設置
アウトランダーPHEVの魅力を最大限に引き出すために、ほぼ必須と言えるのが「自宅充電設備」の設置です。 毎日の通勤や買い物といった日常的な移動のほとんどを電気だけで賄えるようになり、ガソリンスタンドに行く手間とコストを劇的に削減できます。 ここでは、自宅充電設備の必要性から、種類、設置費用、そして災害時にも役立つ「V2H」という新しい選択肢までを詳しく解説します。

なぜ自宅充電設備が必要なのか?
PHEVはガソリンでも走行できるため、「必ずしも自宅に充電設備は必要ないのでは?」と考える方もいるかもしれません。 しかし、それではPHEVのメリットの半分も享受できないと言っても過言ではないでしょう。
自宅充電設備があることのメリットは計り知れません。
- 圧倒的なランニングコストの削減: 深夜の安い電力プランを利用して充電すれば、ガソリン代と比較して走行コストを1/3以下に抑えることも可能です。
- 利便性の向上: 外出先で充電スポットを探す必要がなく、帰宅後にプラグを挿すだけで翌朝には満充電になっています。 「給油」という行為そのものが生活からほぼ無くなります。
- 快適なカーライフ: 事前にエアコンを作動させて、夏は涼しく、冬は暖かい状態で出発できる「リモートコントロール」機能も、バッテリー残量を気にせず使えるようになります。
まさに、自宅充電はPHEVを「賢く、快適に」乗りこなすための必須アイテムなのです。
充電設備の種類と選び方(コンセントタイプ vs. 専用充電器)
自宅用の充電設備は、大きく分けて2つのタイプがあります。
1. 充電用コンセントタイプ
壁に設置する専用の防水コンセントです。 車載の充電ケーブルを使って充電します。
- メリット: 設置費用が比較的安い。 見た目がスッキリしている。
- デメリット: 充電ケーブルを毎回出し入れする手間がかかる。
2. ケーブル付き普通充電器
充電器本体にケーブルが付属しているタイプです。 ガソリンスタンドの給油ノズルのように、使いたい時にすぐに使えます。
- メリット: ケーブルの出し入れが不要で非常に楽。
- デメリット: コンセントタイプに比べて本体価格、設置費用が高めになる傾向がある。
どちらを選ぶかは利便性と予算のバランス次第ですが、毎日のことなので、個人的には多少コストが上がってもケーブル付き普通充電器をおすすめします。 その手軽さは、一度体験すると元には戻れません。
充電設備の設置工事費用はいくら?
気になる設置費用ですが、これは自宅の電気設備の状況によって大きく変動します。
- 分電盤からの距離: 分電盤から駐車スペースまでの距離が遠いほど、配線工事費が高くなります。
- 分電盤の空き状況: 分電盤に空き回路がない場合、分電盤自体の交換や増設が必要になり、追加費用がかかります。
- 壁の材質など: 配線を通すために壁に穴を開ける工事など、建物の構造によっても費用は変わります。
一般的な目安としては、工事費と設備費を合わせておおよそ10万円~20万円程度を見ておくと良いでしょう。 必ず複数の専門業者から見積もりを取り、工事内容と金額を比較検討することが重要です。 三菱自動車のディーラーでも専門業者を紹介してくれるので、まずは相談してみるのが確実です。
V2H(Vehicle to Home)という選択肢と、その費用・メリット
近年、PHEVやEVの購入を検討する人々の間で急速に注目度が高まっているのが「V2H」です。 これは「Vehicle to Home」の略で、車に蓄えた電気を家庭用の電力として使用できるシステムを指します。
V2Hのメリット
- 災害時の非常用電源: アウトランダーPHEVは20kWhという大容量の駆動用バッテリーを搭載しています。 これは一般家庭の約2日分の使用電力量に相当します。 V2Hを導入すれば、停電が発生しても車が巨大な蓄電池となり、冷蔵庫や照明、テレビ、スマートフォンの充電など、普段通りの生活を維持することが可能です。 さらに、ガソリンが満タンであれば、エンジンで発電して電気を供給し続けることができるため、10日以上の電力確保も可能になります。 この安心感は、何物にも代えがたい大きなメリットです。
- 電気代の節約: 太陽光発電を設置している家庭の場合、昼間に発電した電気をアウトランダーPHEVに貯めておき、夜間にその電気を家庭で使う、といった賢いエネルギー利用が可能になります。 電力会社から買う電気を最小限に抑え、電気代を大幅に節約できます。
V2Hの費用
V2Hシステムの導入には、専用の充放電設備が必要です。 機器本体の価格はメーカーや性能によって様々ですが、工事費込みで60万円~100万円程度が相場です。 高額に感じますが、後述する補助金制度を利用することで、自己負担を大幅に軽減できます。
充電設備に初期投資をすることは、未来のランニングコストと安心を手に入れるための投資とも言えます。 特に自然災害が多い日本において、V2Hの価値は今後ますます高まっていくでしょう。
購入価格を大きく左右するCEV補助金制度を徹底解説
さて、ここからが本題です。 アウトランダーPHEVのようなクリーンエネルギー自動車の購入を後押しするために、国や自治体は手厚い補助金制度を用意しています。 この「CEV補助金」をいかにうまく活用するかが、最終的な乗り出し総額を抑える最大の鍵となります。
しかし、制度が複雑で分かりにくいのも事実です。 ここでは、国の補助金、自治体の補助金に分けて、それぞれの金額、条件、申請方法を誰にでも分かるように徹底的に解説していきます。

そもそもCEV補助金とは?
CEV補助金は、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCEV)といった、走行中のCO2排出量が少ない、または全く排出しない環境性能に優れた車の普及を目的とした制度です。 正式名称は「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」と言います。
購入者は、この制度を利用することで、車両購入費用の一部を国や自治体から補助してもらえます。 ただし、補助金を受けるためにはいくつかの条件があり、申請手続きも自分で行う必要があります。 少し手間に感じるかもしれませんが、数十万円単位で総額が変わってくる非常に重要な制度なので、必ず内容を理解しておきましょう。
【国】からのCEV補助金の金額と申請条件
まず、日本全国どこに住んでいても対象となる、国からの補助金についてです。
補助金額
2025年度のCEV補助金において、新型アウトランダーPHEVは一律で55万円の補助対象となっています。
さらに、外部給電機能(車から電気を取り出せる機能)やV2H対応を評価する上乗せ措置があります。 アウトランダーPHEVはこれらの条件を満たしているため、満額の55万円が交付されます。
※補助金の額は年度の予算によって変動する可能性があります。 必ず最新の情報を経済産業省や次世代自動車振興センターのウェブサイトで確認してください。
主な申請条件
補助金を受け取るためには、以下の重要な条件を満たす必要があります。
- 新車登録: 補助金の対象となるのは、新車として登録された車両のみです。 中古車は対象外です。
- 本人名義: 車検証の使用者欄が、申請者本人(個人)の名義である必要があります。
- 保有義務期間: これが最も重要なポイントです。 補助金の交付を受けた車両は、原則として4年間(PHEVの場合)保有する義務があります。 この期間内に車を売却したり、名義変更したりすると、補助金の一部または全額を返納しなければならない場合があります。
【国】CEV補助金の申請方法と注意点
申請手続きは、基本的に車両の登録が完了してから行います。 販売店の担当者がサポートしてくれることも多いですが、最終的な申請者は購入者本人です。 流れを把握しておきましょう。
申請の流れ
- 車両の登録・納車: まずは車を購入し、ナンバープレートが交付されます。
- 申請書類の準備: 申請には以下の書類が必要です。
- 補助金交付申請書
- 本人確認書類(運転免許証のコピーなど)
- 自動車検査証(車検証)のコピー
- 車両の注文書や契約書のコピー
- 代金の支払いが確認できる書類(領収書のコピーなど)
- 補助金の振込先口座がわかるもの(通帳のコピーなど)
- 申請書類の提出: すべての書類を揃え、次世代自動車振興センターへ郵送またはオンラインで提出します。
- 審査・交付決定: 提出された書類が審査され、不備がなければ補助金の交付が決定します。
- 補助金の振込: 交付決定後、指定した口座に補助金が振り込まれます。 申請から振込までは、通常1~2ヶ月程度かかります。
注意点
- 申請期限: 車両の初度登録日によって申請の受付期間が定められています。 納車されたら、できるだけ速やかに申請手続きを進めましょう。
- 予算の枯渇: CEV補助金は国の予算に基づいて運営されています。 年度末近くになると予算上限に達し、受付が早期に終了する可能性もゼロではありません。
【自治体】からの補助金は必ずチェック!
国の補助金に加えて、都道府県や市区町村といった自治体が独自に補助金制度を設けている場合があります。 そして多くの場合、国の補助金と自治体の補助金は併用が可能です。 これを利用しない手はありません。
自治体の補助金は、お住まいの地域によって内容が大きく異なります。 ここでは、特に手厚い補助制度で知られる東京都を例にご紹介します。
東京都の「ZEV導入促進事業」
東京都では、ゼロエミッションビークル(ZEV)の普及を目的として、独自の補助金制度を実施しています。
- PHEV車両への補助:
- 基本額: 45万円
- 上乗せ補助:
- V2H等の導入: 15万円(車両購入と同時にV2Hを設置する場合)
- 再生可能エネルギー電力の導入: 15万円(太陽光などで発電した電気の利用契約をする場合)
つまり、東京都にお住まいの方がアウトランダーPHEVを購入し、V2Hを設置し、再生可能エネルギー電力契約を結ぶと、車両だけで最大75万円もの補助が受けられる可能性があります。 これは非常に大きい金額です。
自治体補助金の調べ方
ご自身がお住まいの自治体の補助金制度を調べるには、以下の方法が有効です。
- インターネットで検索: 「〇〇県 EV 補助金」「△△市 PHEV 補助金」といったキーワードで検索すると、自治体の公式ページや関連情報が見つかります。
- 自治体の担当窓口に問い合わせる: 環境政策課など、担当部署に直接電話で問い合わせるのが最も確実です。
- 自動車販売店に確認する: 地域の販売店の担当者は、地元の補助金制度に詳しい場合が多いです。
自治体の補助金も、国の補助金と同様に申請期間や予算が限られています。 購入を検討し始めた段階で、必ず最新の情報を確認するようにしてください。
補助金を受ける際の重要注意点(保有義務期間と罰則)
繰り返しになりますが、補助金制度で最も注意すべきは「保有義務期間」です。 国、自治体それぞれに保有義務期間が定められていることが多く、期間内に車を売却するなど、条件に違反した場合は補助金の返納を求められます。
例えば、国の補助金(保有義務4年)と東京都の補助金(保有義務4年)の両方を受けた場合、4年間はその車を保有し続けなければなりません。 急な転勤や家族構成の変化など、ライフプランも考慮した上で購入を決定することが重要です。 これは、環境に良い車を長く使ってもらうための「約束」だと考えましょう。
【最終結論】新型アウトランダーPHEVのリアルな乗り出し総額はいくら?
さて、長くなりましたが、いよいよ最終結論です。 これまで解説してきた車両価格、諸費用、充電設備費用、そして各種補助金をすべて考慮して、新型アウトランダーPHEVのリアルな乗り出し総額がいくらになるのかを、具体的なパターンでシミュレーションしてみましょう。

引用 : 三菱HP (https://www.mitsubishi-motors.com/jp/newsroom/newsrelease/2021/20211216_1.html)
シミュレーションの前提条件
- 購入車両: 新型アウトランダーPHEV Gグレード(7人乗り)
- オプション: 電動パノラマサンルーフ
- 車両関連費用(諸費用込): 5,908,400円
- 補助金: 国の補助金、および東京都の補助金を例とします。
パターン1:自宅充電コンセント設置+国の補助金のみ
まずは、全国どこにお住まいの方でも実現可能な、最も基本的なパターンです。 V2Hは導入せず、シンプルな充電用コンセントを設置した場合のシミュレーションです。
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 車両関連費用合計 | 5,908,400円 |
| 自宅充電設備費用 | 150,000円 |
| 費用合計(補助金適用前) | 6,058,400円 |
| <適用される補助金> | |
| 国のCEV補助金 | -550,000円 |
| 補助金合計 | -550,000円 |
| 最終的な乗り出し総額 | 5,508,400円 |
このパターンでは、最終的な乗り出し総額は約551万円となりました。 車両本体価格(555万円)とほぼ同等の金額で、諸費用や充電設備まで含めて乗り出せる計算になります。
パターン2:V2H導入+国と東京都の補助金をフル活用
次に、東京都にお住まいの方が、V2Hを導入し、利用できる補助金を最大限に活用した場合のシミュレーションです。 このケースが、最もアウトランダーPHEVの価値と恩恵を引き出せるパターンと言えるでしょう。
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 車両関連費用合計 | 5,908,400円 |
| V2H設備費用 | 800,000円 |
| 費用合計(補助金適用前) | 6,708,400円 |
| <適用される補助金> | |
| 国のCEV補助金(車両) | -550,000円 |
| 国のCEV補助金(V2H設備) | -500,000円(設備費1/2+工事費上限の例) |
| 東京都の補助金(車両+V2H) | -600,000円 |
| 補助金合計 | -1,650,000円 |
| 最終的な乗り出し総額 | 5,058,400円 |
驚くべき結果が出ました。 補助金をフル活用することで、最終的な乗り出し総額は約506万円にまで下がりました。 V2Hという高価な設備を導入したにもかかわらず、パターン1よりも安くなっています。 これは、V2H導入に対する手厚い補助金があるためです。 災害時の安心というプライスレスな価値を手に入れつつ、乗り出し総額も抑えられる、まさに一石二鳥の選択肢と言えます。
噂は本当?アウトランダーPHEVは本当に「高い」のか
シミュレーション結果からも分かる通り、「アウトランダーPHEVは高い」という噂は、表面的な車両価格だけを見た場合の印象に過ぎません。 補助金制度を正しく理解し、賢く活用すれば、同クラスのガソリンSUVと比較しても、十分に競争力のある価格、あるいはそれ以上に価値のある価格で手に入れることが可能です。
さらに、購入後のランニングコスト(燃料代や税金)を考慮すれば、その差はさらに縮まっていきます。 静かで力強い唯一無二の走り、災害時の安心感、環境への貢献といったPHEVならではの付加価値を考えれば、そのコストパフォーマンスは非常に高いと、私はジャーナリストとして、そして一人のオーナーとして断言できます。
まとめ
今回のレビューでは、新型アウトランダーPHEVの購入を検討する上で最も気になる「総額費用」について、車両価格、諸費用、充電設備、そして複雑な補助金制度まで、徹底的に掘り下げて解説しました。
- **車両価格だけで判断は禁物。 諸費用やオプション、充電設備費用を含めた総額で考えることが重要。 **
- **CEV補助金は購入価格を大きく引き下げる鍵。 国の補助金(55万円)に加えて、お住まいの自治体の補助金制度を必ず確認すること。 **
- **V2Hは初期費用こそかかるものの、手厚い補助金と災害時の安心、日々の電気代節約という大きなメリットがある未来への投資。 **
- **補助金を最大限に活用すれば、乗り出し総額は500万円台前半、場合によっては500万円を切ることも夢ではない。 **
アウトランダーPHEVの購入は、単に「車を買う」という行為以上の意味を持ちます。 それは、新しいカーライフ、エネルギーとの付き合い方、そして万が一への備えを手に入れるということです。 この記事が、あなたの賢い車選びの一助となれば幸いです。 ぜひ、お近くの販売店で実際に試乗し、その素晴らしい走りと価値を体感してみてください。