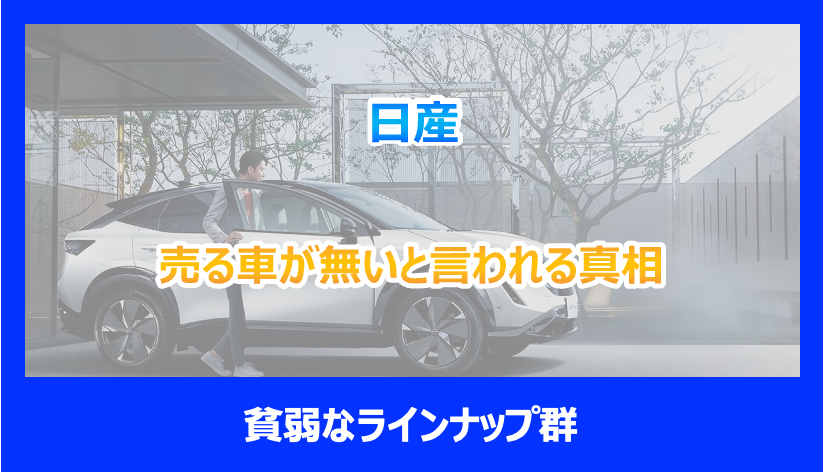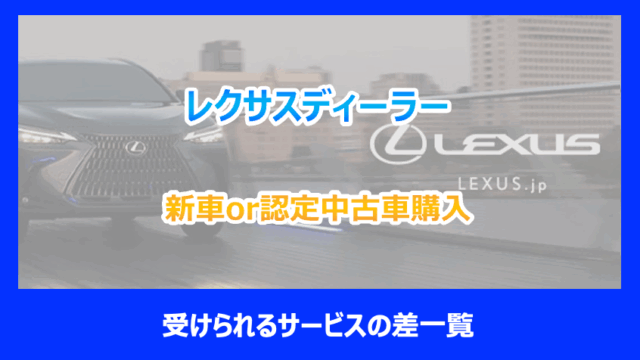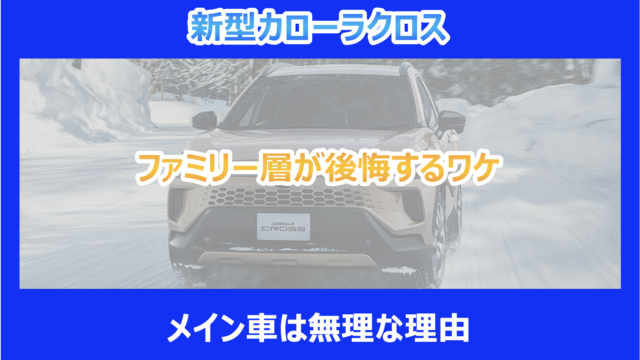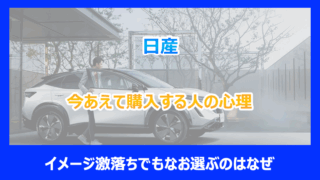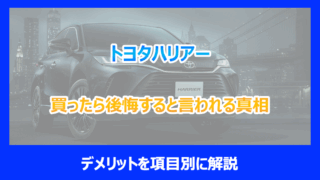モータージャーナリスト兼コラムニストの二階堂仁です。今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、新車選びで日産のディーラーを訪れた際に「思ったより選べる車が少ないな」と感じたり、「なぜ日産はこんなに車種が減ってしまったのだろう?」という疑問をお持ちなのではないでしょうか。
私も複数の日産車を所有し、長年その動向を追いかけてきた者として、その気持ちは痛いほどよくわかります。

引用 : 日産公式HP (https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/ariya-details/interior.html)
この記事を読み終える頃には、なぜ「日産には売る車がない」と言われるようになってしまったのか、その背景と今後の展望についての疑問が解決しているはずです。
記事のポイント
- 日産に売る車がないと言われる構造的な問題
- 車種削減に至った歴史的経緯と経営判断
- ライバル他社と比較したラインナップの現状
- 今後の日産の新型車戦略と復活の可能性
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

日産に売る車がないと言われる深刻な理由
「日産には売る車がない」という言葉は、単なるインターネット上の揶揄(やゆ)ではなく、日産の経営陣自身も認めるほど深刻な問題となっています。
なぜ、かつては「技術の日産」として数々の名車を生み出し、幅広いラインナップを誇っていたメーカーが、このような状況に陥ってしまったのでしょうか。その背景には、長年にわたる経営戦略や市場の変化が複雑に絡み合っています。

引用 : 日産公式HP (https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/ariya-details/interior.html)
経営陣も認める危機的な車種の少なさ
驚くべきことに、「売る車がない」という危機感は、ユーザーや評論家だけでなく、日産自動車のトップである内田誠社長自身が公の場で口にしている言葉です。2020年の株主総会で、株主からの「新型車が出てこない」という厳しい指摘に対し、「今、残念ながら我々のラインアップは、お客さまに十分満足いただける状況になっていない」「商品ラインアップの若返りができていない」と率直に認めました。
企業のトップが自社の製品ラインナップの弱さを認めるのは異例中の異例です。これは、問題が現場レベルではなく、経営の中枢が認識するほどの喫緊の課題であることを示しています。販売の最前線であるディーラーからは、「お客様に提案できる車が限られすぎている」「他社の豊富なラインナップを前にすると、勝負にならない」という悲痛な声が長年上がっていました。この声がようやく経営トップに届き、公の場で認めざるを得ない状況になったと言えるでしょう。
かつての栄光と車種削減の歴史

引用 : 日産HP (https://history.nissan.co.jp/ELGRAND/E52/1008/)
今の若い方には信じられないかもしれませんが、1990年代初頭のバブル期、日産は現在のトヨタに匹敵するほどのフルラインナップを誇っていました。
- 高級セダン: プレジデント、インフィニティQ45、シーマ、セドリック/グロリア、ローレル、セフィーロ、レパード
- スポーツカー: スカイラインGT-R、フェアレディZ、シルビア/180SX
- ミドルクラス: ブルーバード、プリメーラ
- コンパクトカー: サニー、パルサー、マーチ
- SUV/クロカン: サファリ、テラノ
- ミニバン: ラルゴ、セレナ
上記はほんの一例で、実際にはさらに多くの派生車種や商用車が存在し、まさに「ない車はない」と言えるほどの充実ぶりでした。しかし、バブル崩壊後の経営不振により、1999年にフランスのルノーと資本提携。カルロス・ゴーン氏の指揮のもと、「日産リバイバルプラン」が断行されました。
この再建計画は、工場の閉鎖や人員削減といった痛みを伴うものでしたが、その中核にあったのが「選択と集中」です。不採算車種を大胆に整理・統合し、経営資源を売れ筋の車種や将来性のある分野に集中させる戦略でした。この結果、多くの伝統ある車名が姿を消し、日産のラインナップは急激に縮小していきました。
ゴーン体制下で断行された「選択と集中」戦略
カルロス・ゴーン氏が推し進めた「選択と集中」戦略は、短期的には日産のV字回復に大きく貢献しました。しかし、その一方で、長期的なブランドイメージの構築や、多様な顧客ニーズへの対応という点では、負の側面も大きかったと言わざるを得ません。
利益至上主義がもたらした車種の画一化
ゴーン体制下では、プラットフォーム(車台)や部品の共通化が徹底的に推し進められました。これはコスト削減には絶大な効果を発揮しましたが、同時に車種ごとの個性を希薄化させる結果を招きました。特に、アライアンスを組むルノーとのプラットフォーム共通化は、日本の道路事情やユーザーの嗜好とは必ずしも合致しない、大柄で画一的なデザインの車を増やすことにつながりました。
かつての日産は、プリメーラのように欧州車を彷彿とさせる走りにこだわったセダンや、パイクカーシリーズ(Be-1、パオ、フィガロ)のような遊び心あふれるモデルを市場に問い、多様な価値観を提示するメーカーでした。しかし、利益効率を最優先するあまり、そうした「尖った」モデルは姿を消し、最大公約数的な、悪く言えば「無難な」車ばかりが残ってしまったのです。
ルノーとのアライアンスが与えた深刻な影響
ルノーとのアライアンスは、経営危機に瀕した日産を救った一方で、今日のラインナップの貧弱さに直結する大きな影響を及ぼしました。特に問題となったのが、商品開発における主導権の問題です。
アライアンスの規模が拡大するにつれ、日産、ルノー、そして後に加わった三菱自動車の間で、開発する車種の地域やセグメントを分担するようになりました。この中で、日本市場の優先順位が相対的に低下してしまったことは否めません。
例えば、欧州で人気の高いコンパクトカーやCセグメントのハッチバックなどはルノーが主導権を握り、日産は北米や中国市場で需要の大きいSUVや大型セダンに開発リソースを割く、といった棲み分けが進みました。その結果、日本のユーザーが最も求める「5ナンバーサイズのコンパクトカー」や「手頃な価格のセダン」といった、かつて日産が得意としていたカテゴリーが手薄になってしまったのです。
現在販売されているノート オーラは3ナンバーサイズであり、純粋な5ナンバーサイズの量販コンパクトカーは、日産のラインナップから消滅してしまいました。これは、アライアンスのグローバル戦略の中で、日本市場の特殊性がないがしろにされた結果と言えるでしょう。
国内市場の軽視と海外市場への過度な注力
ゴーン体制以降の日産は、明らかに北米や中国といった巨大市場を最優先してきました。世界販売台数を伸ばし、利益を最大化するためには、これらの市場で売れる大型のSUVやピックアップトラック、高級セダンに注力するのが最も効率的だったからです。
その結果、日本国内の市場は「軽自動車とミニバン、コンパクトカー」が販売の主流であるにもかかわらず、日産はこれらのカテゴリーで他社に対抗できる新型車を長らく投入できませんでした。
- 軽自動車: 三菱自動車との合弁会社NMKVが設立されるまで、スズキやダイハツからのOEM(相手先ブランドによる生産)に頼りきりで、自社開発の魅力的なモデルを失っていました。
- コンパクトカー: ヴィッツ(現ヤリス)やフィットといった強力なライバルがモデルチェンジを重ねる中、マーチは基本的な設計を変えないまま10年以上も放置されました。
- ミニバン: セレナはe-POWERの投入で一時的に人気を取り戻しましたが、トヨタのアルファード/ヴェルファイアのような高級路線や、ホンダのステップワゴンのような独自の価値を持つモデルがなく、選択肢の幅で劣ります。
国内市場を軽視したツケは、販売台数の低迷という形で明確に表れています。最盛期にはトヨタに次ぐ国内2位の座を確固たるものにしていた日産ですが、現在ではホンダやスズキ、ダイハツにも抜かれ、指定席だった3位の座すら危うい状況です。
他社と比較してわかるラインナップの現状
口で「少ない」と言うのは簡単ですが、実際に国内の主要メーカーとラインナップを比較すると、その差は歴然です。ここでは、2025年現在の各社の乗用車(軽自動車、商用車を除く)のラインナップを比較してみましょう。
| メーカー | セダン | コンパクト | ミニバン | SUV | スポーツ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 28 |
| ホンダ | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 |
| 日産 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| マツダ | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 |
| スバル | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
※上記は2025年8月時点の各社ウェブサイトを参考に筆者が作成した概算です。モデルの分類は筆者の見解に基づきます。
この表を見れば、日産のラインナップがいかに少ないかが一目瞭然です。特に、かつてのお家芸であったセダンは、スカイライン1車種のみという寂しい状況です。国内で最も販売台数の多いトヨタと比較すると、その差は約3倍。これでは、ディーラーを訪れた顧客が「選ぶ楽しみ」を感じられないのも無理はありません。
顧客が「セダンが欲しい」と思っても、日産では実質的にスカイラインしか選択肢がありません。一方でトヨタのディーラーに行けば、クラウン、カムリ、カローラ、プリウス、MIRAI…と、サイズも価格もキャラクターも異なる様々なセダンから選ぶことができます。この「選択肢の幅」こそが、現在のトヨタの強さの源泉であり、日産が最も失ってしまったものなのです。
販売現場から聞こえる悲痛な声
ラインナップの貧弱さで最も苦しんでいるのは、日々顧客と接する販売の最前線、ディーラーの営業スタッフです。
「お客様が来店されても、自信を持って勧められる車が本当に少ないんです。例えば、トヨタのカローラクロスやヤリスクロスのような、手頃なサイズのSUVが欲しいと言われても、日産にはキックスしかありません。しかもキックスはe-POWERのみで、価格帯も少し高め。もっとシンプルなガソリン車や、4WDの選択肢があれば…と思う場面は数えきれません」
あるベテラン営業スタッフは、そう言ってため息をつきます。
「昔は、お客様の家族構成やライフスタイルに合わせて、『それでしたら、プリメーラがおすすめです』とか『いや、奥様も運転されるならサニーが良いですよ』といったように、様々な提案ができました。今は、軽自動車か、ノートか、セレナか、SUVか…という非常に限られた選択肢の中から、お客様に何とか当てはめてもらうような営業しかできない。これは本当に辛いですよ」
このような状況は、営業スタッフのモチベーション低下に直結し、結果として販売力の低下を招きます。優秀な人材が他メーカーのディーラーに流出するケースも少なくないと聞きます。まさに負のスパイラルに陥っているのです。
ユーザーが感じる選択肢の乏しさ
最終的に、ラインナップの少なさはユーザーの「日産離れ」を加速させます。

引用 : 日産HP (https://history.nissan.co.jp/ELGRAND/E52/1008/)
長年、セドリックやローレルといった日産のセダンを乗り継いできたという年配の男性は、こう語ります。 「スカイラインはスポーティーすぎるし、もう他に乗りたいと思えるセダンが日産にはない。仕方ないから、次の車はクラウンにでもしようかと考えているよ」
また、初めてのマイカー購入を検討している若い女性は、 「日産のデザインは好きだけど、コンパクトカーはノートかマーチ(当時)しかなくて、しかもマーチは古すぎる。ホンダのフィットやトヨタのヤリスみたいに、もっと色々なデザインやグレードから選びたかった」 と話します。
このように、特定のカテゴリーに乗りたいと思っても、日産にはその受け皿となる車種が存在しない、あるいは存在してもモデルが古く、ライバル車に見劣りするといったケースが多発しています。一度他メーカーに乗り換えたユーザーを取り戻すのは、容易なことではありません。ブランドへの忠誠心が高かったかつてのファンでさえも、乗りたい車がなければ、他社を選ばざるを得ないのです。
日産の現状と待たれる今後の展望
厳しい状況が続く日産ですが、未来が完全に閉ざされているわけではありません。経営陣もようやく危機感を共有し、ラインナップの再構築に向けて動き出しています。ここでは、日産が抱える課題と、今後の復活に向けた展望について掘り下げていきます。

引用 : 日産公式HP (https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/ariya-details/interior.html)
新型車投入の遅れとその深刻な背景
近年、日産の新型車投入のペースが著しく遅いことは、多くの人が感じているでしょう。その最大の原因は、ゴーン体制の末期から逮捕後の混乱期にかけて、次世代車の開発が停滞してしまったことにあります。
新車の開発には、通常3年から5年という長い歳月が必要です。つまり、現在のラインナップの古さは、数年前の経営判断の誤りや、開発リソースの不足が今になって表面化している結果なのです。
さらに、CASE(Connected, Autonomous, Shared, Electric)と呼ばれる自動車業界の大変革期において、日産はEV(電気自動車)や自動運転技術といった先進分野への投資を優先せざるを得ませんでした。その結果、既存のエンジン車のモデルチェンジにまで手が回らなかった、という側面もあります。しかし、市場の大部分は依然としてエンジン車が占めており、その商品力を疎かにしたことは、販売不振に直結する大きな失策でした。
EVシフトへの過集中とe-POWER戦略の功罪
日産は、世界に先駆けて量産EV「リーフ」を発売するなど、電動化のパイオニアとしての自負があります。その先進性は高く評価されるべきですが、一方でEVへの過度な集中が、ラインナップ全体のバランスを崩したことも事実です。
e-POWERは諸刃の剣か
エンジンで発電し、モーターだけで走行する日産独自の電動パワートレイン「e-POWER」は、その滑らかで力強い走りから高い評価を得ています。ノートやセレナ、キックスといった主力車種に搭載され、販売を牽引する存在となりました。
しかし、e-POWERに注力するあまり、他のパワートレインの開発が疎かになってしまった感は否めません。例えば、トヨタがハイブリッドシステム(THS)を軸に、通常のガソリンエンジン、ディーゼル、PHEV、EV、そして水素エンジンまで、全方位で開発を進める「マルチパスウェイ」戦略を採っているのに対し、日産は「e-POWERとEV」という二択に絞り込みすぎています。
これにより、「シンプルな構造で価格の安いガソリン車が欲しい」「長距離を走るので燃費の良いディーゼルが欲しい」といったユーザーのニーズに応えられなくなっています。e-POWERは素晴らしい技術ですが、それが唯一の選択肢になってしまうと、かえって顧客を遠ざける結果にもなりかねないのです。
アリア、サクラに続く次世代EVへの期待
暗い話題が続きましたが、希望の光もあります。それが、新世代のEVです。
クロスオーバーEVの「アリア」は、その先進的なデザインと高い走行性能で、世界的に高い評価を受けています。また、軽自動車のEV「サクラ」は、日本の道路事情にマッチしたサイズ感と、EVならではの静粛性・加速性能、そして補助金を含めた価格の手頃さから、大ヒットを記録しました。
これらの成功は、日産がEV開発において依然として高い技術力を持っていることを証明しました。特にサクラの成功は、「日本の市場に合った商品を投入すれば、必ず売れる」ということを社内外に示し、今後の国内向け商品開発に弾みをつけるきっかけになるはずです。
注目される新型車投入計画「Nissan Ambition 2030」
日産は、2021年に長期ビジョン「Nissan Ambition 2030」を発表しました。この中で、2030年度までに27車種の電動車(うち19車種がEV)を投入するという、非常に野心的な計画を打ち出しています。
この計画が順調に進めば、今後数年間で日産のラインナップは劇的に若返り、拡充されることになります。すでに、海外では新型のSUVやセダンが発表されており、それらが日本市場に導入されることも期待されます。
重要なのは、単に車種の数を増やすだけでなく、それぞれのカテゴリーで競争力のあるモデルを投入できるか、そして日本のユーザーの心に響くような、日産らしい魅力を持った車を生み出せるかです。
具体的に期待される新型車
具体的な車種名はまだ公表されていませんが、市場からは以下のようなモデルの登場が期待されています。
- 新型コンパクトSUV: キックスよりも一回り小さい、トヨタ・ヤリスクロス/ライズの対抗馬。
- 新型ミドルサイズミニバン: セレナとエルグランドの中間を埋める、トヨタ・ノア/ヴォクシーの直接的なライバル。
- 新型コンパクトカー: ノートよりも手頃な価格帯の、5ナンバーサイズのコンパクトカー。マーチの後継車。
- 新型スポーツセダン: スカイラインの次期モデル、あるいはそれに代わる新たなFRセダン。
これらの「空白地帯」となっているセグメントに魅力的な新型車を投入できれば、日産が復活への狼煙(のろし)を上げることは十分に可能です。
往年の名車復活の可能性とファンの期待
日産には、シルビア、180SX、パルサーGTI-R、ローレルなど、今なお多くのファンに愛される往年の名車が数多く存在します。ラインナップが縮小し、魅力的な車が減った今だからこそ、これらの車名の復活を望む声は日に日に高まっています。
もちろん、現代の安全基準や環境規制の中で、かつてのような車をそのまま復活させることは不可能です。しかし、その名前が持つ歴史やスピリットを現代的に解釈し、EVやe-POWERといった新しい技術と融合させることで、全く新しい魅力を持った車として蘇らせることはできるはずです。
トヨタがスープラや86(GR86)を復活させて成功を収めたように、ブランドの歴史的資産(ヘリテージ)を活かすことは、ファンの心を再び掴むための有効な手段です。日産がそうしたファンの期待にどう応えていくのか、注目が集まります。
国内販売網の再構築とディーラーの役割
どれだけ良い車を作っても、それを顧客に届け、販売し、アフターサービスを提供する販売網が脆弱では意味がありません。ラインナップの縮小は、ディーラーの経営を直撃し、店舗数の減少やサービスの質の低下を招く恐れがあります。
今後は、単に車を売る場所としてだけでなく、EVの充電ステーションや、カーシェアリングの拠点、地域住民のコミュニティスペースといった、新たな役割をディーラーが担っていく必要があります。
また、オンラインでの商談や購入プロセスのデジタル化を進め、顧客との新しい接点を構築していくことも重要です。魅力的な新型車と、信頼できる販売・サービス体制。この両輪が揃って初めて、日産は真の復活を遂げることができるでしょう。
これから日産が巻き返すための最重要課題
日産が再び国内市場で輝きを取り戻すためには、いくつかの重要な課題をクリアする必要があります。
第一に、日本市場のニーズを徹底的にリサーチし、それに合致した商品を開発すること。 アライアンスのグローバル戦略も重要ですが、国内のユーザーが何を求めているのかを最優先に考える姿勢が不可欠です。サクラの成功は、その最良の証明と言えるでしょう。
第二に、意思決定のスピードを上げ、開発から市場投入までの期間を短縮すること。 市場のトレンドが目まぐるしく変化する現代において、数年前に企画された車では、発売時には時代遅れになりかねません。
そして第三に、「技術の日産」のブランドイメージを再構築すること。 e-POWERやプロパイロット、そしてEV技術など、日産には他社に誇れる優れた技術が数多くあります。これらの技術を、ユーザーが「欲しい」と思える魅力的なデザインやパッケージングの車に搭載し、その価値を分かりやすく伝えていくことが求められます。
道のりは決して平坦ではありませんが、日産には90年以上の歴史の中で培ってきた技術力と、数々の困難を乗り越えてきた底力があります。そのポテンシャルを最大限に発揮できれば、再び日本の自動車市場をリードする存在になることも夢ではないはずです。
まとめ
今回は、「日産には売る車がない」と言われる理由について、歴史的な経緯から現状の課題、そして未来への展望までを詳しく掘り下げてきました。
その原因は、決して単純なものではなく、過去の経営判断、アライアンス戦略、市場の変化といった様々な要因が複雑に絡み合った結果であることがお分かりいただけたかと思います。長年にわたる車種削減と国内市場の軽視が、現在の危機的なラインナップの貧弱さを招いてしまいました。
しかし、サクラやアリアといった成功事例も生まれており、長期ビジョン「Nissan Ambition 2030」のもとで、多くの新型車が計画されています。販売現場や長年のファンからは厳しい声が上がっていますが、それは裏を返せば、今なお日産に大きな期待を寄せている人が多いということの証明でもあります。
かつてのフルラインナップメーカーへの回帰は現実的ではありませんが、日本のユーザーの心に響く、日産らしい「尖った」魅力的な車を再び市場に送り出すことができれば、復活の道は必ず開けるはずです。一人の自動車ジャーナリストとして、そして一人の日産車オーナーとして、今後の日産の動向を注意深く、そして期待を込めて見守っていきたいと思います。