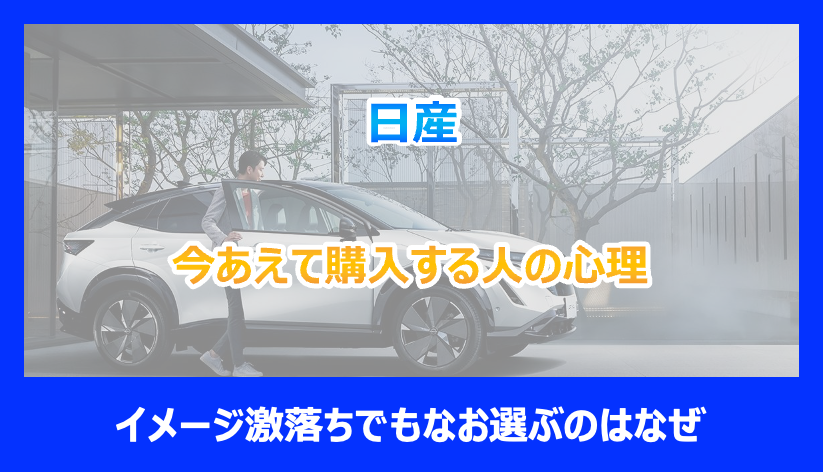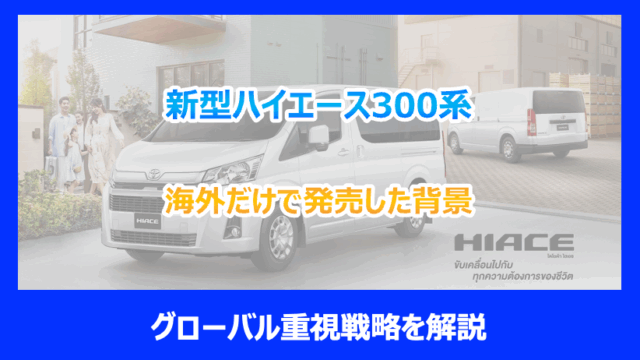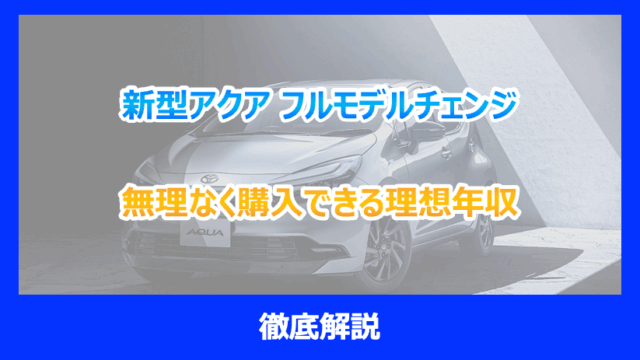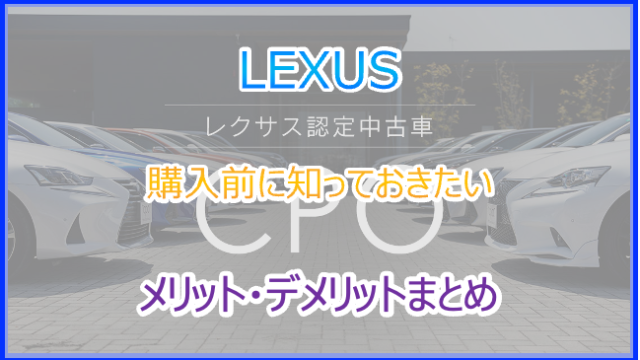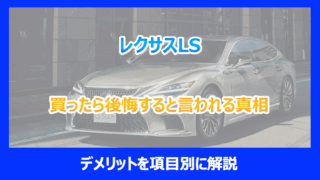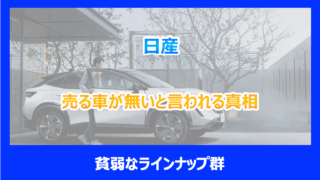モータージャーナリスト兼コラムニストの二階堂仁です。今回も多く寄せられてる質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、「最近の日産車ってどうなんだろう?」「周りからはあまり良い話を聞かないけど、それでも買う人はなぜ買うんだろう?」という点が気になっていると思います。
私自身も仕事柄、そしてプライベートでも複数の日産車を所有し、その変遷を肌で感じてきたので、その気になる気持ちはよくわかります。

引用 : 日産公式HP (https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/ariya-details/interior.html)
この記事を読み終える頃には、なぜ今あえて日産車が選ばれるのか、その深層心理と合理的な理由についての疑問が解決しているはずです。
記事のポイント
- ブランドイメージ低下の歴史的背景
- 日産を選ぶユーザーの多角的な購入動機
- 他社にはない日産独自の先進技術の魅力
- イメージに惑わされない本質的なクルマ選び
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

なぜ日産車のイメージはここまで落ちたのか?その歴史的背景と要因
「やっちゃえNISSAN」という挑戦的なキャッチコピーとは裏腹に、世間からは厳しい目を向けられることが少なくないのが、昨今の日産自動車の姿かもしれません。私の元にも「日産だけは無いかな…」「人におすすめしにくい」といった声が届くことは一度や二度ではありません。

引用 : 日産公式HP (https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/ariya-details/interior.html)
新車選びの土俵にすら上がらない、という方もいるでしょう。では、なぜ「技術の日産」とまで言われたブランドが、ここまでイメージを落としてしまったのでしょうか。まずはその要因を、ジャーナリストとして客観的に、そして時系列に沿って深掘りしていきましょう。
経営の混乱と立て続けに起きた不祥事のインパクト
日産のブランドイメージに最も大きな打撃を与えたのは、間違いなく1990年代後半からの経営危機と、その後のカルロス・ゴーン氏を巡る一連の騒動でしょう。
V字回復の光と影
1999年、巨額の有利子負債を抱え倒産寸前だった日産は、仏ルノーと資本提携を結び、COOとして送り込まれたゴーン氏による大胆なリストラ策「日産リバイバルプラン」によって奇跡的なV字回復を遂げました。この時期、「コストカッター」としての辣腕は世界中から賞賛され、日産復活の象徴として神格化されたと言っても過言ではありません。
しかし、その後の長期政権化と、2018年に発覚した金融商品取引法違反容疑での逮捕、そして翌年の国外逃亡という前代未聞の事件は、日産のブランドイメージを根底から揺るがしました。企業のトップがこのような形でメディアを騒がせたことは、ユーザーに対して「コンプライアンス意識の低い会社」「内紛ばかりしている会社」という強烈なネガティブイメージを植え付けたのです。
信頼を失墜させた品質問題
追い打ちをかけたのが、2017年に発覚した「完成検査不正問題」です。これは、無資格の従業員が新車の最終検査を行っていたというもので、ユーザーの安全・安心に対する信頼を根底から覆す大問題でした。大規模なリコールに発展し、「技術の日産」という看板を自ら汚す結果となったのです。
これらの不祥事は、クルマそのものの性能とは直接関係ない部分ではありますが、企業としての姿勢、すなわち「この会社を信用して大金を払い、命を預けることができるのか?」という根本的な問いに対して、多くのユーザーが疑念を抱くきっかけとなってしまいました。
長期的なモデルチェンジの停滞とヒット車種の不在
ゴーン体制下でのコストカットは、短期的な収益改善には繋がりましたが、長期的な視点で見れば、新技術や新型車への開発投資が抑制されるという副作用も生み出しました。その結果、多くの車種がモデルライフの長期化を余儀なくされたのです。
例えば、かつて一世を風靡したミニバンの「エルグランド」や、コンパクトカーの「マーチ」、セダンの「ティアナ」などは、ライバルが次々と魅了的な新型車を投入する中で、長期間フルモデルチェンジが行われず、商品としての鮮度を失っていきました。
もちろん、その間にも「ノート e-POWER」のような大ヒット作は生まれましたが、全体として見れば、ラインナップの陳腐化は否めず、「日産には欲しいクルマがない」と感じるユーザーが増えてしまったのです。これは、販売台数の低迷に直結し、ブランドの勢いを失わせる大きな要因となりました。
「技術の日産」神話の崩壊とブランドイメージの迷走
かつての日産には、「技術の日産」という確固たるブランドイメージがありました。直列6気筒のRBエンジン、4輪操舵システムのHICAS、電子制御トルクスプリット4WDのアテーサE-TSなど、レースシーンで磨かれた革新的な技術を市販車にフィードバックし、多くのクルマ好きを熱狂させてきました。スカイラインGT-Rはその最たる例でしょう。
しかし、時代の変化とともに、そうした突出した技術的なアイコンが希薄になっていきました。もちろん、e-POWERやプロパイロットといった優れた技術は現代の日産にも存在します。しかし、かつての「技術の日産」が持っていたような、ある種の”尖った”イメージや”憧れ”といった情緒的な価値が薄れてしまった感は否めません。
ブランドイメージがやや大衆的、ファミリー向けにシフトしていく中で、かつてのファン層が離れ、同時に新しいファン層を確固として掴みきれなかった、という側面もあるでしょう。
強力すぎるライバルメーカーの躍進
国内市場に目を向ければ、トヨタ自動車という絶対的な巨人の存在があります。全方位に隙のないラインナップ、圧倒的な販売網、そして「壊れない」という絶大な信頼感。この牙城を崩すのは容易ではありません。

引用 : 日産HP (https://history.nissan.co.jp/ELGRAND/E52/1008/)
さらに、近年ではホンダの個性的なクルマづくりや、マツダの魂動デザインとディーゼルエンジン戦略、スバルのAWD技術とアイサイトなど、他社がそれぞれ明確な強みを打ち出してブランド価値を高めています。
こうした中で、日産の立ち位置がやや曖昧に見えてしまった時期があったことは事実です。他社が明確な”色”を打ち出す中で、日産のユニークな魅力がユーザーに伝わりにくくなっていたのかもしれません。
ディーラー網の課題と顧客満足度の低下
クルマは購入して終わりではなく、その後のメンテナンスやアフターサービスが非常に重要です。ディーラー(販売店)との付き合いは、ユーザーの満足度を大きく左右します。
日産のディーラー網は、一部で店舗数の減少やサービスの質のばらつきが指摘されることがあります。もちろん、これは全ての店舗に当てはまるわけではなく、素晴らしいサービスを提供している店舗も数多く存在します。しかし、一部のユーザーが経験したネガティブな体験が、インターネットを通じて拡散されやすい時代です。
「対応が悪かった」「修理代が高かった」といった声がブランド全体のイメージダウンに繋がってしまうケースも少なくありません。
中古車市場におけるリセールバリューの問題
クルマを資産として考えた場合、数年後にいくらで売れるかという「リセールバリュー」は非常に重要な指標です。残念ながら、一部の人気車種を除き、日産車はトヨタ車などと比較してリセールバリューが低い傾向にある、というのが中古車市場の一般的な認識です。
これは、新車販売時の値引き率の高さや、ブランドイメージ、中古車市場での需要と供給のバランスなどが複合的に絡み合った結果です。購入時の価格が魅力的であっても、売却時の価格が低いとなれば、トータルコストで見たときに損をしてしまう可能性があります。こうした現実的な問題が、新車購入時の選択肢から日産を外す一因となっていることは否定できません。
ネットやSNSでのネガティブな口コミの拡散
現代において、インターネット上の口コミや評判は、購買行動に絶大な影響を与えます。前述したような不祥事や品質問題、ディーラー対応などに関するネガティブな情報は、SNSなどを通じて瞬く間に拡散され、増幅される傾向にあります。
一度定着してしまった「日産は壊れやすい」「日産は対応が悪い」といったイメージは、たとえそれが一部の事象や過去の話であったとしても、なかなか払拭することができません。こうしたデジタルの世界に刻まれた負の遺産が、新規顧客の獲得における高いハードルとなっているのです。
若者世代のクルマ離れと日産ブランドの高齢化
これは日産に限った話ではありませんが、若者世代のクルマ離れは自動車業界全体の課題です。そうした中で、かつての「シルビア」や「180SX」のように、若者が憧れるような手頃な価格のスポーツカーが日産のラインナップから消えて久しいという現実があります。

引用 : 日産公式HP (https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/ariya-details/interior.html)
フェアレディZやGT-Rは存在しますが、これらはもはや若者が気軽に手を出せる価格帯ではありません。結果として、日産の主な顧客層は中高年層が中心となり、ブランドイメージの若返りが進まないという課題を抱えています。
それでも今、あえて日産車を選ぶ人たちの心理と合理的理由
さて、ここまで日産が抱えるネガティブな側面を徹底的に分析してきました。これだけ見ると、「やはり日産車を選ぶ理由はないのでは?」と感じるかもしれません。しかし、現実に日産車を選び、満足してカーライフを送っているユーザーは数多く存在します。私自身もその一人です。
彼らは、単に情報を知らない「情弱」なのでしょうか?あるいは、昔からの付き合いで仕方なく選んでいるのでしょうか?答えは断じて「ノー」です。
ここからは、なぜ彼らが世間のイメージに惑わされず、あえて日産車を選ぶのか、その深層心理と極めて合理的な理由を、ジャーナリストの視点、そして一人のオーナーとしての視点から解き明かしていきます。
先進技術への純粋な魅力と「他とは違う」という体験価値
日産車を選ぶ最大の理由の一つ、それは「他社にはない独自の先進技術」の存在です。特に「e-POWER」と「プロパイロット」は、現代の日産を象徴する二大巨頭と言えるでしょう。
「e-POWER」がもたらす唯一無二のドライビング体験
e-POWERは、エンジンを発電にのみ使用し、100%モーターで駆動するシリーズハイブリッド方式です。これは、トヨタのTHS-II(シリーズパラレル方式)やホンダのe:HEV(基本はシリーズだが高速域はエンジン直結)とは全く異なるアプローチです。
このe-POWERがもたらす最大の魅力は、電気自動車(EV)そのものの滑らかで力強い加速フィールです。アクセルを踏んだ瞬間から最大トルクが立ち上がるモーター駆動ならではのレスポンスは、従来のガソリン車や多くのハイブリッド車では味わえない感覚です。
特に、アクセルペダルの操作だけで加減速をコントロールできる「e-Pedal Step」は、一度慣れるとやめられない中毒性があります。市街地でのストップ&ゴーや、カーブが続くワインディングロードなどで、ペダルの踏み替え頻度が劇的に減り、運転の疲労を大幅に軽減してくれます。
これは単なる燃費技術ではなく、「運転の楽しさ」「移動の快適さ」という体験価値を根本から変える発明なのです。この感覚を知ってしまったユーザーは、「次もe-POWERが良い」と指名買いするケースが非常に多いのが特徴です。
「プロパイロット2.0」が実現する未来の移動体験
高速道路での運転支援システム「プロパイロット」も、日産が他社に先駆けて実用化し、磨き上げてきた技術です。特に、スカイラインに搭載された「プロパイロット2.0」は、一定条件下で手放し運転(ハンズオフ)を可能にした、国内メーカー初の画期的なシステムです。
長距離ドライブにおけるドライバーの負担を劇的に軽減するこの技術は、一度体験するとその価値を誰もが認めるでしょう。高速道路の渋滞時など、精神的にも肉体的にも疲労が溜まるシーンで、システムが運転を高度に支援してくれる安心感は絶大です。
こうした「未来のクルマ」をいち早く体験できるという点に、強い価値を感じるユーザー層が確実に存在します。彼らは、ブランドイメージといった曖昧なものではなく、「この技術があるから日産を選ぶ」という、極めて明確で合理的な判断基準を持っているのです。
近年のデザインの復権と特定のモデルへの強い支持
一時期、デザインの迷走が指摘された日産ですが、ここ数年の新型車は、デザイン面で非常に高い評価を得ています。日本の伝統美を取り入れた新しいデザイン言語は、国内外で多くの賞賛を集めており、これが購入の決め手となるケースが増えています。

引用 : 日産HP (https://history.nissan.co.jp/ELGRAND/E52/1008/)
コンパクトカーの常識を変えた「ノート オーラ」
例えば、私の愛車でもある「ノート オーラ」は、その代表格です。ベースのノートから全幅を拡大し、専用のフロントグリルやフェンダー、そして高品質な内装を与えることで、コンパクトカーとは思えないほどのプレミアム感を演出しています。
ツイード調のファブリックや木目調パネル、そしてBOSEパーソナルプラスサウンドシステムといった装備は、明らかにクラスを超えたものです。「小さいけれど、上質なクルマに乗りたい」というニーズに完璧に応え、グッドデザイン大賞を受賞するなど、その価値は広く認められています。
SUV市場で存在感を放つ「エクストレイル」
新型エクストレイルも、デザインと技術が見事に融合した一台です。第2世代e-POWERと、電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載し、SUVに求められる悪路走破性と、オンロードでの快適な乗り心地をかつてないレベルで両立させています。
その内外装の質感も飛躍的に向上しました。特に、オプションで選択できるタンカラーのナッパレザーシートなどは、欧州のプレミアムSUVにも引けを取らない上質さを誇ります。こうした明確な商品力の高さが、イメージを覆し、多くのユーザーに選ばれています。
軽自動車の概念を覆したEV「サクラ」
軽自動車市場に投入されたEV「サクラ」は、まさにゲームチェンジャーとなりました。軽ならではの取り回しの良さに、EVならではの静粛性と力強い加速が加わり、これまでの軽自動車の常識を覆す上質な移動体験を提供します。
補助金を活用すれば、ガソリン車の上級グレードと遜色ない価格で購入できることもあり、大ヒットを記録。「日本カー・オブ・ザ・イヤー」を軽自動車として初めて受賞したことも、その完成度の高さを証明しています。
これらの車種に共通するのは、「このクルマだから欲しい」と思わせる、強い個性と商品力です。漠然と「日産だから」ではなく、「オーラが欲しい」「エクストレイルに乗りたい」という指名買いが増えているのが、近年の特徴です。
家族のための現実的な選択肢としてのコストパフォーマンス
ミニバンの「セレナ」や軽ハイトワゴンの「ルークス」などは、ファミリー層から根強い支持を受けています。これらの車種が選ばれる理由は、非常に現実的かつ合理的です。
ミニバン王者「セレナ」の強み
セレナは、ライバルであるトヨタの「ノア/ヴォクシー」やホンダの「ステップワゴン」としのぎを削る激戦区に身を置いています。その中でセレナが選ばれる理由は、独自の機能性とパッケージングにあります。
例えば、e-POWERによる静かでスムーズな走りは、同乗する家族、特に乗り物酔いしやすい子供にとって大きなメリットです。また、3列目シートの使い勝手や、多彩なシートアレンジ、そして運転支援技術プロパイロットの標準装備化など、家族での長距離移動を快適にするための工夫が随所に凝らされています。
ライバルと比較した場合の価格設定や装備内容も、非常に競争力があります。
| 車種 | ハイブリッドモデル最安価格(参考) | 特徴的な機能 |
|---|---|---|
| 日産 セレナ e-POWER | 約319万円〜 | e-POWER、プロパイロット、酔いにくい走行性能 |
| トヨタ ノア/ヴォクシー | 約305万円〜 | 圧倒的な販売台数、リセールバリュー、先進安全装備 |
| ホンダ ステップワゴン e:HEV | 約338万円〜 | クラス最大の室内空間、視界の良さ、わくわくゲート |
※価格はグレードや時期により変動します。
このように比較すると、セレナは独自の走行性能と先進機能を持ちながら、価格的にも十分検討の土台に乗る選択肢であることがわかります。家族の幸せを第一に考えたとき、セレナは非常に合理的な選択となるのです。
「昔からの日産ファン」という揺るぎないブランドロイヤリティ
どんなにブランドイメージが揺らごうとも、日産を愛し続ける熱心なファンが存在することも、日産を支える大きな力です。
彼らは、かつての「ハコスカ」や「ケンメリ」、そして歴代のGT-R、フェアレディZが築き上げてきた栄光の歴史を知っています。レースシーンでの活躍や、時代を切り拓いてきた革新的な技術に心を奪われ、日産というブランドそのものに愛着を持っているのです。
こうしたファンにとって、日産車を所有することは、単なる移動手段ではなく、自らのアイデンティティやライフスタイルを表現する行為でもあります。彼らは、一時的な業績の浮き沈みや世間の評判に左右されることなく、日産が持つ本質的な価値を信じ、応援し続けています。
新型フェアレディZが発表された際に、多くの往年のファンが歓喜し、こぞって注文したのがその良い例です。こうした揺るぎないロイヤリティを持つ顧客層の存在は、メーカーにとって何物にも代えがたい財産と言えるでしょう。
販売店の営業努力と築き上げられた人間関係
意外と見過ごされがちですが、クルマの購入において「誰から買うか」は非常に重要な要素です。長年にわたり同じディーラー、同じ営業担当者と付き合いがあり、信頼関係が構築されている場合、メーカーを変える(乗り換える)というのは、心理的なハードルがかなり高いものです。
「いつも良くしてくれる〇〇さんから買いたい」「この店なら、何かあったときに親身に対応してくれる」
こうした人間関係が、購入の決め手となるケースは決して少なくありません。特に地方都市など、地域コミュニティとの繋がりが強いエリアでは、この傾向は顕著です。日産の販売店が、地域に根ざした丁寧な営業活動を続けることで、顧客を繋ぎ止めているという側面も確実に存在するのです。
EV(電気自動車)のパイオニアとしての実績と期待
日産は、2010年に世界初の量産型EVである「リーフ」を発売した、EV市場の紛れもないパイオニアです。初代リーフから10年以上にわたって積み重ねてきたEVに関するデータとノウハウは、他社にはない大きなアドバンテージです。
この実績は、ユーザーに「EVなら日産」という安心感を与えます。バッテリーの信頼性や、全国のディーラーに設置された充電設備、そしてEVならではのトラブルに対応できる整備士の存在など、ソフトウェアとハードウェアの両面で、ユーザーをサポートする体制が整っています。
アリアやサクラといった新型EVの投入により、その先進性はさらに加速しています。また、EVを家庭用蓄電池として活用する「V2H(Vehicle to Home)」の提案など、クルマを単なる移動手段ではなく、エネルギーインフラの一部として捉える未来志向のビジョンも、先進的な考えを持つユーザー層に強くアピールしています。
「人と違うクルマに乗りたい」という天邪鬼な心理
これは少し情緒的な理由になりますが、非常に重要な購入動機の一つです。街中を見渡せば、トヨタ車、特にアルファードやプリウス、ヤリスクロスといった人気車種で溢れています。駐車場で自分のクルマを探すのに苦労する、という経験をしたことがある方もいるでしょう。
そうした状況の中で、「あえて王道を外したい」「人と違うクルマに乗ることで、自分の個性を表現したい」と考える層が一定数存在します。彼らにとって、日産車を選ぶことは、ある種の自己表現なのです。
販売台数でトップを走っていないからこそ、所有する喜びに繋がり、自分の選択に誇りを持てる。こうした天邪鬼(あまのじゃく)的な心理も、日産車が選ばれる一つの要因と言えるでしょう。私自身も、そうした気質が少なからずあることを認めざるを得ません。
海外での高い評価と国内評価の間に存在するギャップ
最後に指摘しておきたいのが、日本国内での評価と、海外での評価には大きなギャップがあるという事実です。
特に北米市場では、日産の高級車ブランド「インフィニティ」は、レクサスやアキュラと並ぶ日本のプレミアムブランドとして確固たる地位を築いています。また、SUVの「ローグ(日本のエクストレイル)」やピックアップトラックの「タイタン」などは、非常に高い評価を得て、販売台数も好調です。
グローバルな視点で見れば、日産は決して「イメージの悪い会社」ではなく、世界中の多くのユーザーから支持される、競争力のある自動車メーカーなのです。こうした海外での客観的な評価を知ることで、「日本の評価だけが全てではない」と判断し、安心して日産車を選ぶユーザーもいます。
まとめ
今回は、「今あえて日産車を購入する人たちの心理」という、非常に興味深いテーマについて深掘りしてきました。
レビューの前半で見たように、過去の不祥事や経営問題、そしてライバルの台頭によって、日産のブランドイメージが傷ついてきたことは紛れもない事実です。そのネガティブなイメージが、今なお多くの人の頭に残り、新車購入の選択肢から日産を外す要因となっているのでしょう。
しかし、その一方で、日産車を選ぶ人々は、決してイメージだけで判断しているのではありません。
- e-POWERやプロパイロットといった、他社にはない独自の先進技術がもたらす「体験価値」に魅力を感じている。
- ノート オーラやエクストレイルのように、近年飛躍的に向上したデザインと商品力を純粋に評価している。
- セレナを選ぶファミリー層のように、ライフスタイルに合わせた極めて合理的な判断を下している。
- EVのパイオニアとしての実績と将来性を信頼している。
- そして、歴史に裏打ちされたブランドへの愛着や、「人と違う」という価値観を大切にしている。
彼らは、世間の評判という”ノイズ”に惑わされることなく、製品そのものが持つ本質的な価値を冷静に見極めているのです。
自動車ジャーナリストとして様々なメーカーのクルマに触れる私から見ても、最近の日産車は、間違いなく面白い。そして、特定の価値観を持つ人にとっては、他のどのメーカーのクルマよりも輝いて見える「最高の選択肢」になり得ると断言できます。
もしあなたが、漠然としたイメージだけで日産車を敬遠しているのであれば、それは非常にもったいないことかもしれません。ぜひ一度、先入観を捨てて、最新の日産車に試乗してみてください。そこには、あなたが知らなかった新しい発見と、クルマ選びの新たな喜びが待っているはずです。