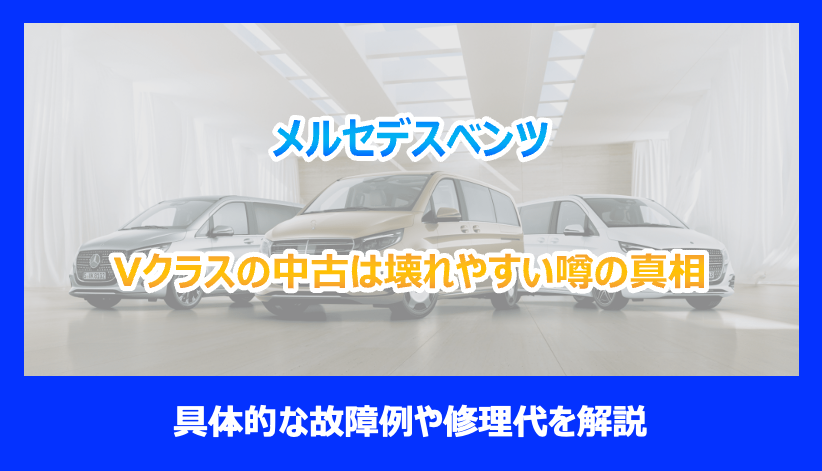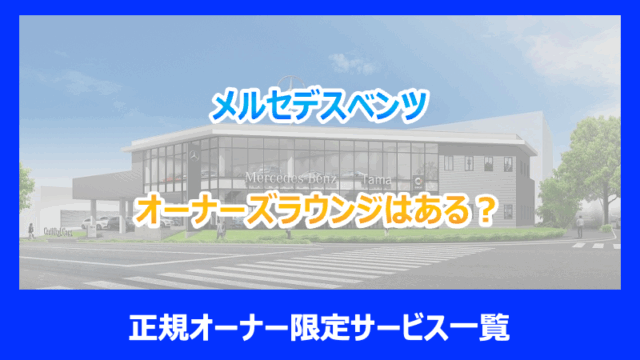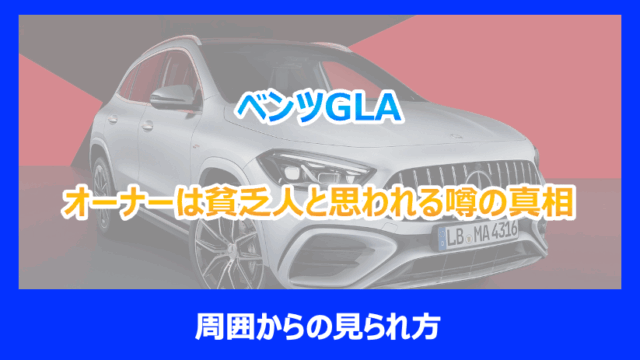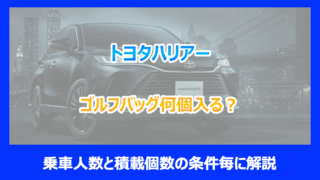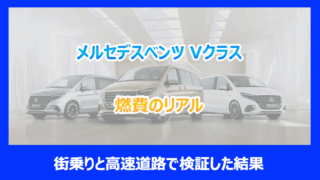モータージャーナリスト兼コラムニストの二階堂仁です。今回も多く寄せられている質問にお答えしていきます。
この記事を読んでいる方は、メルセデス・ベンツVクラスの購入を検討しているものの、「外車は壊れやすい」「特に中古のベンツは維持費がかかる」という噂を耳にして、一歩踏み出せずにいるのではないでしょうか。

引用 : メルセデス HP (https://www.mercedes-benz.co.jp/passengercars/models/van/v-class/overview.html)
私も実際に長年Vクラスを所有し、様々なトラブルを経験してきた一人なので、その気になる気持ちはよくわかります。しかし、その噂は果たして本当なのでしょうか。
この記事を読み終える頃には、中古Vクラスが「壊れやすい」という噂の真相と、安心して付き合っていくための具体的な知識が身についているはずです。
記事のポイント
- Vクラスが壊れやすいと言われる本当の理由
- 定番の故障箇所と具体的な修理費用
- 購入後に後悔しないための車両選びの秘訣
- 維持費を賢く抑えるプロのメンテナンス術
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

ベンツVクラスは本当に壊れやすいのか?噂の真相を徹底解説
まず結論からお伝えします。中古のベンツVクラスは「やみくもに壊れやすい」のではなく、「壊れる可能性のある箇所がある程度決まっている」車です。この事実を知っているか知らないかで、購入後の安心感と維持費は天と地ほどの差が生まれます。
国産のミニバンと同じ感覚で乗ろうとすると、「やっぱり壊れやすいじゃないか」と感じてしまうかもしれません。しかし、その背景にある理由を理解すれば、決して付き合いきれない車ではないのです。

引用 : メルセデス HP (https://www.mercedes-benz.co.jp/passengercars/models/van/v-class/overview.html)
なぜVクラスは「壊れやすい」と言われるのか?3つの理由
では、なぜ世間では「Vクラス=壊れやすい」というイメージが定着してしまったのでしょうか。長年この車と付き合ってきた私の経験から、主に3つの理由が考えられます。
1. 国産ミニバンとの設計思想・文化の違い
最大の理由は、日本の国産ミニバンとドイツのメルセデス・ベンツとでは、車の設計思想や文化が根本的に異なる点にあります。
日本のメーカーは、高温多湿な気候、ストップ&ゴーの多い交通環境、そしてユーザーの「壊れないこと」を最優先する価値観を前提に車を開発します。そのため、多少性能が劣っても、耐久性の高い部品を採用し、定期交換部品を極力減らす設計になっています。
一方、メルセデス・ベンツはアウトバーンでの高速巡航性能や安全性を最優先に考えます。部品は「性能を発揮し、寿命が来たら交換するもの」という消耗品(アッセンブリー)の思想が根付いています。ゴムや樹脂パーツも、日本の気候より乾燥した欧州大陸を基準に設計されているため、日本の高温多湿な環境では想定より早く劣化が進むことがあります。
この「壊れる前に定期的に交換する」という文化の違いが、日本のユーザーにとっては「予期せぬ故障」と映り、「壊れやすい」という評価に繋がっているのです。
2. 複雑な電子制御システムと先進装備
Vクラスは、メルセデスの名に恥じない豪華で先進的な装備が魅力です。電動スライドドア、電動テールゲート、先進安全支援システム(ADAS)、そして乗り心地を劇的に向上させるエアサスペンションなど、数多くの電子制御システムが搭載されています。
これらのシステムは快適性を飛躍的に高める一方で、国産車に比べて構造が複雑であり、故障のリスクポイントが増えることも事実です。特にセンサー類のトラブルは、警告灯の点灯に直結し、オーナーに不安を与えがちです。一つのセンサーの不具合が、クルーズコントロールやブレーキホールドといった他の機能まで停止させてしまうこともあり、それが「また壊れた」という印象を強めてしまいます。
3. 中古車市場での個体差の大きさ
新車価格が1,000万円近くにもなるVクラスですが、中古車になると価格がこなれ、幅広い層が購入を検討できるようになります。しかし、ここで注意が必要なのが「個体差」です。
前オーナーがメルセデス・ベンツの特性を理解し、正規ディーラーや専門工場で適切なメンテナンスを行ってきた車両と、オイル交換すらままならないような乗りっぱなしの車両とでは、コンディションに雲泥の差があります。特に中古車は、購入後のメンテナンス費用をケチった結果、トラブルが多発するケースが後を絶ちません。
このようなコンディションの悪い車両が市場に出回り、それを知らずに購入した人が「すぐに壊れた」とSNSなどで発信することで、「中古のVクラスは壊れやすい」という評判が再生産されてしまうのです。
Vクラスのモデル遍歴と故障リスク
Vクラスと一括りに言っても、世代によって信頼性や故障の傾向は大きく異なります。購入を検討する際は、それぞれのモデルの特徴を把握しておくことが重要です。
| モデル | 型式 | 販売期間 | 主な特徴と注意点 |
|---|---|---|---|
| 初代 Vクラス | W638 | 1998年~2003年 | FF駆動。比較的シンプルな構造だが、年式的に電気系統やゴム部品の劣化は避けられない。特にATのトラブルは修理費用が高額になりがち。今から乗るには相応の覚悟が必要。 |
| 2代目 Vクラス (ビアノ) | W639 | 2003年~2015年 | FR駆動に変更され、走行性能が大幅に向上。前期・中期・後期で改良が重ねられた。エアサスやスライドドアのトラブルが定番。後期モデルは比較的安定しているが、オルタネーターの故障は要注意。 |
| 3代目 Vクラス | W447 | 2015年~現在 | 現行モデル。2.2Lクリーンディーゼルエンジンが主力。先進安全装備が充実。AdBlue(アドブルー)システムやNOxセンサーなど、ディーゼル特有のトラブルが報告されている。電気系統は安定性が増したが、やはりエアサスはウィークポイント。 |
私の経験上、中古で狙うなら W639の後期モデル(2011年以降) や W447の前期モデル が、価格と信頼性のバランスが良い選択肢と言えるでしょう。ただし、どのモデルを選ぶにしても、後述するチェックポイントをしっかり確認することが大前提です。
【実例】ベンツVクラスでよくある故障箇所と修理代の目安
ここからは、皆さんが最も気になっているであろう、具体的な故障事例とその修理費用について、私の経験や専門工場からの情報を基に詳しく解説していきます。修理費用はあくまで目安であり、依頼する工場や交換する部品(純正品、OEM品など)によって変動することを念頭に置いてください。

引用 : メルセデス HP (https://www.mercedes-benz.co.jp/passengercars/models/van/v-class/overview.html)
【Vクラスの定番故障①】エアサスペンションの故障と修理代
Vクラスの乗り心地を支える最重要パーツであり、同時に最大のウィークポイントとも言えるのが、リアに採用されているエアサスペンション(エアサス)です。
- 症状:
- 駐車中に車体のリアが片側または両方下がっている(通称:尻下がり)
- エンジン始動後、車高が上がるまでに時間がかかる
- 走行中に「プシュー」というエア漏れの音が聞こえる
- メーター内にエアサス関連の警告灯が点灯する
- 原因:
- エアベローズの劣化・亀裂: ゴム製の風船であるベローズが経年劣化で硬化し、ひび割れてエア漏れを起こします。5年または5万kmあたりからリスクが高まります。
- コンプレッサーの故障: エア漏れが続くと、空気を送り込むコンプレッサーが常に作動し続け、過負荷で焼き付いてしまいます。
- ハイトセンサーの故障: 車高を検知するセンサーが故障し、適切な車高調整ができなくなります。
- 修理代の目安:
| 修理内容 | 部品の種類 | 費用の目安(部品代+工賃) | 備考 |
|---|---|---|---|
| エアベローズ交換(片側) | 純正品 | 約100,000円~150,000円 | 同時交換が推奨されるため、実際は倍の費用感 |
| OEM品/優良社外品 | 約60,000円~100,000円 | 品質を見極める必要あり | |
| エアサスコンプレッサー交換 | 純正品 | 約150,000円~250,000円 | ベローズと同時交換になるケースが多い |
| OEM品/優良社外品 | 約80,000円~150,000円 | 安価な粗悪品には注意が必要 | |
| ハイトセンサー交換(片側) | 純正品 | 約40,000円~60,000円 | 診断料が別途かかる場合がある |
エアサストラブルは放置すると走行不能になる可能性もあり、非常に高額な修理に発展しかねません。中古車を選ぶ際は、エアサスの交換歴があるか、現状でエア漏れの兆候がないかを最優先で確認すべきです。
【Vクラスの定番故障②】電動スライドドアの不具合と修理代
大きな車体を持つVクラスにとって、電動スライドドアは非常に便利な装備ですが、ここもトラブルが頻発する箇所です。
- 症状:
- ドアが途中で止まる、または閉まりきらない
- 「ピーピー」という警告音と共に作動しない
- ドアが閉まっているのに半ドア警告灯が点灯する
- 手動でも開閉が非常に重い
- 原因:
- ドアロックアクチュエーターの故障: ドアをロック/アンロックする内部機構の不具合。
- 各種センサーの故障: ドアの開閉状態や障害物を検知するセンサーの不具合。
- ワイヤーの伸びや断線: ドアを動かすワイヤーが経年劣化で伸びたり切れたりする。
- モーターの劣化: 開閉を行うモーター自体の寿命。
- 修理代の目安:
| 修理内容 | 費用の目安(部品代+工賃) | 備考 |
|---|---|---|
| ドアロックアクチュエーター交換 | 約80,000円~120,000円 | Vクラスの定番修理の一つ |
| スライドドアセンサー交換 | 約30,000円~50,000円 | 複数のセンサーがあり、故障箇所の特定が必要 |
| スライドドアワイヤー/モーター交換 | 約100,000円~200,000円 | ドアの内張を全て剥がす大掛かりな作業になる |
スライドドアの不具合は、単に不便なだけでなく、半ドア警告灯が点灯し続けることでクルーズコントロールなどの他の機能が使えなくなることもあります。試乗時には、内外のスイッチ、リモコンキーなど、あらゆる方法で何度も開閉テストを行うことが不可欠です。
【Vクラスの定番故障③】オルタネーター(ダイナモ)の故障と修理代
オルタネーターは、エンジンで発電を行い、バッテリーに充電するための重要な部品です。これが故障すると、車は走り続けることができなくなります。
- 症状:
- メーター内にバッテリー警告灯が赤く点灯する
- ヘッドライトが暗くなる、パワーウィンドウの動きが遅くなる
- エンジンルームから「ウィーン」という異音がする
- 最悪の場合、走行中に突然エンジンが停止する
- 原因:
- 内部ブラシやベアリングの摩耗: 走行距離が10万kmを超えると摩耗による寿命を迎えることが多い。
- レギュレーターの故障: 電圧を調整する部品の故障。
- エンジンオイル漏れによる故障: 上部からのオイル漏れがオルタネーターにかかり、内部をショートさせてしまうケースも多い。
- 修理代の目安:
| 修理内容 | 部品の種類 | 費用の目安(部品代+工賃) | 備考 |
|---|---|---|---|
| オルタネーター交換 | 純正品 | 約200,000円~300,000円 | 部品代が非常に高価 |
| リビルト品(再生品) | 約100,000円~180,000円 | コストを抑えるなら最も現実的な選択肢 | |
| OEM品/優良社外品 | 約120,000円~200,000円 | 信頼できるメーカーの製品を選びたい |
オルタネーターの故障は、出先で立ち往生するリスクが非常に高いトラブルです。走行距離が10万kmに近い車両や、エンジン周辺にオイル漏れが見られる車両は特に注意が必要です。
【Vクラスの定番故障④】エンジンオイル漏れ・冷却水漏れと修理代
輸入車全般に言えることですが、エンジン周辺のオイル漏れや冷却水漏れは定番のトラブルです。
- 症状:
- 駐車している地面に黒や緑のシミができている
- エンジンルームから焦げたような臭いがする
- オイルや冷却水の減りが早い
- 原因:
- 各種ガスケット・パッキンの劣化: エンジン各部の接合部に使われるゴム製のパッキンが、熱や経年で硬化し、シール性が失われて漏れを引き起こします。タペットカバーパッキンやオイルフィルターハウジングからの漏れが定番です。
- ラジエーターやウォーターポンプの劣化: 冷却水を循環させるシステムの部品が劣化し、冷却水が漏れ出します。
- 修理代の目安:
| 修理内容 | 費用の目安(部品代+工賃) | 備考 |
|---|---|---|
| タペットカバーパッキン交換 | 約40,000円~70,000円 | 比較的軽度な修理 |
| オイルフィルターハウジングガスケット交換 | 約60,000円~100,000円 | 周辺部品の脱着が必要なため工賃が高め |
| ラジエーター交換 | 約100,000円~180,000円 | 放置するとオーバーヒートの原因に |
| ウォーターポンプ交換 | 約80,000円~150,000円 | ベルト類と同時交換が推奨される |
軽微な滲み程度であれば緊急性は低いですが、ポタポタと垂れるレベルの漏れは放置してはいけません。オイル漏れは他の部品(オルタネーターなど)の故障を誘発することもあるため、早期発見・早期修理が重要です。
【Vクラスの定番故障⑤】ディーゼルエンジン特有のトラブル(DPF、AdBlue)
W447型Vクラスの主力であるクリーンディーゼルエンジンは、燃費も良くパワフルで魅力的ですが、特有のメンテナンスやトラブルも存在します。
- 症状:
- 「あと〇〇kmでエンジン始動不可」というAdBlue(アドブルー)関連の警告が表示される
- エンジンチェックランプの点灯
- マフラーから白煙が出る、加速が鈍くなる
- 原因:
- NOxセンサーの故障: 排気ガス中の窒素酸化物(NOx)濃度を測定するセンサーの故障。非常にデリケートで壊れやすい部品として有名です。
- AdBlueシステムの不具合: AdBlueを噴射するインジェクターやポンプ、ヒーターなどの故障。
- DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)の詰まり: 短距離走行ばかりを繰り返していると、フィルターに溜まった煤(スス)を燃焼させる「自動再生」がうまく行われず、フィルターが詰まってしまいます。
- 修理代の目安:
| 修理内容 | 費用の目安(部品代+工賃) | 備考 |
|---|---|---|
| NOxセンサー交換(1本あたり) | 約80,000円~120,000円 | 車両によっては複数本使われている |
| AdBlueポンプ/ヒーター交換 | 約150,000円~250,000円 | システム一式での交換となり高額 |
| DPF洗浄 | 約50,000円~100,000円 | 詰まりが軽度な場合の対応策 |
| DPF交換 | 約300,000円~500,000円 | 交換となると非常に高額な修理 |
ディーゼルモデルの購入を検討する場合は、高速道路を定期的に走行するなど、DPFの自動再生を促すような乗り方ができるかが一つのポイントになります。また、NOxセンサーは消耗品と割り切るくらいの心構えも必要かもしれません。
中古ベンツVクラス購入で後悔しないためのチェックポイント
ここまでVクラスの故障事例を見てきて、不安になった方もいるかもしれません。しかし、ご安心ください。これからお伝えするポイントを押さえて車両を選べば、トラブルのリスクを大幅に減らすことが可能です。これは私が何台も中古車を乗り継いできた経験から断言できます。

引用 : メルセデス HP (https://www.mercedes-benz.co.jp/passengercars/models/van/v-class/overview.html)
「壊れないVクラス」を選ぶための年式とモデル選びのコツ
前述の通り、年式が新しくなるほど信頼性は向上する傾向にあります。しかし、予算には限りがあるでしょう。そこでおすすめしたいのが、各モデルの「後期型」を狙うという戦略です。
- W639(2代目)なら2011年以降の後期型: エンジンやトランスミッションが改良され、内外装の質感も向上しています。初期・中期型で出がらしとなったトラブルが対策されていることが多いです。
- W447(3代目)なら2018年以降のマイナーチェンジ前後のモデル: 初期ロットで発生しがちだった細かな不具合が解消され、安定性が増しています。
また、グレード選びも重要です。エアサスが標準装備ではないグレード(例えばW447の「V220d Sports long」など、グレード名に注意)や、オプションで付けていない車両を選べば、最大の懸念点であるエアサスの故障リスクを根本から回避できます。乗り心地は若干硬めになりますが、維持費の安心感は格段に高まります。
試乗時に必ずチェックすべき5つのポイント
気になる車両が見つかったら、必ず試乗を行い、以下の5つのポイントを五感で確かめてください。販売店の担当者に遠慮は無用です。
- パワートレインのチェック:
- エンジン始動はスムーズか?異音はしないか?
- アイドリングは安定しているか?不快な振動はないか?
- 加速はスムーズか?変速ショックが大きすぎないか?(特に低速時)
- ディーゼルエンジンの場合、ガラガラ音が過大でないか?
- 足回りと乗り心地のチェック:
- 平坦な道でハンドルをまっすぐにして、左右に流れていかないか?
- 段差を乗り越えた際に、「ゴトゴト」「ギシギシ」といった異音や不快な突き上げはないか?
- 試乗後、車を停めてリアの車高が左右で均等か、下がりすぎていないかを確認。(エアサス車)
- 電動スライドドア・テールゲートの動作チェック:
- 運転席のスイッチ、ドアハンドル(外側・内側)、リモコンキー、全ての操作方法で最低3回以上、左右のスライドドアとテールゲートの開閉テストを行う。
- 動作はスムーズか?途中で止まったり、異音や引っ掛かりはないか?
- 電装品の動作チェック:
- エアコンは冷房・暖房ともにしっかり効くか?風量の切り替えは正常か?
- カーナビ、オーディオ、バックカメラは正常に作動するか?
- パワーウィンドウ、電動格納ミラー、サンルーフなど、動くものは全て動かしてみる。
- 警告灯のチェック:
- エンジン始動時に、全ての警告灯が一度点灯し、その後しっかりと消灯するかを確認する。特にエンジンチェックランプ、ABS、エアバッグ、エアサスなどの警告灯が消えない場合は重大なトラブルを抱えている可能性があります。
整備記録簿の重要性と確認すべき項目
中古車選びにおいて、整備記録簿(メンテナンスノート)は、その車の「履歴書」であり、最も信頼できる情報源です。記録簿がない、または内容がスカスカの車両は、どんなに内外装が綺麗でも避けるのが賢明です。
- 確認すべき項目:
- 定期点検の実施状況: 12ヶ月点検、24ヶ月点検が定期的に正規ディーラーや認証工場で実施されているか。
- オイル交換の頻度: メーカー指定のサイクル(またはそれより短いサイクル)でエンジンオイル、オイルフィルターが交換されているか。
- 消耗品の交換歴: ATフルード、ブレーキフルード、エアフィルター、バッテリーなどの交換履歴。
- 重要な部品の交換歴: エアサス、オルタネーター、ウォーターポンプなどの高額部品が近年交換されていれば、それは大きなプラス材料です。
記録簿を見ることで、前オーナーがどれだけ車に愛情を注ぎ、コストをかけて維持してきたかが一目瞭然となります。
ベンツVクラスの維持費を賢く抑える方法
無事にコンディションの良いVクラスを手に入れた後も、賢いメンテナンスを心掛けることで、維持費を大幅に抑えることが可能です。「ベンツだから維持費が高い」と諦める必要はありません。

引用 : メルセデス HP (https://www.mercedes-benz.co.jp/passengercars/models/van/v-class/overview.html)
正規ディーラーと専門工場の賢い使い分け
車のメンテナンス先として、まず思い浮かぶのが正規ディーラーだと思います。メーカーの専門知識、最新の診断機、純正部品による修理など、安心感は絶大です。しかし、その分工賃や部品代は高額になりがちです。
そこでおすすめしたいのが、メルセデス・ベンツを専門に扱う「専門工場」や「整備工場」の活用です。
- 正規ディーラーのメリット:
- 保証期間内の修理やリコール対応
- 複雑な電子制御系の診断
- メーカー保証が適用される修理
- 売却時のリセールバリュー向上
- 専門工場のメリット:
- 正規ディーラーより安価な工賃
- 純正部品だけでなく、OEM品や優良社外品、リビルト品など、予算に応じた修理方法を提案してくれる
- ディーラーではASSY(一式)交換となる修理も、部分修理で対応してくれることがある
- 豊富な経験に基づく、車種特有の弱点を知り尽くした整備
新車保証が残っている間や、原因不明の複雑なトラブルはディーラーへ。車検や消耗品の交換、定番の故障修理などは信頼できる専門工場へ。このように使い分けるのが、最も賢い選択と言えるでしょう。
純正部品とOEM部品、優良社外品の賢い選び方
修理費用を抑える上で鍵となるのが、交換部品の選び方です。
- 純正部品: メルセデス・ベンツのロゴが入った、最も品質と信頼性が高い部品。価格は最も高価。
- OEM部品 (Original Equipment Manufacturer): 純正部品を製造しているメーカーが、自社ブランドで販売している部品。ロゴがないだけで品質は純正品と同等でありながら、価格は2~4割ほど安いことが多い。
- 優良社外品: 純正品メーカー以外が製造している互換部品。品質はピンキリだが、BOSCHやBILSTEINなど、信頼できるメーカーの製品であれば、純正品に近い品質で価格を抑えられる。
- リビルト品: 使用済みの部品を分解・洗浄し、消耗パーツを新品に交換して再生した部品。オルタネーターやコンプレッサーなどで利用でき、新品より大幅に安価。
安全性に直結するブレーキ関連や、重要な電子制御部品は純正品や信頼性の高いOEM品を選ぶのが安心です。一方で、フィルター類や消耗品、あるいは定番の故障箇所で品質が安定している部品については、OEM品や優良社外品を積極的に活用することで、ランニングコストを大きく削減できます。
予防整備の重要性とおすすめメンテナンス
「壊れてから直す」のではなく、「壊れる前に交換する」という「予防整備」の考え方が、結果的にトータルの出費を抑えることに繋がります。
- 定期的なエンジンオイル交換: メーカー指定は15,000kmまたは1年ですが、日本の交通環境を考慮すると、7,000km~10,000kmまたは半年ごとの交換が理想です。
- ATフルード交換: メーカーは無交換を謳うこともありますが、日本のストップ&ゴーはトランスミッションに大きな負担をかけます。5万kmを目安に交換することで、高額なAT修理のリスクを低減できます。
- バッテリー交換: Vクラスは電装品が多く、バッテリーへの負担が大きい車です。3~4年を目安に、専用診断機で状態をチェックし、早めの交換を心掛けましょう。
これらのメンテナンスは、信頼できる専門工場に相談すれば、適切なタイミングと費用で実施してくれるはずです。
まとめ
今回は、「中古のベンツVクラスは壊れやすい」という噂の真相について、私の経験を交えながら徹底的に解説してきました。
改めて結論を述べると、Vクラスは確かに国産ミニバンと同じ感覚で乗れる車ではありません。エアサスやスライドドア、各種センサー類など、定期的なメンテナンスや交換が必要となるウィークポイントが存在します。しかし、それは「欠陥」ではなく、高性能と快適性を実現するための「特性」と捉えるべきです。
この記事で紹介した「壊れやすい理由」「定番の故障箇所と修理費用」「後悔しないためのチェックポイント」「維持費を抑える方法」をしっかりと理解し、実践すれば、Vクラスは決して手に負えない車ではありません。
適切な知識を持ってコンディションの良い個体を選び、信頼できるパートナー(専門工場)を見つけ、愛情を持ってメンテナンスしてあげれば、Vクラスは国産ミニバンでは決して味わうことのできない、圧倒的な走行性能、所有する満足感、そして家族との豊かな時間を提供してくれる、唯一無二の存在となるでしょう。
漠然とした不安に惑わされることなく、ぜひ勇気を持って、素晴らしいVクラスとのカーライフへの第一歩を踏み出してください。