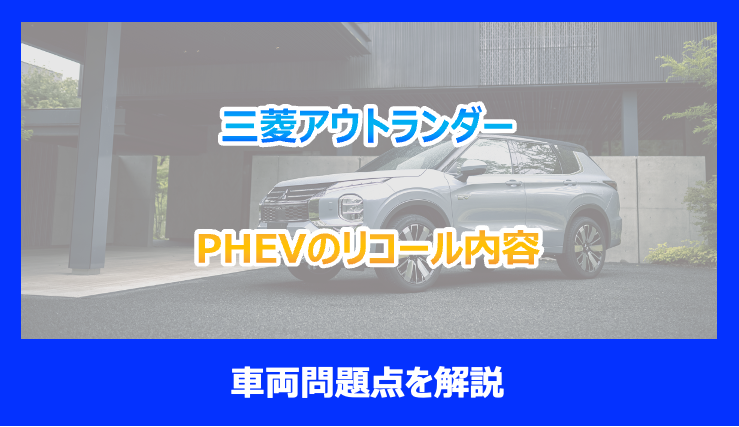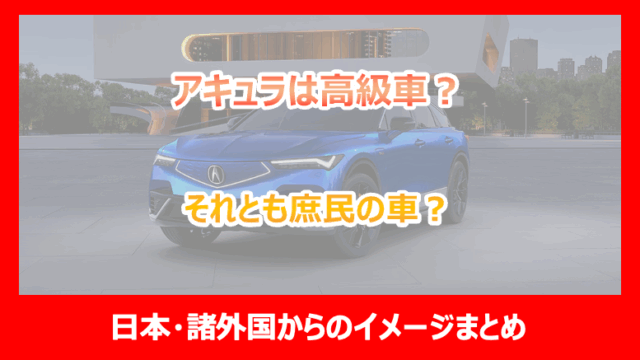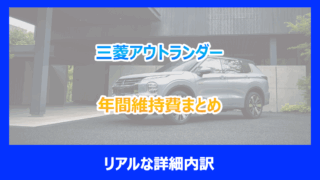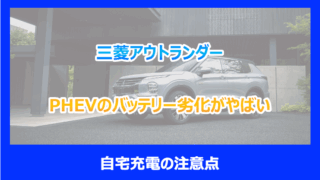新型アウトランダーPHEVは、三菱の看板SUVとして高い人気を誇りますが、その一方で、発売以降たびたびリコール情報が発表されています。

引用 : 三菱HP (https://www.mitsubishi-motors.com/jp/newsroom/newsrelease/2021/20211216_1.html)
特にナビゲーションシステム関連の不具合は、オーナーの間でも度々話題に上がる問題です。本レビューでは、新型アウトランダーPHEVのリコール内容とその背景、そしてオーナー視点での影響や改善への期待を詳しく解説します。
記事のポイント
- 新型アウトランダーPHEVのリコール発生状況と対象範囲
- 繰り返し発生しているナビの不具合とその原因
- OTA(無線アップデート)非対応による不便さ
- 今後の改善への期待とオーナーが取るべき対策
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

新型アウトランダーPHEV|リコールの内容について

引用 : 三菱HP (https://www.mitsubishi-motors.com/jp/newsroom/newsrelease/2021/20211216_1.html)
ナビ不具合による複数回のリコール
新型アウトランダーPHEVのリコールの大半は、スマートフォン連携型ナビゲーションシステムの不具合によるものです。発売から現在までに、このナビ関連だけで4回のリコールが発生しています。ナビ画面のフリーズや誤作動などが原因で、安全運転支援機能にも影響が出る場合があり、リコールの対象となっています。

引用 : 三菱HP (https://www.mitsubishi-motors.com/jp/newsroom/newsrelease/2021/20211216_1.html)
症状の具体像(オーナー体験ベース)
実際に起きやすい挙動は、画面が真っ黒になる・勝手に再起動を繰り返す・案内音声が出ない・タッチが効かない・CarPlay/Android Autoが頻繁に切断される、など。バックギア連動のカメラ映像やアラウンドビューの表示が遅延/無表示になるケースでは、駐車時の安全確認に直接影響します。
なぜ安全リスクと評価されやすいのか
後退時はバックカメラ表示や警報がドライバーの視認・判断を補助します。これらが表示されない、あるいは遅延する状態は“後方視界の確保”という安全要件を阻害しうるため、軽微に見えるソフト不具合でも“安全上の不具合”としてリコールに格上げされることがあります。
発生しやすい条件と再現性
高温環境での長時間駐車後の起動直後、低電圧(バッテリーが弱っている)状態、スマホ接続直後に複数アプリが同時に立ち上がる状況、地図更新直後の初回再起動時などに症状が再現しやすい傾向があります。システム負荷が瞬間的に高まると、処理落ち→再起動→設定巻き戻り、といった連鎖が起こりがちです。
技術的背景の考察
車載インフォテインメントはSoC(演算)・メモリ(領域)・ストレージ(読み書き)・通信(Bluetooth/Wi‑Fi/USB)・車両CANの多要素連携で成り立ちます。典型的な不具合要因は、メモリリーク、スレッド競合、I/Oエラー、起動順序の競合、外部デバイスとのハンドシェイク不整合など。サプライヤのミドルウェア更新で一部は改善しても、派生不具合が残り“複数回の修正リリース”になりやすいのが現実です。
ディーラーでの実際の対処フロー
入庫→診断機でDTC確認→ナビ/ディスプレイオーディオのソフト書き換え(必要に応じてユニット交換)→バックカメラ表示・音声出力・ステア連動ガイドラインの確認→スマホ再ペアリングの案内、という流れが一般的。作業自体は比較的短時間でも、混雑時は予約待ちが発生します。
オーナーができる一次対応
症状が出た瞬間は、(1)安全を確保したうえで再起動(電源長押しまたはACCオフ→一定時間→オン)、(2)スマホ接続を一旦解除・再接続、(3)別のUSBケーブル(データ対応)に変更、(4)地図・アプリ更新の完了を待ってから操作、を試すと復帰することがあります。繰り返す場合は入庫して恒久対処が必要です。
入庫前に用意しておくと早いもの
車台番号、現在のナビ/ソフトバージョン、発生日・時間・天候・気温、再現手順、使用していたスマホ機種とOSバージョン、接続方法(有線/無線)、発生時のスクリーンショットや動画。これらがあると診断がスムーズです。
作業後の確認チェックリスト
バックカメラ表示の遅延有無、ガイドラインの挙動、ブラインドスポットやPDCブザーの連動、案内音声とメディア音のバランス、ハンズフリー通話品質、ステアリングスイッチの反応、時計・日付・プリセットの保持、CarPlay/Android Autoの安定性を順に確認します。
再発時の記録とエスカレーション
再度症状が出たら、発生条件・画面状態・車速・シフトポジションを記録し、サービスアドバイザーに共有します。ソフト更新で解決しない場合、ユニット本体やハーネスの点検・交換へとエスカレーションされます。
今後への期待
最も効果が大きいのはOTA対応の実装です。深夜帯に自動でパッチ適用と検証を行えるようになれば、ディーラー入庫の負担を下げ、品質改善のスピードも上がります。併せて、実使用を想定した長時間・高温/低温・接続切替ストレスなどのシナリオテストを強化することで、再発確率は大きく下げられるはずです。
対象車両の範囲と傾向
特に発売初期〜前期生産ロットの新型アウトランダーPHEVで報告が多く、同一のディスプレイオーディオ/ナビユニットを採用する兄弟車(例:トライトン)へ波及するケースも見られます。背景には、サプライヤ由来の共通部品・共通ソフトウェアの採用、そして生産ロットごとの微細な仕様差が絡み合っていると考えられます。
対象年式・型式のめやす
発売初期〜前期の生産分に集中しやすい傾向があります。マイナーチェンジやサプライヤ更新のタイミングで順次対策が入るため、後期ロットでは発生率が下がることが一般的です。
生産ロットとサプライヤの共通化
近年は開発効率化のため複数車種でナビ/インフォテインメントを共通化します。利点は多い一方、ミドルウェアやファームウェアの不具合が横串で波及しやすい構造的リスクがあります。
同一ナビ搭載車種への連鎖
同一ハード/ソフト構成を持つ車種(例:トライトンなど)で同種の症状が見られることがあります。これは不具合の本質が“車種固有”ではなく“ユニット固有”である可能性を示します。
対象外になりやすいケース
後期ロットや対策ソフトが初期から導入された個体、ナビユニットの交換歴があり最新対策品に更新済みの個体では、同様の不具合が発生しにくい傾向があります。
自分の車が対象か確かめる手順
車検証の車台番号を手元に、メーカーのリコール検索で適合を確認→該当すれば販売店へ入庫予約→来店時に症状の再現条件・発生日・接続していたスマホ情報を共有、という流れが最短です。
オーナーへの示唆
“初期ロット=必ず不具合”ではありませんが、対策前ソフトの個体は影響を受けやすいのも事実。購入時・点検時にソフト/ユニットのバージョンを確認する習慣が有効です。
リコールの背景
ナビは単なる快適装備に見えますが、バックカメラ表示、警報音の案内、設定変更インターフェースなど“安全運転を支える表示/操作系”を兼ねるため、動作不良は安全上の支障と評価されやすくなります。メーカーは安全を最優先して、軽微でも再発可能性がある不具合はリコールで一括是正する方針を取りがちです。
制度上の位置づけ
車両の保安に関わる装置に不具合がある場合、製造者は自主的に是正措置(リコール)を講じ、オーナーへ無償で修理・更新を提供するのが基本枠組みです。
なぜナビが“安全”と結び付くのか
後退時の映像表示や警告の欠落、表示遅延はドライバーの視認・判断を阻害しうるためです。結果として、インフォテインメントであっても安全装置の一部として扱われます。
メーカーが判断する主な軸
影響の重大性、発生頻度、再現性、影響範囲(他車種への波及可能性)、是正の難易度・スピード。このバランスでサービスキャンペーンに留めるか、リコールへ格上げするかが決まります。
市場/地域差の存在
市場ごとの規制・使用環境の違いにより、同一不具合でも対処の切り分けが異なる場合があります。例えば高温多湿/低温下の使用条件は不具合の顕在化に差を生みます。
新型アウトランダーPHEV|繰り返されるナビ不具合の原因と課題

引用 : 三菱HP (https://www.mitsubishi-motors.com/jp/newsroom/newsrelease/2021/20211216_1.html)
ソフトウェア不具合の頻発
ソフトウェアは機能追加とともに複雑化し、起動順序の競合、メモリリーク、キャッシュ破損、デバイス接続のハンドシェイク不整合、電源管理(スリープ/ウェイク)不備などが複合して症状を引き起こします。テストで潰し切れなかったケースが市場で見つかり、修正→副作用→再修正というサイクルが複数回のリコールにつながることがあります。
典型的な根本原因カテゴリ
リソース不足(CPU/メモリ/I/O)、タイミング依存(非同期処理の競合)、データ整合性(ログ/地図データの破損)、外部機器との互換性(スマホOSアップデート)、熱・電圧ストレスによる動作不安定。
再発を抑えるテスト観点
長時間連続動作、極端な温度環境、急な接続切替(有線→無線)、同時多タスク(ナビ案内+通話+音楽再生+カメラ表示)、低電圧起動などの“現実的で厳しい”シナリオが有効です。
ログと再現手順の重要性
ユーザー側の簡易ログ(発生日・時刻・気温・接続スマホ・操作手順)でも診断精度が上がり、対策版の開発スピードが向上します。記録の習慣化が解決への近道です。
OTA非対応による不便さ
OTAに非対応だと、更新のたびに入庫が必要になり、時間的・心理的コストが嵩みます。混雑期には予約待ちも発生し、ユーザー体験を損ねます。
入庫コストの実感
移動・待ち時間・代車手配・業務/家事の調整といった“目に見えない負担”が重なります。更新自体は短時間でも、丸一日が潰れることもあります。
導入を阻むハードル
車載OTAはセキュリティ、電源安定、更新失敗時のロールバック、安全装置との連携検証などクリアすべき要件が多く、実装には時間と投資が必要です。
暫定策の現実解
当面はディーラーでの書き換え精度を高め、予約〜作業〜引き渡しをスムーズにする運用改善(入庫前の問診、必要ファイルの事前準備、検証チェックリストの標準化)が効果的です。
改善の必要性
現代の車は“ソフトウェアで走る”と言われるほど、表示・車両連携・更新の品質が体験を左右します。改善の要は、開発プロセスと更新手段の双方を強化することです。
期待したい品質指標
初期不良率の低減、場内検出率の向上、フィールドでの平均故障間隔(MTBF)の延伸、重大障害の無停止復旧時間(RTO)の短縮。
リリース管理の高度化
機能改善と不具合修正のブランチ分離、段階的ロールアウト、A/B適用、ロールバック手順の明確化。ユーザー影響を最小化しつつ改良を素早く回す基盤づくりが鍵です。
フィードバックループの強化
匿名化テレメトリやサービス現場の診断情報を迅速に開発へ戻す仕組みを整えれば、問題の早期検知と恒久対策に直結します。
新型アウトランダーPHEV|オーナーへの影響と対策
利便性の低下
ナビが不安定だと、日常の移動〜長距離ドライブまで広く影響します。特にバックカメラ連動や駐車支援の表示遅延/無表示は心理的負担も大きく、運転の余裕を奪います。
生活シーン別の影響
都心のコインパーキングや狭路での切り返し、夜間・雨天の後退、初見ルートの高速移動など、視覚情報への依存が高い場面でストレスが増大します。
安全面での留意点
不具合が出たら“まず停車して安全確保”。目視とミラーを基本に、後退速度をいつもより落とす、誘導者がいれば頼る、という原点回帰が有効です。
残価・売却への影響
記録簿にリコール対処歴が残っていること自体はマイナスではありません。むしろ“対策済み”“定期点検実施”が可視化されることで、買い手に安心材料として働くこともあります。
対策と心構え
オーナーができる現実的な対策は、情報を早く掴み、再発を減らし、入庫の手間を最小化することに尽きます。
情報チェックの習慣化
月1回を目安にリコール/サービス情報を確認。長距離前は起動確認とバックカメラ表示のテストをルーティン化します。
ディーラーとの連携術
担当を固定し、症状の再現条件・ログ・使用スマホ情報を事前共有。入庫枠の仮押さえと作業時間の目安を事前にもらうと滞在時間を短縮できます。
予防的メンテ
補機バッテリーの健全性維持(電圧低下は誤動作の温床)、高品質なデータ対応USBケーブルの使用、不要デバイスの同時接続を控えるなど、負荷軽減が有効です。
データのバックアップ
ラジオ/ステーション、ナビお気に入り、ペアリング情報は更新で初期化されることがあります。入庫前にメモやスクリーンショットで控えておくと復旧が早いです。
保証と費用の考え方
リコール作業は無償が原則。新車保証や延長保証の適用範囲も確認しておくと安心です。
まとめ
新型アウトランダーPHEVのリコールは、主としてナビ/インフォテインメントの不具合が引き金です。初期ロットに報告が集中しやすい構造要因、OTA非対応ゆえの運用負担が重なり、結果として“複数回の是正”が必要になりました。とはいえ、対策ソフトやユニット更新で改善は着実に進みます。オーナーは、(1)情報チェックの習慣化、(2)入庫時の記録・再現手順の共有、(3)予防的メンテとデータバックアップ、を実践すれば体験の安定度は大きく向上します。メーカーには、OTA対応の実装と品質指標の明確化、段階的ロールアウトなどの運用強化を引き続き期待したいところです。