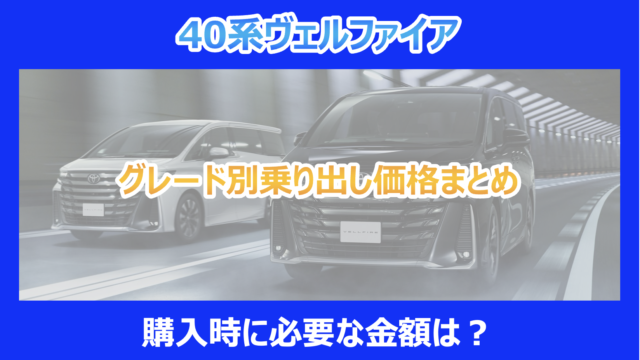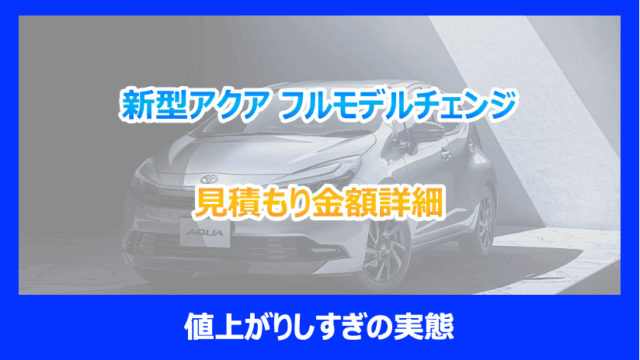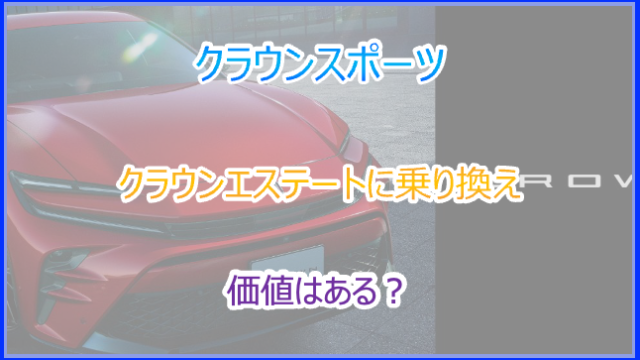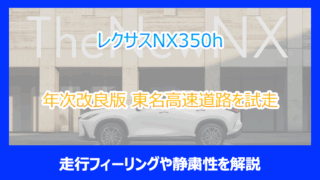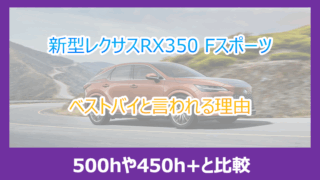年次改良が加えられたレクサスRX。静粛性や乗り心地、装備面での進化が注目される一方で、「ちょっと待った!」と思わせるポイントも存在します。

引用 : TOYOTA HP (https://lexus.jp/models/gx/)
本レビューでは、ディーラーの営業マンが口にしないような悪い点・注意すべきポイントに焦点を当てて徹底解説。
RXはその高級感と信頼性、圧倒的な存在感で多くの支持を集めている一方、「見落とされがち」「知らないと後悔する」部分も少なくありません。
特に今回は、実際のオーナーや購入希望者からのリアルな声をもとに、一般的なセールストークには出てこない真実を掘り下げます。
記事のポイント
- 車幅が大きく、駐車に不便なシーンが多い
- アンビエントライトは想像より暗く期待外れ
- フル液晶メーターは実は周回遅れの採用
- 小回り性能は改善されたが限定的
車買い替えのご検討中の方へ
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。

CTN一括査定は自動車業界紙にも多数掲載されているので、安心してご利用できます。

レクサスRX年次改良版|車幅と取り回しはサイズの進化が裏目に?
レクサスRX年次改良版|車幅1920mmは国産SUV最大級
レクサスRXの車幅は1920mm。これはレクサスのフラッグシップクーペ「LC」と同等で、セダンの「LS」よりも大きい数値です。多くの都市部の駐車場ではこの幅が仇となり、機械式駐車場やコインパーキングではバーの幅に合わない場合もあります。

引用 : TOYOTA HP (https://lexus.jp/models/gx/)
これは数字上の話だけでなく、実際の運転感覚としても「思ったよりも大きく感じる」「隣の車との距離が気になって神経を使う」という声が目立ちます。特に運転が得意でない方や、ご家族と共有する場合には注意が必要です。
レクサスRX年次改良版|駐車場選びに神経を使う必要がある
月極駐車場でも隣の車との距離が近い場合、乗り降りのストレスは増大します。特にファミリー層では後席のチャイルドシートの乗降に支障が出る場面も多く、「ドアを大きく開けられないことで子どもを抱えての乗り降りが困難になった」といったリアルな声もあります。

引用 : TOYOTA HP (https://lexus.jp/models/gx/)
実際、従来モデルから乗り換えたユーザーの中には「前の車では余裕で入った駐車場が入らない」という声もあり、駐車時の左右の余裕が想像以上に限られるとの指摘も複数存在します。
さらに、自宅駐車場での出入りに苦労するケースや、マンションの立体駐車場に入らないといった問題も報告されています。特に都市部では高さ・幅制限のある立体駐車場の利用が避けられないため、契約前に必ずサイズ確認を行うことが推奨されます。
レクサスRX年次改良版|インテリアの期待と現実
レクサスRX年次改良版|アンビエントライトの明るさ不足
実際の明るさと期待値のギャップ
改良によって“明るくなった”とされるアンビエントライトですが、実際に日中の明るさの中で点灯させてみると「どこが明るくなったの?」という感想を持つ人が少なくありません。特に晴天時や明るい環境下ではほとんど認識できず、車内の演出としての存在感は非常に希薄です。
輸入車(メルセデスやBMW)に比べると光量自体が控えめで、調整幅も限られており、色のバリエーションやアニメーション設定にも乏しいため、インテリア演出にこだわるユーザーには物足りない仕様となっています。
「夜間はまあまあ雰囲気が出るけれど、それ以外は期待外れ」といった声も複数見受けられ、特に欧州車からの乗り換え組には落差を感じさせる要因になっています。
レクサスのアンビエントライトは確かに繊細で品があるものの、実用性に欠けるという指摘もあります。例えば、光がインテリア全体に均一に広がるような設計になっておらず、部分的に照らす構造であるため、車内全体の雰囲気づくりにはやや力不足と感じる場面もあります。
加えて、カラーのバリエーションや点灯パターンも限定されており、「もう少し遊び心があってもよいのでは」という感想も一定数存在しています。特にユーザーによっては、好みの色に細かく調整したり、走行モードや時間帯に合わせて変化するような機能を期待する声も見受けられ、現状の仕様ではそのニーズに十分応えきれていないのが現実です。
レクサスRX年次改良版|液晶メーターの採用はようやく
全車標準装備となった12.3インチのフル液晶メーター。見た目の先進性はありますが、これは既に他のトヨタ車(クラウンクロスオーバーやアルファード等)では先行導入されていたもの。
レクサスとしての独自性は薄く、「やっと追いついた」印象が否めません。特に、レクサスというブランドに対して“常に最先端であるべき”という期待を抱いているユーザーからすると、こうした装備のタイムラグは失望感にもつながりかねません。
また、フル液晶化によって得られるインパクトは大きいものの、メーターのグラフィックデザインやレスポンス、表示内容のカスタマイズ性などにおいても、他ブランドに比べて平凡であるという評価も少なくなく、単なる“デジタル化”に留まっているとの指摘もあります。
また、液晶メーターの操作性や視認性に関しても、ユーザーによって評価が分かれています。「情報が詰まりすぎて見づらい」「直感的な操作がしにくい」という声もあり、万人受けするUIとは言い難いかもしれません。
表示される情報が多すぎるがゆえに、必要な情報を一目で把握しにくく、視線移動が増えてしまうことへのストレスを感じるという指摘もあります。加えて、操作系に関してもステアリングスイッチやタッチパッドとの連動が煩雑で、慣れるまでは操作方法に戸惑うケースも報告されています。
特に高齢者やテクノロジーに不慣れな層にとっては、こうしたインターフェースの複雑さがネックとなり得るため、もっとシンプルで視認性に優れた設計が求められているという声が一定数存在します。
レクサスRX年次改良版|操作性の落とし穴|eラッチやドア設計の不便
レクサスRX年次改良版|eラッチの慣れと説明責任
ボタン操作で開閉する“eラッチ”のドアハンドルは、慣れれば便利とされるものの、初めて乗る同乗者には毎回の説明が必須。
家族や友人が戸惑う場面が多く、「とっつきにくい」という評価もあります。特に運転席以外の席では従来のドアノブのような直感的操作ができず、ドアを開けるのに時間がかかるケースも報告されています。
例えば、雨天時に急いで車内へ入りたい場面や、暗い場所で操作部分が見えづらいといったシーンでは、旧来の物理的なレバー式の方が扱いやすかったという意見もあります。
また、子どもや高齢者など、身体的に操作に慣れていない人にとっては、逆にストレスを感じる要素となり得ます。
特に高齢者や小さな子どもなど、説明しても一度では理解しにくいケースも。操作時に力加減が分かりづらく、誤って開閉を試みると「壊してしまいそう」と不安になるという声もあります。
従来の物理的なドアハンドルであれば直感的な操作が可能であったのに対し、eラッチは動作にワンテンポのラグがあるため、タイムラグによる戸惑いが重なります。ドアの基本操作に説明が必要というのは、プレミアムカーとしてはやや残念な仕様かもしれません。
レクサスRX年次改良版|モデルによっては採用されていない
同じレクサスでもGXや一部の車種では採用されていないeラッチ。これは、未だにユーザー評価が分かれる証拠とも言えるでしょう。
便利と感じる人と、煩わしさを感じる人の差が非常に大きい装備です。特にSUVやファミリーカーとして日常使いされるケースが多いRXにおいて、直感的な操作性を重視する層からは不評の声も根強く、ドアという日常の基本動作にストレスを抱えることに抵抗を感じる人も少なくありません。
一方で、未来的な演出として好意的に捉える人もおり、「慣れれば快適」という意見もあるため、まさに評価が真っ二つに分かれる象徴的な装備といえるでしょう。
レクサスRX年次改良版|マークレビンソンの音質|価格との釣り合いに疑問
レクサスRX年次改良版|高額オプションだが期待以下?
プレミアムオーディオとして知られるマークレビンソンですが、実際に装着したオーナーの中には「値段の割に音質は普通」という声が目立ちます。
特に音に敏感なユーザーほど、他のオーディオ機器と比べて物足りなさを感じることが多いようです。音の広がりや解像度、重低音の厚みといった面で「期待していたほどの違いは感じられなかった」「オプション価格に見合う感動がない」といったリアルなレビューも存在します。
また、音場のチューニングが万人向けに平坦化されており、独特の音色が薄れている印象を受ける人も。これにより、車内で高音質な音楽体験を求めるユーザーにとっては、購入後にやや後悔する要素になることも少なくありません。
中には「期待しすぎた」という声や、「純正スピーカーでも十分だったのでは?」という評価も。高価なオプションとしての価値をどう捉えるかは、ユーザー次第とも言えるでしょう。
レクサスRX年次改良版|ショールームでは分かりにくい
音質に関しては、試乗時にしっかり確認するのが重要。ショールーム内での印象と、実走時の音響はまるで異なります。特にショールームでは静かな環境のため低音の響きやサラウンド感が誇張されやすく、実際の走行中にはロードノイズやエンジン音によって音の輪郭がかき消されてしまう場面も多くあります。
さらに、音楽のジャンルによっても印象が変わるため、自分の普段聴く楽曲で確認するのがベストです。可能であればBluetooth接続やUSB再生など、自身のデバイスから音楽を流して試すのが理想的です。
レクサスRX年次改良版|小回り性能|改善点とその限界
レクサスRX年次改良版|DRS非搭載モデルは要注意
ダイナミックリアステアリング(DRS)が搭載されたモデルでは最小回転半径が5.5mと格段に改善されましたが、これは500hなど限られた上位グレードおよび4WDモデルに限られます。
実際にこの恩恵を受けられるのは、ラインアップの中でも高価格帯かつ装備が充実した一部モデルのみであり、多くの人が購入する350hの2WDやバージョンLといった売れ筋グレードでは、依然として最小回転半径は5.9mと小回りが効きにくい仕様となっています。
日常使いでの取り回しのしづらさは改善されておらず、狭い道や駐車場でのストレスは引き続き感じやすい部分です。
この数値の差は、日常使いでの駐車やUターン、狭路での取り回しに大きく影響します。実際に試乗する際には、自宅周辺やよく通る道での取り回しを意識してみることが重要です。
レクサスRX年次改良版|実使用での苦労が多い
ドライブスルーやコンビニ駐車場、狭小住宅地など、現実の使用環境では「何度も切り返しが必要」と感じる場面が多いのが実情です。特にドライブスルーでは一度で旋回できず、後続車にプレッシャーを感じながら何度も切り返す羽目になることも。
車体の大きさに加えて、死角の多さやミラーの見え方にも慣れが必要で、取り回しに不安を覚えるドライバーも少なくありません。レビューでも「最小回転半径があと30cm小さければ…」といった声もあり、わずかな差が日常での運転ストレスを大きく左右する要因となっています。
RXの取り回し性能は、快適性や使い勝手に直結する非常に重要なポイントとして、過小評価すべきではないでしょう。
おすすめの一括査定サイト
CTN車一括査定

引用 : 株式会社CTN HP
今お乗りの車を売却して、新しい車への乗り換えを検討している方は一括査定サイト「CTN車一括査定」がおすすめです。
CTN一括査定では1,000店舗以上から高価買取店3社を厳選している為、効率的に高価売却が実現することが可能です。
また、買取店に対し独自審査基準を設けていたり、優良買取店の表彰など行っている為、買取店の質も担保されており悪質な買取行為が発生しにくい環境が特徴です。
筆者自身も、過去にホンダヴェゼルを驚くべき高額査定で売却することができました。
詳しい内容は過去の記事をご覧ください。

自動車業界紙にも多数掲載されておりますので、安心してご利用いただけます。
新しい車に乗り換える際、今乗っている愛車をどれだけ高く売却できるかは、次の車の選択肢にも大きく影響します。
私自身、一括見積もりサイトを活用したことで、ホンダヴェゼルからレクサスRXに乗り換えることができました。
まとめ
年次改良を受けたレクサスRXは確かに魅力的な進化を遂げていますが、すべての変更が“買い”とは限りません。
- 幅広のボディによる駐車場の不便さ
- 日中見えづらいアンビエントライト
- 実はトヨタ車と同じフル液晶メーター
- 上位グレードに限られる小回り性能
- 慣れと説明が必要なeラッチドア
- コストパフォーマンスに疑問が残るマークレビンソン
これらの点を「事前に知っていたかどうか」で、後悔するかしないかは大きく変わります。レクサスRXは決して“悪い車”ではありません。しかし“完璧な車”でもないのです。営業マンがあまり触れたがらない部分にこそ、ユーザー目線でのリアルな価値判断が隠れています。
購入を検討する際には、こうした注意点を冷静に見極めた上で、自分のライフスタイルに本当に合うかを確認することが大切です。慎重な判断が、満足度の高い買い物につながるのです。