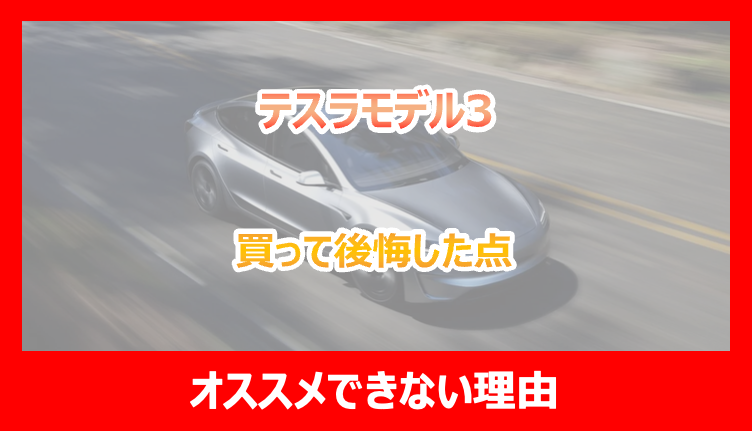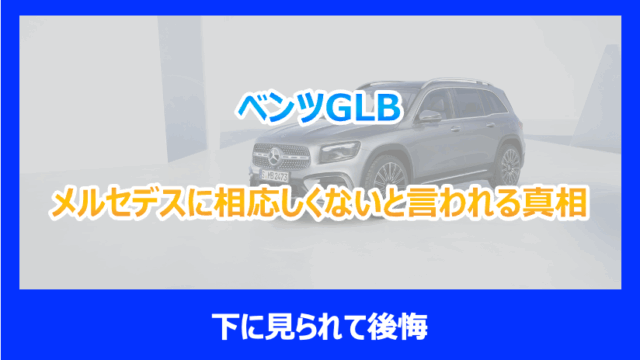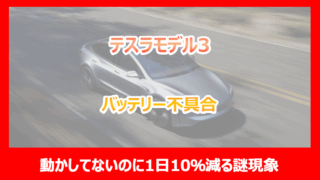テスラから発売された新型モデル3。革新的なEVとして注目を集める一方で、実際に購入して使ってみると意外な落とし穴も多数見えてきます。

引用 : 価格コム HP (https://kakaku.com/item/K0001215150/)
筆者は実際にこのモデルを半年所有し、日常使いからロングドライブまで体験してきました。
本レビューでは、新型モデル3の使い勝手をリアルに検証し、特に“後悔ポイント”を徹底的に紹介します。
記事のポイント
- モデル3は先進的だが、ソフト面やナビ性能に大きな課題あり
- 初心者や高齢者には扱いにくく万人向けではない
- オートパイロットやUIには改善の余地が多い
- 静粛性や加速性能など魅力もあるが、それを上回る不満も多い
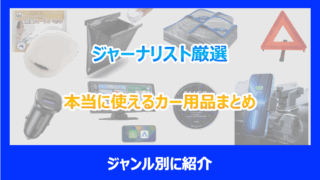
テスラモデル3を買って後悔した点まとめ
ナビ・GPSの精度が壊滅的
トンネル内や高架下でGPSがロストする頻度が異常に高く、ナビが機能しなくなる場面が多発。長距離ドライブ時には致命的な使い勝手の悪さ。

トンネルに入ると即ロストする
特に「山手トンネル」「アクアライン」「外環道」などの長距離トンネルでは、ほぼ確実にGPSがロストします。地図上での現在地表示が消えるだけでなく、ルートガイドも中断されるため、初見の道路では道を間違えるリスクが非常に高くなります。
自社位置のズレが頻発
トンネルを抜けた直後も、GPSがすぐに復旧しないケースが多く、地図上の現在位置が大幅にズレて表示されることがあります。これにより、曲がるべき交差点を見逃したり、誤案内される事例が頻出します。
リルート機能も不完全
ルート逸脱時に即座にリルートされる機能はあるものの、GPSが捕捉できない状態では当然それも働かず。都市高速のような分岐の多い道路では、ナビとして致命的な弱点と言えます。
ランドマークや施設表示が乏しい
他社ナビのように「ガソリンスタンド」「コンビニ」「レストラン」などのPOI(ポイント・オブ・インタレスト)が地図上に表示されないため、休憩場所や立ち寄りスポットを見つけにくいという不便さも際立っています。
スマホナビ未満の精度
Android AutoやApple CarPlay未対応のため、Google Mapsなど高精度なスマホナビを使う選択肢もなし。純正ナビのみで全ての移動をこなすには、運転スキルと事前のルート確認が必要になるのが実情です。
オートパイロットが不安定で危険
自動運転機能の一歩手前として期待されたオートパイロットだが、実際の使用感は不安定であり、想定外の挙動が頻繁に発生します。
トルク検知の厳しさと解除リスク
ハンドルに少しでもトルクを加えると、すぐにオートパイロットが解除されます。特に緊急回避や微調整をしようとした際でも、制御が途切れ、急減速が発生してしまう場面が多く見受けられます。
ハンドル操作の“強要”警告が頻出
ハンドルを握っているにも関わらず「ハンドルを少し回してください」という警告が10秒に1回程度の頻度で表示されます。静電容量センサーがないため、握っていても検知されない場合があり、操作中のストレスになります。
オーバーライド不可で回避が難しい
一般的なADAS(先進運転支援システム)では、ドライバーがハンドルを操作しても支援機能が継続しますが、テスラの場合は少しでも力を入れると即座に解除され、システムから人間への制御移行が唐突に起きます。
ワンペダル走行との相性の悪さ
オートパイロット解除後にアクセルから足を離していると、強制的な減速が発生。後続車への急なブレーキとなり危険な状況を招く恐れもあり、システム設計上の連携不足が否めません。
レーンチェンジアシストも不安定
自動でのレーンチェンジも、ウィンカー操作と同時に“軽いハンドル操作”が求められますが、この動作の加減が非常にシビアで、少しでも強く力を入れるとオートパイロット自体が解除されるため、運転中に余計な神経を使います。
結論:安全装備としての信頼性に欠ける
アダプティブクルーズや自動車線維持などの基本性能は備わっているものの、「自動で快適に走る」ことよりも「注意深く操作する必要がある」点が多く、リラックスした運転ができる状態には程遠いのが現実です。
カスタマイズ性ゼロのUI
Apple CarPlayやAndroid Auto未対応、アプリの拡張も不可。表示画面やショートカットも変更不可で、ユーザーの好みに合わせる余地がない。
スマホ連携機能が完全非対応
ほとんどの現行車で標準装備されているApple CarPlayやAndroid Autoに非対応のため、スマホアプリをそのまま使うことができません。ナビや音楽、通話の利便性が著しく損なわれます。
UIの変更ができない固定式デザイン
地図の縮尺や表示形式、到着予想時刻の表示位置など、変更できる箇所が非常に少なく、使いづらさを感じる場面が多いです。地図が自動で縮小される仕様も煩わしく、好みの表示に固定できないのは大きなストレスです。
アプリの追加・拡張ができない
SpotifyやAudibleなどプリインストールされた一部サービスは利用可能ですが、YouTube MusicやAmazon Musicなどユーザーがよく使う他サービスの追加は不可。ユーザーの選択肢を奪っている仕様になっています。
ショートカットや操作割り当ての自由度が低い
ステアリングダイヤルなどに割り当てられる機能も限られており、独自のショートカット設定は不可。結果としてドライバーは用意された枠組みの中で操作を覚える必要があります。
結論:自由度のなさがユーザー体験を制限
EVの最先端をうたう車でありながら、インフォテインメントシステムのカスタマイズ性は旧世代的。柔軟なユーザー体験を求める人にとっては不満が残る設計です。
ワンペダル強制の走行スタイル
アクセルオフで急減速するワンペダルモードしか選べず、従来の車に慣れた人にとっては非常に扱いにくい。切り替え不可なのは大きなマイナスポイント。
慣れないと違和感しかないブレーキ挙動
アクセルを緩めただけで即座に減速が始まるため、従来の車で慣れている「クリープ走行」や「惰性での滑走」ができません。結果として、街中でのノロノロ運転や駐車場での微調整が極めて難しく感じる人も多いです。
走行モードの選択肢が一切ない
他社EVでは、”Bモード(強めの回生)”と”Dモード(弱め回生)”を選べたり、ブレーキ感覚をカスタマイズできるものが多いですが、テスラでは一律でワンペダルモードしか用意されていません。この仕様はユーザーの多様なニーズに応えられていないと言えます。
減速時の挙動に戸惑うケースが多発
ドライバーの意図に関係なく減速が強くかかる場面では、後続車との車間距離に気を配る必要があります。ブレーキランプも点灯するため、後続車が減速意図を読み違えるリスクもあります。
惰性で走れない疲労感
渋滞時や長距離走行時に、アクセルを微調整し続けなければならず、右足が疲れやすくなる傾向があります。特にストップ&ゴーが多い日本の都市部では、頻繁な微調整が求められ、運転疲労の要因にもなります。
「選ばせてくれない」設計思想
他社のように「ワンペダルON/OFFを選べる自由」が与えられていれば、多くの不満は解消されていたはずです。しかし、現状ではドライバーが車に合わせる必要があり、柔軟性に欠けるという印象は拭えません。
ナビ画面の表示が直感に反する
案内が上下逆に表示され、次に曲がるポイントが分かりにくく、ミス誘発。特にジャンクションなどではミスリードしやすく危険。
表示レイアウトが一般常識と逆
多くの国産車ナビやスマホアプリでは、次に曲がるポイントが画面の下に、次の次が上に表示される構成になっており、視覚的にも直感的に理解しやすくなっています。しかし、テスラのナビはこの表示が逆になっており、上に次の案内、下にその次の案内という構成になっています。これにより、とっさの判断が必要なシーンでは混乱を招きやすくなっています。
ジャンクション案内が分かりづらい
特に首都高速や都市高速のように複雑な分岐が連続するエリアでは、ナビの表示が曖昧で、案内通りに進んだはずがルートを外れてしまうことも少なくありません。距離表示こそあるものの、「今曲がるのか」「次なのか」が判断しづらく、ミスリードにつながりやすい構成です。
ナビ画面の直感性が不足
目的地までのルートが直線的に描かれることが多く、細かなカーブや分岐が視認しにくいのも課題の一つです。スクロールや縮尺の自動リセットも相まって、細かく見たい場面でうまく表示されず、利便性に欠けます。
慣れるまでのリスクが高い
「使っていれば慣れる」といった声もありますが、ナビゲーションはとっさの判断が求められる場面も多く、初見のルートや都市高速走行中の誤案内は重大なリスクを伴います。安全性を考慮すると、より直感的で分かりやすいレイアウトが求められます。
車体操作に慣れが必要すぎる
物理的なシフトレバーもなく、操作は全て液晶とタッチ。高齢者や機械操作に慣れていない人には厳しく、直感操作がしにくい。
液晶によるシフト操作の難しさ
テスラモデル3では、一般的なシフトレバーの代わりに液晶画面上でスライドする操作が採用されています。この方式は慣れないと即座にD(ドライブ)・R(リバース)を選ぶことができず、特に駐車場などでの微妙な操作に戸惑うことが多くなります。
操作系のすべてがタッチパネル依存
ワイパーやヘッドライトの操作、エアコンの風向き設定までが物理スイッチではなくタッチパネルに依存しています。運転中に手探りで調整できないため、目線をそらす必要があり、安全面でも懸念が残ります。
直感操作が通用しないレイアウト
たとえば、ウィンカーやハザードボタンの位置も従来車とは異なり、押し間違いや戸惑いが頻発。走行中にとっさの操作がしにくいため、運転中のストレスを感じやすい構造となっています。
機械操作に不慣れな層には不親切
特に高齢者や、これまでスマートデバイスにあまり触れてこなかった層にとっては、タッチ操作に慣れるまでのハードルが高く、「乗るたびに緊張する」という声も少なくありません。
結論:ユーザーが順応を強いられる設計
テスラの先進的な操作系は、逆に言えばユーザー側がそれに合わせる必要がある仕様です。車の方がドライバーに歩み寄るのではなく、ドライバーがテスラに順応するという思想が色濃く現れており、万人向けとは言い難い操作性になっています。
ミラーやスイッチ配置が独特
ウィンカーやミラー操作が分かりづらく、ドライバーが車に合わせる必要がある設計思想。慣れるまでに時間がかかる。
ステアリングに統合されたウィンカー
テスラモデル3では、一般的なレバー式ウィンカーが存在せず、ステアリングの左右に配置されたボタン式操作が求められます。この方式はステアリング操作と同時に行うには難しく、特にハンドルを切っている状態ではどちらのボタンを押せばいいか混乱する場面が多く発生します。
ミラー調整がタッチパネル連携
ドアミラーの調整もタッチパネルとステアリングダイヤルの併用によって行うため、直感的ではありません。物理スイッチによる調整に慣れたユーザーにとっては煩雑で、車両発進前の準備に時間がかかることもしばしばです。
ハザードスイッチの位置も独特
ハザードランプのスイッチがステアリング上部の見えづらい位置にあるため、緊急時に即座に押すのが困難。視線を外す必要があり、安全上のリスクも否定できません。
総合的に見てユーザー側の順応が必須
こうした独自レイアウトの数々は、従来の自動車とはまったく異なる操作体系を求められます。結果として、ドライバーがテスラの設計思想に慣れる必要があり、万人受けするインターフェースとは言い難い仕様です。
テスラモデル3を買って良かった点
静粛性は他のEVを圧倒
アコースティックガラスの採用で徹底的な静音化を実現。内燃機関がないこともあり、EVの中でもトップクラスの静かさ。

アコースティックガラスによる遮音性能
フロントガラスだけでなく、リアやルーフにもアコースティックガラスが採用されており、外部の走行音や風切り音を効果的に遮断しています。従来のEVや高級セダンと比較しても、ワンランク上の静粛性が体感できます。
エンジン音・振動が皆無のEV構造
内燃機関が存在しないため、エンジンノイズや振動が皆無。これにより、低速から高速まで一貫して静かな走行が可能で、疲労感も大きく軽減されます。
路面ノイズも最小限に抑制
サスペンションのセッティングや床下の遮音材の工夫により、ロードノイズ(タイヤからの振動音)も抑え込まれています。舗装が荒れた道路でも、室内の会話や音楽を邪魔しないレベルの快適性を確保。
高級オーディオとの相乗効果
優れた静粛性は、テスラが誇る高性能サウンドシステムの真価を引き出します。低音の響きや中高音のクリアさが際立ち、車内がまるでコンサートホールのような空間に感じられます。
EVならではの贅沢な空間演出
静けさそのものが贅沢であり、特に夜間の移動や長距離ドライブではその恩恵を強く実感します。目に見えない価値として、所有する満足感を支えてくれる重要な要素です。
加速性能が異次元
AWDロングレンジの加速力は圧巻。0-100km/h加速4秒台で、合流や追い越しでも安心して踏み込める。
体感できる即応性のある加速
電動モーター特有のレスポンスの良さにより、アクセルを踏んだ瞬間に力強く前に出る感覚は、内燃機関車では味わえない魅力です。信号待ちからの発進、合流地点での加速、追い越し時の反応が非常にスムーズで、ストレスフリーな運転を実現しています。
高速道路での合流・追い越しも余裕
高速道路への合流や追い越し車線での加速も俊敏。0-100km/h加速4秒台の実力により、安全にスピードを乗せることができ、周囲の車両とのスムーズな距離調整が可能です。特に「追い越し加速」での加速力には目を見張るものがあります。
脳が置いていかれるような加速感
フル加速時には、シートに押し付けられるようなGを体感でき、まさに“脳が置いていかれる”感覚に近い爽快さがあります。この体感はスポーツカー顔負けで、EVならではの楽しさを強く感じさせてくれます。
回生ブレーキとの一体感
加速後の減速も自然で、回生ブレーキとのバランスが絶妙。強い加速を楽しみながらも、滑らかに減速できるため、カクつきの少ない運転が可能です。スポーティかつコントローラブルな仕上がりになっています。
加速の気持ち良さが運転の楽しさを支える
毎回の運転で加速の滑らかさ・鋭さに感動を覚えるレベルで、EVの価値を再認識させてくれる重要な要素です。”運転していて楽しい”という感覚を味わいたい人には、大きな魅力となるでしょう。
スーパーチャージャーの利便性
全国に整備されつつあるスーパーチャージャーでの急速充電が非常に早く、30分以内で80%近く充電できる実力。アプリ連動で通知も来るため運用性も高い。
充電時間の短さが圧倒的
スーパーチャージャーは150kW〜250kWという高出力で、長距離ドライブ中の立ち寄り時間を最小限に抑えてくれます。通常の急速充電では40〜60分ほどかかる80%充電が、テスラでは約20〜30分で完了するため、休憩中にほぼ満充電が可能です。
立地の良さと増加する設置箇所
主要高速道路のSA/PAや都市部の大型商業施設など、アクセスしやすい場所に設置されており、実用性は年々向上。ドライブの計画が立てやすくなり、「充電の不安」から解放されるのは大きな利点です。
アプリ連携で待ち時間も可視化
テスラ専用アプリを使えば、最寄りのスーパーチャージャーの空き状況や出力、混雑具合までリアルタイムで確認可能。充電開始や完了の通知も届くため、車から離れていても安心です。
決済のスマートさも秀逸
充電開始から決済までがすべて自動で処理される仕組みのため、専用カードやアプリ操作すら不要。ケーブルを挿すだけで充電が始まり、煩雑さとは無縁のユーザー体験が得られます。
他社EVとの差別化ポイント
多くの他社EVでは「どこで・どのように・何分待つか」に頭を悩ませがちですが、テスラのスーパーチャージャーならその心配が大幅に軽減されます。この“インフラの強さ”は、実際に運用してみると最も安心感につながる要素のひとつです。
オーディオ・アンビエント環境が優秀
音響品質の高さが際立つ
テスラモデル3は高品質なスピーカーシステムを搭載しており、クリアな中高音と迫力ある低音が楽しめます。まるで車内がプライベートスタジオのように感じられるほどで、細かな音のニュアンスまで忠実に再現されます。音楽に没入したいドライバーにとっては、この音響空間は大きな魅力です。
車内照明による演出力
アンビエントライトのカラーや明るさはシーンに応じて変化し、車内全体を心地よい空間に仕上げています。夜間走行中は特にその効果が際立ち、リラックスした雰囲気を演出してくれます。これにより、単なる移動時間が“癒しの時間”へと変わります。
音と光のシナジー
静粛性の高い車内環境と高音質オーディオ、そして柔らかく包み込む照明が相まって、まるで上質なラウンジにいるかのような心地よさを生み出しています。音楽に集中できるだけでなく、同乗者との会話もスムーズに楽しめるのも特徴です。
長距離ドライブの満足度を底上げ
これらの装備は、日常の通勤はもちろん、長時間のドライブや旅行の際にも快適性を支えてくれます。車内で音楽を楽しみながら移動する時間が、思い出に残るひとときとなるでしょう。 音質の良さ、車内照明のクオリティが高く、移動時間を贅沢な空間に変えてくれる。音楽好きには特におすすめ。
ソフトウェアアップデートの楽しみ
定期アップデートで日々進化
テスラは月に1〜2回の頻度でソフトウェアアップデートを配信しており、新機能の追加やUIの改善が継続的に行われます。これはスマートフォンのような進化体験であり、購入後も車が“成長”していく感覚を味わえるのが大きな魅力です。
機能追加だけでなく性能改善も
アップデート内容は単なるバグ修正にとどまらず、例えばオートパイロットの制御精度向上、バッテリー効率の最適化、さらにはエンタメ機能の追加など多岐にわたります。購入当初と比べて性能が良くなっていく感覚は、他の車にはない体験です。
新機能が“サプライズ”のように届く
新しいUIや機能が突然届くことで、まるで新しい車に乗り換えたかのようなワクワク感があります。ゲーム機能やイースターエッグ的な演出が含まれることもあり、オーナーコミュニティ内でも話題になりやすく、所有する楽しみが倍増します。
オーナーとの“対話感”が生まれる
「アップデートで何が変わったかな?」と確認する習慣が生まれ、まるで車と対話しているような感覚が芽生えます。これにより、単なる移動手段としての車ではなく、日常のパートナーとしての愛着が強まっていきます。
所有体験に直結する満足感
アップデートにより機能が増えたり、使い勝手が良くなるたびに「買ってよかった」と思える瞬間が訪れます。これは従来の自動車にはなかった“アップデート体験による満足”であり、テスラならではの魅力です。 月1〜2回の頻度でUIや機能が進化。成長を見守る感覚で使える。オーナーにとっては所有の喜びに直結。
サイズ感が日本向き
都市部での取り回しの良さ
モデルYよりもコンパクトで、全幅185cm未満・全高155cm以下のため、都内や都市部の狭い道でもスムーズに走行可能。立体駐車場にも問題なく入るサイズで、コインパーキングやマンションの機械式駐車場に対応しやすい。
駐車時の安心感
車幅が185cmを切っていることは、狭い駐車スペースでも隣の車との距離を確保しやすく、ドアの開閉時のストレスも軽減される。運転に自信がない人でも扱いやすいサイズ感。
税金や洗車の面でも恩恵
全幅が190cmを超える大型車に比べると、車庫証明取得のハードルが低く、洗車機の対応幅にも収まるためメンテナンス面でもメリットがある。結果として、都市生活における“ちょうどいいサイズ”としての魅力が際立つ。
快適装備も充実
冬場も快適なヒーター機能
シートヒーターとステアリングヒーターは寒冷地や冬季の通勤で大活躍。エンジンを使わないEVだからこそ、即暖性に優れており、出発直後から温かさを実感できる。
夏場にうれしいベンチレーション
シートベンチレーションは夏の暑さ対策に効果的。長時間運転しても背中が蒸れにくく、快適性を損なわないのは高評価ポイント。
ケーブル不要の非接触充電
スマートフォンなどを置くだけで充電できるワイヤレス充電パッドも標準装備。コードの煩わしさがなく、整理整頓された空間を保ちつつ充電できる利便性がある。
オートエアコンの賢い制御
キャビン内の温度を自動で最適に保つオートエアコン機能も優秀。外気温や日射センサーと連動しており、常に快適な車内環境を提供する。
高級感ある快適性が標準
これらの装備がすべて標準で付帯する点も、価格帯を考えると非常に魅力的。日々の通勤や買い物、長距離ドライブまで、快適性を重視した設計が際立っている。
まとめ
テスラモデル3は確かに魅力的なEVであり、特に加速性能・静粛性・ソフトアップデートの将来性には目を見張るものがあります。しかし、その先進性の裏には、使い勝手や安全性への配慮が不十分な側面もあり、誰にでもオススメできる車ではありません。とくに初めてEVに乗る方や高齢者には向かず、「運転に慣れている人」や「新しい技術を積極的に楽しめる人」向けのクルマです。
一言で言えば、「ユーザーがテスラに合わせなければならない」車。それでも魅力を感じるなら、きっと満足できる一台になるでしょう。